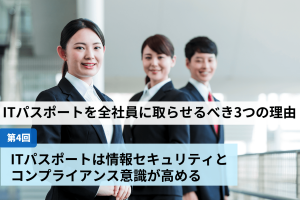人材育成は企業の発展に欠かせないものの、以下のような課題を抱えている企業様も多いのではないでしょうか。
- 社員が忙しくて、人材育成を行う時間と余裕がない
- 人材育成の知識やスキルが不足している
- 社員が人材育成の重要性を認識できていない
こうした課題は、人材育成計画そのものに欠陥がある場合も多く、既存の人材育成計画が現場の状況を無視した古い体制運用を強いていることもあるため、早急に見直す必要があります。
古い人材育成計画を現場の課題に即した内容へアップデートすることで、育成担当者・対象者の双方が実行に移しやすい環境が出来上がります。
まずは人材育成におけるよくある課題を整理し、解決のための具体策を把握しましょう。加えて企業の取り組み事例を知ることで、自社に最適な育成スキームを検討することができます。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
人材育成のよくある6つの課題と解決策
人材育成のよくある課題には以下の6つがあります。
- 社員が忙しくて時間と余裕がない
- 人材育成の知識やスキルが不足している
- 社員が重要性を認識できていない
- 人材育成そのものが目的化している
- 計画的に行えていない
- 目に見える効果が感じられない
社員が忙しくて時間と余裕がない
人材育成を推進しようとしても、社員が忙しくて時間と余裕がないというのは非常にありがちなケースです。現場の社員は日常業務や目標などに追われて、プラスアルファの時間を取りにくい状況がよく見られます。
また現場に限らず、人材育成を担う人事関連の部署も同様に忙しく、推進に向けた動きをとれない場合もあります。
人材育成は企業の将来を育む取り組みの一環です。そのため、企業全体でその重要性を理解し、育成期間の前後を含む一定期間は関連部署や担当者が育成に手をかけられるよう、通常業務などの調整を図り、育成時間を別に設けるようにしましょう。
育成時間を別に設けることが難しい場合は、e-ラーニングの導入がおすすめです。育成対象者の習熟度に合わせた学習提供が可能で、端末があればいつでもどこでも学習に取り組めます。
育成担当者は受講案内を行い、受講中は分からないところに対して回答するといったピンポイントの関わりでも育成が勧められます。そのため、育成のための時間が取りづらいケースに最適な手法といえます。
人材育成の知識やスキルが不足している
人材育成についての知識やスキルが社内に不足している場合もあります。事業の発展や業績アップに注力する一方で「人に教え、育てる」ための知識やスキルの習得が課題として残っているケースも少なくありません。
業務で結果を出す能力と、育成に必要なスキルはまったくの別物です。そのため、人材育成の前段階として、教育担当者の育成にも力を入れなければいけません。教育担当者の育成は次のようなテーマでの実施がおすすめです。
- OJTトレーナー:OJTを行うトレーナーとして「OJTの質」「育成スキル」の向上が図れる。管理職候補としての成長も見込める
- メンター:知識と経験のある先輩社員がメンター(育成担当者)となり、後輩社員(育成対象者)に対して指導・業務支援・メンタル面のサポートを行うことで、自身もメンターとしての能力向上を図る
- ティーチング:業務に対して経験豊富な人から経験が浅い人へ知識やノウハウを教えるためのスキルの向上を図る
- コーチング:目標達成に向けた個人面談において、対話を通じて対象者の能力・気力を引き出し、自己成長や自発的な行動を促すためのスキル向上を図る
- マネジメントスキル:組織が成果を上げるために経営資源(ヒト・モノ・カネ)を効率的に活用するための能力の向上を図る
教育担当者の苦手分野に合わせて、取り入れるテーマを変え、人材育成における総合的な能力を伸ばせるようにしましょう。
社員が重要性を認識できていない
経営層や人材育成を担う部署が推進を図る一方で、その他の社員が人材育成の重要性を認識しておらず上手く巻き込めないパターンもあります。「現場は研修どころではない」「研修参加は義務ですか?」のような声があがる場合、重要性の認識が不足している可能性が高いでしょう。
人材育成の重要性を分かってもらうためには、現状課題と育成後の将来像を見せることが重要です。人材育成によるカリキュラムを受けることで、自身がどのように変化し、その変化が企業全体にどのような効果をもたらすのかを周知することで、人材育成に対する重要性の認識を高められます。
また、人事評価制度を見直すのも一つの手です。成長意欲に関する項目を設けることで自主的な参加を促せるでしょう。
人材育成そのものが目的化している
人材育成を行っているものの、施策そのものが目的化しているケースも見受けられます。具体例は以下の通りです。
- OJTを行っているが、具体的な目標は設けずにトレーナーを任命するだけになっている
- 集合研修を行っているが、開催後の効果測定やフォローはしていない
- ジョブローテーション制度を導入しているが、形式的な配置替えになっている
人材育成は育成後に企業が成長・発展しなければその意味を成しません。そのため、人材育成を通して、どのような変化を遂げたいのか「具体的な目標設定」が重要です。
また、育成期間中は充実した時間を過ごせたとしても、終了後に習得したスキル・知識を活かせなければ、その期間は無駄になります。スキルや知識は定着してこそ、効力を発揮します。そのため、育成期間中の振り返りはもちろん、終了後には「どのように業務に活かせたか」を共有する場を設け、スキル・知識の定着を図りましょう。
関連:研修計画の立て方は?確認ポイントや研修後の取り組みについて | 人材育成サポーター
計画的に行えていない
人材育成の目的が曖昧なまま不定期・単発で開催されたり、継続的な育成手法が中断されたりなど、計画性が不足していると研修内容が良くてもその効果は薄れます。計画的ではない人材育成は、費用や人などのコストがかかるだけでなく、育成対象社に人材育成に対する不信感を抱かせかねません。
人材育成を完遂し、社員の着実な成長に繋げるためには、育成計画書の作成が必須です。育成計画には5つのポイントがあります。
- 目標設定
- 実施する教育の内容
- 現状の把握
- 課題発見
- フィードバック
人材育成を行う目的や目指す目標を明確にすることで、社員をどこに向かって育成すれば良いのか見失わずに済みます。また、計画書を基に振り返りを行いながら育成を進めることで、不足点を補いつつ社員の着実な成長を図れます。
さらに作成した計画書は記録として残るため、各社員の成長過程を記録・共有することが可能です。加えて、どのような育成を行ったのかという実績は、育成に関するノウハウとして組織の資産になるため、次回以降の人材育成に対しても効果的な方法を選択しやすくなるでしょう。
育成計画書の作り方が分からないという場合は、下記記事で詳細を解説しているので、あわせてご確認ください。また、無料のフォーマットも公開しているので、育成計画書の作成にお役立てください。
関連:人材育成の育成計画書の作り方|無料のサンプルフォーマット付き
とはいえ、「実際、何から手をつければ良いのか分からない」とお悩みの場合、企業での取り組み事例を知ることで、人材育成施策を進める上での具体的なイメージを持つことが重要です。
目に見える効果が感じられない
コストや時間をかけて人材育成を行ったとしても、目に見えた効果が感じられないために人材育成に時間や予算を使えないという悪循環に陥りやすいのも課題として挙げられます。
効果的な人材育成を行うとともに、人材育成の効果を適切に測定することが必要です。
人材育成の効果は、研修などを行う前後で従業員の意識やスキル、業務の変化をもとに測定します。研修や教育内容に合わせて、以下のような方法が有効です。
- 研修後アンケート
- 理解度テスト
- 行動量調査
- 業務上の成果の確認
ただ、長期間をかけて効果が現れることもあります。継続的かつ計画的な人材育成とモニタリングによって、効果を可視化することができるでしょう。
関連記事:研修の効果測定とは|4つの評価レベルと段階別の測定手法を解説 | 人材育成サポーター
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
効果的な人材育成を行うために大切なこと
育成計画の作成や具体的な手法の選択に入る前に、人材育成を行ううえで重要なポイントを抑えておきましょう。9つのポイントを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
1. 目的を明確にする
人材育成はただ教育やトレーニングを行うだけではなく、その目的を明確にすることが非常に大切です。
目的を明確にすることで、各個人がその目的に向けて自己啓発を進めていく動機付けとなります。人材育成の目的例として以下があげられます。
- ビジネスマインドの醸成
- スキルや専門性の向上
- 帰属意識の向上
- 幹部候補人材の育成
各個人の目指すべき具体的なゴール設定とともに、これらの目的を追求することで、より有意義かつ効果的な人材育成が可能となります。
2. 目標を設定する
人材育成を行う上で、目標の設定は欠かせません。人材育成における目標とは、自社が理想とする人材像へ社員を成長させるための指標です。
社員それぞれが設定した目標の達成に向け取り組み、主に上司が管理・フォローを行います。人事・教育担当者は各部署からあがってきた目標を取りまとめ、研修・セミナーなどの育成施策の企画に活用します。
組織をあげた人材育成は、明確な目標があって初めて行えるのです。
また人材育成の目標は、「客観的に判断できる指標であること」「企業としての成果にもつながること」が重要です。
関連:人材育成の目標とは?基本的な設定方法や管理のポイントを紹介
3. スキルの可視化を行う
スキルの可視化は、各従業員の現在地を把握し、成長を図る上で重要です。可視化を行うことで、個々人のスキルレベルや育成の必要性が明らかになります。
一般的には、スキルマップを作成し、長所・短所を評価します。スキルマップは、各種業務スキルを軸にした表で、それぞれのスキルレベルを数値化します。各従業員のスキル状況が一目でわかるよう、採点やレーティングを行い、その結果をもとに育成計画を立てます。
また、スキルの可視化は、リーダーと部下のコミュニケーションを促進します。具体的なスキルとそのレベルを示すことで、共通の理解を深め、育成の方向性や目標を明確化することが可能です。
4. 期日を決める
人材育成において、具体的なスキル獲得や能力開発のための期日設定は重要です。
まず育成計画を策定する際には、目標とするスキルや業績の向上度を明示し、それを達成するための具体的な期日を設定します。これにより、育成対象者は自身の成長を具体的にイメージしやすくなります。
また、期日設定は育成の進行管理にも寄与します。期日があることで、育成担当者と育成対象者の双方が進行状況や成果を確認し、必要に応じて育成計画を修正することが可能となります。
5. 自主性・自発性を養う
人材育成において、育成対象者の「自主性・自発性」は不可欠です。成長は、本人の「成長したい」という思いがあって初めて実現します。いくら周りが成長させようとしても、本人に成長を望む気持ちが無ければ成り立ちません。そのため「自主性・自発性」を持っていることが前提となるのです。
なお「自主性」と「自発性」は似た言葉ですが、以下のような違いがあります。
- 自主性:決められたことを自分の判断でこなしていくこと
- 自発性:決められていなくても自ら進んで行うこと
自主性を養うには、育成対象者に自ら考える機会を多く与えることが有効です。一方で自発性を養うには、あるべき姿や理想とする状態を育成対象者に問いかけ、明確化させることが有効です。
6. モチベーションを管理する
人材育成では、育成対象者のモチベーション管理も大切です。モチベーションがなければ、成長につながる活動を行えません。
育成対象者のモチベーションを管理するためには、そもそも「モチベーションとは何か」を正しく理解する必要があります。モチベーションは単なる「やる気」と捉えられる場合も多いのですが、正確には「やる気を起こさせる動機づけ」のことです。「行動するための目的や理由」と表すとよりイメージしやすいでしょう。
また下表の通りモチベーションは「内的モチベーション」と「外的モチベーション」に分けられます。
モチベーション (やる気を起こさせる動機づけ=行動するための目的や理由)
| 内的なモチベーション | 外的なモチベーション |
|---|---|
| どうなりたいのか 何がしたいのか どう生きたいか …など | 給料アップ 報奨金 ライバルの存在 …など |
| 特徴 上がりにくく下がりにくい 外部の影響を受けにくい 自らコントロールしやすい (中長期) | 特徴 上がりやすく下がりやすい 外部の影響を受けやすい 自らコントロールしにくい (短期) |
人材育成においては、日々の指導や面談などを通じて「内的なモチベーション」を高めつつ、社内施策などで「外的なモチベーション」にも働きかけるのがポイントです。とくに内的なモチベーションは、外部の影響を受けにくく自らコントロールしやすいため、やる気を安定させるのに有効です。
「内的なモチベーション」と「外的モチベーション」それぞれに働きかける指導や施策を組み合わせて、社員のやる気が高まった状態を維持しましょう。
7. 育成担当者のスキルを高める
人材育成を行う上では、育成担当者のスキル向上も欠かせません。
具体的には、設定した目標を達成できるようにする「目標管理能力」やティーチングやコーチングなどを含む「コミュニケーションスキル」、正確な状況把握と判断のために必要な「ロジカルシンキング」などです。
いずれのスキルも日々多忙な業務を遂行するなかで、並行して学び、適切な評価を下すことは困難を極めます。育成担当者のスムーズなスキルアップを図るならば、社員が好きなタイミングで学びを深められる「e-ラーニング」の活用がおすすめです。
オンラインで学習できるeラーニングシステムを使えば、時間や場所に縛られることなく、より広範囲な人材のスキルアップや教育の均質化を実現できます。
また、最新の情報に常にアップデートして学習コンテンツを提供できるため、新人向け・管理職向けといった階層別研修や、従業員のリスキリングなども幅広く対応可能です。
8. 人材育成に関する制度を整える
人材育成を安定して行うためには、人材育成に関する各制度を整備することが必要です。具体的には、OJT制度、研修制度、ジョブローテーション制度、人事評価制度、目標管理制度、メンター制度があります。
人材育成に関する制度を整えるためには、フレームワークを活用して既存の制度を見直すのも効果的です。
ただ、人材育成に関する各制度が完璧に整備されている企業は決して多くありません。
整える努力をすると同時に、少なくとも「制度が整っていないから人材育成を行えない」という認識をもたない・もたせないことが大切です。
日常業務における一つひとつの経験やコミュニケーションが人材育成の機会であり、制度はそれらの効果や効率をさらに高めるためのものという位置づけが好ましいでしょう。
9. 最適な育成スキームを選択する
人材育成を成功させるためには「最適な育成スキームの選択」が重要です。育成スキームの選択が適切でないと、時間やコストを無駄に消費し、結果として育成が進まないどころか、従業員のモチベーション低下を招くこともあります。
以下に示す表は、具体的な職位とよくある課題、それに対応する育成スキームの例です。
| 職位 | よくある課題 | 育成スキーム |
|---|---|---|
| 新入社員 | ・ビジネスマナー不足 ・基礎知識不足 ・報連相不足 ・時間管理ができない | ・OJT ・OFF-JT ・メンター制度 ・eラーニング |
| 中堅社員 | ・モチベーション低下 ・スキルアップ停滞 ・キャリアへの不安 ・後輩指導に課題 | ・OJT ・メンター制度 ・eラーニング ・ジョブローテーション |
| マネージャー | ・チームマネジメント ・部下育成 ・上司とのコミュニケーション ・プレッシャー対処 | ・eラーニング ・外部研修 ・人事評価研修 |
| 管理職 | ・経営視点の欠如 ・人材育成の停滞 ・変化への対応力不足 | ・eラーニング ・外部研修 ・自己研鑽 |
育成スキームは個々の職位や能力によって最適な選択が異なるため、企業全体が推進する人材育成モデルの整備(最適な育成スキーム選び)が重要になるのです。
新入社員の育成
新入社員における人材育成の課題としてあがりやすいのが「モチベーションマネジメント」です。
仕事に対するモチベーションは定着率にも影響しやすく、上手くマネジメントできないがゆえに離職に至ったというケースが後を絶ちません。慣れない環境や業務からくる不安をいかに解消するかが求められます。
解決策としては、育成対象者(新入社員)と育成担当者の両者が「モチベーションマネジメント」について学ぶことです。具体的には以下が挙げられます。
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 育成対象者 | 自らのモチベーションをいかに維持・向上させるかという視点でセルフマネジメントについて習得させます。組織としてしっかりと社員のモチベーションをマネジメントしつつ、「自らのモチベーションは自らでマネジメントする」ことの大切さを説きましょう |
| 育成担当者 | 部下や後輩のモチベーションには、自らの言動も大きく関わることを認識させることが大切です。例えば、部下に対して「期待を言葉にして表す・意見を求める・裁量権を与える」等を行うことで、部下は「期待されていることを実感」でき、成果向上にもつながります |
なお、「周囲からの期待が高いと成果も高くなる傾向」はピグマリオン効果と称されています。以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。
関連:ピグマリオン効果とゴーレム効果の違い|ビジネスでの活用と注意点
育成対象者の「自らのモチベーションは自らでコントロールしないと」という思いと、育成担当者による「部下のモチベーションを高く維持するには、自分の言動も意識しなければ」という認識が合致することで、真価を得られます。
中堅社員の育成
中堅社員における人材育成の課題としてあがりやすいのが「管理職候補としての自覚・育成」です。ここには、育成担当者としてのスキルも含まれます。独り立ちしたプレーヤーから、いかに管理職候補としての自覚を持たせるか、マネジメントスキルを向上させるかが課題です。
解決策としては、「OJTやメンター、プロジェクトリーダーとして抜てき」など、現場でのマネジメントが必要になる経験をさせることです。もちろん、任命・抜てきだけ行い、あとは本人任せというケースはあってはなりません。
例えば、OJTやメンターを行う前には、マネジメントする側および育成担当者としての学びを得るための「OJT研修」や「メンター研修」の受講をおすすめします。
また中堅社員は担当する業務も増えており、育成担当者としての立場が追加されると業務過多になることも懸念されます。こうしたケースでは、周囲が一部業務を代理したり、育成対象者の予習や復習にeラーニングを活用して負担を軽減することが大切です。
リーダーの育成
リーダーは部下を育成する立場であり、自らの人材育成力が問われます。リーダー層の人材育成は、組織の成長や業績向上に直結するため、特に重要視されます。
リーダーに求められる能力として、以下のようなものがあげられます。
- 問題解決力
- 意思決定力
- コーチング力
- ファシリテーション力
リーダー層の育成は、OJT(On the Job Training)と研修を組み合わせて行うことが一般的です。OJTでは先輩リーダーからの実践を通じた指導を、研修では座学による知識やスキルの習得を図ります。eラーニングの活用も有効な手段の一つとなります。
リーダー育成では、単にリーダーとしての知識やスキルを身につけるだけでなく、自覚やマインドセットの醸成も重要になってきます。
関連:リーダー育成のポイントは?必要な要素やスキル、育成方法を解説
管理職の育成
教育対象者となる機会は少ない管理職ですが、それゆえに組織から見れば自らも育成対象であることを忘れがちになります。こうした管理職特有の課題に対する解決策として、以下が挙げられます。
- 経営知識やハラスメントなど管理職にも必要な内容での研修に参加させる
- 資格取得や書籍購入の補助など自己啓発の機会を与える
- 部下が参加する研修にオブザーバーとして参加させる
管理職として自ら積極的に学ぶ姿勢を部下に示すことで、部下の学習意欲向上も期待できます。
管理職に求められる主なスキルは以下になるため、具体的な育成手法とあわせて理解しておきましょう。
- リーダーシップ
- 目標管理能力
- 部下育成力
- コミュニケーションスキル
- ロジカルシンキング(論理的思考)
- クリエイティブシンキング(水平思考)
- クリティカルシンキング(批判的思考)
関連:マネジメントスキルを高める人材育成手法|重視すべき部下育成力
人材育成にeラーニングを活用した事例
人材育成の課題解決には、従来の集合研修の限界を超えた新しいアプローチが求められます。
ここでは、eラーニングを効果的に活用して、様々な人材育成課題を解決した企業事例をご紹介します。インプット効率化による研修時間短縮、専門性に応じたカスタマイズ学習、継続的なフォローアップ体制など、各社が直面していた具体的な課題と解決策が詳しく紹介されています。
これらの成功事例から、自社の人材育成課題に適した解決方法とeラーニング活用のポイントを見つけることができます。
インプット×アウトプット研修の効率化でBtoB人材育成を推進|株式会社エムエム総研様

BtoBマーケティング支援を行う株式会社エムエム総研様では、新規事業のインサイドセールス人材育成において研修プロセスの効率化が課題でした。独自の講義プログラムを開発し、社内ディレクターが講師を担当して体系化を進めていましたが、さらなる効率化を求めて新たなアプローチが必要でした。従来のインプット×アウトプットの講義スタイルにおいて、より効果的な教育手法の検討が急務となっていました。
AirCourseの直感的なUI・UXと独自コンテンツ作成機能を活用し、インプット部分のeラーニング化によるブレンディッド研修を実現しました。オンライン×オフラインの組み合わせにより、運用サイドが簡単に講義プログラムをeラーニング化することに成功。受講者にとっては「繰り返し、いつでも復習できる」メリットが生まれ、従来の座学形式では実現できなかったオンライン化の利点を活用しています。AirCourse研修ナビ機能を通じて、外部ユーザー企業へのBtoBマーケティングノウハウ提供も構想しています。
導入後の主な成果
- インプット部分のeラーニング化でブレンディッド研修を実現
- 運用サイドが簡単に講義プログラムをeラーニング化することに成功
- 受講者の復習機会向上により学習効果とノウハウ定着が改善
参考:業界でも類を見ないBtoBマーケティング人材の育成から提供|株式会社エムエム総研様 AirCourse導入事例
カナツアカデミー発足でOJT効率化と技術継承を推進|カナツ技建工業株式会社様

総合建設業を展開するカナツ技建工業株式会社様では、「一人前になるには10年」といわれる建設事業において、社員の高齢化が進む中でいかに効果的な技術継承を実現するかが重要な課題でした。従来のOJT中心の指導では限界があり、今のうちにノウハウをきっちりと教育できる仕組み整備が急務となっていました。人材育成・人づくりを目的としたeラーニングシステム活用によるOJT効率化が検討されました。
「カナツアカデミー」を発足し、各部門から選出されたメンバーが講師となってオリジナルコースを作成する体制を構築しました。土木部門の新入社員教育など、現場で必要な内容をeラーニング化し、現場への取材・撮影からPowerPointスライドや写真を用いた作り込みまで自社で実施。動画冒頭にはカナツアカデミーのロゴを表示するなど、品質にこだわったコンテンツを制作しています。アカデミーメンバーの活動は考課で評価し、受講側も各コースの受講歴をもとに評価する仕組みを整備しています。
導入後の主な成果
- カナツアカデミーによる社内横断的な人材育成体制を確立
- 自社制作オリジナルコンテンツで現場に即した実践的教育を実現
- 受講者からの高評価により若手の早期育成効果に期待
参考:未来を創る人材育成のためにeラーニングを活用|カナツ技建工業株式会社様 AirCourse活用事例
階層別研修の体系化で組織力強化|医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様

福岡徳洲会病院様では、24時間体制の医療現場において「時間的制約による教育機会格差」と「職位に応じたスキル体系の未整備」が人材育成の課題でした。集合研修では全職員への平等な教育提供が困難で、特に事務職員に求められるスキルの高度化に対応した体系的な教育プログラムが不足していました。
eラーニングを活用した階層別研修システムを導入し、役職ごとに必要なスキルを明確化した体系的な人材育成を実現しました。課長クラスには経営視点(アカウンティング、KPI管理)、係長クラスにはチーム運営スキル(リーダーシップ、フォロワーシップ)、主任クラスには実務効率化(Excel統計)など、段階的なスキルアップを支援。マイクロラーニング形式により、忙しい医療現場でもスキマ時間を活用した継続的な学習が可能になりました。
導入後の主な成果
- 階層別研修による体系的なスキルアップで組織力を強化
- 24時間体制の職場でも公平な学習機会を全職員に提供
- マイクロラーニングによるスキマ時間活用で学習継続率が向上
参考:医療現場の教育課題を解決!マイクロラーニングで実現する効率的な人材育成|医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様 AirCourse活用事例
導入から運用まで失敗しない育成スキームを選択しよう
オフラインでの育成だけでなく、リモートワークも普及した現代ではオンラインとの掛け合わせや、オンライン完結での育成など多様な手法が広がっています。
より自社に適した育成の取り組みを行うためにも、ケース別の育成モデルや企業の成功事例を参考にしてみましょう。
以下資料では、これまでの育成モデルの変遷や、オンラインでの人材育成を推進するためのポイントを、企業事例も交えて解説しています。どなたでも無料でダウンロードいただけますので、自社で取り組む際の参考事例としてぜひご活用ください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。