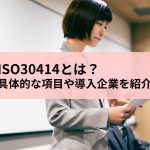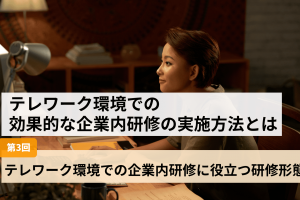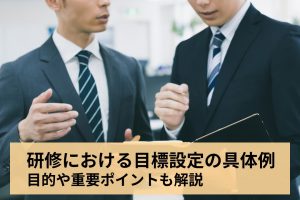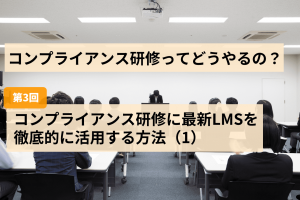企業にとって、新入社員の社会人としての一歩を支える“新入社員研修”は、その後の業績や社員満足度に直結する重要なプロセスです。
また、人事担当者が適切な新人研修を検討・実施することで、即戦力となる人材を作り上げ、企業に大きく貢献できます。
しかし、いままで新人研修を実施したことがない、もしくは自社に新人研修の前例がない場合は
「そもそも新人研修にどんなメリット・デメリットがあるのかわからない」
「どんなテーマを取り扱い、どのように研修計画を立てればよいのかわからない」
とお困りではないでしょうか?
そこで本記事では、新入社員研修のメリット・デメリットや具体的な研修方法、取り扱うべきテーマや計画の立て方、新入社員研修育成のコツや成功事例を紹介します。
効果的な新人研修を実施して、社員のスキルアップや即戦力の育成につなげて会社に貢献したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
新入社員研修育成の重要性
新入社員研修は、業務知識、コミュニケーションスキル、エチケットなど、社会人として身につけておくべき基本的な能力の向上はもちろんのこと、組織の文化や価値観の理解にも役立ちます。
そのため、業務を遂行できる力をつけるとともに、自社の目標や理念に共感して組織として同じ方向を見て働けるようになります。
結果として、新入社員は自身の仕事が企業全体の目標達成にどのように貢献するかを理解し、自己実現と企業の成長を両立する力を育むことが可能となるのです。
新入社員研修のメリット
まずは、新入社員研修のメリットについて解説します。主なメリットは以下の3つです。
早期戦力化
新入社員の育成においてぶれてはならない軸は、新入社員に早く会社の戦力になってもらうことです。適切な新入社員研修を実施しつつ、育成担当者は新人に対して効果的なサポートを行うことで早期戦力化を図れるでしょう。
しかし、新入社員が入社した後の数ヶ月間は、人事担当部署が預かって研修など行う場合は十分注意が必要です。人事担当部署と新入社員のみでは、学校の先生と学生のような関係になりやすいため、育成方法を誤ると新入社員が社会人の自覚を持つまでに余計な時間がかかります。
そのため、会社から給料(報酬)をもらって働くという意味を理解してもらい、浸透させることが早期戦力化には欠かせません。
離職防止
効果的に新人研修を実施することで、離職の防止につながる点も大きなメリットの1つといえます。
しっかりと企業努力を欠かさずに新人研修を実施すれば新人と企業、もしくは新人と上司間で信頼が生まれ、働きやすい環境を構築できるのです。
そのため、「採用や育成にかかったコストが無駄になる」「新入社員の育成や世話にかかった労力が無駄になる」「再度一から採用活動をしなければならない」といった早期離職によるリスクを軽減して生産性の向上につなげられるといえるでしょう。
モチベーション維持・向上
基本的に新入社員は会社に希望を持って入社してくるため、入社時点ではモチベーションが高い傾向にありますが、入社後に会社の雰囲気や業務内容などを知ることで、入社前に抱いていた希望とのギャップからモチベーションを下げる社員もいるでしょう。
しかし、新人研修を適切に行っていれば、自分の立場や役割を理解したうえで、明確化した目標に向かって進めるためモチベーション維持・向上ができるのです。
また、育成担当者は新入社員の状態に応じたフォローを徹底して、頑張った先の未来を示しながら新入社員に希望を持ってもらえる環境を整えてあげられると、よりモチベーション維持・向上がしやすくなります。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
新入社員研修のデメリット
ここまで、新人研修のデメリットについて解説してきましたが、新人研修にはデメリットも存在します。
ここからは、そんなデメリットを2つ解説していきます。
講師を担当する社員への負担
新人研修を実施するには、講師となる社員が不可欠となります。
また、普段の業務とは別に、新人研修に関する工数や労力を多く必要とし、その負担は決して軽いものではありません。
例えば、研修プログラムを設計するためには、新入社員が必要とするスキルや知識を把握し、それを効果的に教えるためのカリキュラムを組む必要があります。これには専門的な知識だけでなく、教育のスキルや経験も求められます。
他にも、新入社員へのフォローやフィードバックを行うためには、講師自身が新入社員と密接にコミュニケーションを取り、彼らの成長を見守り続けることが求められるため、講師を担当する社員には大きな負担がかかってしまうのです。
そのため、どうしても自社の社員を講師に抜擢する余裕がない場合には、講師を外部委託することも検討できるとよいでしょう。
研修の質の担保が困難
研修の質の担保の難しさも、新人研修のデメリットのひとつです。
研修プログラムが一定の成果を上げるためには、講師のスキルや経験、そしてその教材の質が求められますが、これらを常に一定のレベル以上に保つことは容易なことではありません。
特に講師のスキルや経験に関しては講師ごとに大きく異なるため、場合によってはレベルの低い新人研修となってしまう可能性もあります。
常に研修の質を担保した状態で、一定の成果を上げたい場合にはeラーニングを活用し、講師によって左右されない教育環境を整備してあげられるとよいでしょう。
新入社員の具体的な研修方法
新入社員の具体的な育成方法は、以下の5つです。新入社員の人数や会社のバックアップ体制などを加味しながら、育成内容を使い分けてみてください。
集合型研修(座学研修)
1つ目は、集合型研修(座学研修)です。集合型研修は、研修対象者を一つの会場に集め、社内外から選抜された講師が直接教える研修方法です。
集合型研修を行うメリットは、以下の3つなどがあります。
- 体系的な学習に向いている
- 新入社員のモチベーションの向上が期待できる
- 会社側としても一斉に研修できるため時間効率がよい
このため、集合型研修は初期の段階に向いている育成方法といえるでしょう。集合型研修を利用して会社の理念や社会人の心構えなどを教えつつ、社員同士の交流の場を設けることで新入社員の帰属意識を高められる効果があります。
ただし、集合型研修の注意点も抑えておく必要があるでしょう。集合型研修は実務の場ではないため、集合型研修で優秀だと会社が評価する社員が、必ずしも実務で高いパフォーマンスを発揮するとは限りません。集合型研修での評価は、あくまで参考程度にみておきましょう。
また、集合型研修の内容と現場の状況にあまりにもギャップがあると、新入社員のモチベーション低下に繋がる可能性があります。そのため集合型研修を実施する場合は、最終的に現場へスムーズに橋渡しできることをイメージして組み立てることをおすすめします。
オンライン研修
2つ目は、オンライン研修です。オンライン研修は、研修対象者を1ヶ所に集める必要がない上にリアルタイムで研修できることから、特にコロナ禍以降は集合型研修の代わりに多く採用されている研修方法です。
PCがあればどこからでも研修可能なため、新入社員の移動にかかる時間やコストを削減でき、効率的な研修が可能となるでしょう。
ただし、オンライン研修は臨場感がないため、受け身になりやすくモチベーションの向上に繋げにくいのが注意点です。オンライン研修を実施する場合は、新入社員が発言する機会を意識的に設けるなどの工夫が必要となるでしょう。
OJT制度
3つ目は「OJT制度」ですが、まず「OJT」から簡潔に解説します。
OJTとは「On the Job Training」の略で、実践を通して仕事のスキルを身につける手法のことです。新入社員に実務を教える先輩や上司のことをOJT担当者と呼び、教える行為をOJTと呼ぶことが多いです。
OJTは、経験豊富なOJT担当者のもとで、座学研修では学べない知識や経験が得られるため、新入社員がひとり立ちをするまでの過程で最も重要な育成方法の1つだといえます。
ただ、従来のOJTではOJT担当者の経験値や育成スキルに委ねられるため、どうしても研修品質にムラが出てしまいます。それにより、会社が求める教育が行き届かないことから新入社員が辞めてしまうなどの障害が生じやすいのもOJTの難点です。
そのため、OJTを現場任せにするのではなく制度化すること、つまり「OJT制度」を確立することでOJTの品質を会社が担保するのです。
メンター制度
4つ目は、メンター制度です。メンター制度とは、経験値のある先輩社員がメンターとなり、新入社員に対してキャリアにおける課題やメンタル面の支援などを行う制度です。
メンターは、新入社員とは部署が異なる先輩社員が担当するのが一般的です。また、社歴や年齢が近い先輩社員が担当することが多いため、新入社員が安心して相談できる環境となり、先輩社員としても新入社員特有の悩みなどを想像・共感しやすいといった利点があります。
とはいえ、メンターである先輩社員の負担が増すことに加え、相性によってはメンター制度のメリットを活かせないデメリットも持ち合わせています。
そのため、メンター制度を効果的に活かすためには、先輩社員と新入社員双方を必要に応じてサポートする上司の存在が欠かせません。メンター制度を導入したとしても決して放置しないよう注意が必要です。
eラーニング
eラーニングとは、ネット上で研修、アンケート、理解度テストなどを実施できる研修ツールのことです。スマホやパソコン1台あれば場所や時間に縛られずに実施可能なことから、とても効率のよいツールだといえます。
ネット環境さえあればいつでもどこでも受講可能なため、受講者側は空き時間などを活用できます。開催側も受講案内のみで、研修のために参加者全員のスケジュール調整を行う必要もありません。
「新入社員の育成ツールの幅を広げたい」という課題の解決策になるでしょう。
eラーニング成功のコツは”導入設計”にあります
eラーニングの基本的な仕組みは理解できても、実際に成果につながる運用を継続することは簡単ではありません。多くの企業が「導入したが受講率が低い」「コンテンツ作成に時間がかかりすぎる」「効果測定ができない」という課題に直面しています。
これらの課題解決には、単なるシステム選定ではなく、学習文化の醸成から効果測定まで含めた包括的な導入戦略が不可欠です。成功企業では、5つのステップで段階的にeラーニングを組織に定着させ、継続的な学習環境を構築しています。
戦略的な視点からeラーニング活用を推進する、体系的な導入アプローチを学んでみませんか。
新入社員の育成で取り扱うべきテーマ
ここからは、新入社員の育成で取り扱うべきテーマを解説します。
ビジネスマナー
新入社員の育成テーマの中でも最初に身につけてもらうべき項目と位置づけられるのがビジネスマナーです。新入社員が社会人としてのキャリアに躓かないためにも欠かせません。
社会人になると社内の同僚や先輩、社外のクライアントや協力会社など、さまざまな人とのかかわりを持つことになります。このときに、ビジネスマナーが身についていないと相手からマイナス評価を受けてしまい、あらゆる場面で機会損失を招きかねません。
また、ビジネスマナーを理解していない社員が対外交渉の場に出ることで、会社の評価も下がってしまうのも注意点の1つです。
新入社員のキャリア形成のためにも、会社の生産性を高めるためにも、新入社員にはビジネスマナーをしっかりと身につけてもらう必要があるでしょう。
具体的なビジネスマナーの項目は、以下などがあります。
- 挨拶
- 言葉遣い
- 電話応対
- 来客応対
- 名刺交換 など
ビジネスマナーの重要性をしっかりと説いた上で育成していきましょう。
ビジネスマインド
ビジネスマナーと同様に教育しておくべき項目が、ビジネスマインドです。社会人としての心構えやタイムマネジメント、セルフモチベーションといったマインド面を教育し、社会人としての自覚を芽生えさせることが大切です。
授業料を払う対価として教育が受けられる学生と、誰かに価値提供する対価として報酬(給料)をもらう社会人では根本の考え方が異なります。
報酬をもらう立場である以上は自分で自分を監督する力が求められます。こうしたビジネスマインドの重要性を説いていき、自立を促していくことが新入社員の育成では大切です。
コミュニケーション
コミュニケーションの大切さ、コミュニケーションの取り方を教えることも新入社員の育成で外せないテーマの1つです。
コミュニケーションは、相手との意思疎通を図るためであったり、目的を達成させるためであったりなど、あらゆる場面で必要となります。
実際に、順調にキャリアを重ねている人ほどコミュニケーション能力が高い傾向にあります。なぜなら、コミュニケーション能力が高い人は、他者の求めるニーズを適切に捉えられる上に、過不足なく正確なやり取りができるためです。それにより、周囲に多くの価値提供ができることから信頼される人材となるのです。
しかし、コミュニケーション能力はあくまで天性のものであり、鍛えられるものなのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、仕事に必要となるコミュニケーション能力は訓練によって鍛えることが十分可能です。
仕事におけるコミュニケーションスキルとは、仕事の目標や目的を達成するために必要なスキルを指すため、誰とでも気軽に仲良くなるスキルのようなものとは性質が異なります。
したがって、育成の内容としては以下となります。
- 報連相の重要性やその方法
- 相手への伝え方と聞き方
- プレゼンや発表のコツ など
このように、仕事で必要になるコミュニケーションの要素を中心に教えていくとよいでしょう。
また「明るくて話し上手な人=コミュニケーションスキルが高い」というわけではないことへの理解が大切です。相手の気持ちを汲み取ることが円滑なコミュニケーションには欠かせません。そのため、むしろ聞く能力を高めるほうが重要ともいえるでしょう。
ビジネス文章の書き方
ビジネス文章の書き方を教えることも重要な項目の1つです。代表的なビジネス文章はEメール、企画書、稟議書の作成などがあります。また、グループウェア機能を導入している会社であれば回覧板やメッセージの作成なども必要です。
ビジネス文章の書き方は、家族・友人と連絡ツールを使ったやり取りや日記などとは大きく異なります。そのことを新入社員に意識づけする必要があるでしょう。
ビジネス文章の書き方で大切なポイントは、以下の3つです。
- 正しい敬語を使うこと
- TPOをわきまえること
- 伝わりやすさを意識すること
まずは、これらを常に心がけながら文章作成するよう意識づけするとよいでしょう。また、新入社員が作成したビジネス文章を添削してフィードバックすることで、文章作成スキルの飛躍的な向上が期待できます。ぜひ参考にしてみてください。
ITスキル
会社や配属部署により程度の差はあるものの、現代ではパソコンを使用して業務を行うケースが増加傾向にあるため、ITスキルを高めるのも必須項目の1つとなっています。
教育の範囲としては、IT領域にかかわる企業でなければ、基本的なパソコンや社内システムの操作方法を理解させる程度で問題ないでしょう。
ITスキルについては、若年層のほうが順応性が高い傾向にあるため、基本的な操作方法を教えてしまえば、あとは実務のなかで必要となるスキルを習得してくれます。
また、IT関連の業務を教える際には、情報漏洩などのリスクを排除するための情報管理方法
についてもしっかりと伝えるようにしましょう。
新入社員研修の具体例
新入社員研修は、企業によって実施項目が多種多様です。期間もおよそ2週間〜3ヶ月とバラつきがあり、より短い場合は1週間以内、長い場合は1年以上というケースもあります。短期の場合は集合型研修が中心で、実践研修は配属後、長期の場合は現場での実践研修まで含むパターンが多いでしょう。
ここでは、社内での集合型研修で2週間(10日間稼働)の研修を想定して作成しました。各項目は引用しやすいように一般的な内容で構成していますが、期間の取り方や研修の順番は目安ですので実状に応じて調整してください。
1日目(入社式後~):会社の全体像
- 会社の理念、行動規範、歴史など
- 自社の組織構造(部署や部門の概要)
- グループ会社、協業企業、競業企業の説明
- 就業規則(概要とポイント)
- 試用期間から正社員までのフロー
- 事務手続きの説明(交通費精算など)
- 以降の研修スケジュールの説明
- 研修日報を作成する際のポイントを説明(報告書の書き方)
- 各自にて研修日報作成と提出(質問の受付)
2日目:学生から社会人へ
- 前日の振りかえり+研修日報で質問があれば回答
- 研修の目的・趣旨を説明
- 研修への心構えを発表(例:研修後どうなっていたいか)
- 社会人としての心構え
- 学生と社会人の違い「グループワーク+発表」
- 社会人としてのルール(コンプライアンスとは、SNSの使い方など)
- 職場のルール(出勤時、勤務中、休憩中、退勤時)
- 各自にて研修日報作成と提出(質問の受付)
3日目:ビジネスマナー(1)
- 前日の振りかえり+研修日報で質問があれば回答
- 身だしなみ、第一印象の大切さ
- あいさつ「ペアになって相互チェック」
- 表情、態度「同上」
- お辞儀の種類とポイント「同上」
- 言葉づかい、敬語「演習問題」
- 各自にて研修日報作成と提出(質問の受付)
4日目:ビジネスマインド
- 前日の振りかえり+研修日報で質問があれば回答
- 主体性(自ら考えて動くこと)の大切さ
- ビジネスマインド(目的意識、責任感、協力意識)
- 社会人基礎力※の説明
- 社会人基礎力の自己分析(長所と短所の自覚)
- 各自にて研修日報作成と提出(質問の受付)
※参照:厚生労働省「社会人基礎力」
https://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/
5日目:仕事の進め方
- 前日の振りかえり+研修日報で質問があれば回答
- 仕事の全体イメージ、進め方
- 報連相の重要性、分かりやすい報連相「ケーススタディ(実例や事例で演習)」
- PDCAの回し方(実例や事例の紹介)
- 各自にて研修日報作成と提出(質問の受付)
6日目:ビジネスマナー(2)
- 前日の振りかえり+研修日報で質問があれば回答
- 電話応対の基本(組織の代表である自覚、声のトーンなど)
- 電話の受け方とかけ方「ケーススタディ」
- 伝言の書き方
- 電話応対の実践「実際の電話を受けてみる」
- 来客応対の心構えと基本
- 席次(会議室、車、エレベーターなど)
- ご案内の仕方「ロールプレイング」
- お見送りの仕方
- 訪問時の基本マナー
- 名刺交換「ロールプレイング」
- 各自にて研修日報作成と提出(質問の受付)
7日目:パソコン基本操作
- 前日の振りかえり+研修日報で質問があれば回答
- 社内で使用する主要システムやソフトの説明「実践演習」
- パソコンやネットワーク使用上の注意(セキュリティへの意識)
- メールの基本(電話との違い、用途)
- メールの送受信(toやccの使い分けなど)
- メールの書き方「ケーススタディ」
- 封書の送り方「ケーススタディ」
- 各自にて研修日報作成と提出(質問の受付)
8日目:各部署・部門からの説明
- 前日の振りかえり+研修日報で質問があれば回答
- 各部署ごとに上長や先輩社員から役割や業務の説明
- 先輩社員の体験発表、後輩へのメッセージ
- 各自にて研修日報作成と提出(質問の受付)
9日目:社内および現場見学
- 前日の振りかえり+研修日報で質問があれば回答
- 社内および現場を見学(学んだあいさつや名刺交換の実践も兼ねる)
- 各自にて研修日報作成と提出(質問の受付)
10日目:まとめ・補足
- 前日の振りかえり+研修日報で質問があれば回答
- 全体の振り返り
- 各自から研修の感想と今後の抱負を発表
- 今後の流れについて説明
- 各自にて研修日報作成と提出
その他ポイント
- 休憩は定期的に設ける
- アイスブレイクは受講者の状況をみて適宜行う(朝一番や昼食後がおすすめ)
- スケジュール調整の可能性もふまえて、後半や最終日には余裕をもたせておく
- 日報は配属予定先の上司へも日々共有する
- eラーニングを用いれば「予習・当日の上映・復習・フォロー研修」が可能
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
新入社員研修のコツ
ここからは、新入社員研修のコツを解説します。
考える機会を与えて意見を尊重する
新入社員の成長を促すには、考える機会を与えて意見を尊重することが重要です。
仕事においては正解が決まっていない事柄に取り組む機会が多々あるため、自分の力で問題解決する力が求められます。問題解決能力を育むことは、本人の自信を高める効果と企業価値の向上の両面から見て重要なポイントだといえるでしょう。
そのためにも、本人の意見を尊重して自分で考える楽しさを覚えてもらうことが大切です。
仕事の意義や目的を認識させる
仕事の意義や目的を認識させるのも重要な要素の1つです。具体的には、会社の理念を浸透させることと本人のキャリアビジョンの確立を支援することが重要だといえるでしょう。
生活のためだけではなく「やりがい」や「他者貢献」などを仕事に見いだせたときに、新入社員が飛躍的に成長するポイントがあります。ただ、これらは一朝一夕では育まれないため、常に会社が新入社員に伴奏する意識が大切です。
仕事の意義や目的を認識できた新入社員は自走してくれるようになるため、育成担当者としても1つの目標において取り組むべき項目だといえるでしょう。
気軽に相談できる窓口を設けておく
気軽に相談できる窓口を設けておくのも大切です。社会人経験のない新入社員はすべてが新鮮に映っている反面、これまで抱えたことのないストレスを感じる時期でもあります。
新入社員の段階では、自分でストレスを解消する引き出しが少ない傾向があるため、一度抱えた悩みに耐えられずに辞めてしまうケースもあるでしょう。
このときに、気軽に相談できる窓口を設けておくことで、新入社員が悩みを抱え込むのを防止できる効果が得られます。また、新入社員の悩みに向き合う方法としてメンター制度を導入するのも有効な手段の1つです。
本人への期待を示す
本人への期待を示すことも重要なポイントの1つです。周囲からの期待が高いと本人が認識することでモチベーションの向上や自信に繋がり、成長速度が上がるでしょう。そのため成果にもよい影響を及ぼします。
反対に、本人が期待されていないと感じたときはモチベーションの低下や自信喪失を招くため、適切なフォローが必要です。
このように、本人への期待を示すことは重要ですが、プレッシャーにならない程度にする見極めも欠かせません。
本人への期待を示す効果については、別記事にて詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
【関連記事】ピグマリオン効果とゴーレム効果の違い|ビジネスでの活用と注意点
効果的な学習手法を取り入れる
新入社員の教育においては、参加者の業務スケジュールとの調整が課題となることがあります。特に、新入社員は業務に慣れていないため、研修への参加が負担になりがちですが、受講形式を工夫することで参加者のニーズを満たすことができます。
例えば、「eラーニング」を導入すると、新入社員が自身のスケジュールに合わせて好きな時間に受講でき、受講負担を軽減することが可能です。
さらに、eラーニングの一手法として注目を集めている「マイクロラーニング」を活用すると、受講効率が大きく向上するためおすすめです。マイクロラーニングとは、5分~10分といった短時間での学習スタイルのことを指します。短いコンテンツで学習するため、受講者はスキマ時間を活用して効率的に学習できます。
昨今のビジネス環境では、新入社員が日々の業務に忙殺されることが多く、まとまった学習時間の確保が難しくなっています。移動中や休憩時間といった「スキマ時間」にサクッと学びたいというニーズが高まっており、マイクロラーニングは、こうした昨今のビジネスマンの行動様式に対応できる学習手法として注目されています。
マイクロラーニングのコンテンツは学習内容が細分化されており、受講者は集中力やモチベーションを維持しやすく、短時間の集中した学習によって記憶の保持につながりやすいのも特徴です。反復学習や確認テストなどを組み合わせると、より効果的に知識を定着させることもできます。
マイクロラーニングについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
【関連記事】マイクロラーニングとは?導入メリットや定着率向上のポイントを解説 | 人材育成サポーター
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
新入社員研修の成功事例
先述した通り、研修の主なデメリットとして「講師を担当する社員への負担」「研修の質の担保が困難」の2つが挙げられますが、そのどちらもeラーニングを活用することで解消できます。
ここからは、eラーニングを活用して社員の育成に成功した事例について紹介します。
eラーニングが新規事業推進の重要インフラの1つに|株式会社エムエム総研
株式会社エムエム総研は、クリエイティブ制作、WEB支援、テレマーケティング、メディアプランニング、イベント企画など、マーケティングにおける複合的な要素をワンストップで支援する、BtoBマーケティングに特化した企業です。
最近では新規事業の根幹である、インサイドセールス・デジタルマーケティングのノウハウを伝え、インサイドセールス人材の育成に力を入れていましたが、事業拡大に向けて人材の工数確保や継続的な育成が課題となっていました。
そこで、eラーニングシステムを導入し、効果的な講義プログラム受講体制を確立。
その結果、ノウハウを伝える側の大幅な工数削減と継続的な社員の育成が可能となり、理想的な社内体制の構築が実現しました。
【事例記事】マーケティングで「はたらく」を変える。│エムエム総研様導入事例
eラーニング導入で新人教育の負担軽減とスペシャリスト育成の高速化を|株式会社フィールドパートナー
株式会社フィールドパートナーは土壌汚染問題に向き合い、さまざまなリスク分析・評価しながら土壌汚染の専門家として課題を解決し続けてきました。
しかし、土壌汚染という「ニッチ」な業界であるため、経験者や有識者が少なく、どうしても未経験の社員を採用せざるを得ない状況のなか、事業の成長スピードに合わせて未経験者を即戦力にする方法の検討が求められました。
そこで、コストパフォーマンスや使いやすさといった観点からeラーニングシステムを導入し、優れた自社オリジナルコンテンツの作成や学習管理を徹底し、業務に関する学習を習慣化させています。
今後の展開として、「研修コースを作成し、受講の指示をする強制的な教育だけではなく、eラーニングシステムのコース作成(動画共有)の権限を現場の社員にも与え、現場で行っているOJTにeラーニングを活用したり、現場で日々培われているノウハウを共有したりするツールとしても活用していきたい」と語っています。
【事例記事】スペシャリストに最速で育成するプロセス構築に向けて│フィールドパートナー様導入事例
eラーニングで研修の「場所と時間」の問題を解決|株式会社MS-JAPAN
管理部門(経理・財務・人事・総務・法務・経営企画等)、スペシャリスト(公認会計士・税理士・弁護士・金融専門職)に特化した人材紹介サービスを提供し、人材紹介サービス業界内で独自のポジショニングを確立している株式会社MS-JAPAN。
2016年の東証マザーズ上場から約1年で東証一部に市場変更も達成しており、その後は業務拡大や社員数の増加、株式上場で組織の体制は大きく変化しました。
そのような社内体制のなか、社員の教育は不定期に集合研修をしたり、社員が作成したマニュアルをもとにOJTをしたりしているのみで、危機感を感じる方から不安の声が上がりました。
そこで階層別の研修制度を整えるために、月額制で受け放題の集合型研修のサービスを利用を開始しましたが、特に外回り中心の営業スタッフは勤務の時間や場所も不規則なため、全く研修が受講できず、内勤の従業員との間で教育格差が生じてしまっていたのです。
このような「場所と時間」の問題を解消するために、eラーニングシステムの『AirCourse』を導入し、企業理念やビジョンの共有、社内ナレッジ共有も独自の研修として作成しました。AirCourseでは、独自のeラーニングを簡単に作成できるため、研修受講者・管理者ともに使いやすいことが導入の決め手となったと語っています。
また、AirCourseには「標準コース」という作成済みのビジネス研修コースが備わっているため、ビジネススキルの研修や新人向けの研修など汎用的な研修は作成する必要がなく、eラーニングの導入がスムーズに進む要因となっています。
【事例記事】eラーニングで研修の「場所と時間」の問題を解決|株式会社MS-JAPANMS-Japan
まとめ
本記事では、新入社員研修のメリット・デメリットや具体的な研修方法、取り扱うべきテーマや計画の立て方、新入社員研修育成のコツや成功事例を紹介しました。
新人研修は、社会人として身につけておくべき基本的な能力の向上や組織の文化や価値観の理解に大きく役立ちますが、そのためには自社の社員にとって効果的な方法で研修を実施しなければなりません。
場合によっては講師を外部に委託したり、eラーニングを活用したりするのもよいでしょう。
新入社員の段階でしっかりとした育成ができれば企業に欠かせない人材に育ちます。そのため、新入社員の育成は企業価値の向上には欠かせない命題だといえるでしょう。ぜひ、本記事を参考にして最適な新人研修を検討していただければ幸いです。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。