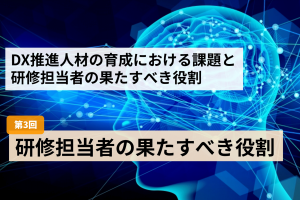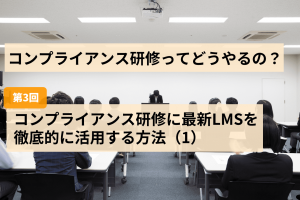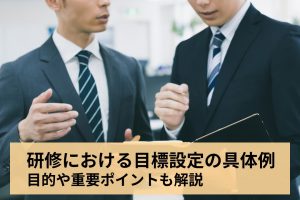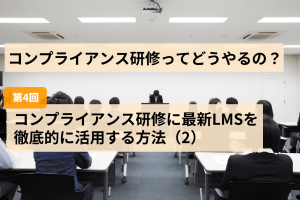社員研修に取り組む企業の多くが、その効果について悩みを抱えています。「研修を実施しているが成果が見えない」「受講者のモチベーションが低く定着しない」「研修内容が実務に活かされない」といった課題は、人材育成担当者が直面する共通の問題となっています。
これらの課題は、戦略的な社員研修の設計と体系的な運用により解決できます。社員研修とは、企業が社員のスキルや知識を向上させるために行う教育訓練で、新入社員向けのオリエンテーションやビジネスマナー研修から、中堅社員のスキルアップ研修、管理職のリーダーシップ研修まで多岐にわたります。
OJTや集合研修、オンライン研修、eラーニングなど、さまざまな形式で実施され、企業の競争力を維持・向上させるために欠かせない活動です。
社員研修は、単なるスキル伝達ではなく、組織の成長戦略と連動した重要な投資です。適切な目的設定、効果的なプログラム設計、そして継続的なフォローアップを通じて、社員の能力向上と企業の競争力強化を同時に実現している企業が増えています。
本記事では、社員研修の種類やテーマ例、効果的な進め方のポイントまで、実践的な研修運営に必要な情報を体系的に解説します。研修効果の測定方法や継続的な改善のコツも含め、自社に最適な社員研修の構築をサポートします。
効果的な社員研修で、組織の成長力を最大化しましょう。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
社員研修の見直しが必要な理由
社員研修は、企業の人材育成において重要な役割を担っています。
しかし、近年の急速な社会環境の変化に伴い、従来の研修内容や方法では、必ずしも十分な効果が得られなくなってきました。
企業が継続的に成長するためには、社員研修の在り方を見直し、時代に合った形に進化させていく必要があります。ここでは、社員研修の見直しが求められる主な理由について詳しく見ていきましょう。
働き方の多様化
働き方の多様化(テレワーク、リモートワーク、時短勤務など)に伴い、従来の一律的な社員研修では、全ての社員に効果的な学習機会を提供することが難しくなっています。
柔軟な受講が可能なeラーニングなど、多様な働き方に対応した研修形式への転換が求められます。
価値観の変化
近年、働き手の価値観が大きく変化していることも社員研修の見直しが必要とされる要因の1つです。
「生涯同一企業」から「キャリアアップ重視」へと働き手の価値観が変化しているため、社員研修も従来の「会社ルール習得」中心から「自己実現・スキルアップ支援」へとシフトしていく必要があります。
社員の価値観に合わせた研修は、満足度やモチベーション向上ひいてはパフォーマンスの向上にもつながります。
DX推進の必要性
DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、現代企業が取り組むべき最重要課題の一つですが、その実現には社員一人ひとりのスキルアップが欠かせません。そこで必要になるのが「DX推進のための社員研修」です。
この研修は、社員全員がDXの必要性を正しく理解し、DXを自身の課題として捉える意識を養うことを目的としています。
新しいツールを自身の業務に生かせる力を身につけるとともに、新しいビジネスモデルや働き方を生み出す可能性を感じ取る機会でもあります。
研修では、社員それぞれが自ら考え、提案できる「創造力」や「思考力」を鍛え、DXを活用した価値創造に貢献できる人材を育成することも重要なテーマとなっています。
社員研修の形式
社員研修を効果的に実施するためには、研修形式の特性を理解し、目的に応じて最適な方法を選ぶことが求められます。
代表的な研修形式には「OJT」と「Off-JT」の2種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、研修の目標や参加者の特性を考慮しながら、適切な形式を採用することが重要です。
ここでは、研修形式ごとのメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
OJT
OJTは職場内で行う教育訓練です。実際の業務を通じて実践的なスキルを身につけられるので実践に強いメリットがある一方で、指導者にリソースがかかる、指導者によって成果にばらつきが出る、教育効果の測定が難しいといったデメリットがあります。
研修後アンケート・理解度テストの実施なら「AirCourse」
研修後のアンケートや理解度テストの実施は、管理がしやすい「AirCourse(学習管理システム)」がおすすめです。
AirCourseなら、動画視聴後・集合研修後のアンケート・テスト実施が容易で、必要に応じて追加の学習や声かけを行うことができます。システムに標準搭載されているコンテンツに加え、企業オリジナルのコンテンツを作成・配信することが可能です。
自社の社員研修を実りあるものにしたい、さらにアップデートしたいとお考えの方はAirCourseが分かる下記資料をご覧ください。
Off-JT
OJTに対してOff-JTは、業務を離れて行う職場外研修です。社外に依頼する場合にコストがかかるデメリットはあるものの、教育内容が統一されるので、社内でのスキルや知識の均一化を図れるのが大きなメリットです。
Off-JT形式の研修には、次の3つの方法があります。
集合研修(座学研修)
集合研修または座学研修は、社員研修の基本形ともいえます。集合研修の一番の特徴は、全員が一斉に同じ内容を学べることです。
これにより、共通認識の形成や全体のスキルアップが期待できます。例えば、企業の理念や方針、新たなビジネス戦略などを社員一同に伝える場合に効果的です。
しかし、全員が同じテンポで学ぶため、個々の理解度に差が出る可能性もあります。そのため、集合研修の効果を引き出すには、質疑応答の時間を設けるなど、受講者の理解度や吸収度を確認することが必要です。
また、参加者全員が同じ場所に集まる必要があるため、地方拠点や海外拠点の社員が参加する際には出張や時間調整が必要になります。
オンライン研修
オンライン研修は、インターネットやweb会議システムなどを利用して行う研修です。近年では、新型コロナウイルス感染症の影響や時間・場所の制約をなくすために導入する企業が増えています。
主な特徴としては、以下の3点が挙げられます。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 柔軟性 | さまざまな場所からアクセスが可能 |
| コスト削減 | 会場のレンタル料や移動費などが発生しない |
| 安全性 | 集団での研修に比べ、感染症のリスクが低い |
ただし、物理的な距離があるため、参加者同士のコミュニケーションや、直接指導を受ける機会が少なくなるというデメリットもあります。
適切なツールを使用し、参加者同士の交流や、質疑応答の時間を設けるなど工夫しましょう。
eラーニング
eラーニングとは、パソコンやスマートフォンなどを使って、インターネット経由で学習を進める方法です。場所や時間を選ばず、受講者の都合に合わせて学習できるので、受講者がモチベーションを保ちやすい形式といえます。
また、受講者の学習状況を管理システム上で確認することができるため、進捗や理解度のチェックも容易です。
これらのデータは、自社の人材の傾向分析や教育施策の検討に活用することができるので、社員研修においても非常に効果的な方法といえるでしょう。
研修内で用いられる学習手法の種類
成果を高めるためには、研修内で用いる学習手法を適切に選択して組み合わせることも重要です。研修の目的や参加者の特性に合わせて、さまざまな学習手法を組み合わせれば、研修の効果を高めることができるでしょう。
ここでは、社員研修でよく用いられる学習手法を紹介します。
ロールプレイング
ロールプレイングは、社員研修において非常に効果的な学習手法です。具体的なシチュエーションを設定し、社員それぞれが役割を担いながら対話を展開することで、業務を想定した対応を体験できます。
例えば、新入社員向けのビジネスマナー研修では、先輩社員や上司、顧客などとのコミュニケーションを模擬体験することで、実際の職場で必要となるスキルを身につけることができるでしょう。
また、営業研修では、顧客との商談シーンを想定したロールプレイングが考えられます。具体的な商品説明や交渉技術はもちろん、臨機応変に対応を変える柔軟性や困難な状況に対する対処能力も養うことができます。
ロールプレイングは、自分がどのように振る舞うべきかを体感することです。実務に対する理解を深め、自己の行動改善に繋げる効果があります。
ただし、ロールプレイングを効果的に行うためには、専門知識を持った研修講師が進行・フィードバックを行える環境が必要です。
グループワーク
グループワークは、複数の社員でチームを組み、共通の課題を解決する活動です。
グループワークの最大の特徴は、コミュニケーション力やチームワークを鍛えられる点です。異なる意見を比較し、議論を重ねる過程で、思考力や表現力を磨きながら他者の理解も深めていきます。
また実際の業務では、個々の職務だけでなくチームとしての成果も求められます。グループワークは実務経験が少ない新入社員だけでなく、中堅社員や管理職にとっても有意義な学習手法といえるでしょう。
以下に、具体的なグループワークの例を挙げます。
| テーマ | ねらい | 内容 |
|---|---|---|
| 新製品企画 | 創造力・発想力 | 市場調査から企画提案まで |
| 社内改善案 | 問題解決能力 | 既存の問題を改善する提案 |
これらは参考例であり、目的や参加者のレベルによって、テーマや内容は無限に広がります。
自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう
クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。
階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。
個人ワーク
個人ワークは、講師の説明を聞くだけでなく、参加者一人ひとりが主体的に考え、課題に取り組む手法です。具体的には、個人で問題を解いたり、ケーススタディに取り組んだり、自己分析を行ったりします。
個人ワークの主な目的は、以下の3点です。
- 自分の考えを深める:個人ワークでは、自分の頭で問題を解決することが求められます。学んだ内容をより深く理解し、応用力を高めることにもつながります。
- 主体的な学習姿勢を養う:個人ワークは、受動的に講義を聞くだけでなく、自ら積極的に学習に取り組むことを促します。この経験を通じて、主体的な学習姿勢を身につけることができます。
- 実践的な問題解決能力を身につける:個人ワークで実際の業務で直面するような問題やケースを扱うことで、実践的な問題解決能力を養うことができます。
個人ワークを研修に取り入れることで、参加者の能動的な学びを促し、研修の効果を高めることができるでしょう。
チェックテスト
チェックテストは、参加者の理解度を測るだけでなく、学習内容がきちんと頭に残っているかを確認するためのツールです。
具体的には、研修の途中や終了時に、学んだ内容に関する問題を出題します。テスト形式はクイズ形式、記述形式、実技試験など、研修内容に沿った形式を選択するとよいでしょう。
例えば、新人研修でビジネスマナーを学んだ場合、クイズ形式で「ビジネスシーンにおける適切な言葉遣い」や「挨拶の仕方」について問うことができます。
また、商品知識を学んだ場合は、その商品の特徴や効果等について記述させることで知識の定着が可能です。
チェックテストでは、受講者の理解度や定着度がわかります。研修担当者にとってはフィードバックの一環として。研修内容の見直しや改善に活用できるでしょう。
課題・宿題
課題や宿題は、学んだ知識やスキルを自己のものにするための手段です。研修後も社員が独自に学習を進めるきっかけを作り、理解を深めるために有効な方法です。
具体的には、研修で扱ったテーマに関連する実践的な課題を与え、受講者が自分で考え、解決策を見出すよう促します。
例えば、マネジメント研修であれば、部下とのコミュニケーションを改善するための具体的な行動計画を立てる課題を出し、あるいは営業スキル研修で実際の顧客を想定したロールプレイングを課題とすることも有効でしょう。
研修効果を高めるためには、研修後に学んだ内容をいかに想起・実践させるかが重要です。そのための手段として課題・宿題を積極的に取り入れましょう。
【階層別】社員研修のテーマ・コンテンツ例
社員の階層(新入社員・中堅社員など)に応じて、必要とされる知識やスキルは異なります。
そのため、効果的な社員教育を行うためには、各階層に合わせた研修テーマやコンテンツを用意することが重要です。
ここでは、新入社員から管理職まで、階層別の研修テーマとコンテンツ例を紹介します。
また、Aircourseが提供するeラーニングコンテンツも併せてご案内しますので、自社の研修プログラム設計にぜひお役立てください。
新入社員向け
新入社員(入社1から3年目を想定)では、ビジネスマナーやビジネススキルの基礎を固めることが大切です。この時期に基礎を固めておけば、実践経験を重ねるごとに知識やノウハウの定着や強化、自ら振り返りを行えるようになります。
また初めての業務・慣れない業務に翻弄されがちな時期でもあるため、セルフマネジメントに関する知識の習得もおすすめします。
具体的には以下のとおりです。
- ビジネスマナー(挨拶、言葉づかい、敬語、電話応対、来客応対、名刺交換など)
- ビジネスマインド(社会人としての心構え、タイムマネジメント、セルフモチベーションなど)
- コミュニケーション(報連相、伝え方と聞き方、プレゼンや発表のコツなど)
- ビジネス文章の書き方(Eメール、企画書、稟議書など)
- ITスキル(パソコン操作、社内システム操作)
Aircourseでは、新入社員向けに以下のようなeラーニングのコンテンツを提供しています。
| 講座名 | 概要 |
|---|---|
| コミュニケーション講座(社内編) | 社内で必要なコミュニケーションの方法や目的を正しく学ぶことができます。具体的なスキルをケーススタディを交えてわかりやすく解説しています。 |
| 情報セキュリティ基本知識【入門編】 | 最新情報も反映したコンテンツです。以下の内容を学ぶことができます。・情報セキュリティで「何を」守るのか?・仕事やプライベートなどで具体的にやった方が良いこと、やってはいけないこと・新しく入社する社員全員が共通認識として持っておくべき知識 |
| 新人社員の名刺交換の基本 | 名刺交換の一連の流れをNG例、OK例の動画でわかりやすく学びます。 |
新入社員の育成については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:新入社員の教育方法|研修方法やテーマ、事例や成功のコツを解説
中堅社員向け
中堅社員(入社4年目以降を想定)は、業務にも慣れて独り立ちし、部下や後輩もできる頃です。中堅社員に対しては、組織の中枢を担うことの自覚や育成担当者としてのスキル向上、管理職候補としてのマネジメントスキル向上などが必要になります。
具体的には以下のとおりです。
- 担当業務の専門性向上(営業研修、技術研修など)
- メンター研修
- OJT研修(OJTトレーナーのための研修)
- マネジメント(管理職候補として)
- リーダー研修
- コーチング
- プレゼンテーションスキル強化
Aircourseでは、中堅社員向けに以下のようなeラーニングのコンテンツを提供しています。
| 講座名 | 概要 |
|---|---|
| リーダーシップトレーニング①:リーダーシップの基本知識 | 全4回のこのコースではリーダーシップの基本的な知識、概念を習得し、リーダーシップ強化の第一歩を踏み出すための実践トレーニングを行います。リーダーシップとは何なのかを明確にして、リーダーシップの強化の方向性を明確にします。 |
| 部下育成トレーニング①:部下育成の基本 | 部下育成トレーニングシリーズ(全5回)の第1回目のコースです。本コースでは、部下育成に関する基本知識を学び、効果的な育成をするためのマインドセットを実践的に行います。 |
| WIN-WINを実現する実践的交渉力:①交渉の基本知識 | WIN-WINを実現する実践的交渉力(全5回)の第1回コースです。交渉(ネゴシエーション)に関する基本知識を学び、仕事におけるさまざまな交渉場面に活用できる知識を理解できるようになります。WIN-WINの視点から社外との打ち合わせ、商談や社内の会議などで持つべき交渉の場面を想定し、その後、実践ワークを通じて、交渉の課題設定を行います。 |
中堅社員向けの研修については、以下の記事でそれぞれ詳しく解説しているので、研修プログラム作りの参考にしてください。
関連記事:OJTトレーナー研修とは?目的や実施メリット・デメリット、研修手順をご紹介
関連記事:メンター研修とは?必要性や効果、研修内容をわかりやすく解説
関連記事:リーダー研修とは?リーダーに必要な能力や効果的な研修内容を解説
自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう
クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。
階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。
管理職向け
管理職は、企業理念や経営層の経営方針やビジョンを正しく理解して、目標達成に向けマネジメントを行う立場です。
そのため、経営やマネジメントスキルに関するテーマが中心となります。
具体的には以下のとおりです。
- 経営戦略
- マネジメント(現役の管理職として)
- 目標管理
- 人事評価
- 部下育成
Aircourseでは、管理職向けに以下のようなeラーニングのコンテンツを提供しています。
| 講座名 | 概要 |
|---|---|
| 中堅・管理職のためのダイバーシティ講座_①今なぜダイバーシティなのかその意義を知る | 「ダイバーシティ=多様性を活かす」とは何なのか、その基本を適切に理解するとともに、ダイバーシティに着手・推進する意義を踏まえた具体策や行動へのマインドセットを整えます。 |
| ビジネスに役立つKPI分解の実践演習①KPIツリーの基礎とバランスト・スコアカード | データを可視化しビジネス成果につなげるためには、KPIという指標が欠かせません。本コースでは、KPIの必要性や、KPIツリーを作成する意図を学習します。また、KPIツリーを作成する際に意識したいバランスト・スコアカードについてもご紹介します。 |
| 【MBAシリーズ】経営戦略:001_経営戦略を学ぶ目的 | 本コースでは経営戦略を学ぶ目的を確認します。さまざまな業種・立場・状況の方が経営戦略を学びますので、本コースを参考に、自分なりの学びの目標を立てましょう。 |
全社員向け
階層や入社時期に関わらず、全社員が学ぶべきテーマもあります。ハラスメント関連やコンプライアンスなど、法令やモラルに関するものが中心です。
具体的には以下のとおりです。
- 各種ハラスメント
- コンプライアンス
- 情報セキュリティ
- チームビルディング
チームビルディングは全階層・全社員が参加するゲームやスポーツのようなエンターテイメント要素の強いものがおすすめです。社内のチームワークの向上や、コミュニケーションの円滑化に寄与します。
Aircourseでは、全社員向けに以下のようなeラーニングのコンテンツを提供しています。
| 講座名 | 概要 |
|---|---|
| 事例で学ぶ「しない・させない」ためのハラスメント総合研修 | 誰もが加害者にも被害者にもなる可能性を秘めている「ハラスメント」について、全社員共通の認識を持つことにより、しない・させない・ゆるさない職場づくりに役立てることができます。わかってるつもりのパワハラ・セクハラについて定義から学び、マタハラやセカンドハラスメントまで理解を深めます。 |
| ここが危ない著作権(著作物の引用・転載) | 業務の中に潜む著作権侵害の危険性をNG例の動画でわかりやすく学びます。 |
| 情報セキュリティの動向 | 本コースでは、情報セキュリティ対策の実態や、対策を怠ることで被る被害を、調査データや事例をもとに学習します。あわせて、情報セキュリティに関連する法律・認証の概略を学習します。 |
社員研修のステップ
効果的な社員研修を実施するには、体系的な設計プロセスが欠かせません。ニーズ分析から目標設定、計画策定、実施、効果測定までの一連の流れを適切に管理することで、個人と組織のニーズに合致した研修を提供できます。
各段階で重要なポイントを押さえながら、社員の成長と組織力の向上を目指しましょう。
ニーズ・課題の抽出
社員研修を設計する際に不可欠なのが、企業や組織のニーズと課題の抽出です。この段階では、「現状のスキルレベルはどうか」「何が足りないと感じているか」「これから必要となるスキルは何か」等を明確にすることが求められます。
課題抽出のためには、全社員を対象にスキルや知識の不足点や、研修の改善希望点を尋ねる「アンケート調査」や、上司・部下・同僚など複数人の評価者による授業員の評価を行う「360度フィードバック」などが有効でしょう。
これらはあくまで一例ですが、適切なニーズと課題の抽出を行い、それを研修の設計に反映させることで効果的な人材育成が可能となります。
研修目標の設定
研修を設計する際、研修目標の設定は重要なプロセスです。これは、研修を通じて達成したいスキル上達レベルや理解度を具体的に明示するものです。
目標設定が明確でないと、受講者が何をどこまで学ぶべきか、また、達成感を感じるための基準が曖昧になってしまいます。
具体的な設定方法としては、”SMART”原則が有用です。
- Specific(明確な):具体的に何をどの程度理解・習得するか。
- Measurable(測定可能な):達成度を測定できる具体的な指標を設ける。
- Achievable(達成可能な):現実的な目標を設定し、挫折しないようにする。
- Relevant(関連性のある):ビジネス目標や個々の職務と関連付ける。
- Time-bound(期限が明確な):達成までの期限を設定する。
これらを踏まえて設定した研修目標は、研修の振り返りを行う際にも重要な役割を果たします。研修は振り返りと改善を繰り返すことで、より良いものになっていきます。効果的な改善につなげるためにも、目標設定は慎重に行うようにしましょう。
研修計画の策定
研修目標の設定が完了したら、いよいよ具体的な研修計画の策定を行います。研修計画を立てる際は、以下のポイントを押さえると良いでしょう。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 研修の目的 | 抽出した課題やニーズに基づいて、作成・見直しを行う研修の目的を考えます。 |
| 研修のターゲット | 研修の対象となる参加者を明確にします。職種、役職、経験年数などを考慮して設定します。 |
| 研修の場所 | 研修を実施する場所を決定します。社内の会議室、外部の研修施設、オンライン上など、目的に合った場所を選びます。 |
| 研修の内容・テーマ | 研修の目的を達成するために必要な知識やスキルを習得できる内容を設定します。参加者のニーズや課題に合致したテーマを選定しましょう。 |
| 研修の日時 | 参加者のスケジュールを考慮しつつ、研修の目的や内容に適した日程と時間帯を設定します。 |
| 研修の形式 | 講義形式、グループワーク、ロールプレイ、e-ラーニングなど、研修の内容や目的に適した形式を選択します。 |
研修の実施
研修のコンテンツが固まったら、いよいよ本番の実施段階に入ります。研修を効果的に進めるためには、まず参加者全員に研修の目的や狙いを明確に理解してもらうことが不可欠です。
事前に目的などを伝えていたとしても、全員が完全に把握しているとは限りません。
そこで、研修の冒頭で、なぜこの研修が企画されたのか、これからの時間で何を学ぶのかを丁寧に説明することが重要です。これにより、参加者一人ひとりが研修の意義を認識し、共通の目標に向かって学習に取り組むことができるようになります。
効果測定
研修の最終段階に位置する「効果測定」は、研修の有効性を検証する重要な工程です。
まず、具体的な研修の目標に対して、その達成度合いを定量的に評価することが求められます。
例えば、営業スキル向上を目指す研修であれば、研修前後での売上実績の差分や顧客満足度の変動など、数値で捉えられる指標を用いて効果を測定します。
また、効果測定は参加者の視点からも行いましょう。研修終了後にアンケートを実施し、研修内容の理解度や満足度、今後の仕事への活用度などを確認します。
以下の表は、効果測定の一例です。
| 測定項目 | 測定方法 |
|---|---|
| 研修目標の達成度 | 定量的指標による評価 |
| 研修内容の理解度 | 参加者アンケート |
| 研修満足度 | 参加者アンケート |
より効果的な人材育成を行うためには、これらのデータに基づいて、研修の内容や進め方を改善していくことが大切です。
社員研修にeラーニングを活用した成功事例3選
社員研修の方法は多岐にわたりますが、近年ではeラーニングを取り入れ、社員研修を効果的に行なっている企業が増えています。eラーニングは時間や場所の制約を受けずに学習できる利点があり、社員のスキルアップや人材育成に有効です。
ここでは、実際にeラーニングを社員研修に活用している企業の事例を紹介します。
継続的呼びかけでリスキリング文化を構築|マグチグループ株式会社様

総合物流企業のマグチグループ株式会社様では、従来は体系だった研修がなく現場での作業を通じた学びが中心でした。物流業界特有の365日24時間稼働の中で、皆が集まっての研修実施は容易ではなく、指名制で各社から数名のみを集める形式では「学ぶ環境」の整備や「学ぶ風土」の醸成が困難でした。
2023年に経営方針として「リスキリングの浸透」を掲げ、抜本的な組織改革に取り組むこととなりました。
AirCourse選定の決め手は、多岐にわたるグループ企業に対応可能なコースの多さと、どの企業にとっても学びやすい豊富なコンテンツでした。
運用では「発信を途切らせないこと」を重視し、月次での朝礼時受講状況共有、執行会議での資料配信、戦略本部会議での活用状況報告など継続的な呼びかけを実施しています。経営層の理解を得て部門長経由での未受講者フォローアップ、個人面談による学習意欲向上など、組織一体となった学習文化の構築を実現しています。
【導入後の主な成果】
- 時間・場所を選ばない「学ぶ環境」をグループ全体に整備
- 受講必須コースの設定で多くの社員に「学ぶ習慣」を定着
- 継続的な呼びかけによる受講率の維持・向上を実現
24時間体制の医療現場で実現した公平な学習機会|医療法人徳洲会福岡徳洲会病院様

600床以上を有する総合病院として地域医療を支える医療法人徳洲会福岡徳洲会病院様では、約1,800名の職員を対象とした教育体制の強化が課題でした。24時間体制で運営される病院では、夜勤やシフト勤務により全職員が同じ時間に集まることが困難で、看護部、医療技術部、薬剤部、リハビリテーション科、事務部など多職種にわたる職員それぞれに適した研修を効率的に実施する必要がありました。
AirCourse導入の決め手は、スマートフォンでいつでもどこでも学習できる利便性と、豊富な標準コンテンツに加えて自社独自のコンテンツも配信できる機能でした。
現在は新入職員研修から管理職研修まで幅広く活用し、感染対策、医療安全、接遇など医療現場に必要な研修を体系的に配信しています。夜勤明けや休憩時間など個々のペースで受講でき、全職種に公平な学習機会を提供することで、医療の質向上と職員の成長を同時に実現しています。
【導入後の主な成果】
- 24時間体制でも全職員に公平な学習機会を提供
- 多職種対応の体系的な研修体制を構築
- 個々のペースでの学習により医療の質向上を実現
参考:医療法人徳洲会福岡徳洲会病院様のAirCourse導入事例
自主学習文化醸成でDX人材育成基盤を構築|エフエムジー&ミッション株式会社様

化粧品や栄養補助食品、ファッション関連品の製造・販売を行うエフエムジー&ミッション株式会社様では、マネジメント層から「各社員のボトムアップ」「マネージャー層の育成」「会社方針の理解度向上」といった要請が高まっていました。
しかし、既存のサービスでは受講履歴が残らないため受講管理ができず、DXやリスキリングへの対応や社員の意識付けも課題となっていました。
AirCourse選定の決め手は、料金の安価さとコンテンツの数・質の充実、そして自社作成動画を配信できる機能でした。
営業部門のセールス研修、階層別研修、会社方針に関するマネジメント層からのメッセージ配信など様々な場面で活用し、標準コンテンツと自社コンテンツを組み合わせた効果的な運用を実現しています。受講をKPIに含めて評価に反映させることで促進し、関連会社間でも共通コンテンツと各社独自コンテンツを柔軟に運用しています。
【導入後の主な成果】
- 「セルフラーニング・自己学習」の風土が形成され始める
- DXやリスキリングに対応するための基礎を構築
- 関連会社間での効率的なコンテンツ運用を実現
参考:エフエムジー&ミッション株式会社様のAirCourse導入事例
社員研修を効果的に行うためのポイント
ここまで、社員研修の形式や種類などについて詳しく解説してきましたが、既存の研修プログラムを惰性的に実行するだけでは、社員研修の成果を最大化することができません。ここでは、社員研修を効果的に行うためのポイントを紹介します。
事前にスキル・能力の現状把握を行う
効果的な研修を設計するには、事前に参加者のスキルや能力の現状を把握することが不可欠です。
具体的な方法として、スキルマップの作成が挙げられます。スキルマップとは、職種や役割ごとに必要なスキルを一覧化し、各スキルの習得度を評価したものです。
面談や過去の評価結果をもとに、参加者ごとのスキルマップを作成することで、個々のスキルレベルや強み、弱みを可視化できます。
このスキルマップを活用した現状把握によって、自社の課題やニーズに合致した研修プログラムを作成することができるようになるでしょう。
また、参加者自身も自分の課題を認識することで、研修への参加意欲を高めることができます。このように、スキルマップを用いた事前の現状把握は、研修の効果を最大限に引き出すための重要な基盤となるのです。
研修の意義を周知し参加へのモチベーションを高める
研修の成果を最大化するには、単に研修を受講するだけでは不十分です。社員自身が研修の意義を理解し、自発的に取り組む姿勢を持つことが重要です。
まず、研修の目的や目標を社員全体に共有することから始めましょう。それが業務にどのように活かせるのか、また自身のスキルアップにどうつながるのかを具体的に提示すれば、社員にとって研修がより身近で価値のある存在になります。
次に、社員のモチベーション向上には、研修の進行形式も大切です。
例えば、グループワークでの意見交換や、ロールプレイでの実践的な経験によって、学びの楽しさや達成感を得られるようにしましょう。
また、参加者の声を定期的に取り入れるフィードバックシステムも効果的です。研修後にアンケートを実施し、参加者の意見や感想を反映させることで、研修の質を高め、参加意欲を維持することできます。
このように、研修の意義を明確にし、社員のモチベーションを高める取り組みを進めることで、研修の効果をより高めることが可能になります。
優先順位をつけて研修を進める
社員研修は優先順位を付けて進めることも重要です。優先順位は「影響範囲」と「即効性」を考慮し、予算と人的リソースの制約内で決定しましょう。
一般的な企業の優先度は以下のとおりです。
| 対象者 | 影響範囲 | 即効性 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 役員クラス | 大 | 低 | 低 |
| 管理職・中堅層 | 中~大 | 中 | 高 |
| 若手・新人層 | 小~中 | 高 | 中 |
役員クラスの上位層への研修は、影響範囲は大きいものの実施が難しく、若手・新人層への研修は即効性は高いものの影響範囲は限定的です。
そのため、影響範囲と即効性のバランスが取れ、投資対効果が高いと考えられる管理職・中堅層への研修を優先的に実施することが推奨されます。
研修アンケートを実施し改善を繰り返す
社員研修では、研修効果を把握し、継続的な改善を図るために、研修後にアンケートを実施することが推奨されます。
具体的には、研修の内容、方法、講師の質、理解度など、さまざまな観点から参加者のフィードバックを得ることが重要です。
例えば、以下のような質問項目を設けてみます。
- 研修へ参加する前に悩んでいたことは何ですか?
- 研修に参加して何を得ることができましたか?
- 研修で学んだことを活かして今日からどんな行動をしますか?
- 今回の研修を100点満点で採点すると何点ですか?
- 研修の運営に関して、ご意見やご要望を教えてください
- 今後、受講したい研修のテーマを教えてください
このアンケート結果を基に、研修内容や講師選定の見直し、教材の改善などを行い、研修の品質向上につなげます。また、参加者の意見を反映させることで、より具体的なニーズに対応した研修を提供できるようになるでしょう。
研修アンケートの作り方については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:研修アンケートの項目例・作り方のコツを紹介【無料テンプレ付】
実践の機会を設ける
研修を成功へと導くために欠かせないポイントの1つが、実践の機会を設けることです。なぜなら、研修で得た知識が仕事の場で活かされなければ意味がないからです。
研修で得た知識を「知っている」状態から、「使える」状態へと引き上げることも研修担当者の重要な役割といえます。
具体的には、研修後にその内容を活用する機会をスケジュールに組み入れます。
例えば、営業スキル研修を受けた後は、実際に顧客へのプレゼンテーションをスケジュールすると良いでしょう。
また、実践の場を設けることは、研修の成果が目に見える形で現れるため、受講者に達成感や自信を与えることができます。これにより、学習意欲を高め、受講者のさらなる自己成長を促すことができるでしょう。
スキマ時間を生かした学習を取り入れる
社員研修を実施する際には、参加者の業務スケジュールとの調整が課題となることがあります。
特に、業務が忙しい社員の場合、研修への参加が負担になることもあるため、オンライン研修や動画教材を活用するなど、受講形式を工夫することで参加者のニーズを満たすことができます。
例えば、「eラーニング」を導入すると、社員が自身のスケジュールに合わせて好きな時間に受講でき、受講負担を軽減することが可能です。
さらに、eラーニングの一手法として注目を集めている「マイクロラーニング」を活用すると、受講効率が大きく向上するためおすすめです。
マイクロラーニングとは、5分~10分といった短時間での学習スタイルのことを指します。短いコンテンツで学習するため、受講者はスキマ時間を活用して効率的に学習できます。
昨今のビジネス環境では、社員が日々の業務に忙殺されることが多く、まとまった学習時間の確保が難しくなっています。
移動中や休憩時間といった「スキマ時間」にサクッと学びたいというニーズが高まっており、マイクロラーニングは、こうした昨今のビジネスマンの行動様式に対応できる学習手法として注目されています。
マイクロラーニングのコンテンツは学習内容が細分化されており、受講者は集中力やモチベーションを維持しやすく、短時間の集中した学習によって記憶の保持につながりやすいのも特徴です。
反復学習や確認テストなどを組み合わせると、より効果的に知識を定着させることもできます。
マイクロラーニングについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:マイクロラーニングとは?導入メリットや定着率向上のポイントを解説|人材育成サポーター
まとめ
効果的な研修には、事前の準備や工夫、実践機会の提供が不可欠です。具体的な事例も参考に、社員のスキル向上と、組織全体の成長につながる社員研修を計画・実施しましょう。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。