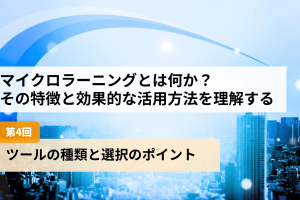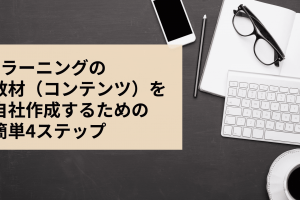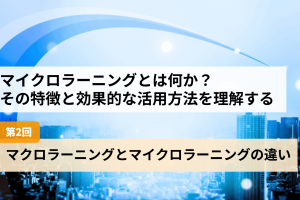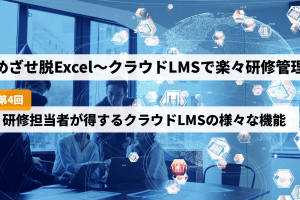eラーニングを導入したものの、「受講率は高いが実際にスキルが身についているかわからない」「テスト機能があるが効果的な活用方法がわからない」といった学習効果の測定に課題を抱える企業が増えています。
こうした課題は、 eラーニングテストの特性を理解し、戦略的に活用することで解決できます。 eラーニングテストなら時間・場所を選ばずに学習効果を測定でき、受験者の負担軽減と運営コストの削減を同時に実現できます。
本記事では、 eラーニングテストの基本知識から具体的な作成手順、効果的な運用のコツ、注意すべきポイントまで を体系的に解説します。学習成果の可視化と継続的な人材育成の実現を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
eラーニングでテストを行うメリット
eラーニングでのテスト実施には、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下で具体的なメリットを4つ紹介します。
受験者の負担軽減
会場でテスト用紙を用いて行うケースとは異なり、eラーニングは場所や時間を選びません。受験者側はわざわざ会社に赴く必要もなく、業務の空き時間などを有効に活用することができます。
実施コストの削減
eラーニングでテストを行えば、以下のようなコストをかける必要がありません。
- テスト用紙の印刷
- 会場の手配や準備
- 当日の案内係や監視係
- 採点や集計
また、テスト問題の差し替えや更新もパソコン上で一斉に反映できるため、運営側の手間も軽減されます。
研修後アンケート・理解度テストの実施なら「AirCourse」
研修後のアンケートや理解度テストの実施は、管理がしやすい「AirCourse(学習管理システム)」がおすすめです。
AirCourseなら、動画視聴後・集合研修後のアンケート・テスト実施が容易で、必要に応じて追加の学習や声かけを行うことができます。システムに標準搭載されているコンテンツに加え、企業オリジナルのコンテンツを作成・配信することが可能です。
自社の社員研修を実りあるものにしたい、さらにアップデートしたいとお考えの方はAirCourseが分かる下記資料をご覧ください。
学習機会の増加
eラーニングであれば、簡単にテストを作成・実施できるので、知識の確認・定着・補足などを行いやすくなります。例えば以下のような活用が可能です。
- 各担当業務に必要な知識の理解度チェック
- 新たな商品やサービスに関する理解度チェック
- 研修後の習熟度チェック
- ビジネスマナーなど基本知識のおさらいテスト
- 各種ハラスメントやコンプライアンスなどの確認テスト
結果として、業績アップやリスク回避につながるでしょう。
人材育成施策の効果測定を行える
eラーニングでのテストを用いれば、各種研修など人材育成施策の効果を測定可能です。効果測定の理論として有名な「カークパトリックの4段階評価」にて、eラーニングでのテストを用いれば、レベル1〜2の測定が容易に行えるようになるのです。
各施策の効果を測定できれば、社員の自己成長に対するモチベーション向上や、新たな人材育成施策のヒントを得ることも期待できるでしょう。
カークパトリックの4段階評価
| 段階 | 項目 | 内容 | 施策例 |
|---|---|---|---|
| レベル4 | 成果 | 学習者の行動は 組織の成果に貢献したか? | 研修実施前後の KGI・KPIの変化確認 |
| レベル3 | 行動(行動変容) | 理解した知識・スキルを 実行したか? | 職場観察/言動チェック /パフォーマンスインタビュー |
| レベル2 | 学習(理解度) | 学習者は知識・スキルを 理解したか? | 理解度テスト/課題提出 |
| レベル1 | 反応(満足度) | 学習者はプログラムに 満足したか? | 研修後アンケート |
eラーニングでテストを行う際の注意点
eラーニングでテストを行う際には、注意すべき点があります。具体的には以下の通りです。
迷いなく解答できる表現になっているか
テスト問題を作成する際、各設問や選択肢の表現が分かりにくくないか注意が必要です。以下で具体的に説明します。
「問い方」を統一する
例えば、正しいものと間違っているものを選ばせる問題を作成した場合、「問い方」は統一すべきです。以下の良い例と悪い例を参照してください。
〇良い例
問1:正しいものを選びなさい
問2:間違っているものを選びなさい
問3:正しいものを選びなさい
問4:間違っているものを選びなさい
✕悪い例
問1:正しいものを選びなさい
問2:間違っているものを選びなさい
問3:適切なものを選びなさい
問4:間違っているものはどれですか
良い例では問い方が統一されています。一方で悪い例では質問形式であるはずの「問1と問3」および「問2と問4」の問い方がバラバラです。これでは受験者に迷いを生じさせかねません。
文章の調子を統一する
テスト問題内の文章は、「です・ます」調もしくは「だ・ある」調のいずれかを用います。この際、両調子が混在しないように注意しましょう。混在していると受験者に違和感や不要なストレスを与えてしまいます。
問題が「1:1対応」になっているか
1:1対応とは、1つの質問に対して1つの知識によって答えることができることを示しています。1つの質問の答えを出すために複数の知識が必要となってしまうと、誤答した際に「どの知識が不足して間違えたのかが分からない」という状況に陥ります。理解度の傾向を知りたい場合などは特に注意しましょう。
テスト機能に対応しているか
eラーニングシステムによっては、テスト機能が備わっていないものも存在します。eラーニングでテストを実施する構想がある場合、導入前に必ず確認しておきましょう
実施したい出題形式に対応しているか
eラーニングシステムにテスト機能が備わっていたとしても、実施したい出題形式(〇✕式や記述式など)に対応していなければ目的とする効果を得られません。出題形式に柔軟に対応できるシステムを選定することをおすすめします。
eラーニングでテストを作成する手順
eラーニングでテストを作成して実施するまでの手順について解説します。
1. 実施目的を明確化する
テスト作成において目的の明確化は非常に重要です。テストを通じて、どのような学びや気づきを得て欲しいのか、どの知識を身につけさせたいのか、何を測り評価したいのか、などを明確にします。
目的を明確にしておくことで、的確な問い(テスト問題)を作成することが可能となります。少なくともテスト自体が目的化しないようにしましょう。
2. テスト問題を作る(出題形式を決める)
目的を明確に定めたら、目的を達成するためのテスト問題を作成します。
テストは何を聞くか(内容・題材)が重要ですが、どう聞いてどう答えさせるか(出題形式)も同様に重要です。同じ内容を問う場合でも出題形式によって難易度や効果は異なります。以下は、テストで用いられる主な出題形式です。
主な出題形式
〇✕式
例文:以下の内容のうち、正しいものは〇、間違ったものには✕を記入しなさい。
単一選択式
例文:以下の選択肢のうち、正しいものを1つ選びなさい。
複数選択肢式
例文:以下の選択肢のうち、正しいものを全て選びなさい。
穴埋め選択式
例文:以下の空欄部分に適する語句をリストから選択して記入しなさい。
傾聴とは、相手の立場に立ち、気持ちに( )しながら話を聞くことである。
リスト[共感 集中 反発 反応]
穴埋め記述式
例文:以下の空欄部分に適する語句を記入しなさい。
傾聴とは、相手の立場に立ち、気持ちに( )しながら話を聞くことである。
自由記述式
例文:あなたは出席予定の打合せに5分程度遅れそうです。この際の適切な行動について自由記述で解答してください。
難易度は選択式より記述式の方が高まります。また〇×式や選択式は、成否を考える過程で選択肢を熟読させることにより、記憶への定着を図れます。一方で自由記述式であれば、受験者の応用力や思考力を測り、鍛えることが可能です。
3. eラーニングシステムに反映して試し受験をする
テスト問題が完成したら、eラーニングシステムに反映した上で必ず試しに受験してみましょう。受験者の目線で見ることで、分かりにくい点や勘違いや誤解が生じそうな点など
出題側としては気づけなかった部分を発見することができます。
また、試し受験は1人ではなく複数人に行ってもらうことをおすすめします。1人では見落としてしまいがちな点にも気づくことが可能です。
eラーニングのテストを運用するコツ
続いて、eラーニングのテストをスムーズに運用するための3つのポイントを解説します。
導入するeラーニングを統一する
導入するeラーニングを統一しましょう。複数のeラーニングのシステムを使わなければならないと、従業員のスキル把握が難しくなります。ほかにも、人材育成に関する履歴を一貫して整理できなくなるなどのデメリットが生じかねません。
しかし、使用するeラーニングが統一できていれば、学習者は複数のプラットフォームや教材を使い分ける必要がなくなります。学習効果の向上や学習負担の軽減が期待できるはずです。eラーニングを実施する企業側としても、統一したプラットフォームの方が教材の管理が容易になるでしょう。
アクセス環境を整える
アクセスする環境を整えることも忘れずに行いましょう。eラーニングはインターネットを用いて行われるため、安定したネットワーク環境が必要です。
また、学習者がアクセスする場所においては、適切なデバイスやブラウザが求められます。例えば、スマートフォンやタブレットなどのデバイスからアクセスする場合には、画面の大きさや操作性にも配慮すべきです。
さらに、eラーニングに必要なソフトウェアやプラグインがある場合には、事前にインストールするように周知を徹底しましょう。
効果測定を行う
eラーニングのテストを実施したら、必ず効果測定も行いましょう。効果測定は学習者がeラーニングのテストを通じてどの程度の成果を上げたかを測ることで、効果を客観的に評価するために必要な作業です。
具体的には学習者のテストの成績やアンケート調査などを通じて、eラーニングのテストの効果を測定できます。また、効果測定の結果をもとに、eラーニングのテストの改善点を見つけ出し、バージョンアップを行うことも可能です。
まとめ
eラーニングテストは、時間・場所・コストの制約を大幅に軽減しながら、学習効果の測定と向上を同時に実現できる効果的な手法です。受験者の負担軽減、実施コストの削減、学習機会の増加、そして人材育成施策の効果測定という4つのメリットにより、従来の集合型テストでは実現困難だった継続的な学習環境の構築が可能になります。
効果的なeラーニングテストを実現するには、明確な目的設定、適切な出題形式の選択、そして受験者目線での問題作成が不可欠です。特に「問い方の統一」「文章調子の統一」「1:1対応の徹底」といった基本ルールを守ることで、正確な理解度測定と学習者のストレス軽減を両立できます。
また、継続的な効果測定と改善により、テストそのものも学習ツールとして機能させることが重要です。戦略的にeラーニングテストを活用し、組織全体の学習文化醸成と人材育成効果の最大化を目指しましょう。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。