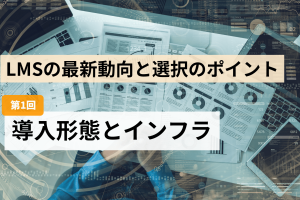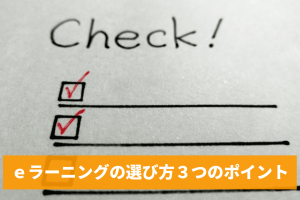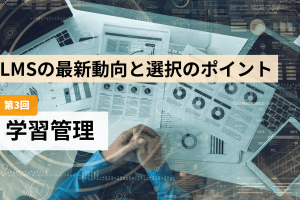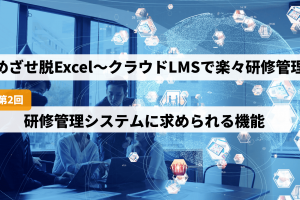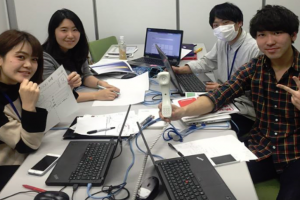企業の人材育成を取り巻く環境は大きく変化しています。リモートワークの普及やDX推進の必要性により、従来の集合研修だけでは限界を感じている人事・教育担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで注目されているのが「eラーニング」です。eラーニングは、時間と場所を選ばずに学習できるデジタル研修システムであり、現代の働き方に適した効率的な人材育成手法として広く活用されています。約9割の企業がeラーニングの定着に課題を感じているという調査結果もありますが、適切な導入手順と運用方法を理解することで、組織全体の学習文化を大きく変革できます。
本記事では、eラーニング導入の全体像から具体的なステップ、システム選定のポイント、成功事例まで、人材育成担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。eラーニング導入を成功させ、組織の持続的な成長を実現しましょう。
失敗しない『eラーニング導入』のノウハウを無料でお届け
eラーニング導入の成否を分けるのは導入前の設計にあります。「何を学ばせるか」ではなく「どう学習を継続させるか」に焦点を当てた体系的なアプローチが必要です。
先進企業では、eラーニング導入を単なるシステム導入ではなく、組織の学習文化変革として捉え、段階的な導入ステップで成果を実現しています。
「使われつづける」eラーニング導入のノウハウを、ぜひ手に入れてください。
目次
eラーニング導入の全体像
eラーニング導入は、単なるシステム導入ではなく、組織の学習文化を根本から変革する取り組みです。
導入プロセスは大きく6つのフェーズに分かれます。準備段階での課題整理と目標設定、要件定義とシステム選定、試験導入での検証、全社展開、そして継続的な改善サイクルです。
各フェーズで適切な判断を行うことで、導入後の定着率向上と学習効果の最大化を実現できます。特に、導入前の準備と社内体制の構築が、その後の成否を大きく左右するポイントとなります。
導入前の準備
導入前の準備は、eラーニング成功の土台となる最も重要なフェーズです。
現状の研修課題の洗い出し
eラーニング導入を検討する前に、まず現在の研修体系における課題を明確にすることが重要です。「集合研修の開催が困難」「受講者の理解度にばらつきがある」「研修管理の業務負担が大きい」といった具体的な問題点を整理しましょう。
課題の洗い出しには、人事担当者だけでなく、現場の管理職や受講者へのヒアリングも有効です。多角的な視点から課題を把握することで、eラーニング導入の必要性と期待効果を明確にできます。
導入目的と成果目標の設定
課題分析を踏まえて、eラーニング導入の目的を明確に定義します。「研修の効率化」「社員のスキル向上」「学習機会の均等化」など、組織が目指すゴールを具体的に設定しましょう。
目標設定では、定量的な指標も重要です。「受講率80%以上」「理解度テスト平均点85点以上」「研修管理工数50%削減」など、測定可能な成果指標を設けることで、導入効果を客観的に評価できます。
社内体制と予算の検討
eラーニング運用には、システム管理者やコンテンツ作成担当者など、専任または兼任のスタッフが必要です。現在の人員体制を踏まえて、運用に必要なリソースを検討しましょう。
予算面では、初期導入費用だけでなく、月額利用料やコンテンツ制作費、運用人件費などの継続的なコストも含めて計画を立てることが大切です。全社員を対象とした導入を前提に、1人当たりのコストを算出し、費用対効果を検証します。
対象者とスケジュールの策定
導入対象者の範囲を明確にします。「まず管理職から開始し、段階的に全社員に拡大」「新入社員研修から先行導入」など、組織の状況に応じた展開計画を立てましょう。
スケジュール策定では、システム選定から運用開始まで3〜6ヶ月程度の期間を見込むのが一般的です。研修繁忙期を避けた導入時期の選定や、既存研修との並行期間の設定も重要なポイントです。
eラーニング成功のコツは”導入設計”にあります
eラーニングの基本的な仕組みは理解できても、実際に成果につながる運用を継続することは簡単ではありません。多くの企業が「導入したが受講率が低い」「コンテンツ作成に時間がかかりすぎる」「効果測定ができない」という課題に直面しています。
これらの課題解決には、単なるシステム選定ではなく、学習文化の醸成から効果測定まで含めた包括的な導入戦略が不可欠です。成功企業では、5つのステップで段階的にeラーニングを組織に定着させ、継続的な学習環境を構築しています。
戦略的な視点からeラーニング活用を推進する、体系的な導入アプローチを学んでみませんか。
導入の具体的なステップ
適切な段階的アプローチにより、リスクを最小化しながら確実な導入を実現できます。
要件の整理と仕様策定
システム選定に入る前に、自社の要件を詳細に整理します。必要な機能(動画配信、テスト機能、進捗管理など)、同時接続数、モバイル対応の必要性、既存システムとの連携要件などを明確にしましょう。
コンテンツ要件も重要な検討項目です。既存の研修資料をeラーニング化する必要があるか、外部コンテンツの活用予定はあるか、自社オリジナルコンテンツの制作は必要かなど、具体的な利用イメージを固めます。
複数システムでの比較検討
要件定義を基に、複数のeラーニングシステムで比較検討を行います。機能面だけでなく、操作性、コンテンツの質と量、サポート体制、費用などを総合的に評価することが重要です。
多くのシステムでは無料トライアル期間が提供されています。実際に管理画面や受講画面を操作し、直感的な使いやすさや動作の安定性を確認しましょう。複数の担当者で評価することで、より客観的な判断が可能になります。
試験導入での効果検証
本格導入前に、限定的な範囲で試験導入を実施します。特定の部署や研修テーマに絞って運用し、システムの動作確認や受講者の反応を検証しましょう。
試験導入では、技術的な問題だけでなく、受講促進方法や管理業務の工数、サポート体制の有効性なども評価します。得られた知見を基に、本格導入時の運用方法を改善できます。
全社展開と運用開始
試験導入の結果を踏まえて、全社への展開を開始します。システムの設定、ユーザー登録、初期研修の配信準備など、運用開始に必要な作業を計画的に進めましょう。
運用開始時には、受講方法の説明会やマニュアル配布、問い合わせ窓口の設置など、社員がスムーズに利用開始できるサポート体制を整備することが重要です。
継続的な改善と最適化
運用開始後は、受講データの分析や受講者からのフィードバックを基に、継続的な改善を行います。受講率の低いコンテンツの見直しや、新たな研修ニーズへの対応など、PDCAサイクルを回しながら最適化を進めましょう。
定期的な効果測定も欠かせません。導入時に設定した成果指標の達成状況を確認し、必要に応じて運用方法の見直しや追加投資を検討します。
システム選定のポイント
適切なシステム選定により、導入後の運用効率と学習効果を大きく左右します。
操作性と使いやすさの確認
eラーニングシステムの成功は、利用者にとっての使いやすさに大きく左右されます。管理者画面では、受講者登録やコース設定、進捗確認などの作業が直感的に行えるかを確認しましょう。
受講者画面では、ログイン方法の簡単さ、コンテンツの検索性、視聴環境の安定性などが重要です。特に、ITリテラシーに差がある社員が混在する組織では、マニュアルなしでも操作できる直感性が求められます。
モバイル対応も現代では必須要件です。スマートフォンやタブレットでも快適に受講できるかを、実際のデバイスで確認することをお勧めします。
コンテンツの質と量の評価
標準で提供されるコンテンツの質と量は、システム選定の重要な判断材料です。自社の研修ニーズに合致するテーマが充実しているか、講師の話し方や映像品質が統一されているかを評価しましょう。
コンテンツの更新頻度や追加予定も確認ポイントです。ビジネス環境の変化に対応した新しいテーマが定期的に追加されるシステムを選ぶことで、長期的な活用価値を高められます。
自社オリジナルコンテンツの作成・アップロード機能も重要です。対応ファイル形式の幅広さや、編集機能の充実度を確認しましょう。
費用対効果の検証
導入費用だけでなく、運用コストも含めた総合的な費用対効果を検証します。利用人数に応じた料金体系、コンテンツ利用料、サポート費用などを比較検討しましょう。
全社員での利用を前提とした場合の1人当たりコストを算出し、従来の研修費用と比較することで、導入メリットを定量化できます。特に、会場費や講師費用、資料印刷費などの削減効果を考慮することが重要です。
サポート体制の充実度
eラーニング導入成功の鍵は、ベンダーからの適切なサポートにあります。導入時のキックオフ支援、運用中の技術サポート、カスタマーサクセスによる活用促進支援などが提供されるかを確認しましょう。
問い合わせ対応の迅速性や、定期的な活用状況レポートの提供、改善提案の頻度なども評価ポイントです。特に、eラーニング運用が初めての組織では、手厚いサポート体制があるベンダーを選ぶことをお勧めします。
eラーニングシステムの導入事例
実際の導入事例から、成功のポイントと具体的な活用方法を学びましょう。
反転学習による研修効率化と受注単価15.2%アップを実現|株式会社SHIFT様

ソフトウェアテスト専門として5兆円市場のリーディングカンパニーを目指す株式会社SHIFT(グループ約5,000名)では、急成長に伴う人材育成の課題に直面していました。毎月100名の中途入社者に対する集合研修は拠点ごとの講師手配が必要で研修内容に差が生じるケースがあり、さらに地方拠点も含めた全社統一の教育環境整備が急務でした。また、スキルアップとキャリアアップを目指す独自の社内検定試験制度「トップガン教育」の全社展開も課題となっていました。
同社がAirCourseを選んだ決め手は、受講者からの問い合わせがほとんど発生しない直感的なUI/UXと、スマートフォンでの簡単利用でした。入社者研修では講義動画を各自がAirCourse上で事前学習し、対面時間は演習やディスカッションに集中する反転学習を実現しました。「トップガン教育」では学習から試験までワンストップで運用し、合格者には上位業務へのアサインと収入アップという明確なインセンティブを設定し、全社的な検定試験ブームを創出しています。
得られた主な成果
- 平均受注単価15.2%アップを実現
- 反転学習により研修効率が格段に向上
- 拠点に関係ない平等な学習環境を全社に提供
- 約1,000名が登録する自発的学習文化を構築
研修業務の50%時間削減とナレッジ体系化を実現|リノべる株式会社様

年間施工件数業界No.1のプラットフォーマーとして中古住宅のリノベーション事業を展開するリノべる株式会社では、テクノロジーを活用した業務効率化の一環として人材育成の課題に取り組んでいました。各自が共有サイトに資料や動画をアップしていましたが、情報が整理されておらず、進捗状況の可視化やテストの一元管理ができない状況でした。さらに新卒採用の内定者が遠隔地にいることや、中途採用時に覚えるべき内容が多いことも課題となっていました。
AirCourse導入により、散在していたナレッジの共有と体系化に成功しました。フランチャイジー向け新入社員・営業研修から入社者研修の事前学習、自社独自研修メニューまで幅広く活用し、eラーニングで顕在化できた弱点を徹底フォローアップする仕組みを構築しました。研修業務の大幅な効率化により、深い知識やスキルが求められる業務内容を最速で習得できる環境を整備しています。
得られた主な成果
- 研修業務の50%の時間削減を実現
- 散在及び属人化していたナレッジの共有と体系化に成功
- eラーニングで顕在化できた弱点を徹底フォローアップ
- フランチャイジー向け研修の効率化と品質向上を両立
企業内大学「TGKU」開設で全社統一教育環境を構築|豊田合成九州株式会社様

トヨタグループの自動車部品メーカーである豊田合成九州株式会社では、2018年の設立以降、工場勤務者の比率が高いという特性を活かした人材育成環境の整備に取り組んでいました。従来の集合研修では決まった時間・場所での受講が必要で、移動コストや運営手間がかかる一方、現場トラブルやスケジュール調整により参加できない社員も多く、均等な教育機会を提供できていませんでした。
AirCourseの6,000本以上の学習コンテンツを活用し、企業内大学「TGKU」(Toyoda Gosei Kyushu University)を開設しました。体系的かつ豊富な学習コース、短時間で学べるマイクロラーニング、優れたコストパフォーマンスを評価して導入を決定。階層別研修からDX教育、自己学習の文化醸成まで、「インプット」はeラーニング、「対話」は集合研修とした新しい人材育成モデルを確立しています。
得られた主な成果
- 企業内大学のプラットフォームとして全社活用を実現
- 工場勤務者が負担なく受講できる制度設計を確立
- 標準化された一貫性のある教育と全社員への均等な学習機会を提供
- 教育のばらつきを防ぎ、質の高い研修を効率的に実現
社内定着と学習力向上のポイント
導入後の継続的な活用により、組織全体の学習文化を醸成できます。
魅力的なコンテンツの継続提供
eラーニングの定着には、受講者が「学習したいコンテンツが常にある」状況を作ることが重要です。初期導入時の標準コンテンツだけでなく、定期的な新コンテンツの追加や、社員のリクエストに応じたコンテンツ拡充を行いましょう。
自社オリジナルコンテンツの制作も効果的です。社内の専門知識やノウハウを動画化し、組織内のナレッジ共有を促進できます。勉強会の録画配信や、トップメッセージの共有なども、社員のエンゲージメント向上につながります。
コンテンツの質的向上も継続的に図る必要があります。受講者アンケートや完了率データを分析し、評価の低いコンテンツの改善や、新たな学習ニーズの発掘を行いましょう。
進捗把握と学習促進の仕組み
管理者にとって重要なのは、受講者の進捗や理解度を容易に把握できることです。詳細な学習進捗レポート機能を活用し、個人・部門別の受講状況を定期的に確認しましょう。
部門長ミーティングでの学習状況共有や、進捗の遅れている部署への個別フォローアップなど、データに基づいた学習促進策を実施します。受講者同士の競争意識を高める取り組みも効果的です。
必須受講と推奨受講の組み合わせにより、段階的な学習定着を図ります。まず重要テーマを必須として浸透させ、その後自発的な学習文化へと発展させていく戦略が有効です。
管理者の負担軽減と運用効率化
eラーニング運用の継続には、管理者の業務負担軽減が欠かせません。直感的なUI/UXにより、専門知識がなくても容易に運用できるシステムを選択することが重要です。
自動化機能の活用により、受講促進メールの配信や、未受講者リストの作成、進捗レポートの生成などを効率化しましょう。これにより、管理者はより戦略的な人材育成業務に集中できます。
カスタマーサクセス担当者との定期的な打ち合わせを通じて、運用改善のアドバイスを受けることも効果的です。他社の成功事例や最新の活用方法を学ぶことで、継続的な改善を実現できます。
まとめ:eラーニング導入で組織の持続的な学習文化を実現する
eラーニング導入は、単なるシステム導入ではなく、組織の学習文化を根本から変革する取り組みです。
適切な準備と段階的な導入プロセス、継続的な改善により、全社員の学習機会を平等化し、組織全体のスキル向上を実現できます。成功の鍵は、導入前の課題分析と目標設定、システム選定時の総合的な評価、そして導入後の継続的な運用改善にあります。
特に、受講者にとっての使いやすさと、管理者の運用負担軽減の両立が重要なポイントです。約9割の企業がeラーニング定着に課題を感じる中、適切な導入手順と運用方法により、組織の持続的な成長を支える学習基盤を構築しましょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。