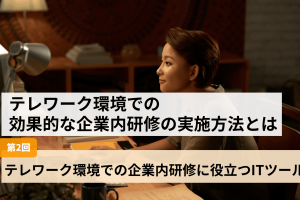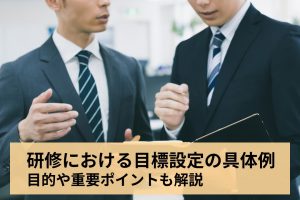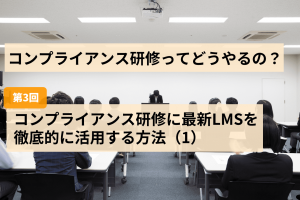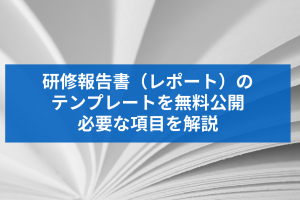コンプライアンスとは、法令や社会規範を守ることを意味しますが、その範囲は年々拡大しています。単に法令を守るだけでなく、企業倫理や社会的責任まで含まれるようになってきました。
コンプライアンスの範囲が広がる中、企業は従業員一人ひとりにコンプライアンスを「自分ごと化」してもらい、予防意識の醸成に努めなければなりません。
また、仮に違反が発生した際にも適切な初期対応がとれるよう、具体的な場面を想定し、対応方法や考え方を身につけてもらう必要があります。
そこで重要な役割を果たすのが「コンプライアンス研修」です。
本記事では、コンプライアンス研修のテーマ例、実施手順、研修効果を高めるポイントなどを解説します。
成果が見えにくいコンプライアンス研修を評価し、定着させる方法についても紹介しますので、自社のコンプライアンス研修の参考にしてください。
コンプライアンス研修の課題解決に今すぐ使える実践ツールを
コンプライアンス研修のゴールは、研修によって社員一人ひとりが各種法令・社内ルールを順守することの重要性を自分事として理解し、研修後の行動に変化が生まれることにあります。
質の高い研修を計画・実施するのはもちろん、効果を持続させるために「研修後の振り返り」と「継続的な学習環境の整備」が欠かせません。とはいえ、毎年のように変わるコンプライアンスの範囲や、全社員向けの実施が前提の研修に、多くの企業が実施そのものに課題を抱えています。
そんなコンプライアンス研修特有の課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「動画研修コース」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
導入企業の具体的な成功事例と実践方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
コンプライアンス研修にも最適なeラーニングシステム『AirCourse』は、研修の実施から実施後のアンケート・振り返りテストにも対応しています。コンプライアンス研修を着実に実行に移し、組織の成長を加速させたい方はぜひご活用ください。
目次
コンプライアンス研修のテーマ・学習プログラム例
コンプライアンス研修で何を取り扱えば良いかわからない場合は、次の4点を優先的に取り扱うとよいでしょう。
- ハラスメント
- 情報セキュリティ
- 各種法律
- SNSの取り扱い
これらは特に問題になりやすいテーマです。あわせて学習プログラムも紹介しますので、以下の内容を参考に、自社にあったプログラムを設計・検討しましょう。
ハラスメント
ハラスメントは、広く一般的に取り上げられるようになったテーマです。職場におけるハラスメントの代表的な類型としては、以下のようなものがあげられます。
| ハラスメントの類型・学習プログラム | 概要 |
|---|---|
| 性的ハラスメント | 性的な言動によってプライバシーを侵害したり、 不快な思いをさせたりすること |
| 妊娠・出産等に関するハラスメント | 妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いなど |
| 育児・介護休業等に関するハラスメント | 子の養育や家族の介護を理由とした不利益取扱いなど |
| パワーハラスメント | 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景にした言動 |
研修ではこれらハラスメントの背景にある構造的問題や、被害者の心理的影響についても触れることが重要です。一人ひとりのちょっとした気づきや、意識改革がハラスメントの予防につながるからです。
各ハラスメントに対応する学習プログラムの一例も紹介しますので、研修イメージの参考にしてください。
| 学習プログラム例 | 概要 |
| 25年受講用/セクシュアルハラスメント防止研修_①法改正とセクハラの定義 | 労働施策総合推進法の適切な理解と、改正されたポイントを学習します。また、セクシュアルハラスメントの定義を学習します。 |
| 25年受講用/ハラスメント防止研修_①マタニティハラスメント | マタニティハラスメントの特徴と傾向を事例を通して学習し、未然防止を目指します。 |
| 【令和7年改正対応】柔軟な働き方の実現へ!育児・介護休業法①育児休業制度とは | 育児休業制度の基本的な仕組みを理解し、働きながら育児に取り組む具体的なイメージを描けるようになることを目指します。育休の取得条件や期間など、令和7年の法改正ポイントを含めてわかりやすく解説します。 |
| 25年受講用/一般社員のためのパワーハラスメント防止研修【パワハラ防止法対応】_①パワハラ防止法とパワハラの定義 | 改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)を知り、パワハラの定義について学習します。 |
ハラスメント研修については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:ハラスメント研修の目的と内容|研修効果を高めるポイントについて
情報セキュリティ
企業が保有する個人情報や機密情報の漏えい事故は、企業の信用を大きく損なうリスクがあります。情報セキュリティに関する研修は、重要なコンプライアンステーマの1つと言えます。
具体的な研修内容としては、以下のようなものが考えられます。
- パスワードの設定ルール
- USBメモリやクラウドストレージの利用ルール
- SNSやメールの書き方のルール
- 個人情報や機密情報の取り扱い方
- セキュリティインシデントが発生した際の対処法
また、単に知識を教えるだけでなく、以下のような工夫も有効です。
| 工夫 | 内容 |
| 体験型の研修 | 実際に不審メールに返信する練習をするなど |
| ゲーム形式の研修 | クイズ形式で知識を確認するなど |
| 事例の共有 | 過去の事故事例を具体的に紹介する |
従業員一人ひとりが、情報セキュリティの重要性を実感できるような研修を心がける必要があります。
| 学習プログラム例 | 概要 |
| 情報セキュリティ基本知識【入門編】 | ・情報セキュリティで「何を」守るのか?基本を学べます。・仕事や、プライベートなどで身近に使う物を取り上げ、具体的に「やった方が良いこと・やってはいけないこと」をレクチャーします。・新しく入社された方全員に見て頂きたい内容となっております。 |
| 25年受講用/社員として守らねばならない情報セキュリティ | 本コースでは、現場の社員が守らなければならない基本的なルールについて学習します。アカウントやパスワードの取り扱い、パソコンやスマートフォン、メールや印刷物で注意するポイントを具体的にご紹介します。 |
| 25年受講用/情報セキュリティと密接な個人情報保護法 | 本コースでは、個人情報保護法について学びます。『個人情報の対象となるデータは何か?』『どのように個人情報を保護するのか?』を学習します。 |
各種法律
コンプライアンス研修において、関連する法律の理解は不可欠です。特に、以下の基本的な法律の知識は従業員が共有しておくべき内容です。
- 労働基準法
- 個人情報保護法
- 独占禁止法
研修例としては、労働基準法に基づく労働時間の管理や、個人情報保護法における個人データの取り扱い方針など、日常的な業務に直結するテーマが挙げられます。
法改正が頻繁に行われる分野については、最新の情報を盛り込むことで、より実践的な内容にできるでしょう。
| 学習プログラム例 | 概要 |
| 新任管理職のための労働基準法①労働基準法とは | 「労働者」と「使用者」の定義を確認し、管理監督者とはどういった立場が対象となるか解説します。また、労働関係でよくあるトラブルや、労働基準法に違反した場合に起こりうるリスクや罰則についても学び、管理職として、労働基準法の基本を正しく理解することで、職場での適切な労務管理に活かすことができます。 |
| 知らないでは済まされない!改正個人情報保護法③2024年改正ポイントと対策 | 現代ビジネスの世界では、個人情報の適切な取り扱いが企業の信頼性と直結しています。2024年に改正された個人情報保護法は、特にウェブスキミング対策を念頭に置いたもので、従来の「個人データ」だけでなく、「個人情報」も保護の対象に拡大しています。本コースでは、2024年改正個人情報保護法の重要ポイントと、企業が取り組むべき対策を解説します。改正の背景にあるウェブスキミングとは何か、そしてそれが企業の個人情報管理にどのような影響を及ぼすのかを学習します。 |
| 知らないでは済まされない!独占禁止法①独占禁止法とは | 独占禁止法は、企業間の競争を公正に保ち、消費者や市場全体の利益を守ることを目的とした法律です。この法律は、不公正な競争や市場の支配を防ぐために、企業の行動に対する規制が設けられています。本コースでは、ビジネスパーソンとして押さえておくべき独占禁止法の基本的な知識を学び、具体的に禁止されている4つの行為を詳しく解説します。企業活動における法令遵守の基礎を築き、公正なビジネス環境を支えるための知識を身につけましょう。 |
SNSの取り扱い
SNSの普及に伴い、企業や個人のSNSの利用に関するトラブルも増加しています。そのため、SNSの適切な利用をテーマとする研修は、現代のコンプライアンス教育において欠かせない要素です。
例えば、SNS上での発言が企業や顧客に与える影響や、プライバシー侵害、著作権の問題について理解を深めることが大切です。
また、社員自身が企業の一員であることを認識し、SNSを通じた情報発信が個人だけではなく組織全体の評価につながることを学ぶ必要があります。
SNSの利用に関する社内ルールやガイドラインを周知し、トラブルの未然防止を図る内容を含めることで、リスク管理の意識を高められます。
| 学習プログラム例 | 概要 |
| 知っておかないと危ない!デジタルリスク対策③SNSにおける情報漏えい | 技術の進歩により、情報の伝達方法や管理方法が変化していますが、昨今もSNS上での情報漏えいは後を絶ちません。本コースでは、SNSにおける情報漏えいについて、情報漏えいがなぜ発生するようになったのかを事例とともに、企業が行うべき防止策についても解説します。 |
| 知っておかないと危ない!デジタルリスク対策⑤公式SNS運用におけるリスク | 昨今、公式SNSを運用する企業は増加しています。公式SNSを運用することで、商品のPRや企業情報の発信が可能です。新しいファン層の獲得や認知拡大を狙えるのもSNSのメリットですが、一方でイメージ低下や炎上のリスクも伴います。本コースでは、事例を交えながら公式SNS運用におけるリスクについて解説します。 |
| 知っておかないと危ない!デジタルリスク対策⑨管理職向けSNSリスクリテラシー向上 | 本コースは、管理職向けのSNSリスクリテラシー向上を目的とした研修です。炎上が発生した場合、多くは管理職の判断で対応が進められます。そのため、リスクの判断方法や評価方法を理解し、判断や評価を正しく行うことがSNS炎上の収束に重要なポイントであることをお伝えします。 |
自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう
クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、コンプライアンス・ハラスメント関連の研修動画を200以上ご用意しております。
コンプライアンス研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。
コンプライアンス研修のネタ・事例の探し方
コンプライアンス研修では、リスクを身近に感じてもらうため、具体的な事例を紹介することが大切です。
コンプライアンス研修のネタや事例を自社で探す際は、次の4点を実施しましょう。
- 自社・同業他社の過去の不祥事事例を活用する
- 社内アンケートで関心のあるテーマを調査する
- 省庁・関連団体で取り上げられている事例を活用する
- 新聞・ニュースサイトでキーワード検索を行う
自社・同業他社の過去の不祥事事例を活用する
自社や同業他社で過去に起きたコンプライアンス違反の事例を活用することで、研修の訴求力を高めることができます。
| 事例の種類 | 効果 |
| 自社の事例 | 身近で現実味がある。再発防止の必要性を強く感じられる。 |
| 同業他社の事例 | 業界関係者なら同じリスクがあることを認識できる。 |
ただし、個人や企業が特定されないよう配慮し、必要に応じて一部情報を加工・修正する必要があります。
事例の選定に当たっては、以下の点に留意しましょう。
- 違反の内容が研修テーマに合致していること
- 事実関係が明確で、詳細を把握できること
- 社会的影響が大きく、注目を集めた事例であること
適切な事例を抽出し、研修で活用することで、受講者の問題意識を高め、違反防止につなげることができます。
社内アンケートで関心のあるテーマを調査する
社内のコンプライアンス意識や、従業員が関心を持っているテーマを事前に把握することも重要です。
アンケートを実施する際は、以下の点に留意しましょう。
- 無記名方式で実施し、本音が出しやすい環境を整える
- 自由記述欄を設け、意見を幅広く収集する
- 部門・役職・年代別の集計を行い、偏りがないか確認する
アンケートの設問例は以下の通りです。
| 設問 | 選択肢 |
| コンプライアンスに関する関心度は? | ①高い ②やや高い ③普通 ④やや低い ⑤低い |
| 特に関心のあるテーマは? | ①ハラスメント ②情報セキュリティ ③贈収賄 ④環境問題 ⑤その他(具体的に記述) |
| 過去に研修を受けたことがあるか? | ①ある ②ない |
| 研修の受講形態は? | ①集合研修 ②eラーニング ③両方 |
このように社内の実態や要望を把握した上で、優先すべきテーマや受講形態を検討することが大切です。
省庁・関連団体で取り上げられている事例を活用する
省庁や業界団体が公表しているコンプライアンス違反事例は、研修の題材として大変有用です。
例えば、公正取引委員会が過去に行った企業への排除措置命令の事例集は、具体的な事案とその背景、関連法規を分かりやすく解説しています。
| 事例 | 概要 |
| 大手食品メーカー | 従業員に対し、過剰な長時間労働を強いる違法な労働管理を行っていた |
| 大手通信事業者 | サービス契約の締結に際し、不当に有利な条件を設定していた |
特定の事例を題材に取り上げることで、法令違反の実態や影響を具体的に伝えられます。また、業界団体が発行している規範やガイドライン、事例集なども活用できます。
研修にこうした第三者機関の資料を取り入れることで、より客観性と説得力が高まります。
新聞・ニュースサイトでキーワード検索を行う
新聞・ニュースサイトは、コンプライアンス事例を収集する際の有力な情報源です。検索エンジンでキーワードを入力することで、最新の不祥事事例を網羅的に把握することができます。
| キーワード例 | 関連情報 |
| コンプライアンス違反 | 企業の不正会計事例 |
| 内部統制 | 社内規程違反の事例 |
| ハラスメント | パワハラ・セクハラの具体例 |
| 製品事故 | リコール隠しの事例 |
| 情報漏えい | 個人情報・機密情報の流出事例 |
上記のようなキーワードから検索を行うと、さまざまな企業における最新の不祥事例を入手できます。新聞社や報道機関の情報は客観的でわかりやすく、実際に起きた事例のため研修ネタとして活用しやすいでしょう。
ただし、個別の事例に留まらず、その背景や問題点、対策などを幅広く学べるよう工夫する必要があります。
コンプライアンス研修を実施する流れ
コンプライアンス研修は以下の流れで実施しましょう。
- コンプライアンスの知識・意識レベル調査
- 優先順位の決定
- 内容の策定・実施
- 振り返りと調査
コンプライアンスの知識・意識レベル調査
コンプライアンス研修を実施する前に、まず従業員のコンプライアンスに関する知識と意識のレベルを把握することが重要です。これには以下の方法が有効でしょう。
- アンケート調査
- テスト・試験
- 上長・部下間の面談
調査結果を分析し、従業員の強み・弱みを把握したうえで、研修の優先順位や内容を決定することが求められます。
優先順位の決定
コンプライアンス研修のテーマを決める際には、以下の要素を総合的に勘案し、優先順位を決定します。
| 要素 | 内容 |
| 重大性 | 違反があった場合の影響が大きいものから優先する |
| 発生頻度 | 過去の事例が多発しているものから優先する |
| リスク顕在化の可能性 | リスクが顕在化しやすいものから優先する |
| 法令上の義務づけ | 法令で義務付けられているものから優先する |
| 従業員の関心 | 従業員から関心が高いものを優先する |
例えば、重大な影響があり、発生頻度も高く、リスクも顕在化しやすいハラスメントについては優先度が高くなります。一方、発生頻度が低く、従業員の関心も低い分野は後回しにすることができます。
さまざまな要素を考慮しながら、自社の実情に合わせて優先順位を決定することが重要です。
内容の策定・実施
コンプライアンス研修の内容は、目的に合わせて適切に選定する必要があります。
例えば、新入社員向けの研修では、社会人としてのモラルや倫理観を養うことに重点を置きます。一方、管理職向けの研修では、部下のコンプライアンス違反を見逃さない姿勢を養うことが求められます。
研修内容を策定する際は、以下の3点を押さえましょう。
| 項目 | 内容 |
| 重点テーマの選定 | ・ハラスメント・情報セキュリティ・インサイダー取引 |
| 事例の収集・作成 | ・社内外の過去事例を収集・フィクションの事例も有効 |
| 資料の作成 | ・スライド資料・動画教材・eラーニングコンテンツ |
研修の実施方法も、集合研修とeラーニングを組み合わせるなど工夫が必要です。年1回の集合研修に加え、eラーニングで定期的に意識を高めるのが理想的です。
振り返りと調査
コンプライアンス研修の効果を検証し、改善につなげるためには、研修後の振り返りと調査が欠かせません。
具体的には以下の項目を確認することが重要です。
| 項目 | 内容 |
| 研修後アンケート | 研修内容の理解度や満足度、改善要望などを収集する |
| 理解度テスト | 研修内容の知識定着度を確認する |
| 行動量の比較 | 研修前後での行動変化を確認する |
| 意識レベル比較 | 研修前後でのコンプライアンス意識の変化を確認する |
| 業務上の成果確認 | コンプライアンス違反の減少や業務効率化など、研修の効果を確認する |
コンプライアンスを徹底するためには継続的な取り組みが必要不可欠です。次章で紹介する「コンプライアンス研修の成果を評価する方法」を参考に、しっかりと研修後に行動変容が起こせる研修内容を設計しましょう。
コンプライアンス研修の成果を評価する方法
コンプライアンス研修における大きな課題の一つが、「成果がわかりづらい」という点にあります。なぜなら、コンプライアンス研修の成否は、究極的には問題が発生していないということでしか判断できないからです。
それでもコンプライアンス研修の効果を可能な限り測定し、評価することに努める必要があります。適切な評価は、研修プログラムの改善や、組織全体のコンプライアンス体制の強化につながります。
研修後アンケート
研修後のアンケートは、理解度や満足度を確認するためだけでなく、改善点を把握する上でも重要な役割があります。
アンケートでは以下の項目を設けることをおすすめします。
| 項目 | 目的 |
| 理解度 | 研修内容の理解状況を把握する |
| 満足度 | 研修の質を評価してもらう |
| 改善点 | 次回に活かすべき意見を収集する |
| 自由記述欄 | 質問項目以外の意見を収集する |
アンケート結果を分析し、研修内容や方法の見直しを行うことで、より効果的な研修を実現できます。
継続的にアンケートを実施し、経年変化を追うことも重要です。従業員のコンプライアンス意識の変化を把握でき、研修の成果を評価する一助となります。
理解度テスト
コンプライアンス研修の理解度を確認するため、研修終了後に理解度テストを実施します。これは受講者が研修内容をどの程度理解できたかを測るためのものです。
理解度テストの実施方法としては、以下のようなパターンが考えられます。
| 方法 | 特徴 |
| 筆記テスト | 設問に対して記述式で解答する形式。理解度を細かく測ることができる |
| クイズ形式 | 選択式の問題に答える形式。大人数に対して短時間で実施可能 |
| レポート課題 | 研修内容に関するレポートを課す。理解度に加え思考力も測れる |
理解度テストは、単に知識の有無を確認するだけでなく、実際の業務で活かせる理解度があるかどうかを測ることが重要です。そのため、具体的な事例を示しつつ、受講者の判断力や適用力を問う出題形式が求められます。
研修後アンケート・理解度テストの実施なら「AirCourse」
研修後のアンケートや理解度テストの実施は、管理がしやすい「AirCourse(学習管理システム)」がおすすめです。
AirCourseなら、動画視聴後・集合研修後のアンケート・テスト実施が容易で、必要に応じて追加の学習や声かけを行うことができます。システムに標準搭載されているコンテンツに加え、企業オリジナルのコンテンツを作成・配信することが可能です。
自社のコンプライアンス研修を実りあるものにしたい、さらにアップデートしたいとお考えの方はAirCourseが分かる下記資料をご覧ください。
行動量の比較
コンプライアンス研修の効果を評価する際に、研修前後における社員の行動量を比較することは有効な手段です。
例えば、次のような指標を設定し、研修前後でその変化を観察することができます。
| 指標例 | 内容 |
| コンプライアンス違反件数 | ハラスメント、情報漏洩、贈収賄等の違反件数 |
| 内部通報件数 | 社内の通報窓口に寄せられた通報件数 |
| ヘルプデスクの問い合わせ件数 | コンプライアンスに関する質問や相談の件数 |
| 研修受講率 | eラーニングなどの研修の受講率 |
研修前は違反や通報が少なく、研修後に一時的に増加することもありますが、中長期的に見れば違反は減少し、問い合わせは増加するなど、社員の意識向上が見られるはずです。
客観的な数値を継続的にモニタリングすることで、コンプライアンス研修の効果を評価することができます。ただし、単に数値を追うだけでなく、根本原因の分析や是正措置を講じることが重要となります。
研修前後の意識レベルの比較
コンプライアンス研修の効果を測る上で、研修前後の受講者の意識レベルを比較することは有効な手段です。事前に意識調査を行い、研修後に同様の調査を実施することで、どの程度意識が向上したかを把握できます。
具体的には、以下のような調査項目が考えられます。
| 調査項目 | 研修前 | 研修後 |
| コンプライアンスに関する基礎知識 | ○ | ◎ |
| コンプライアンス違反のリスク認識 | △ | ◎ |
| 自身の業務とコンプライアンスの関係性 | △ | ○ |
| 違反発生時の自身の対処方法 | × | ○ |
研修の前後で受講者の意識がどのように変化したかを可視化することで、研修の効果を客観的に把握することができます。さらに、研修後のアンケートでは、自由記述欄を設けることで、受講者の気づきや疑問点を収集することも重要です。
これらの声を次回の研修に反映させることで、より効果的な研修を実施できるようになります。
評価測定の方法については以下の記事でも解説しています。
関連記事:研修の効果測定方法|4つの評価レベルと段階別の測定手法を解説 | 人材育成サポーター
コンプライアンス研修の効果を高めるポイント
コンプライアンス研修の目的は、単に知識の伝達をすることではなく、従業員の意識と行動の変容を促し、組織全体のコンプライアンス体制を強化することです。
したがって、社員ごとに理解度が異なる状況や、毎年のように発生する法改正にも対応していくことが求められます。そこで重要となるのが「更新性」と「管理のしやすさ」、「反復学習」という視点です。
LMS(学習管理システム)の活用
企業が「毎年のように発生するコンテンツのアップデート」や「受講者ごとの学習の進捗管理」に対応していくためには、LMS(学習管理システム)の活用がポイントとなってきます。
LMSはeラーニングコンテンツの配信のほか、受講後のテスト・アンケート結果の管理を行うシステムであり、多くの場合、企業にとって必要な学習プログラムが標準搭載されています。
そのため、以下のような課題を抱えている企業にとって、コンプライアンス研修にLMSを導入することは大きなメリットがあります。
- 研修コンテンツの準備に時間がかかる
- 研修コンテンツを更新する手間・コストがかかりすぎる
- 研修後の知識の定着や、行動変容に課題がある
自社のコンプライアンス研修において、研修実施のハードルや受講後の定着に課題がある企業は、LMSの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
マイクロラーニングの視点を取り入れる
実施したコンプライアンス研修を実りあるものにするためには、知識の定着が何よりも重要です。一般的に知識の定着には、何度も同じ内容を学習する「反復学習」が効果的とされており、コンプライアンス研修でも同様の視点が欠かせません。
そこで重要となるのが「マイクロラーニング」の視点です。マイクロラーニングとは、5〜10分程度の短時間コンテンツで学習を進めるeラーニングの手法で、移動中やちょっとしたスキマ時間に視聴できるのが特徴です。
5~10分で手軽に視聴できるため、受講者のストレスも少なく、受講者100%を達成する企業も少なくありません。質の高い学習コンテンツを用意・作成した後は、そのコンテンツが受講されやすい形になっているかどうか、受講者の立場で見直すことが大切です。
コンプライアンス研修にeラーニングを活用した事例

「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」というビジョンのもと、印刷・集客支援・物流・ITデバイス管理など様々な事業を展開するラクスル株式会社様では、上場企業として最重要テーマの一つであるコンプライアンス教育に対し、法務として幅広い業務を担う中で十分な時間をかけることができない課題を抱えていました。効率的かつ効果的にコンプライアンス教育を行えるツールの導入が必要でした。
AirCourse選定の決め手は、安価な価格帯と1000コース以上の豊富な研修コンテンツ、SAMLサリング」「自社独自のコンテンツ」を組み合わせて配信できる機能でした。現在は毎回受講率100%を目指して未受講者へのリマインドを実施し、受講状況を詳細把握することで適切な声かけを実現しています。統計データの正確な取得により、統合報告書やサステナビリティに関するウェブサイトへの客観的データ掲載も可能になりました。
導入後の主な成果
- 複数分野のコンテンツを限られた人員で効率的に配信
- 客観的なデータによるコンプライアンス取り組み実績の明示
- 社外への情報開示における一定の効果を実現
まとめ
コンプライアンス研修は、従業員一人ひとりの意識向上を目指すだけでなく、企業としてのリスク管理にも重要な役割を果たします。
研修の成果を適切に評価するためには、以下の方法が有効です。
| 評価方法 | 内容 |
| 研修後アンケート | 研修内容の理解度や満足度を確認する |
| 理解度テスト | 知識の定着度を把握する |
| 行動量の比較 | 研修前後の行動変化を測る |
| 意識レベルの比較 | アンケートやヒアリングで意識変化を確認する |
| 業務上の成果を確認 | コンプライアンス違反件数の減少など |
研修の効果を高めるためには、参加者の当事者意識を高める工夫や、経営層・管理職への優先的な実施、定期的な実施といった取り組みも必要です。eラーニングの活用も有効な手段の一つになるでしょう。
こうした評価と改善を継続的に行うことで、コンプライアンス研修の質を高め、企業価値の維持・向上につなげることができます。
コンプライアンス研修の課題解決に今すぐ使える実践ツールを
コンプライアンス研修のゴールは、研修によって社員一人ひとりが各種法令・社内ルールを順守することの重要性を自分事として理解し、研修後の行動に変化が生まれることにあります。
質の高い研修を計画・実施するのはもちろん、効果を持続させるために「研修後の振り返り」と「継続的な学習環境の整備」が欠かせません。とはいえ、毎年のように変わるコンプライアンスの範囲や、全社員向けの実施が前提の研修に、多くの企業が実施そのものに課題を抱えています。
そんなコンプライアンス研修特有の課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「動画研修コース」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
導入企業の具体的な成功事例と実践方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
コンプライアンス研修にも最適なeラーニングシステム『AirCourse』は、研修の実施から実施後のアンケート・振り返りテストにも対応しています。コンプライアンス研修を着実に実行に移し、組織の成長を加速させたい方はぜひご活用ください。