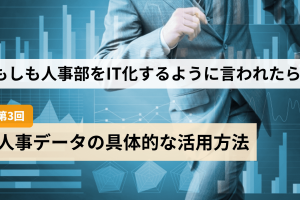人材開発に取り組む企業が増える中、多くの人事担当者がその実践方法に課題を感じています。「人材開発と人材育成の違いがわからない」「戦略的な人材開発の進め方がわからない」「個人の能力向上が組織パフォーマンスに結びつかない」といった悩みは、現代の人事管理において重要な問題となっています。
これらの課題は、人材開発の本質を理解し、体系的なアプローチを実践することで解決できます。人材開発は、単なるスキル向上ではなく、企業の戦略目標と連動した組織全体のパフォーマンス向上を目指す包括的なプロセスです。適切な仕組み構築、効果的な進め方、そして継続的な改善により、社員の能力最大化と企業の持続的成長を実現している企業が増えています。
本記事では、人材開発の基本概念から人材育成との違い、具体的な仕事内容と進め方のポイントまで、実践的な人材開発推進に必要な情報を体系的に解説します。効果測定の方法や成功事例も含め、自社に最適な人材開発システムの構築をサポートします。
効果的な人材開発で、組織の競争力を飛躍的に向上させましょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
人材開発の定義
人材開発とは、企業が持つ「人材」のスキルや能力を引き上げ、組織全体のパフォーマンスを向上させるためのプロセスを指します。
定義上では、人材育成との違いがわかりづらい言葉ですが、両者の違いをしっかりと理解することで、人材開発の重要性がより明確になるでしょう。その上で、組織の成長戦略に人材開発の視点を取り入れることで、一般的な社員教育や人材育成をアップデートすることができます。 それでは、項目別に人材開発と人材育成の違いを解説していきます。
人材開発と人材育成の違い
| 項目 | 人材開発 | 人材育成 |
|---|---|---|
| 対象 | 全社員(ただし、一律の内容ではなく、個別の取り組みとなる) | 新入・若手社員など、階層や役職別に実施される |
| 目的 | スキルアップを通じた組織力の強化 | 業務遂行上必要なスキルの習得 |
| 手法 | 自己啓発支援やOJTなど、個別支援に適した手法 | 目的に応じて、集合研修、OJT、ジョブローテーションなど適宜最適な手法が選ばれる |
| 習得スキル | ・問題解決力 ・コミュニケーション力 ・主体性、チャレンジ精神 | ・特定の業務に関する専門知識やスキル |
人材開発と人材育成の違いは、対象・目的・手法・習得スキルの4つの観点から考えることができます。
対象の違い
人材開発と人材育成では、対象者が異なります。
人材開発の対象者は、主に企業が雇用している社員全般です。企業は社員全体のスキルアップを目指し、経営戦略に沿った形で人材開発を行います。
| 人材開発の対象 | 人材育成の対象 |
|---|---|
| 社員全般 (ただし、一律の内容ではなく、個別の取り組みとなる) | 特定の人材 |
一方、人材育成の対象は、企業が重点的に育成したい特定の人材に限定されます。経営層の後継者育成や、グローバル人材の育成など、企業の将来を見据えた対象者を選定し、重点的に育成していきます。
つまり、人材開発は企業の全従業員を広く対象としたスキルアップですが、人材育成は将来の経営を担う人材などに絞り込んだ育成を行うという違いがあります。
ただし人材開発が「全従業員を対象にする」と言っても、画一的な教育を施す訳ではありません。人材開発では、企業全体の成長を加速させるために幅広い従業員を対象としますが、その内実は社員一人ひとりの課題や目標に寄り添ったものになります。この点が人材開発の大きな特徴と言えるでしょう。
目的の違い
人材開発と人材育成の目的は大きく異なります。
人材開発の目的は、企業の経営戦略に沿って、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織の成長に結び付けることにあります。
| 人材開発の目的 |
|---|
| 経営戦略実現に向けた人材の確保・育成 |
| 組織の競争力強化 |
| 従業員の士気向上と定着率の向上 |
一方、人材育成の目的は、業務遂行上必要なスキルの習得にあります。個々の従業員のスキルアップと自己実現を後押しすることで、結果として組織の活性化につなげることを目指します。
つまり、人材開発は組織の視点から、人材育成は個人の視点から、お互いに密接に関係しながらも、目的が異なるのがポイントです。
手法の違い
人材開発と人材育成では、その手法が異なります。
人材開発では、主に以下の手法が用いられます。
| 手法 | 概要 |
|---|---|
| OJT | 実際の業務を通じて、上司や先輩が部下を指導する手法です。 |
| OFF-JT | 職場外の研修施設などで行う集合研修です。座学や実習などが含まれます。 |
| 自己啓発支援 | 社員の自主的な学習を支援する制度です。通信教育や、資格取得支援などがあります。 |
一方、人材育成では以下のような手法がとられます。
- メンター制度・・・ベテラン社員が新入社員などをサポートする制度
- ジョブローテーション・・・計画的に異動を行い、多様な経験を積ませる
- 評価フィードバック・・・上司から適切な評価とフィードバックを行う
人材開発は主に知識やスキルの習得を目的とした手法が中心ですが、人材育成では経験の積み重ねを重視した手法が用いられる傾向にあります。
習得スキルの違い
人材開発と人材育成では、習得を目指すスキルが異なります。
人材開発では、以下のような汎用的な能力の習得を重視します。
| スキル | 内容 |
|---|---|
| 問題解決力 | 課題を発見し、解決策を導き出す力 |
| コミュニケーション力 | 円滑な対話を通じて、相手の意図を正しく理解する力 |
| 主体性・チャレンジ精神 | 自ら課題に取り組み、失敗を恐れずにチャレンジする姿勢 |
一方、人材育成では、特定の業務に関する専門知識やスキルの習得が中心となります。例えば、営業職なら商品知識や提案力、技術職なら設計力や分析力などが求められます。
このように、人材開発は汎用的な能力を高めることで、様々な職種に横断的に活用できる人材を育成します。一方、人材育成は特定の職務に特化したスキルを身につけさせるところに違いがあります。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
人材開発が必要とされる背景
組織のパフォーマンスを上げるのであれば、人材開発以外のアプローチもあるはずです。にもかかわらず、人材開発が重要であるのはなぜでしょうか。これは人材開発が必要とされている背景に着目することで理解できます。
ポイントは、人材開発においては、組織のパフォーマンス向上が個人の成長に基づいている、ということです。
VUCA時代に適応できる主体的な個人の育成
現代のビジネス環境は、急速に変化しています。VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)と呼ばれることもあり、このような予測困難な状況では、社員一人ひとりが自ら情報を収集し、状況を分析して、素早く適切な行動を取ることが求められます。
しかし、多くの企業では、社員の主体性を引き出すことに課題を感じているのではないでしょうか。このような状況を打開するためにこそ、人材開発が有効です。
人材開発の対象は社員全員ですが、その支援の仕方は一律ではありません。なぜなら、社員一人ひとりが抱える課題や目指すべき方向性は異なるからです。社員一人ひとりの状況に合わせて、きめ細やかな支援を行うのが人材開発なのです。
そして、個々のニーズに寄り添った支援を行うことで、社員の主体性を効果的に引き出すことができます。
このように人材開発の視点を取り入れることで、従来の人材育成の視点では見落とされがちな社員の主体性を育成することができます。その結果、組織全体の変化への対応力が高まり、VUCA時代における競争力を維持することができるでしょう。
DXを推進できる組織の確立
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、現代のビジネスにおいて避けて通れないテーマです。DXを成功させるためには、単なるIT技術の導入だけでは不十分で、新しい技術を活用しながら、ビジネスモデルや業務プロセスを根本から変革しなければいけません。
しかし、多くの企業では、DXを推進できる人材が不足しているのが現状です。実際、従来のIT部門の枠を超えて、ビジネス戦略とデジタル技術を融合させ、イノベーションを起こせるようなスキルセットを持った人材の育成は簡単ではありません。
そこで、人材開発が重要になってきます。
従来の人材育成では、業務遂行上必要なスキルを身につけさせることが中心となりがちです。しかし、DXを推進するには、それだけでは不十分です。変化を恐れずに新しいことにチャレンジし、失敗から学ぶ姿勢や、自ら課題を発見し解決する主体性が求められるからです。
DXの波は、今後ますます加速していくでしょう。その波を乗りこなし、競争優位を確立するためには、DXを推進する人材の育成が不可欠です。人材開発への投資は、単なるコストではなく、デジタル時代を勝ち抜くための戦略的な布石なのです。
仕事観の多様化
近年、職場では仕事観の多様化が進行しています。これは、従業員一人ひとりの価値観や働き方が多種多様になっていることを指します。例えば、「仕事は生活の一部であり、仕事とプライベートを両立させたい」という考え方や、「自分のスペシャリティを活かして活躍し、高い成果を上げたい」という志向などが存在します。
このように、社員一人ひとりの仕事観が多様化する中で、画一的な教育では、社員のエンゲージメントを引き出すことが難しくなっています。社員のモチベーションや生産性を高めるためには、一人ひとりの価値観や志向性を理解し、それぞれに合った働き方やキャリア形成の機会を提供することが不可欠です。
まさに人材開発ではこの点を重視します。後述しますが、人材開発では「個人支援」が原則です。つまり、社員一人ひとりの仕事観や目指すキャリアに合わせて、最適な成長の機会を提供することが求められます。
個別のニーズに寄り添った支援を行うことで、多様な人材が活躍できる環境を整備し、社員のエンゲージメントを高め、組織の成長につなげることができるでしょう。
人材開発担当の役割
ここまで人材開発の特徴を説明してきましたが、実際にどのような仕事があるのか気になる方もいるでしょう。人材開発の仕事内容は以下の通りです。
- 教育・研修の制度設計
- 研修の運営
- 自己啓発支援
- 育成担当者の支援
人材開発の仕事は一般的な人材育成と重なる部分も多いですが、一方で人材開発ならではの取り組み方もあるので、以下ではこの点に着目しながら説明していきます。
教育・研修の制度設計
人材開発担当者の主要な役割の一つは、教育・研修の制度設計です。これは、社員のスキルアップを実現し、組織全体の成長を促進するための重要な仕事です。
多くの企業では、これまでも人材育成として階層別の研修が行われていたでしょう。これらの研修の設計も重要な役割ですが、人材開発ではさらに、社員一人ひとりのニーズや必要な人材に応じた教育・研修を設計する必要があります。
研修の運営
研修の設計だけでなく運営も人材開発担当者の重要な仕事です。日時や場所の決定、関連資料の準備、講師の手配といった研修自体の準備のほか、場合によっては研修前の他部署との調整も必要になるかもしれません。
なぜなら、繁忙期真っ只中の部署や人手不足の部署では、研修の参加に難色を示す可能性があるためです。このようなケースでは、人材開発担当者が研修の重要性を説明し、積極的な参加を促さなければなりません。
自己啓発支援
自己啓発支援とは、社員一人ひとりが自ら成長の意欲を持ち、スキルを磨くことをサポートする活動です。人材開発では内発的動機付けによるスキルアップを重視するので、1on1ミーティングでメンタル面のケアを行なったり、学習のモチベーションを高める資格取得支援制度の導入なども、ときには必要になります。
育成担当者の支援
人材開発担当者も育成に携わる場面がありますが、多くの場合、実際の育成は専門的なスキルを持った社員や、チームのリーダーが請け負うことになるでしょう。そのため、人材開発担当者は、育成担当者の支援を行うことで、人材開発を成功に導く役割を担います。
具体的には、育成計画の作成をサポートしたり、必要な学習ツールを提供するなどの支援が挙げられます。また場合によっては、人材育成を始めて行う担当者には、育成に必要なスキルを身に付けさせるために研修を行うこともあるでしょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
人材開発担当に求められるスキル
人材開発の仕事内容からも想像できる通り、人材開発担当者にはいくつか必須のスキルがあります。具体的には以下の通りです。
- コーチングスキル
- ファシリテーションスキル
- 戦略的思考
ぜひ自分自身のスキルアップや、人材開発担当チームの組織力アップの参考にしてください。
コーチングスキル
コーチングとは、コーチとクライアントの対話を通じて、クライアントが目標達成に向けて主体的に行動することを支援するプロセスです。コーチングの大きな特徴は、クライアントが主導権を握っているという点にあります。
コーチングは特別なスキルというより、育成対象者と関わる際に必要な態度であり、基本的なコミュニケーションのあり方として理解するとよいでしょう。「承認」「傾聴」「質問」といった要素をコーチングのスキルとされることがありますが、重要なのは、相手の考えを尊重し、目標達成に向けて最後まで伴走する意識だからです。
また、ティーチングという似た言葉がありますが、これは指導者が持っている知識を学習者に付与する取り組みです。社員教育には不可欠な取り組みですが、基本的に受動的な学習になってしまうというデメリットがあります。
一方でコーチングでは、目標達成までの道のりはクライアント自身が能動的に発見します。そのため、コーチングを行うことで、人材開発に不可欠な、社員の主体性を引き出すことが可能になります。
コーチングについては以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
コーチングとは?ビジネスに取り入れる効果や方法、学び方を解説
ファシリテーションスキル
人材開発担当者は、研修やワークショップを運営する際にファシリテーターの役割を担うことがあるため、ファシリテーションスキルも必要になります。ファシリテーターに必要な能力は以下の通りです。
- 話の内容を即座に理解する力
- 議論を整理する力
- 質問力
- 傾聴力
また人材開発担当者は、企業全体のパフォーマンスを底上げするために、部署間連携を行う場面もあります。各部署の課題や人材ニーズを吸い上げて、最適な教育・研修制度を設計するためにも、ファシリテーションスキルが不可欠です。
戦略的思考
戦略的思考とは、会社のビジョンや目標に向けて、長期的な視点で必要な人材をどのように育成するかを計画する能力のことです。人材開発担当者としては、組織の現状や将来予測を把握し、それに対応した適切な人材育成計画を立てることが求められます。
例えば、DXを推進する場合、ITスキルやデータ分析能力を持った人材が必要となるでしょう。その場合、戦略的思考を持った人材開発担当者は、既存の社員がこれらのスキルを習得できるような研修プログラムを計画するか、新たに該当スキルを持つ人材を外部から採用するかを決定します。
人材開発に有効な6つの手法
人材開発では、人材育成と同じように必要に応じて集合研修なども行いますが、多くの場合、以下のような個人の成長に特化した手法が選ばれます。
- 自己啓発(SD:Self Development)
- 1on1ミーティング
- OJT
- OFF-JT
- タフアサインメント
- eラーニング
自己啓発(SD:Self Development)
自己啓発とは、社員が能動的に自分のレベルアップを図る行為です。人材開発では、企業が用意した研修や教育プログラムを受講することも重要ですが、大前提として社員自身が人材開発の目的を理解し、それに向かって自分自身が主体となって行動しなければいけません。
そのため、まずは自己啓発支援を行いましょう。具体的には、コーチングを取り入れた1on1ミーティングや資格取得支援制度の導入、外部研修の紹介などでも自己啓発を促すことができます。
1on1ミーティング
1on1ミーティングとは、上司と部下が定期的に1対1で行う面談のことです。1on1ミーティングの最大の目的は、部下の成長促進を支援して能力を引き出すことにあり、部下の仕事の進捗や課題、悩みを共有し、適切な支援を行います。
その際には上司の一方的なコミュニケーションではなく、上司と部下の双方向のコミュニケーションを意識的に行い、今後なにをすべきか、どのように業務に取り組むべきかを気づかせてあげるような対話の仕方が重要とされます。
頻度は週1回程度とし、時間は長くても1時間、部下がリラックスして会話できる落ち着ける場所で実施しましょう。
OJT
OJT(On-the-Job Training)とは、職場での実務経験を通じて知識やスキルを習得する育成方法です。主に新人を対象として、同じ部署の上司や先輩がトレーナー(育成担当者)となり育成を行います。人材育成では一般的な手法ですが、社員一人ひとり丁寧な指導ができるため、人材開発においても有効な手法です。
ただ、各部署とも日常業務に追われるなかで、明確な目的や計画もなく効果的なOJTを行うのは困難なのが実状です。先輩社員が新人に対して必要に応じて行う業務説明や指導までにとどまるケースも少なくありません。
そのためOJTを意図的・計画的・継続的に行うための取り決めである「OJT制度」を整える必要があります。
OFF-JT
OFF-JT(オフ・ジョブトレーニング)とは、職場から離れた環境で行われる教育・研修のことを指します。具体的には、社内研修や外部セミナー、ビジネススクールなどで学ぶ方法が一般的です。特に、自社に不足しているナレッジやスキルを習得する際に有効な手法といえます。そのため、人材開発で新しい領域に挑戦する際は、適宜OFF-JTも取り入れると良いでしょう。
タフアサインメント
人材開発における「タフアサインメント」とは、難易度の高い業務を担当者に任せることです。具体的には、新規プロジェクトのリーダーを任せる、海外事業の立ち上げを担当させるなどが考えられます。これらの業務は困難かもしれませんが、その過程で得られる経験やスキルは計り知れません。
タフアサインメントを活用する際のポイントは、適切な「支援」と「フィードバック」を行うことです。アサインメントの前後で十分なヒアリングを行い、進行中は定期的なサポートを提供しましょう。そして終了後は反省会を設け、次のステップにつなげる工夫が求められます。
eラーニング
eラーニングは、インターネットやデジタルメディアを活用した教育・学習手法です。従来の教育形式と比較して、時間や場所に制約がなく、自分のペースで学ぶことができる点が大きなメリットといえるでしょう。
またeラーニングでは、各学習者の進捗や理解度を管理・把握し、必要に応じて学習内容を調整することも可能です。これにより、個々の学習者に合わせたパーソナライズドな学習体験を提供することができるため、効率的に人材開発を進めることができます。
eラーニング成功のコツは”導入設計”にあります
eラーニングの基本的な仕組みは理解できても、実際に成果につながる運用を継続することは簡単ではありません。多くの企業が「導入したが受講率が低い」「コンテンツ作成に時間がかかりすぎる」「効果測定ができない」という課題に直面しています。
これらの課題解決には、単なるシステム選定ではなく、学習文化の醸成から効果測定まで含めた包括的な導入戦略が不可欠です。成功企業では、5つのステップで段階的にeラーニングを組織に定着させ、継続的な学習環境を構築しています。
戦略的な視点からeラーニング活用を推進する、体系的な導入アプローチを学んでみませんか。
人材開発の進め方
人材開発は、組織全体の生産性や競争力を高めることを目的としています。具体的には、従業員一人ひとりの能力を最大限引き出し、組織全体の人材力を向上させていくことが重要です。そのためには、まずは組織の課題やニーズを明確にし、求められる人材像を定義することから始まります。
その上で、自己啓発やOJT、OFF-JTなど、効果的な育成手法を組み合わせて、体系的な人材開発プログラムを構築していく必要があります。人材開発の取り組みを通じて、組織の活性化と持続的な成長につなげていくことが重要です。
課題の抽出
人材開発を実施する際の第一歩は、組織や個人がどのような課題に直面しているのかを明確にすることです。この課題の抽出は、次の3つのステップで行います。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 現状の把握 | 業績データや従業員の声などから、現状を正しく把握する。 |
| ギャップの特定 | 現状と理想の姿との差異(ギャップ)を特定する。 |
| 課題の設定 | ギャップの原因を分析し、解決すべき具体的な課題を設定する。 |
漠然とした問題意識では、効果的な施策を打つことはできません。解決すべき課題を具体的に特定することで、初めて最適な育成方法の検討が可能になるのです。
求める人物像の確立
続いて、組織の理念や目標、事業戦略などを踏まえ、求められる人材像を具体的に定めます。
例えば、経営企画部門では以下のような人物像が求められるでしょう。
| 期待される人物像 | 具体的な行動特性 |
|---|---|
| 戦略的思考力 | 環境変化を的確に捉える中長期の視点で課題を発見できる |
| 企画立案力 | 新しい発想ができる論理的な企画書を作成できる |
| リーダーシップ | 部下を方向付けられる組織をまとめあげられる |
このように、部門ごとの役割や求められる資質を明らかにしておくことで、人材開発の目標が明確になり、より効果的な育成が可能になります。
必要なスキルの洗い出し
人材開発を効果的に進めるためには、育成したい人材が備えるべき知識、スキル、能力を具体的に特定することが重要です。
【人材開発で習得を目指すスキル例】
- 業務知識
- 問題解決力
- コミュニケーション能力
- リーダーシップ
- 創造力
習得スキルは、企業の経営戦略や人事戦略、業界動向などを踏まえて検討します。また、部門や職種ごとに異なるスキルが必要となるため、それらを洗い出す必要があります。
スキルの特定には、上位者や先輩社員へのヒアリング、職務分析、業績評価結果の分析などが有効です。スキルを体系的に整理し、個人やチーム、組織レベルでの育成目標を明確にすることが肝心です。
開発方法の検討
人材開発の育成方法を検討する際は、以下の3点に留意しましょう。
育成目標に合わせた適切な手法の選定
ステップアップを目指す役職や習得を目指すスキルに応じて、以下の手法などから最適な組み合わせを選びます。
| 手法 | 概要 |
|---|---|
| 自己啓発(SD) | 個人が主体的に学ぶこと |
| 1on1ミーティング | 上司が部下に対する個別指導 |
| OJT(On-the-Job Training) | 実務を通じた実践的な育成 |
| OFF-JT | 研修や講習会での理論的育成 |
| タフアサインメント | 挑戦的な課題への挑戦による育成 |
| eラーニング | インターネット上の学習コンテンツ |
たとえば、全社員のDXスキル向上を目指す場合、次のような組み合わせが考えられます。
- eラーニングを活用し、デジタルリテラシーの基礎を効率的に身につけさせる
- Off-JTとして、外部の専門講師を招き、データ分析やAI活用に関するより実践的な研修を実施
- DX推進の主要メンバーに対し、適宜1on1ミーティングを実施し、経験のない業務に対する不安を取り除き、モチベーションを維持させる
このように人材開発では、育成目標に合わせて、複数の手法を組み合わせることがポイントです。
費用対効果の検討
育成に要する費用(外部研修費用、eラーニングシステム整備費用など)と、育成による生産性向上効果のバランスを検討します。検討する際は、育成によるスキルアップが実際の業務遂行能力の向上や生産性の向上につながるかを確認することが重要です。
単に研修を行えば良いというわけではなく、どの程度の効果が得られるかを試算する必要があります。例えば、育成によってどの程度の業務効率化が見込まれるのか、業務プロセスの改善度合いはどうなのかなど、定量的なメリット算出が求められます。この検討結果を踏まえて、最適な育成手法を選定し、効率的な人材開発計画を策定していくことが重要になります。
社内インフラの整備状況の確認
OJTやOFF-JTを円滑に進められる環境が整っているかを確認し、必要に応じてインフラ整備を行います。具体的には、eラーニングシステムの導入、研修実施に必要な機材の準備、OJTが効果的に行えるような業務フローの再構築などが考えられます。
これらのインフラ整備を適切に行うことで、効果的な人材開発を実践することができます。また、インフラの整備状況を定期的に確認し、必要に応じて改善を図ることで、継続的な人材開発の実現が可能になります。
開発目標・計画の策定
具体的な開発計画を立てる際は、育成対象者のキャリアステージや目標とする役割などに合わせた育成プログラムを設計することが重要です。入社1年目の新入社員と、管理職候補の中堅社員では、求められるスキルも異なり、育成手法も変わってきます。対象者の特性を正確に把握し、それぞれにふさわしい育成計画を立案することで、効果的な人材開発が実現できます。
また、育成計画の策定にあたっては、短期・中長期の育成目標を明確に定め、KPIを設定し、進捗状況を適切にモニタリングすれば、必要に応じて計画の修正を行うことができます。また、具体的な目標値を設定しておくことで、客観的な評価が可能になり、育成の成果を可視化しやすくなります。さらに、KPIの設定に当たっては、単に数値目標を立てるだけでなく、行動指標や能力指標などを組み合わせることで、より効果的な人材開発が実現できます。
実践・フィードバックを繰り返す
人材開発は一過性のものではありません。継続的な実践とフィードバックのサイクルが重要です。
| 実践 | フィードバック |
|---|---|
| 研修や自己啓発を実際に行う | 上司や先輩からの評価を受ける |
| OJTで実務を経験する | 目標に対する達成度を確認する |
| 新しい役割を任される | 習得した知識や技術を振り返る |
実践の場を設けてみるだけでは不十分といえるため、 上司や先輩からの適切なフィードバックを受け、自身の長所や改善点を認識することが大切です。
振り返りを行い、次の実践に向けた目標を立て直すことで、 スパイラルに成長を続けることができます。 フィードバックを受けて気づいた課題に対し、新たな育成方法を検討することも重要なプロセスとなります。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
人材開発を効果的に進めるポイント
これまでの人材育成に加えて、企業の成長を加速させるために人材開発に取り組む場合、人材開発ならではのポイントを押さえておく必要があります。
- 企業の目標に必要な人物像を明確にする
- 企業と社員の間にあるギャップを明らかにする
- 「個人支援」の原則を守る
- 社員が主体的にキャリアを描けるようサポートする
- タレントマネジメントシステムを整える
- eラーニングを活用する
企業目標に必要な人物像を明確にする
人材開発の目的は、組織のパフォーマンスを高めたり、企業の目標を達成したりすることです。したがって、企業目標に必要な人物像を明確にすることから始まります。必要なスキルは何か、どのようなマインドを持っているべきかといった点を、できるだけ具体的に整理しましょう。
この際、現場からのニーズにも耳を傾けるようにしてください。企業目標に沿った人物像を人材開発担当者が一方的に定義しても、必ずしもそれが現場の課題を解決するものとは限りません。また、人材開発を通じたパフォーマンス向上に対する期待が現場にも浸透していなければ、自己啓発も困難になるでしょう。
人材開発を進める場合は、部署間、組織間で連携して、一体となって進めていくという意識が大切です。
企業と社員の間にあるギャップを明らかにする
求める人物像を明確にしたら、現状把握を行い、目標と現状のギャップを明らかにします。スキル面のギャップだけでなく、企業ビジョンに対する理解なども測定対象です。なぜなら、企業ビジョンに対する理解や共感は、社員のエンゲージメント、ひいては組織のパフォーマンスに関わるためです。そのほか、社員一人ひとりのキャリアプランや行動特性なども明らかにすると良いでしょう。
これらの調査をすることで、以下のような点が明らかになってきます。
- 最適な人材配置
- 身に付けさせるべきスキルセット
- 育成に必要な期間
- 最適な育成手法
- 必要なケア
「最適な人材配置」「必要なケア」について補足します。例えば、人材開発を通じてDX推進体制を整備したいとすると、場合によっては非IT人材をIT人材に育成し、部署転換や職種転換を要求されます。この時、闇雲に対象者を選抜する訳にはいきません。社員の特性に基づいて、最適な人選を行う必要があります。
また、大きな職種転換は社員にプレッシャーを与えることもあります。そのため、育成期間を通してメンタル面のケアも必要になるでしょう。
教育・研修制度の設計は、明らかになったこれらの要素に基づいて進めていきます。
「個人支援」の原則を守る
「個人支援」の原則を守るとは、一人ひとりの社員が自己成長するための支援を具体的に行うことです。人材開発では、社員全体のスキル向上を目指すと同時に、個々の社員が抱える課題を理解し、それぞれに適した成長の機会を提供することが求められます。
そのためには丁寧な事前調査が必要です。先に説明したように、現状把握を行うことで必要なスキルセットや最適な育成手法などが明らかになります。これらに基づいて最適な「個人支援」の形を模索するようにしましょう。
社員が主体的にキャリアを描けるようサポートする
人材開発の目的は社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織の成長に結びつけることです。それぞれが目指す姿も異なるため、人材育成とは違って取り組みも一律ではありません。
そのためにも、社員が自身のキャリアを振り返る場づくりを行うことをおすすめします。自己啓発支援やOJTなどを活用し、内発的動機付けを促すことで、一人ひとりが意欲的に臨むサポートを行うようにしましょう。
タレントマネジメントシステムを整える
人材開発を効果的に進めるためには、タレントマネジメントシステムの整備が欠かせません。タレントマネジメントシステムとは、社員の情報を一元管理し、人事や人材育成を効率的に行うためのシステムです。
タレントマネジメントシステム上の社員情報には、一般的に以下の内容が含まれます。
- 氏名などの基本情報
- 所属部署
- 保有スキル・資格
- 職務適正
- 過去の評価
こういった情報を、人材開発担当者や育成担当者が共有することで、「個人支援」の人材開発を効率的に進めることができます。
eラーニングを活用する
「人材開発に取り組みたいが、日々の業務で手一杯で、時間の確保が難しい」と考える人材開発担当者の方もいるのではないでしょうか。そこでおすすめなのが、eラーニングの活用です。
eラーニングとは、パソコンやタブレットなどのデジタル機器を使い、インターネット上で学習をする方法です。時間や場所を選ばず、一人ひとりの目的や習熟度に合わせて、自身のペースで学習することができます。
コンピュータ上で全体の学習状況を把握できるため担当者の業務負担を軽減することができます。さらに、自ら学びたいことを選べる方法でもあるため、社員の自主的な成長を促すこともできるでしょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
eラーニングを活用し人材開発に取り組んだ企業事例
人材開発の成功には、個人の成長意欲を引き出しながら、組織全体のパフォーマンス向上につなげる戦略的なアプローチが重要です。
ここでは、eラーニングを活用して効果的な人材開発を実現し、個人支援と組織力強化を両立させた企業事例をご紹介します。インサイドセールス人材の育成と提供、専門スペシャリストの効率的育成、組織拡大と教育体制強化の両立など、各社が取り組んだ人材開発の具体的な手法と成果が詳しく紹介されています。
これらの実践例から、自社の人材開発戦略をより効果的に展開するためのヒントを見つけることができます。
インサイドセールス人材を育成し顧客への人材・ノウハウ提供を実現|株式会社エムエム総研様

BtoBマーケティングに特化してワンストップ支援を展開する株式会社エムエム総研様では、新規事業のインサイドセールス支援サービスにおいて、インサイドセールス・デジタルマーケティング人材の育成効率化が課題でした。独自の講義プログラムを開発し社内ディレクターが講師を担当していましたが、従来の集合研修では講義に多くの工数がかかり、育成における教育・学習コストの増大が問題となっていました。
AirCourseを活用して「育成におけるインプット部分のeラーニング化」を実現し、教育を効率化しました。eラーニング×集合(対面)研修を実施することで、基礎知識のインプットはeラーニングで自身のペースで習得し、集合研修では実践的なスキル習得に集中できる体制を構築。講義プログラムが体系化される中で、さらなる効率化を求めて導入したAirCourseにより、顧客に提供できる価値を最大化するPDCAサイクルを確立しています。
導入後の主な成果
- インプット部分のeラーニング化により教育工数を大幅削減
- eラーニング×集合研修の組み合わせで人材育成を効率化
- 体系化された講義プログラムでインサイドセールス人材を安定供給
参考:業界でも類を見ないBtoBマーケティング人材の育成から提供|株式会社エムエム総研様 AirCourse導入事例
土壌汚染専門スペシャリストに最速で育成するプロセス構築|株式会社フィールド・パートナーズ様

土壌汚染に関するコンサルティング・調査業務を展開する株式会社フィールド・パートナーズ様では、土壌汚染専門のスペシャリスト育成において、オフライン勉強会による教育・学習にかかる工数増大が課題でした。土壌汚染問題の環境的側面と土地活用の経済的側面の両方からアプローチする高度な専門知識が必要で、個人の専門性レベルに応じた効果的な育成プログラムが求められていました。
AirCourseを活用して「土壌汚染専門のスペシャリストの育成をeラーニング化」し、未経験者のオンボーディングで即戦力化を実現しました。eラーニングとOJTを合わせることで、オンボーディングを最適化し、人材採用から即戦力化までのプロセスを体系化。コンテンツ作成の権限を現場社員にも付与することで、実務に即した専門知識の共有と継続的な改善を実現しています。土壌汚染問題を解決できるスペシャリストに最速で育成するシステムを確立しています。
導入後の主な成果
- eラーニング化により専門スペシャリスト育成の工数を大幅削減
- eラーニング×OJTの組み合わせでオンボーディングを最適化
- 未経験者から即戦力化までのプロセス構築を実現
参考:スペシャリストに最速で育成するプロセス構築に向けて|株式会社フィールドパートナーズ様 AirCourse導入事例
組織拡大と教育体制強化を両立し研修を効率化|株式会社MS-JAPAN様

管理部門・スペシャリスト特化の人材紹介事業を展開する株式会社MS-JAPAN様では、組織規模が大きくなるにつれて教育体制強化が求められました。東証マザーズ上場、東証一部市場変更によりガバナンスやコンプライアンス強化が必須となり、社員急増と株式上場により組織が大きく変化する中で、教育のスピードとクオリティを担保する必要がありました。集合研修では物理的に一か所に集まることが困難な状況でした。
AirCourseの導入により「eラーニングで研修の『場所と時間』の問題を解決」し、研修効率が格段に向上しました。インサイダー取引防止、ハラスメント対策、情報セキュリティなどのコンプライアンス教育を全社展開し、受講状況の詳細管理により効率的なフォローアップを実現。社員が急増する中でも統一的な教育機会を提供し、時間・カネのリソースを最適化することで、組織拡大と教育体制強化を両立させています。
導入後の主な成果
- eラーニング化により研修の場所・時間制約を解決し効率が格段に向上
- 東証上場に伴うコンプライアンス強化を全社レベルで実現
- 組織拡大と教育体制強化を両立し時間・コストリソースを最適化
参考:eラーニングで研修の「場所と時間」の問題を解決|株式会社MS-JAPAN様 AirCourse導入事例
まとめ
本記事では人材開発の重要性を、人材育成と比較しながら解説してきました。重要なポイントは、人材開発は「個人支援」を原則に進め、それを通じて企業や組織のパフォーマンスを向上させるものであるという点です。
また、人材開発は様々な関係者とコミュニケーションをとりながら進める取り組みです。そのため、コーチングやファシリテーションなどのスキルが必要とされます。これから人材開発を進めていく場合は、これらのスキルを自分自身や、そのチームで身に付けていく意識も持っておくと良いでしょう。
人材開発は企業の成長を加速させる重要な取り組みです。ぜひ本記事を振り返りながら、人材開発に取り組んでみてください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。