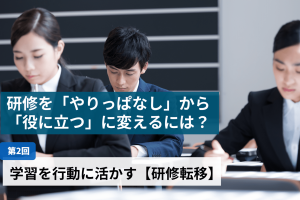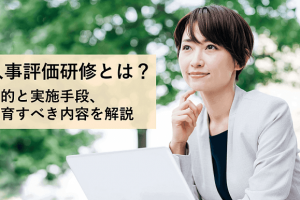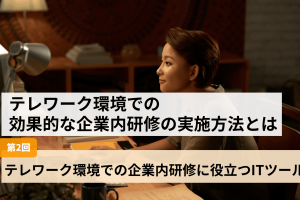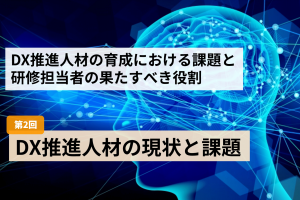「集合研修のスケジュール調整が困難」「会場手配の負担が大きい」「研修の質にばらつきが生じる」といった課題を抱える人材育成担当者が増えています。特に人材の流動性が高まる中、効率的かつ効果的な研修体制の構築は企業にとって急務の課題です。
こうした課題を解決する手段として、動画研修(eラーニングの一種) が注目されています。動画研修なら、時間や場所の制約を受けずに、均質な研修内容を提供できるからです。
本記事では、動画研修のメリット・デメリットから、具体的な活用方法、さらに導入企業の成功事例 まで詳しく解説します。新人研修やマネジメント研修の効率化を図りたい人材育成担当者は、ぜひ参考にしてください。
eラーニング活用の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
eラーニング活用の重要性は分かっている。でも「具体的にどう運用するか」「結局どのeラーニングシステムが自社に合うのか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「幅広いニーズに対応するeラーニングシステム」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
動画研修とは
動画研修とは、オンラインで研修動画を配信して受講させる育成手法です。本来は動画を視聴して学ぶ形式の研修であれば全て動画研修と定義しますが、一般的にはオンラインで受講する形式を指します。
つまり、動画研修はパソコンやスマートフォン等とインターネットを利用して教育や学習を行う「eラーニング」の一種として位置づけられます。
具体的な動画研修の例として以下のものが挙げられます。
- 新人研修
- マネジメント研修
- コンプライアンス研修
階層別の研修やビジネススキルに関する研修、社会人として守るべき規範に関する研修など、幅広いコンテンツを利用することができます。
動画研修が注目される背景
動画研修が注目される背景としては、人材の流動性が高まったことで、定着率を維持・向上させるために人材育成の充実化が求められていることが挙げられます。
動画研修を用いて組織内の人材育成を充実させることで「成長できる場」を実現して企業としての魅力を高めるのです。
また、人材確保が難化していることもあり、限られた人員で充実した育成を行うためには、提供側と受講側の負担軽減が不可欠です。
こうした点からも負担を少なく人材育成を行えるというメリットにより、動画研修が注目されています。さらに昨今はコロナ禍の影響もあり、場所に縛られずに人材育成を行える点が評価されています。
動画研修を提供する育成担当者のメリット
動画研修のメリットについて、まずは動画研修を「提供する側」の視点からみてみましょう。
会場手配など準備の負担を軽減できる
動画研修であればオンライン上で完結するため、一般的な集合型研修と比較して以下の準備が不要となります。
- 会場の手配
- 会場内の机や椅子のセッティング
- プロジェクターやモニターの準備とテスト
- マイクやスピーカーの準備とテスト
- 資料の印刷
- 終日の研修であれば昼食の手配
上記の例を見るとわかる通り、集合型研修はその都度、多くの人的コストと時間的コスト、さらに資料などの準備コストがかかります。しかも一度限りではなく、新人向けの研修などは毎シーズンこれらのコストがかかるのです。
一方で、動画研修であればこの問題を大きく解消することができます。たしかに導入時は既存の教育体制に動画研修を取り入れ、システムを構築する必要があるため、多くのリソースが必要になります。
しかし、一度環境を整えてしまえば、長期的なコストカットを図ることができ、その分のリソースをその他の業務にあてることができるのです。
講師や受講者のスケジュール調整が不要
動画研修は、事前に撮影・録画された研修動画をオンラインで配信することで、いつでも視聴可能です。そのため、集合型研修のように講師や受講者のスケジュール調整を行う必要はありません。
現実問題として各部門・部署ともに通常業務が忙しいなか、同日時に一堂に会して研修を行うことは、困難なケースが多いのではないでしょうか。
例えば、「ある部署は参加できるが別の部署は繁忙期にあたるため参加不可」、「特定の部署を対象としたいが部署内全員が参加すると業務が回らない」などの問題が後を絶ちません。全国各地に拠点がある場合などでも同様の問題が発生します。
個人視聴形式の動画研修であれば、受講者が都合の良いタイミングで視聴することができるため、こうしたスケジュール調整に関する問題が一挙に解消されます。
研修の質や内容を統一できる
1つのテーマに対して、受講者は同じ研修動画を視聴して学びます。
そのため、研修の質に差が出たり、内容に違いがあったりということは起こりません。いつ誰が見ても均一の質と内容で学習が可能です。
社内教育で起こりがちな「育成担当や講師によって教える内容が異なる」「教える能力にムラがある」といったケースを避けることができます。
動画研修を受講する育成対象者のメリット
動画研修のメリットについて、動画研修を「受講する側」の視点からみてみましょう。
いつでもどこでも受講できる
動画研修は、パソコンやスマートフォンとネット環境さえあれば「いつでもどこでも受講可能」です。
例えば常に外回りの営業担当であっても、空き時間を利用してカフェや車内などで受講可能です。急な電話が入ってきても動画を途中で止めて対応することもできます。
また、大事なプレゼンや商談の前に、ちょっとした空き時間でプレゼンのコツなどを解説した動画を視聴することで、より良い成果が期待できるかもしれません。
さらに、動画研修の時間と場所に対する柔軟性の高さは、育児休暇中の社員などにとっても大きなメリットです。
育児休暇後の職場復帰は、職場の変化にうまく馴染めず、疎外感を感じてしまうケースがあります。しかし、eラーニングを通じて社内の動向や新しいスキルを身につけることができれば、スムーズな職場復帰を果たすことができます。
職場復帰に対する安心感は、育児休暇取得率の向上にも繋がります。その結果、企業の評判を高め、優秀な応募者の増加も期待できるでしょう。
繰り返し視聴できる
動画研修であれば、「見逃した・聞き逃した」という場合も好きなように巻き戻して何度も視聴できます。また復習を目的として、期間を空けて同じ研修動画を視聴することも可能です。
例えば実務のノウハウに関する研修動画であれば、現場で不明点や疑問点が発生した際でも該当の動画を視聴することで解消できます。
現場での疑問を他者の手をかりずにその場で解消することは、業務効率化にもつながります。
心理的なハードルが低い
動画研修は対面の集合型研修とは異なり、目の前にあるのはパソコンやスマートフォンです。そのため、指名で発表を強いられることもなく、気軽に受講できる点は受講者にとってのメリットです。
社員によっては心理的な負担が軽減されて研修に対するイメージが改善され、社員のエンゲージメントの向上に繋がるケースもあるでしょう。
また、動画研修は視聴する場所を選ばないので、自宅などのプライベートな空間でリラックスして学習することができます。
そしてプライベートな空間だからこそ、周囲の目を気にせず納得いくまで繰り返し視聴することができるので、深い理解に落とし込むことができるでしょう。つまり、心理的ハードルの低さが、結果として学習効果を高めることにも繋がるのです。
映像と音で理解しやすい
動画研修であれば、必要に応じて実際の手順を映像で示したり、重要な部分をズームアップやテロップ、音で強調したりすることが可能です。
例えば、名刺交換の手順など文字や画像では伝えにくい情報も、動画であれば実際の動作をわかりやすく伝えることができます。
このように、単純なテキストでの学習と比較して、動画研修は視覚や聴覚への刺激が多く、理解が深まりやすいというメリットがあります。
eラーニング活用の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
eラーニング活用の重要性は分かっている。でも「具体的にどう運用するか」「結局どのeラーニングシステムが自社に合うのか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「幅広いニーズに対応するeラーニングシステム」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
動画研修のデメリットと対処法
動画研修にはメリットに対して、デメリットもあります。ここでは、動画研修のデメリットと対処法をあわせて紹介します。
質問への返答に時間を要する
動画研修はリアルタイムではないため、その場での質疑応答はできません。そのため、質問がある場合は別途、講師や担当者へ質問内容を伝えて返答を待つことになります。
対処法としては、研修動画の最後にアンケート記入を設けておき、動画視聴後すぐに質問を収集できるようにしておきます。
その上で、返答を受講対象全員に行うことで、似た疑問を同時に解消できます。この手法を用いれば、質疑応答をテキストデータで残せるため、「よくある質問への回答」を用意して、回答にかかる負担を減らすことが可能です。
受講管理が煩雑になりやすい
動画研修で起こりがちなのが、受講管理の煩雑化です。動画研修を効果的に運用するためには、どの社員が研修を完了し、どの社員がまだ研修を受けていないのかを把握する必要があります。
しかし受講状況の把握は社員自身の報告に依存しているため、正確な状況の把握が難しくなり、担当者は逐一報告を呼びかけなければなりません。
そのほかにも、担当者は受講管理のために以下のことを行う必要があります。
- 受講案内(手順や期限など)
- 受講完了報告の呼びかけと受付け
- Excelなどで管理表の作成
- 管理表での受講状況管理
- リマインド連絡
- 資料の配信
このような受講管理の煩雑さを改善し、適切に運用するための対処法として以下の2点が挙げられます。
1点目は、各部署に受講管理担当を設ける対策です。
対象となっている部署ごとに受講を促進するための担当者を設けます。
担当者は自部署メンバーの受講状況を管理しながら、期限内に全員が受講するように促します。全員の受講が完了したら、総管理者(例:人事部社員など)へ報告します。人事部などが一括で全社員を管理するよりも、効果的かつ効率的です。
2点目は、受講管理が行えるeラーニングシステムの導入です。
動画研修をオンライン環境で配信でき、受講管理やリマインドを簡単な操作で行えるものを選定しましょう。システムによっては、1人で管理できるものもあるため、管理を一元化したい場合に特に有効です。
ただし、eラーニング導入・切り替えに際してはいくつか注意すべきポイントがあるため、以下の資料から「eラーニング導入・切り替えを成功させる方法」を学び、より良い社員研修の実現を目指しましょう。
通信環境の影響を受ける
リモートワークが広がりつつある昨今では比較的表れにくいデメリットですが、動画研修はネットワーク通信を利用するため、通信環境が学習効果に直接影響します。
受講する場所の通信環境が悪ければ、視聴に支障をきたすリスクもゼロではありません。
対処法として、各社員にポケットWi-Fiを支給することが挙げられます。
働き方の多様性などにも効果があるリモートワークが、今後ますます推進されることを勘案すると、いずれにしても通信環境の整備は必要となるでしょう。
緊張感を保ちにくい
動画研修は、講師はもちろん誰の監視もない状況で受講可能です。そのため心理的なハードルが低い反面、緊張感を保ちにくい状況になってしまいます。
緊張感が無ければ集中力が途切れてしまい、つい他のことを考えてしまったり、別の作業をしながら受講したりということが起きかねません。このような場合の対処法を2点紹介します。
1点目は、研修動画のなかに個人ワークを入れます。一方的に講義を行っても受け身になってしまい緊張感を保ちにくいため、要所で受講者に向けて考えるテーマを与えて、受講者自身に考えさせることで緊張感を保ちます。
例えば、顧客対応に関する研修動画なら「お客様から、このようなクレームがありました。どう対処すべきかを5分間考えてメモなどに記してください」のように課題を設けましょう。
自ら考えた上で、正解を学ぶことでより知識として習得しやすくなります。
2点目は、動画の最後に確認テストを設ける方法です。
研修動画の内容をしっかりと聞いておかなければ解けないテストを準備しておき、動画の最後で実施します。この方法を採用することで、動画を見返し、自ら理解不足を補うことが期待できます。
人材育成に活かす動画研修の活用方法
動画研修のさまざまなメリットを活かせば、効果的かつ効率的な人材育成が可能です。
新人社員研修
新人社員研修とは、新卒社員や中途社員など、新たに入社した社員を対象に実施される研修全般のことです。
新人社員向けの研修では、ビジネスマナーやコミュニケーション術、タイムマネジメントなどの基本的なスキルに関することや、企業文化などを伝えることが多いです。
これらの内容は全社員が身につけるべき内容であるため、質や内容が均一な動画研修は、新人社員研修に有効であるといえるでしょう。
集合型研修だけでは、同じインプットの量で成果を出す必要があり、新入社員に負担がかかる可能性があります。しかし動画研修であれば、自身の理解度に合わせて学習を進めることができるので、周囲と比較して感じる焦りも軽減できるでしょう。
新人社員研修で動画研修を活用する際の注意点については、以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせて参考にしてください。
関連記事:新人研修でeラーニング活用|6つのメリットと注意点
リーダー研修
リーダー研修は、組織の中核をなすリーダーや管理職の育成のために行なわれる研修です。
研修の内容として、部下の能力開発やモチベーションのマネジメント、チームビルディングなどが挙げられます。
動画研修はこのようなリーダー研修に特に適しています。なぜなら、動画研修を活用することで、各リーダーの役職やスキルレベルに合わせて、カスタマイズされたプログラムで学習することができるからです。
また、動画研修を導入することで、受講者は時間や場所を選ばず、自分のペースで学ぶことが可能になります。管理職のような忙しい立場にとって大きなメリットといえます。
リーダーに必要なスキルや研修方法ついては、以下の記事をご覧ください。
関連記事:リーダー研修とは?リーダーに必要な能力や効果的な研修内容を解説
メンター研修
メンター研修は、メンター制度において、メンター(育成担当者)が後輩社員に対して、キャリア形成上の課題解決や、メンタル面のサポートを行うためのスキルを身につける研修です。
メンタースキルの向上が、社員の定着率に繋がるため、企業としても力を入れるべき研修といえます。メンター研修では、メンター制度の目的、メンターの役割のほか、以下のようなスキル・知識を学びます。
- 傾聴力
- コーチングスキル
- メンタルヘルス
- 各種ハラスメント
メンター研修において取り上げるべき「メンタリングに必要な知識やスキル」は多岐にわたるため、全てを集合研修内で補うのは困難です。
しかし、動画研修を活用することで、一人ひとりのスキルレベルにカスタマイズされたプログラムを自身のペースで学習することができるため、効率的にメンターを育成できます。
メンター研修の内容やポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。
マネジメント研修
マネジメント研修は、管理職候補や現役の管理職を対象として、目標管理や部下のモチベーションマネジメントを学ぶために実施します。
マネジメントスキルはリーダーシップ、目標管理能力、部下育成力など多岐にわたるため、それぞれのテーマに特化した研修が必要です。
しかし、テーマごとにオフラインで研修を実施するのは、特に忙しい管理職にとってスケジュール調整が難しい場合があります。この問題を解決するために、動画研修が効果的です。
動画研修では、テーマごとにコンテンツを細分化でき、管理職は限られた時間の中で、自分のペースで必要なスキルを学ぶことができます。
マネジメントスキルの育成方法については、以下の記事で詳しく解説しますのであわせてご覧ください。
関連記事:マネジメントスキルを高める人材育成手法
コンプライアンス研修
コンプライアンス研修とは、不祥事の防止や自社の評価を高めるために、社員へコンプライアンスの重要性や違反のリスク、遵守すべき法令、就業規則を理解させるために行う研修です。
特に昨今は、不適切な販売方法やSNSの炎上などで信頼を失うケースも見られます。自社および社員を守るためにも優先して取り上げるべきテーマです。
関連記事:コンプライアンス研修をeラーニングで行うメリットやコツを解説
ハラスメント研修
ハラスメントに関する理解や予防対策のために、ハラスメント研修を実施するケースが増えています。ハラスメントの内容は多岐に渡り、時代の変化とともに増える可能性があります。
そこで更新性の高い動画研修を有効に活用することで、ハラスメントに対する社員の認識を常に最新の状態に保つことができます。
ハラスメント研修に動画研修を効果的に活用する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:ハラスメント研修をeラーニングで学ぶメリットと実施ポイントを解説
eラーニング活用の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
eラーニング活用の重要性は分かっている。でも「具体的にどう運用するか」「結局どのeラーニングシステムが自社に合うのか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「幅広いニーズに対応するeラーニングシステム」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
主要なeラーニングシステム5サービス
ここからは、主要なeラーニングシステムをご紹介していきます。自社に導入するeラーニングシステムでお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
AirCourse|万能型eラーニングシステム

「AirCourse」は、動画研修が受け放題のクラウド型eラーニングシステムです。
自社オリジナルコースの作成・共有が容易で、優れた管理機能を備えており、自由度の高い研修プランが検討できる点が大きな魅力です。
また、直感的な操作性により受講者や管理者の負担を軽減し、誰でもすぐに使いこなせるため、余計な手間をかけることなく人材育成における課題解決ができます。
初期費用がなく、月額料金も低コストで運用できるので、初めてeラーニングシステムをご利用いただく企業でも安心してご利用いただけます。
【利用料金】
・ベーシックプラン:1ライセンス月120円~
・コンテンツプラスプラン:1ライセンス月200円~
【形態】
クラウド
【特徴】
・動画研修コンテンツの豊富さ:幅広いテーマの動画研修が受け放題
・柔軟なコース作成:自社オリジナルのコースを簡単に作成・配信可能
・スムーズな導入・活用の実現:導入・運用担当者向け説明会で運用者向けにトレーニングの支援
【こんな企業におすすめ】
初めてeラーニングシステムを導入しようと検討している企業
セキュリオ|セキュリティ研修に特化

「セキュリオ」は、最新の情報セキュリティ教育に特化したeラーニングシステムです。
90種類以上の専門家監修教材を提供し、企業のセキュリティ教育を効率的にサポートしてくれるため、全体的なセキュリティレベルの底上げが可能です。
また、自動採点・集計機能やオリジナル教材の登録も可能で、一人ひとりに合わせたカスタマイズができ、従業員のセキュリティ意識向上を促進します。
スマホからも受講できるので、どこでも手軽に繰り返し学習できる点も大きなメリットといえます。
【利用料金】
要お問い合わせ
【形態】
クラウド
【特徴】
- 90種類以上の専門家監修教材:基礎から専門まで幅広いセキュリティ教材を提供。
- 自動採点・集計機能:業務効率を大幅に向上させる自動化機能。
- オリジナル教材の登録:企業独自の教材を追加可能。
【こんな企業におすすめ】
従業員のセキュリティ意識向上を図りたいと考えている企業
参照元:セキュリオ公式サイト
SEプラス|エンジニア研修に特化

「SEプラス」は、エンジニア向けの研修に特化したeラーニングシステムです。
SEプラスの最大の特徴は現役エンジニアによる実践的な教材提供で、14年以上もの間、さまざまなIT企業に提供し続けている実績があるため、確実な個々のスキル向上が実現できます。
また、多様なプログラミング言語や技術トピックに対応し、初心者から上級者まで幅広い層に適したカリキュラムを揃えているので、全従業員が満足度の高い研修を受講できます。
午前免除対応の基本情報技術者コースも用意されているので、一人前のSEとして従業員を成長させたい、もしくは資格取得を推進している企業におすすめです。
【利用料金】
各研修サービスを参照
【形態】
要お問い合わせ
【特徴】
- 実践的な教材:現役エンジニアが監修したリアルな教材
- 効率の良いインプットとアウトプット:書籍とwebテストで学習するハイブリッドeラーニング
- 基本情報技術者資格対策:「科目A免除制度」に対応している研修でスムーズな資格取得が可能
【こんな企業におすすめ】
最新技術に対応した教育を実施して、エンジニアのスキルアップにつなげたいと考えている企業
参照元:SEプラス公式サイト
LearningWare|グローバルな研修を実現

「LearningWare」は、導入企業2800社以上、月間利用者100万人以上の圧倒的な実績を誇るeラーニングシステムです。
企業研修、代理店研修、学校教育、オンライン講習、オンライン試験など多様な用途に対応しているため、企業ごとに異なる課題や教育手法に関するご要望に対応ができます。
また、多言語対応や高度なカスタマイズ機能を提供しているので、海外支店での利用や社内システムと連携など、さまざまな企業の教育ニーズに柔軟に対応することも可能です。
使いやすさとセキュリティを兼ね備えたLearningWareは、効果的かつ効率的なオンライン学習環境を提供します。
【利用料金】
- Lightプラン:月20,000円~
- Standardプラン:月40,000円~
- Premiumプラン:月52,000円~
【形態】
クラウド
【特徴】
- 多言語対応:世界中の拠点で利用可能。
- 豊富な機能:顔認証、API連携、決済機能など多彩な機能。
- 高いカスタマイズ性:企業のニーズに合わせたシステム構築が可能。
【こんな企業におすすめ】
グローバル展開している、もしくは目指している大企業
まなびプレミアム|コストを抑えて運用

「まなびプレミアム」は、ライトワークスが提供する企業向けeラーニングシステムです。
月に一人当たり74円からという低コストを実現しつつ、階層や役職に合わせた幅広い教育コンテンツを提供しているので、高いコストパフォーマンスを誇ります。
また、1つの教材は3〜5分程度で学べるため、学習者の負担を軽減しつつスキマ時間に活用できる点が大きな魅力です。 企業独自の教材制作もサポートしているため、特定のニーズに応じたカスタマイズも可能です。
【利用料金】
契約ID数によって変動あり
【形態】
要お問い合わせ
【特徴】
- 低コスト運用:リーズナブルな価格設定で多彩なeラーニング教材を提供。
- スマホ対応:スマートフォンでの受講が可能で、時間や場所を問わず学習できる。
- カスタマイズ可能:企業独自の教材制作にも対応し、特定のニーズに応じた研修が可能。
【こんな企業におすすめ】
予算を抑えつつ社員教育を充実させたいと考えている企業
参照元:まなびプレミアム公式サイト
動画研修のメリットを活かした成功事例
営業人材育成用のコンテンツをeラーニングで一元管理し、運用工数を大幅削減|株式会社ぐるなび

日本の外食の健全な発展のため飲食に関する幅広い事業を展開する株式会社ぐるなび。一元管理が可能なeラーニングシステムを導入して動画研修を始めたことで、以下を実現しました。
| 成果 | 概要 |
|---|---|
| 運営・管理側の工数削減 | 様々な情報を一元管理できるシステムを採用したため、動画を作ってアップロードすれば、受講の進捗状況確認からアンケート結果管理、レポーティングまで完結可能となりました。 |
| 社員の積極的な学習促進 | 管理者の方は標準コースを自身で100本受講して「おすすめコース一覧」の資料を用意しメンバーに紹介する、といった事例も見受けられます。「動画でいつでも学べる環境ができてよかった」という評価も得ています。 |
| 営業プロセスの動画化コンテンツ | 営業のスキルアップを目的とした「営業パフォーマンス」という動画コンテンツの作成。営業のプロセスを細かく分解し、各プロセスにおける活動内容を整理したうえでポイントを紹介する動画です。プロセスは「案件探し」から、「社内システムの使い方」「契約後の手順」まで多岐にわたっています。 |
参考:育成に関する情報をeラーニングで一元管理し、運営工数を大幅削減!
クライアントの新人社員研修にeラーニングを提案し、一定水準の受講満足度を獲得|株式会社マイナビ
幅広いソリューションで人事の課題解決を支援している株式会社マイナビ。eラーニングシステムの導入および動画研修の運用開始により、以下を実現しました。
| 成果 | 概要 |
|---|---|
| 研修の効率化 | 受講者が大勢いる場合の集合型研修では、運営側もより多くの人員が必要となり、運営のオペレーション自体もどうしても煩雑になってしまいます。動画を活用することで、煩雑さが軽減して効率化を図ることができました。 |
| 研修の安定性・均一性 | 集合型研修はいわば「ぶっつけ本番」になるので、オペレーションで事故が起きるリスク等もありますが、動画に関しては事前に準備・制作したものを活用するのでそういったリスクを回避することができるのも動画研修の良さと評価しています。 |
参考:動画をフル活用してクライアント先の社員1人1人がオンライン上で学習できる環境を提供
eラーニングで散在および属人化していたナレッジの共有・体系化を実現|リノべる株式会社

年間施工件数業界トップクラスのプラットフォーマーであるリノべる株式会社。eラーニングシステムを導入の上、動画研修を始めたことで以下を実現しました。
| 成果 | 説明 |
|---|---|
| テストを行いウィークポイントの可視化 | 動画研修と併せてテストを行い分析することで、平均点が低いポイントや、同じところで同じミスをしてしまうといったウィークポイントを可視化。ウィークポイントにフォーカスした研修の実施や、理解促進やスキルアップの効率化を図れるようになりました。 |
| 50%の時間削減を実現 | ある担当者の場合、一つの研修コース業務を完了するのに90時間の工数を割いていましたが、それを45時間に半減することができました。AirCourseの活用が実際の研修工数の時間短縮につながったことは非常に大きな効果でした。 |
参考:AirCourse導入により研修業務の50%の時間削減を実現
動画研修のメリットを活かして人材育成を成功させよう
動画研修のメリットは、時間と場所を選ばず、繰り返し受講可能といったメリットがあります。
一方で、受講管理が煩雑になりがち、緊張感を保ちにくいなどのデメリットもあります。
ではメリットを最大限に発揮しつつ、デメリットを最小限にして、人材育成を成功に導くにはどうすれば良いのでしょうか。
弊社が提供するAirCourseは、動画研修のメリットを満たすのはもちろんのこと、さらに以下のようなメリットがあります。
- 500種類以上の動画研修やコンテンツが受け放題
- 自社オリジナルコースを柔軟かつカンタンに作成
- 充実した管理機能と受講者も使いやすい操作画面
- 初期費用0円&月額200円/名からの圧倒的コストパフォーマンス
出欠管理やリマインド、資料配布、アンケート集計などをシステム上で完結させることができるため、受講管理が煩雑になるデメリットを解消できます。
またほとんどの動画には簡単な個人ワークが含まれており、テスト作成機能を用いた確認テストも実施可能なため、緊張感と集中力を維持して効果的な研修を実現可能です。
まとめ
動画研修は、時間や場所に制約されずに受講でき、研修の質を統一できる点で優れた人材育成手法です。一方で、受講管理の煩雑化や緊張感の維持といった課題もあるため、これらのデメリットを補う工夫が重要になります。
効果的な動画研修を実現するには、適切な受講管理システムの導入と、動画内に個人ワークや確認テストを組み込むことが有効です。また、新人研修やマネジメント研修など、目的に応じたコンテンツの選択も成功の鍵となります。
導入企業の事例が示すように、動画研修は運用工数の削減と研修品質の向上を両立できる手法です。自社の人材育成課題に合わせて段階的に導入を進めることで、より効率的で効果的な研修体制を構築しましょう。
eラーニング活用の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
eラーニング活用の重要性は分かっている。でも「具体的にどう運用するか」「結局どのeラーニングシステムが自社に合うのか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「幅広いニーズに対応するeラーニングシステム」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。