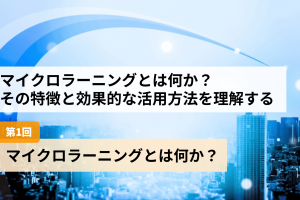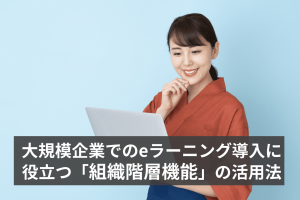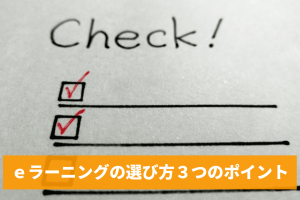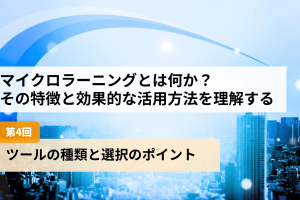企業にとってハラスメント防止は重要な経営課題ですが、従来の集合研修では時間と場所の制約や、講師による品質のばらつきが課題となっています。また、新任管理職の登用や中途入社のたびに研修を実施する必要があり、人事担当者の負担も大きくなりがちです。
こうした課題を解決する有効な手段が、 eラーニングを活用したハラスメント研修 です。eラーニングなら、時間や場所を問わず質の均一な研修を効率的に実施できます。
本記事では、 ハラスメント研修にeラーニングを導入するメリット・デメリット、実施時のポイント、さらに具体的な成功事例 まで詳しく解説します。効果的なハラスメント防止教育の実現を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
ハラスメント研修をeラーニングで行うメリット
前章でご説明した実施のポイントを踏まえて、eラーニングでハラスメント教育を行うメリットを4つご紹介します。
1. 時間や場所を問わず学習できる
eラーニングの最大のメリットは、時間や場所を問わずに受講者の都合のよいタイミングで学習に取り組めることです。
現在ではスマートフォンのようなモバイル端末を用いたeラーニングが主流になってきているため、まさに「学習の場所を選ばない」時代となっています。
2. 教育の質が均一である(講師に左右されない)
eラーニングでは、同じ学習教材を用いる限り、教育の質が均一といえます。対面型学習では、デメリットとして教育の質が講師の質に左右される点が挙げられます。eラーニングなら、そのような心配がありません。
また、教材などの改変が容易なため、常に最新の学習教材を提供できることも大きなメリットといえます。
3. 学習の進捗状況やフィードバックを一元管理できる
eラーニングにはLMS(Learning Management System)と呼ばれる学習管理システムが実装されています。
進捗状況やテスト結果などをプログラムで自動的に処理することもできます。手入力や紙ベースでの管理が不要となり、簡単で効率的な一元管理を実現できるのが魅力です。
4. コスト削減と量・質的向上との両立が出来る
日々の定型業務や他研修の運営と兼任であることが多い研修事務局担当者にとって、特に新規教育、さらに多種多様かつ対象も多岐にわたる「ハラスメント」研修教育企画と運営には、相当の負荷が掛かります。
eラーニング化によりこれらの負担が大幅に削減でき、ADDIEモデルにおけるEvaluation(評価)~Analysis(分析)~Design(設計)に注力することで、コスト削減と量・質的向上との両立が可能となります。
ハラスメント研修をeラーニングで行うデメリット
eラーニングは、時間や場所を選ばずに学習できるなどのメリットがある一方、デメリットも存在します。主なデメリットとして、以下の点が挙げられます。
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| モチベーション 維持 | 受講者が自分のペースで学習を進められるため、学習意欲の維持が難しい場合がある。 |
| コスト | eラーニングシステムの導入や教材作成に費用がかかる場合がある。 |
特に、受講者の自主性に委ねられる部分が大きいeラーニングでは、モチベーション維持が課題となるケースが多いです。学習管理システムなどを活用し、進捗状況を把握したり、定期的にコミュニケーションをとったりするなど、受講者をフォローする体制作りが重要になります。
モチベーション維持が難しい
eラーニングは、自分のペースで学習を進められる反面、学習意欲の維持が難しいという側面があります。
従業員によっては、
- 学習の進捗状況が把握しづらい
- 学習内容が理解できても質問しづらい
- 強制力がなく、ついつい後回しにしてしまう
といった理由から、学習に対するモチベーションを維持することが難しい場合があります。
eラーニング学習教材を製作する手間やコストがかかる
eラーニング学習教材を一から制作する場合、以下のような費用が発生します。
| 項目 | 内訳 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 企画・設計 | ニーズ調査、カリキュラム設計、シナリオ作成など | 数十万円~数百万円 |
| コンテンツ 制作 | 動画撮影・編集、ナレーション収録、教材デザインなど | 数十万円~数百万円 |
| システム開発 | 学習管理システム(LMS)の構築、教材配信システムの開発など | 数十万円~数百万円 |
| 運用・保守 | システム運用、教材更新、問い合わせ対応など | 数万円~数十万円/月 |
上記はあくまでも目安であり、教材の内容や規模によって費用は大きく変動します。そのため、予算と照らし合わせながら、自社で制作する範囲と外部に委託する範囲を検討する必要があります。
eラーニングを活用したハラスメント研修を実施する際のポイント
上記のデメリットを解消するためのポイントをご紹介します。
社員が自走できるeラーニングシステムを選定する
eラーニングシステムには様々な種類があります。
中には、コンテンツを登録するのに、都度ベンダーに依頼しないとアップロード出来ないシステムがあり、これでは更新の度に手間がかかり、多忙極まる担当者の「足かせ」となる懸念があります。
「使いやすさ」と「自走できるか」を軸に実際のシステムを体験してみるのがおすすめです。
自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう
クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。
階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。
既製コンテンツをあわせて活用する
こちらも上述の通り、会社独自の重要なノウハウ等は、自社でコンテンツを作っていく必要があります。
一方、それ以外の一般的な内容に関する教材は、ベンダーによる豊富な既成のコンテンツがありますので、その利用が得策と言えます。コスト・手間・クオリティなどの面でメリットが期待出来ます。
マイクロラーニングを推奨する
eラーニングにおける実際の受講シーンは、業務のスキマ時間に行われることがほとんどかと思います。
「マイクロラーニング」という、5分~15分といった短時間で学習する方法が注目されています。
eラーニングと相性がよく、スキマ学習にも向いているため、忙しい部署の社員でも受講が可能です。
定期的にテストを実施して習熟度を測る
eラーニングでハラスメント研修を実施する際は、定期的にテストを実施して、社員の習熟度を測ることが重要です。テストの結果は、個別にフィードバックを行い、理解不足のポイントを明確化します。
| テストの実施頻度 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 高頻度 | 定着率向上 | 負担増加 |
| 低頻度 | 負担軽減 | 定着率低下 |
上記のように、テストの実施頻度にはメリットとデメリットがあります。そのため、自社の状況に合わせて、適切な頻度を設定する必要があります。
例えば、新入社員研修など、重要な研修であれば、高頻度でテストを実施する方が、学習内容の定着を促進できます。一方で、既存社員向けの研修など、既に知識を持っている可能性が高い場合は、負担軽減の観点から、低頻度で実施する方が適切と言えるでしょう。
eラーニングを活用したハラスメント研修の成功事例
eラーニングを活用したハラスメント研修の成功事例を紹介します。
スキマ時間活用で全社ハラスメント防止教育を効率化|株式会社フレスタ様

広島県を中心に63店舗のスーパーマーケットを運営する株式会社フレスタ(従業員数約1,500名)では、コロナ禍で集合研修が実施困難になったことをきっかけに、eラーニングシステムの導入を決定しました。
これまで対面で行っていたハラスメント防止研修について、集合開催の困難さや地方拠点の従業員への研修機会提供が課題に。また、PC1人1台環境でない現場が多く、eラーニングでの学習定着に不安もありました。
同社が選択したAirCourseでは、管理職向けに例年人事部長が実施していたハラスメント防止研修を「しない・させない ハラスメント研修」の受講必須に置き換えました。マイクロラーニング設計により、天候不順で業務に余裕ができた際などのスキマ時間に、店舗でスマートフォンを使って受講することが可能になりました。また、確認テストによる知識定着の確認と履歴管理も実現しています。
この取り組みにより、全従業員に対してハラスメント防止教育の機会を効率的に提供できるようになりました。受講者からも「内容がとても分かりやすかった」「スキマ時間に学べるのが良かった」という好評の声が上がっており、短期間で一定の知識を備えた状態を実現できたことは経営層からも高く評価されています。
導入後の主な成果
- 全社展開:地方拠点含む全従業員へのハラスメント防止教育実現
- スキマ時間活用:業務の合間を利用した効率的な学習環境構築
- 学習効果向上:確認テスト機能による知識定着の確認と記録化
- 経営層からの評価:短期間での知識浸透に対する高い評価を獲得
参考: 株式会社フレスタ様|eラーニングシステムAirCourse
世代間コミュニケーション向上でハラスメント予防を実現|株式会社あいはら様

電気設備工事を主体に70有余年の実績を持つ株式会社あいはら(従業員数約300名)では、コロナ禍での集合研修困難化と若手への技術継承課題の解決を目的として、eラーニングシステムを導入しました。
世代が幅広い職場環境において、特に管理者クラスが「若手とどう接すれば良いのか」について不安を抱えており、ハラスメント防止やメンタルヘルス対策の重要性が高まっていました。また、現場作業が多い業種特性上、従来の集合研修では全員参加が困難で、教育機会の格差が生じていました。
同社では、eラーニング委員会を発足し、各拠点担当者による月次オンライン会議で運営方針を決定しています。ハラスメントやメンタルヘルス、ダイバーシティ関連のコンテンツを重点的に配信し、週1コース視聴を目標とした習慣化を図りました。特に管理者クラスが若手との適切なコミュニケーション方法を学ぶことで、ハラスメント防止の土台作りを行っています。
この取り組みにより、デスクワーク社員はPC、現場社員はスマートフォンでそれぞれの環境に応じた学習が可能となりました。年配社員も操作に慣れ、世代間のコミュニケーション課題解決に向けた意識向上が図られています。新卒採用においても「社員教育に積極的な企業」として評価され、採用力向上にも寄与しています。
導入後の主な成果
- 委員会体制:各拠点連携によるeラーニング推進体制の確立
- 世代間交流:管理者の若手接し方スキル向上によるハラスメント予防
- 学習習慣化:週1コース視聴目標による継続的な意識向上
- 採用力向上:教育制度充実による新卒採用での差別化実現
参考: 株式会社あいはら様|eラーニングシステムAirCourse
各部署自発的活用で職場の安全意識とハラスメント防止を強化|多摩都市モノレール株式会社様

東京都多摩地域で鉄道事業を展開する多摩都市モノレール株式会社(年間利用者5,200万人)では、集合研修の非効率性解消と、新型コロナウイルス感染症対策を目的としてeラーニングシステムを導入しました。
鉄道事業という現場業務が中心の環境で、従来は集合研修がメインでしたが、知識確認やルール読み合わせに時間がかかり、欠席者への対応工数も膨大になっていました。また、多様な部署特性(技術系、運輸系、総務等)に応じたハラスメント防止・安全教育の個別最適化が課題となっていました。
同社では、安全管理推進室主導で全社的な認知活動を徹底し、各部署が自発的にオリジナルコンテンツを作成できる環境を整備しました。ハラスメント防止を含む安全教育について、各部署がそれぞれの特性に応じたコンテンツを作成し、若手社員がYouTube感覚で映像編集を楽しみながら取り組んでいます。社長の年頭挨拶配信や外部講師講演会のeラーニング化も実現しています。
この取り組みにより、コロナ禍でも継続的な教育実施が可能となり、時間効率の大幅改善を実現しました。「いかに動画でわかりやすく伝えるかを考えることが自分自身の学びにもなる」という社員の声が示すように、アウトプットを通じた学習効果の向上も得られています。
導入後の主な成果
- 自発的活用:各部署が主体的にハラスメント防止・安全教育コンテンツを作成
- 効率化実現:集合研修からの切り替えによる時間効率の大幅改善
- 継続性確保:コロナ禍でも中断のない教育実施環境を構築
- 学習効果向上:コンテンツ作成プロセス自体が社員の成長機会に
参考: 多摩都市モノレール株式会社様|eラーニングシステムAirCourse
まとめ
eラーニングを活用したハラスメント研修は、時間や場所の制約を受けずに質の均一な教育を実現できる優れた手法です。特に、教育の質が講師に左右されない点、学習進捗の一元管理が可能な点、コスト削減と教育効果向上を両立できる点が大きなメリットといえます。
一方で、受講者のモチベーション維持や初期コストの課題もあるため、社員が自走できるシステム選定、既製コンテンツの活用、マイクロラーニングの推奨、定期的なテスト実施といった工夫が重要になります。
効果的なハラスメント防止教育を構築するには、eラーニングの特性を理解し、自社の課題や環境に応じた適切な導入計画を立てることが不可欠です。時間効率と教育効果を同時に実現するために、まずは現在の研修課題を整理し、段階的な導入を検討してみてはいかがでしょうか。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。