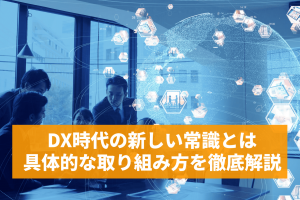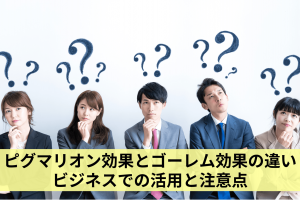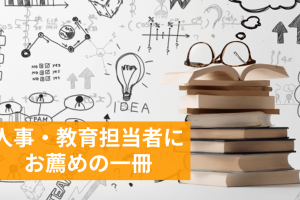企業の競争力を維持・強化していくためには、若手社員を一人前の戦力へと育成し、定着してもらうことが重要です。
とはいえ、従来型の育成方法が通用しにくくなっている現状もあり、若手社員の育成には、多くの企業担当者が頭を悩ませています。
本記事では、若手社員を育成する重要性や目的、育成課題、育成のポイントなどを解説します。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
若手社員を育成する重要性や目的
多くの企業で若手社員の育成が重要視される理由として、以下の2つが挙げられます。
- 早期戦力化
- 定着率の向上
早期戦力化
企業が競争優位性を保ち、持続的な成長を遂げるためには、採用した人材を一人前に育成し、いち早く組織の戦力として活躍してもらうことが重要です。
若手社員を早期戦力化させるメリットは、主に以下の2つです。
- 事業目標の早期達成
- 教育コストの抑制
若手社員が戦力になると、企業の業績向上や目標達成を早める効果が期待できます。また、短期間で新入社員を戦力化できれば、長期的な教育コストの削減につながるでしょう。
変化の激しいビジネス環境に対応するためには、新しいスキルや知識を習得した人材が必要です。そのため、若手社員をいち早く戦力化し、変化に対応できる組織を作ることが企業にとって急務となっています。
定着率の向上
厚生労働省の「令和3年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況」によると、就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が38.4%、新規大学卒就職者が34.9%です。
就職後3年以内にこれだけの割合の若手社員が離職してしまうと、採用や育成にかかったコストが無駄になってしまいます。
若手社員が定着すると、企業は採用や教育にかかるコストを削減できるだけでなく、社員のスキルや経験を活かして、事業の成長につなげられます。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
若手社員の育成でよくある課題
若手社員の育成における課題には、以下のようなものがあります。
- 育成方針と若手のモチベーションにギャップがある
- 育成内容に若手社員がついていけない
- 担当者が多忙で十分な育成ができない
- 育成担当者の指導力が不足している
課題解決のために、まずはそれぞれの内容を正確に把握することが重要です。
育成方針と若手のモチベーションにギャップがある
企業が人材育成を行う際、育成方針と若手社員のモチベーションにギャップが生じることがあります。それぞれが仕事に対してもつ視点は、以下のとおりです。
| 企業側の視点 | 若手社員側の視点 |
|---|---|
| ・将来の幹部候補を育成したい ・特定のスキルを習得させたい ・長期的な育成計画に基づいて研修やジョブローテーションを組みたい | ・今後のキャリアが見えない、将来よりも今の成長を実感したい ・自分の興味関心に沿った業務でスキルアップしたい ・短期的な成果を求めたい、すぐに昇進、昇給できないとモチベーションが上がらない |
育成方針は、企業の長期的な視点に立ち、将来の経営を担う人材を育成することを目的として策定されることが一般的です。
そのため、多くの企業でまずは新入社員研修などを通して、ビジネスマナーや基礎的なスキルを習得させる取り組みが積極的に行われています。
しかし、最近の若手社員は「指示されたこと以外は行わない」「報告・連絡・相談が不足している」といった傾向が見られ、実際に業務に携わる段階になると受け身の姿勢が目立ちます。
また、目の前の業務にやりがいや成長の実感を求めている若手社員も多いでしょう。
このようなギャップを放置すると、若手社員のモチベーション低下や離職を招き、企業の成長を阻害する可能性があります。
育成方針と若手社員のモチベーションギャップを埋めるために、企業は若手社員の意見を聞きながら育成計画に反映していく、短期的・長期的な目標設定やキャリアパスを明確にするなどの取り組みが必要です。
育成内容に若手社員がついていけない
育成内容が高度化・スピード化していることで、若手社員がついていけないといったケースもあります。
本来はじっくり時間をかけて身につけるはずのスキルの習得や、経験を積んでできる仕事の遂行を早期から求められると、若手社員は負担に感じてしまうでしょう。
育成担当者が多忙で十分な育成ができない
若手社員の育成担当者は、通常業務に加えて育成も行わなければなりません。そのため、業務過多となり、十分な育成ができないケースもあります。
特に、育成が現場任せになっている場合、教育の質も育成担当者に属人化してしまいます。フォロー体制のないまま若手育成を現場に任せてしまうと、育成まで十分に手がまわらず、良い効果は得られないでしょう。
育成担当者の指導力が不足している
若手社員の育成到達レベルは、育成担当者の指導力で左右されます。
若手社員の特徴を把握できないまま育成担当者にしてしまうと、組織に馴染めない、スキルや知識が身につかないといった状況になるだけでなく、教育自体が苦痛になり、離職意向につながる恐れもあるでしょう。
育成担当者は、十分な指導力をもっているか確認したうえで選任することが重要です。
若手社員を育成する具体的な方法
若手社員を育成するには、以下4つの方法があります。
- 仕事の全体像と流れを伝える
- キャリアパスを共有する
- 業務を切り分ける
- 自己啓発を促す
具体的な育成方法を解説しますので、ぜひ取り入れてください。
仕事の全体像と流れを伝える
受け身な傾向のある若手社員への対策として、最初に仕事の全体像と流れを伝えましょう。仕事の全体像と目標達成までの流れが明確になることで、若手社員は進んで仕事ができるようになります。
具体的には、以下のステップで指導します。
- 業務の目的や目標を共有する
- 業務の全体像を説明する
- 各業務の進め方やポイントを具体的に指示する
- わからない点は質問させる
- 定期的に進捗確認を行い、フィードバックする
これらのステップを踏むことで、若手社員はスムーズに業務に取り組めます。
キャリアパスを共有する
キャリアパスの共有は、モチベーション対策になります。どのような仕事を行い、どのような結果を出せば評価につながるのかを、1on1ミーティングなどを通して共有しましょう。
若手社員自身が考えるキャリアプランをヒアリングし、それに対して企業としてどのようなキャリアパスを用意できるのかを伝え、お互いに納得できる形にもっていけると理想的です。
若手社員が憧れをもてるようなロールモデルを用意できると、具体的に将来像がイメージしやすくなります。
業務を切り分ける
ある程度できてほしい業務のラインはあるとはいえ、どうしてもうまくいかない場合は思い切って切り分けるのも一つの方法です。この場合には、切り分けた業務をこなす度にフィードバックを行い、成功体験を積み重ねましょう。
ただし、業務の切り分けは、周囲のモチベーションを下げる可能性が高まるため、周りへのフォローが必須です。
自己啓発を促す
若手社員にある程度モチベーションがある場合は、自己啓発を促すのもよいでしょう。研修を用意する方法もあります。
ただし、モチベーションがない場合には空振りに終わる可能性があるため、注意が必要です。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
若手社員の育成を成功させるためのポイント
若手社員の育成を成功させるためには、以下のポイントが重要です。
- 効果的な育成計画をたてる
- OJTとOFF-JTを組み合わせる
- メンター制度を活用する
- 若手社員の育成方針・内容を組織内で共有する
効果的な育成計画をたてる
育成計画は、計画的かつ体系的なアプローチで立てると効果的です。明確な目標を設定し、それを達成するために必要なプログラムを段階的に実施しましょう。
評価とフィードバックも定期的に行うことで、より効果的な育成につながります。具体的な育成計画の立て方は、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:人材育成計画の立て方|階層別の記入例や目標設定、テンプレート
OJTとOff-JTを組み合わせる
若手社員の育成は、eラーニングや集合型研修(座学研修)などのOFF-JTでインプットし、業務内で実務経験を積むOJTでアウトプットする流れを作るとよいでしょう。
| OJT | OFF-JT |
|---|---|
| ・職場で実際の業務を通して教育 ・育成担当者からの直接指導 ・実務に即したスキルを習得 | ・職場を離れて行う体系的な教育 ・多様な人との交流を通じて視野を広げる ・専門的な知識やスキルを習得 |
ただし、OFF-JTでインプットした知識やスキルを、OJTですぐアウトプットできない場合もあります。そのため、育成対象者には反復学習を促すのがおすすめです。
関連記事:OJTとは?意味や研修のやり方、OFF-JTとの違いを解説
関連記事:OFF-JTとは?意味やOJT・自己啓発との違い、メリットを解説
メンター制度を活用する
メンター制度とは、育成担当者である先輩社員が、育成対象者である新人社員や若手社員をサポートする人材育成方法です。育成担当者は、育成対象者の実務面以外のキャリア形成やメンタル面のフォローをする役割をもちます。
若手社員は気軽に相談できる相手を得られるため、ストレスの軽減から、早期離職を予防できるでしょう。
関連記事:メンター制度とは?メリット・デメリットや成功事例を紹介
若手社員の育成方針・内容を組織内で共有する
育成担当者が属人性なく育成にあたれるよう、若手社員の育成方針や内容を社内全体で共有しておくことも重要です。
育成担当者に任せきりになってしまうと、忙しくなったときに育成に手がまわらなくなります。育成方針や内容の共有により、負担を分散させられるでしょう。
そのためにも、客観的な評価体制を整えておくことが重要です。
また、育成マニュアルを整備するのもおすすめです。マニュアルは若手社員が自ら学び、業務を効率的に習得するためのツールとしても役立ちます。
人材育成で大切なことやフレームワークについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:人材育成で大切なこと9つ|必要なスキルやフレームワークを解説
スキマ時間を生かした学習を取り入れる
若手社員研修を実施する際には、参加者の業務スケジュールとの調整が課題となることがあります。
特に、業務が忙しい社員の場合、研修への参加が負担になることもあるため、オンライン研修や動画教材を活用するなど、受講形式を工夫することで参加者のニーズを満たすことができます。
例えば、「eラーニング」を導入すると、社員が自身のスケジュールに合わせて好きな時間に受講でき、受講負担を軽減することが可能です。
さらに、eラーニングの一手法として注目を集めている「マイクロラーニング」を活用すると、受講効率が大きく向上するためおすすめです。
マイクロラーニングとは、5分~10分といった短時間での学習スタイルのことを指します。短いコンテンツで学習するため、受講者はスキマ時間を活用して効率的に学習できます。
昨今のビジネス環境では、社員が日々の業務に忙殺されることが多く、まとまった学習時間の確保が難しくなっています。
移動中や休憩時間といった「スキマ時間」にサクッと学びたいというニーズが高まっており、マイクロラーニングは、こうした昨今のビジネスマンの行動様式に対応できる学習手法として注目されています。
マイクロラーニングのコンテンツは学習内容が細分化されており、受講者は集中力やモチベーションを維持しやすく、短時間の集中した学習によって記憶の保持につながりやすいのも特徴です。
反復学習や確認テストなどを組み合わせると、より効果的に知識を定着させることもできます。
マイクロラーニングについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事: マイクロラーニングとは?導入メリットや定着率向上のポイントを解説 | 人材育成サポーター
若手社員を育成する育成担当者に必要な心構え
若手社員を育成するうえで、育成担当者には若手社員の人となりを理解する、価値観で判断していないか常に見直す、育成方針・内容を組織内で共有するといった心構えが必要です。
育成担当者に必要な心構えを解説します。
若手社員の人となりを理解する
まずは、それぞれの若手社員の考え方や仕事に対する姿勢を理解することが、若手育成の出発点です。
適切な育成方法は、若手社員一人ひとりで異なります。積極的にコミュニケーションをとり、若手社員の価値観の把握に努めましょう。
価値観で判断していないか常に見直す
若手社員を育成する際、知らずしらずのうちに自身の価値観で若手社員を見極めていないか、常に見直しましょう。
最近の若手社員の傾向が、必ずしも全員に当てはまるわけではありません。若手社員を育成するときには、その人としっかり向きあって対話を重ねて判断していくことが重要です。
メンタルケアにも気を配る
若手社員は仕事の不安やストレスを抱えやすいため、積極的にコミュニケーションをとり、打ち明けやすい環境を作っておきましょう。
メンター制度を導入している場合には、メンター担当の従業員に状況を確認しつつフォローを入れることも必要です。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
若手社員育成の取り組み事例
若手社員をうまく育成したいときには、成功事例を参考にする方法もあります。以下で若手社員育成の取り組み事例を2つ紹介します。
株式会社浅野製版所
株式会社浅野製版所は、新聞や雑誌などの広告原稿をより美しく、より効果的に表現するためのDTP・デザイン・印刷などのサービスを提供している企業です。広告業界における幅広い分野でのサポートを行っています。
株式会社浅野製版所では、若手社員の教育情報を共有するきめ細やかなフォロー体制を確立しています。
具体的な取り組み例は、以下のとおりです。
- 内定時、面接所見と適性検査結果を若手社員本人に開示
- 「誰が」「どのように」教育を実行すれば即戦力化できるかをヒアリングと適性検査で分析し、効果的な組み合わせで若手社員と育成担当者を配置
- 育成担当者向け教育の実施
- ライフプランやキャリア形成を含めた「働くということ」の意識づけをしたうえでの部署研修を実施
- 新入社員の報告・成長記録をすべて人事部門で管理
人事(部長)、配属部署、関連部署、管理職、教育担当者が連携することで教育レベルのばらつきを抑え、個人の特性を活かした効果的なキャリア形成を行っています。
株式会社 エイワ
株式会社 エイワは、建築設計施工やFRP製品(タンク、角槽、トラフ、覆蓋、その他)、コバルト合金他各種合金の製造販売を行う企業です。若手社員の育成として、新入社員教育プログラムを実施しています。
「図解でわかる会社の教科書 品質管理」をテキストにして外部講師と各部門長が講師になり、教育を実施しました。
品質管理の手法を軸に、会社事業の価値(意味)、製品価値、企業人としての考え方や態度、品質管理、生産管理の手法など、統一した教育を行い、ものづくり企業の一員として若手社員を育成しています。
まとめ
企業の持続的成長、早期戦力化、人材の定着化には若手社員の育成が不可欠です。しかし、多くの企業では、育成の時間が取れない、育成方針が明確でないなど、さまざまな課題を抱えています。
若手社員の育成を成功させるには、効果的な育成計画をたてたうえで、OJTとOFF-JTを組み合わせたり、メンター制度を活用したりすることが重要です。
また、育成担当者には、若手社員の育成に向けて必要な心構えを共有しておく必要があります。
これらのポイントを踏まえ、若手社員一人ひとりの個性や特徴に合わせた育成方法を検討していきましょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。