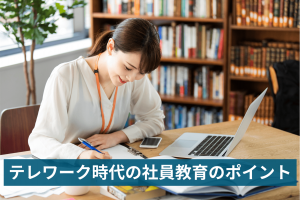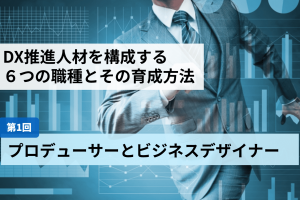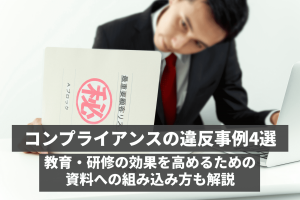人材育成とは、組織の成長や発展に寄与できるよう、社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、育て上げる活動のことです。手法も多岐にわたり、どのように進めるとうまくいくのか知りたい方も多いでしょう。
人材育成を成功させるためには、手法の特徴を把握するだけでなく、適切な人材育成計画を作成する、階層別の関わり方のポイントを押さえるなどの対応が重要です。
本記事では、人材育成の目的から具体的な手法、人材育成計画の立て方、階層別の関わり方のポイント、よくある課題、成功に導くために大切なことまで詳しく解説します。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
人材育成とは?

人材育成とは、企業に貢献できる人材を育成することです。組織の成長や発展に寄与できるよう、社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、育て上げる活動を指します。
重要なポイントは、「自社」で貢献・活躍できるようにするということです。そのため、人材育成計画は自社の理念や戦略、現状の課題などに基づいた自社独自の計画を立てることが求められます。
人材育成のアプローチには、狭義では「OJT」「自己啓発」「eラーニング」など、広義では「ジョブローテーション制度」「人事評価制度」など、さまざまな手法があります。
いずれも、社員一人ひとりがもつ可能性を伸ばし、そのスキルや知識を向上し、より高いパフォーマンスを発揮できるように支援することを目指します。
人材開発との違い

人材開発とは、自己啓発支援やOJTなどの個別支援に適した手法で、スキルアップを通じた組織力の強化を図る方法です。社員1人ひとりに適した手法を用いて必要なスキル習得を図ります。
一方、人材育成は業務遂行に必要なスキル習得を目指し、階層や役職別に実施される方法です。目的に応じて、集合研修なども用いられます。
関連記事:人材開発とは?人材育成との違いや仕事内容・進め方のポイント
人材教育との違い
人材育成と混同されがちな言葉に「人材教育」もあります。人材育成は「企業が望む方向に人材を育て、成長させること」であるのに対して、人材教育は「業務上、必要な知識やスキルを教えること」を意味します。
人材教育の方法には、座学等の教育のほか、実技による経験も含まれます。また、内容は人間性や理念など、概念的なことも多く、対象範囲が広いのもその特徴です。一方、人材育成は、経営目標の達成のために役職ごとに必要とされる実践的な知識・スキルの習得を対象とします。
社会人・組織人としてのベースを人材教育で教えることになるため、人材教育は人材育成の手法の一つとして捉えられます。
人材育成の目的

企業に貢献できる人材を育成することは、組織に対する高いエンゲージメントがあり、身につけたスキルや知識を、組織のために積極的に活用するモチベーションがある人材を育成することです。
そのため、人材育成の目的にはスキルや専門性の向上だけでなく、ビジネスマインドの醸成、帰属意識の向上といった要素も含まれます。
ビジネスマインドの醸成
人材育成には、企業理念や組織人としての心構え、ビジネスマナーなど「仕事の基本となる姿勢や考え方」を身につける目的があります。姿勢や考え方は日々の行動と結果に影響するため、新入社員に限らずベテラン社員にとっても重要な要素です。
また、ビジネスマナーは、ステークホルダーとの良好な関係性を構築するうえでも重要です。高いビジネスマインドをもった社員の育成により、企業のブランド力強化にも貢献します。
スキルや専門性の向上
自社で活躍するためには、業務に求められるスキルと専門的な知識を身につける必要があります。
実践的なスキルを身につけるためには、実務を経験する人材育成を行うのが近道です。実務での試行錯誤と状況に即した上司からのアドバイスが、部下のスキルと専門性を大きく向上させます。
また、IT技術の向上などによって仕事のあり方が目まぐるしく変わる時代においては、最先端の知識やスキルを社員に身につけさせることで、企業は長期的に競争優位性を確保できます。
帰属意識の向上
人材育成で自社の理念や戦略を共有すると、社員1人ひとりの「組織に属している」「社員みんなが仲間である」といった帰属意識・エンゲージメントが向上します。
また、キャリアアップに積極的な社員に対し、スキルアップできる機会を提供することでも、企業に対する愛着を高められるでしょう。
帰属意識やエンゲージメントが高ければ、社内課題の「自分ごと化」や退職防止にもつながります。社員は、自分の目標を明確に認識できるため、モチベーションアップにも良い影響を及ぼします。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
近年の人材育成の傾向
近年、人材育成で注目されているのが「リスキング」です。リスキングとは、DX(デジタル・トランスフォ-メーション)や第4次産業革命といった社会の変化に対応できるようにするために、新しい知識やスキルを学ぶことです。
内容は以下のように、多岐にわたります。
- プログラミング
- ビッグデータの分析
- マネジメント
- マーケティングなど
厚生労働省でもリスキング支援を行っており、「厚生労働省委託事業 キャリア形成・リスキリング推進事業」を展開しています。さまざまな研修や支援を無料で受けられるため、こういった事業を活用するのもよいでしょう。
人材育成の手法

人材育成には、さまざまな手法が存在します。それぞれの特性を理解したうえで、組織や社員一人ひとりのニーズに合わせて柔軟に取り入れましょう。
OJT
OJT(On-the-Job Training)とは、職場での実務経験を通じて知識やスキルを習得する育成方法です。主に新人を対象とし、同じ部署の上司や先輩がトレーナー(育成担当者)となり育成を行います。
とはいえ、日常業務に追われるなかで明確な目的や計画もないと、効果的なOJTを行うのは困難なのが実状です。先輩社員が新人に対して必要に応じて行う業務説明や指導までにとどまるケースも少なくありません。
そのため、OJTを意図的・計画的・継続的に行うための取り決めである「OJT制度」を整える必要があります。
関連記事:OJT制度とは?構築時の注意点と効果を高める方法を解説
OJT研修
OJT研修とは、OJTを行うトレーナーを育成するための研修です。
OJT研修の実施により、OJTの質とトレーナーとしての育成スキルが向上します。さらに育成者・指導者としての経験が、管理職候補としての成長につながるメリットもあるでしょう。
人材育成の大切なことの一つ「育成担当者のスキル向上」を実現できる施策といえます。
関連記事:OJT研修とは?目的や実施メリット・デメリット、研修手順をご紹介
OFF-JT
OFF-JT(Off The Job Training)とは、職場や通常業務から離れ、特別な時間や環境において行う教育や訓練のことです。
体系的な学習を行えるため、知識・スキルを整理しながら身につけられます。ただし、実務へ活かすための応用力が求められるでしょう。
関連記事:OFF-JTとは?意味やOJT・自己啓発との違い、メリットを解説
自己啓発支援
自己啓発支援とは、自発的に学習できる機会を設け、自己成長の習慣化を促すことです。例えば、以下のような施策で自己啓発を支援できます。
- 書籍購入支援:社員が希望する書籍を企業が購入して配布する
- 資格取得支援:自社の業務に役立つ資格の取得を支援する
自己啓発の支援は、社員の知識・スキル・意欲・帰属意識の向上が期待できます。企業としてのイメージアップにつながり、採用活動時に有利に働くでしょう。
ただし、相応のコストがかかる、支援制度の導入や運用面で担当部署の業務負担が増すなどの懸念点もあります。予算や担当部署の状況、人材育成目標に確実につながるかを勘案して導入を検討しましょう。
関連記事:人材育成マネジメントとは|育成のコツや必要なスキル、階層別のポイント
その他の手法
人材育成では、他にも以下のような手法が活用できます。
| 手法 | 特徴 |
|---|---|
| eラーニング | PC、スマートフォンなどのデジタル機器とインターネットを利用して教育、学習、研修を行う。他の手法と比較して管理者側・受講者側の負担が少ない |
| ジョブローテーション | 部署異動・職種の変更を定期的に行い、幅広い業務に対応できる人材を育成する。適材適所の実現や部門を越えた社内ネットワークの構築、応用力の習得を期待できる |
| 人事評価制度 | 各社員の「業績・能力・勤務態度や意欲」などを客観的指標により評価して、昇給や昇格に反映する。被評価者は「何が足りないのか」「何を身につけるべきか」を明らかにでき、次回の目標設定に活用できる |
| 目標管理制度 | 各社員が個人目標を設定して、進捗や達成度合いを評価する |
| メンター制度 | 知識と経験のある先輩社員がメンター(育成担当者)となり、後輩社員(育成対象者)に対して指導・業務支援・メンタル面のサポートなどを行う。後輩社員は相談しやすい環境を得られる、先輩社員は後輩社員の悩みなどを想像・共感しやすいなどのメリットがある |
人材育成計画の立て方

人材育成の目的は、自社で貢献・活躍できる人材を育成することであるため、人材育成計画は最初に自社の課題を洗い出すところから始めます。
自社の事業課題や経営課題を明らかにし、目標から逆算した場合に足りないスキルや能力を、人材育成を通じて獲得できるよう、戦略を立てなければなりません。
基本的には、以下のようなプロセスで目標の達成を目指します。
- 現状把握から目標設定を行う
- 目標達成に必要なスキル・行動を整理する
- 実践・フィードバックを繰り返す
現状把握から目標設定を行う
人材育成の育成計画書で最も重要なことは、目標設定です。目標を明らかにできると、必要な計画も具体的になります。
目標を立てるためには、まず「どのような人材育成が必要か」「何が不足しているか」といった現状の把握から行うことが重要です。そのためにも、組織の全メンバーに対するスキルや能力の評価が必要となります。
| 評価項目 | 説明 |
|---|---|
| 学歴・資格 | 一定の知識・スキルを保証するもの |
| 経験年数 | 実務での経験があるかどうか |
| 業績 | 過去の実績や成果 |
これらを踏まえて、社員1人ひとりが必要とするスキルや能力、組織全体として達成すべき目標を設定します。
設定された目標は明確で達成可能なものにし、達成可能な目標は「こうなりたい」という理想だけでなく、予実管理における「実績値」を参考にするとよいでしょう。
例えば、組織全体の目標を「売上」に設定する場合、現状の組織形態・リソース状況で記録した実績をもとに、最も売上に貢献している業務や人材を洗い出します。その後、どの変数を増やせば売上へのインパクトを最大化できるかを検討します。
検討の結果、「社員育成による人材の確保」が成果に最も貢献する可能性が高いと判断できれば、人材育成計画は組織全体の目標達成に紐付く施策として実行できるでしょう。
目標達成に必要なスキル・行動を整理する
目標を設定した後は、目標達成に必要な各職種・役職における必要なスキルを明確にしましょう。そのうえで、現状のスキルレベルを把握し、目標とのギャップを明らかにします。
その差を埋めるために必要な行動を具体的にリスト化すると、具体的な育成プログラムを描くことが可能です。
例えば、支援会社における営業職の目標が「クライアントの信頼を勝ち取り、契約を増やす」であれば、以下のようにテキストで書き出して整理していきます。
| 目標 | クライアントの信頼を勝ち取り、6ヶ月以内に契約を1つ増やす |
| 現状 | 入社3ヶ月の社員。クライアントと弊社のこれまでの取り組みや現状の課題をおおよそ把握してはいるが、先方担当者との信頼関係が十分に構築されておらず、どのようなコミュニケーションをとれば良いかわからない。ゆえに普段の業務もタスク単位でこなしており、指示された業務ばかり行っている。自身の業務がどれだけクライアントの成果につながっているのかも正確に把握できておらず、日々の業務に一貫性がない。 |
| 原因 | ・前任の担当者から必要な情報を引き出せていない ・逆算思考ができていない ・達成すべき目標や日々の業務を自分の言葉で理解できていない ・どうすれば信頼してもらえるかを考え抜けていない |
| 必要なこと | ・前任担当者や上司とミーティングを組み、目標達成に向けた動きを確認する ・社内ナレッジや商材理解のインストール時間を設ける ・短期間で小さな実績を作り、それを踏まえたコミュニケーションを行う |
このように分解して考えると、現状と目標の間のギャップを可視化できます。
「クライアントの信頼を勝ち取り、6ヶ月以内に契約を1つ増やす」という目標だけを考えると、コミュニケーションスキルの向上やプレゼンテーションスキルの向上、といった課題が見つかりそうです。
しかし、現状の状態を踏まえると、それ以前の動き方やインストール、仕事の仕方に問題がある場合もあります。
計画段階では、こうした目標と現状の差分を明らかにするところに時間をかけ、必要なプロセスを1つずつ階段をのぼるように可視化することが重要です。
実践・フィードバックを繰り返す
人材育成計画は作成して終わりではありません。設定した目標達成に向け、実践とフィードバックを繰り返すことが重要です。
研修や教育プログラムなどを実施した場合は、参加者がどの程度スキルを習得したかを確認しましょう。フィードバックをコメント欄に記載するなど、必ず人材育成研修の受講者に対してリアクションを行います。
そして、その結果をもとに反省点や改善点を洗い出し、再度実行に移してください。このようにPDCAサイクルを回すことで、育成対象者のスキルアップを図れます。
育成計画の立て方や計画書の作り方について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。無料でダウンロードできる「育成計画書サンプル」も配布しております。
関連記事:人材育成計画の立て方|階層別の記入例や目標設定、テンプレート
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
【階層別】人材育成のポイント
社員は属する階層によって、スキルや企業に対する帰属意識、役割にばらつきがあります。そのため、効果的に人材育成を進めるためには、階層別に人材育成のポイントを理解することが重要です。
新入社員の育成

新入社員には、自社の経営理念から組織人としての心構え、ビジネスマナーなどの基礎を理解させることが大切です。近年では、離職率の高まりも指摘されており、帰属意識の向上も重要なテーマといえます。
自社への理解を深めてもらう
まずは、組織に属して活動するうえでの基礎・基本である自社への理解を深めることが大切です。以下のポイントで、組織や活動についての全体像を理解してもらいましょう。
- 経営理念
- 自社の歴史と今後のビジョン
- 自社のビジネスモデル
- 自社の組織構造
- 業界の基礎知識
全体像をイメージできれば、以降の経験で得る情報に対して「どの部分の話か」をすぐに認識できるため、知識として定着しやすく、不明点があれば質問もしやすくなります。
心構えやビジネスマナーを身につけてもらう
新入社員は学生時代の感覚や習慣が残っていることも多く、組織人としての心構えやビジネスマナーを学ばせる必要があります。具体的には以下のようなテーマが挙げられます。
- 挨拶と表情
- 動作や態度
- 身だしなみ
- 電話応対
- 生活習慣
- 言葉づかい(敬語)
- 名刺交換
- ビジネスメール
ポイントは、やらされ感や受け身にならないように「なぜ大切なのか」をセットで伝えることです。心構えやマナーは「自分ごと化」できて初めて身につきます。
業務遂行に必要な知識とスキルを習得させる
基本的な知識やマナーなどを身につけたら、次は業務遂行に必要な知識・スキルを習得させます。集合研修形式での学びも基礎知識の習得には有効ですが、スキルの習得にはOJTやメンター制度を通じた実践形式での学びがおすすめです。
また、新しい環境で慣れない業務に忙殺されることも想定されるため、eラーニングを導入して、自分のペースで学習できる環境を整えるのもよいでしょう。
自らの役割を自覚させる
新入社員は、入社後しばらくは自社や業務についてさまざまな知識習得に追われるため、自らの役割を自覚するまでには至らないことも少なくありません。
そこで、あらためて「自分は組織から何を期待されているか」「自分はこの組織でどうなりたいのか」を考える機会を設け、組織における自らの役割を自覚させましょう。
自らの役割や目標が明確になると、成長スピードだけでなく、モチベーションや帰属意識の向上も期待できます。
メンタル面を意識した育成を行う
新入社員は、環境の変化のなかで慣れない業務へのチャレンジや失敗を経験するため、少なからずプレッシャーやストレスを感じています。こうした状況下では、メンタル面を意識した育成を行うことも大切です。
具体的には、以下のような点を意識しましょう。
- 定期的に面談の機会を設ける
- 雑談など気軽なコミュニケーションを心がける
- 良いことは具体的かつ直ぐに褒める
- 悪いことも具体的かつ直ぐに指摘する
- 人格や性格を否定しない
- 指摘や指導の後にはフォローを行う
もちろん、自らの経験を指導に活かすことも重要ですが、育成対象者は自分とは異なる性格や考え方をもった他人であることを忘れてはなりません。
相手の性格や考え方を尊重しつつ、自己開示を交えたコミュニケーションを行えば、信頼関係を構築でき、結果として帰属意識の向上、ひいては定着率の向上にもつながります。
以下の記事では、新入社員の育成で大切なことを紹介しています。あわせて参考にしてください。
関連記事:新入社員の教育方法|研修方法やテーマ、事例や成功のコツを解説
中堅社員の育成

中堅社員(入社4年目以降を想定)は、業務にも慣れて独り立ちし、部下や後輩もできる時期です。
中堅社員に対しては、組織の中枢を担うことの自覚や育成担当者としてのスキル向上、管理職候補としてのマネジメントスキル向上などが必要となります。
組織の中枢を担っていることを自覚させる
中堅社員には、あらためて自分たちが組織の中枢を担う重要な存在であることを再認識させることが必要です。
中堅社員は業務にも慣れ、効率的に成果を上げられるようになるケースが多いものの、慣れがマンネリ化による効率ダウンやモチベーション低下につながることも少なくありません。
新入社員に比べると育成の対象となる機会も減少し、こうした傾向を助長してしまいます。
そこで、自分たちは組織の大部分を占める階層であり、実績をつくる役割や新人社員をけん引する役割を担っていることを、あらためて自覚するよう促すことが大切です。
具体的な育成手法としては、役員や管理職による啓発を目的とした研修や、個別面談によるヒアリング・キャリアプランの確認などが挙げられます。状況に応じてジョブローテーションも活用しましょう。
育成担当者としてのスキルを向上させる
中堅社員になると、部下や後輩の育成を担当する場面も増えていきます。そのため、以下のような育成を行うのが良いでしょう。
- 部下育成をテーマにした研修やeラーニングを受講させる
- 得意分野で社内研修の講師を経験させる
- メンターを経験せる
- OJTでトレーナーを経験させる
- OJT研修を受講させる
メンターやトレーナーを任せる場合は、育成担当者の負担増加に注意が必要です。周囲の業務支援や上司との定期的な面談などにより、育成担当者任せにならないようにしましょう。
マネジメントスキルを身につけさせる
中堅社員は管理職候補としても期待されるため、マネジメントスキルを身につけていく必要があります。
そのためには、プロジェクトリーダーなどを任せ、現場で実際にマネジメントを経験させると効果的です。先にリーダー補助を経験させておく、いざというときの相談役を設けておくといった配慮も不可欠です。
マネジメントでは、以下のようにさまざまなスキルが必要となります。
- リーダーシップ
- 目標管理能力
- スケジュール管理能力
- コミュニケーションスキル
- ロジカルシンキング
- ラテラルシンキング
- クリティカルシンキング など
中堅社員の育成を担う上司は、各スキルが定着するよう、現場で生じた課題や経験と結びつけながら指導・育成を行いましょう。各スキルを、研修やeラーニングなどの学習で補うとさらに効果的です。
関連記事:リーダー育成に大切なことは?必要な要素やスキル、育成方法を解説
管理職の育成

管理職は、企業理念や経営層の経営方針やビジョンを正しく理解して、目標達成に向け社員をマネジメントしていく役割をもちます。
マンツーマンのような形式ではなく、実際のマネジメント業務や研修、自己啓発などを通じて自ら学びを得ていくケースが多いでしょう。
経営戦略や組織論などを学ばせる
管理職には、組織全体を俯瞰できる視野と経営的な視点が求められます。具体的には、以下のようなテーマへの理解を深める必要があります。
- 経営に関わる数値
- 組織構造や人員配置の展望
- 業界全体の傾向
- 競合他社の動向
育成手法としては、外部研修への参加や経営層による研修、代表が指定した書籍での学習などが挙げられます。
社員を評価および育成する能力を高める
社員に対する正当な評価と育成は組織の発展には欠かせません。管理職はそのどちらもを担う重要な立場です。
それにも関わらず「管理職が人事評価制度の運用方法を理解していない」「人事評価を育成に活かせていない」といった状況がみられる場合は、人事評価研修の実施をおすすめします。
関連記事:人事評価研修とは?目的と実施手段、教育すべき内容を解説
コミュニケーションスキルを再確認する
昨今はハラスメント問題が頻繫に取り沙汰されており、多くの部下をもつ管理職にとって不安な状況であることは間違いありません。
また、コーチングやティーチングなど、管理職に求められるコミュニケーションが必要なスキルは多いため、あらためてコミュニケーションスキルについて学びなおす機会を設けましょう。
管理職の育成で大切なことを紹介している以下の記事も参考にしてください。
関連記事:管理職の役割・責任とは?あるべき姿と求められる能力を解説
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
人材育成のよくある課題と失敗例

人材育成のよくある課題と失敗例には、以下のようなものがあります。
- 社員が忙しくて時間と余裕がない
- 人材育成の知識やスキルが不足している
- 社員が重要性を認識できていない
- 人材育成そのものが目的化している
- 計画的に行えていない
運用を仕組み化し、実行計画を立てることで、失敗しない人材育成を推進できます。
社員が忙しくて時間と余裕がない
人材育成を推進しようとしても、社員が忙しくて時間と余裕がないというケースは多くあります。日常業務に追われる社員は、プラスアルファの時間を確保しにくいでしょう。
現場に限らず、人材育成を担う人事関連の部署も同様に忙しく、推進に向けた動きをとれない場合もあります。
人材育成の知識やスキルが不足している
人材育成についての知識やスキルが、社内に不足している場合もあります。
事業の発展や業績アップに注力する一方、人材を育成し、育てるための知識やスキルの習得が課題として残っているケースも少なくありません。
社員が重要性を認識できていない
経営層や人材育成を担う部署が推進を図る一方、その他の社員が人材育成の重要性を認識しておらず、うまく巻き込めないパターンもあります。
「現場は研修どころではない」「研修参加は義務ですか?」のような声が聞かれた場合、重要性の認識が不足している可能性が高いでしょう。
人材育成そのものが目的化している
人材育成を行っているものの、以下のように施策そのものが目的化しているケースも見受けられます。
- OJTを行っているが、具体的な目標は設けずにトレーナーを任命するだけになっている
- 集合研修を行っているが、開催後の効果測定やフォローはしていない
- ジョブローテーション制度を導入しているが、形式的な配置替えになっている
計画的に行えていない
人材育成の目的が曖昧なまま不定期・単発で開催されている、継続的な育成手法が中断されているといった場合には、人材育成が計画的に実施されていないと考えてよいでしょう。
計画的でない人材育成は、人件費がかさむうえ、きちんとした成果が期待できません。
人材育成における課題と解決策については、以下の記事で詳しく解説しています。
人材育成を成功に導くために大切なこと

闇雲に知識やスキルを身につけさせるだけでは、人材育成はうまくいきません。計画的に進めつつ、育成対象者に対しては継続的なフォローを行い、場合によっては必要な制度を整備する必要もあるでしょう。
人材育成を成功させるためには、人材育成を1つの大きなプロジェクトとして捉え、組織的に取り組んでいく姿勢が求められます。
目的を明確にする
人材育成は、ただ教育やトレーニングを行うだけではなく、その目的を明確にすることが大切です。
目的を明確にすることで、育成対象者がその目的に向けて自己啓発を進めていく動機付けとなります。
個人の目指すべき具体的なゴール設定とともに、目的を追求すると、より有意義かつ効果的な人材育成が可能となります。
目標を設定・共有する
人材育成は目標を設定し、共有しておくことが重要です。設定により目指すべきゴールが明確になり、さらに共有することで人材育成の方向性の統一化が図れます。
目標は、客観的に判断できる指標であること、企業としての成果にもつながることをポイントに作成しましょう。また、人事・教育担当者で各部署の目標をまとめておくと、研修・セミナーなどの育成施策の企画にも有効活用できます。
関連記事:人材育成の目標|目標例や立て方、目標管理のポイントまで解説
スキルの可視化を行う
スキルの可視化は、育成対象者の現在地を把握し、成長を図るうえで重要です。可視化により、スキルレベルや育成の必要性が明らかになります。
可視化する際には、一般的には、スキルマップを作成して長所・短所を評価します。スキルマップとは各種業務スキルを軸にした表で、それぞれのスキルレベルを数値化したものです。
スキル状況が一目でわかるよう、採点やレーティングを行い、その結果をもとに育成計画を立てましょう。
また、スキルの可視化は、リーダーと部下のコミュニケーションを促進する効果もあります。具体的なスキルとそのレベルを示すことで、共通の理解を深め、育成の方向性や目標を明確化できます。
期日を決める
人材育成において、具体的なスキル獲得や能力開発のための期日設定は重要です。
育成計画を策定する際には、目標とするスキルや業績の向上度を明示し、それを達成するための具体的な期日を設定します。これにより、育成対象者は自身の成長を具体的にイメージしやすくなるでしょう。
また、期日設定は、育成の進行管理にも役立ちます。期日があることで、育成担当者と育成対象者の双方が進行状況や成果を確認でき、必要に応じて育成計画を修正できるようになります。
自主性・自発性を養う
人材育成において、育成対象者の自主性・自発性は不可欠です。
成長は、本人の「成長したい」という思いがあって初めて実現します。いくら周りが成長させようとしても、本人に成長を望む気持ちがなければ成り立ちません。
なお、「自主性」と「自発性」は似た言葉ですが、以下のような違いがあります。
- 自主性:決められたことを自分の判断でこなしていくこと
- 自発性:決められていなくても自ら進んで行うこと
自主性を養うには、育成対象者に自ら考える機会を多く与えることが有効です。一方、自発性を養うには、あるべき姿や理想とする状態を育成対象者に問いかけ、明確化させるとよいでしょう。
モチベーションを管理する
モチベーションがなければ成長につながる活動を行えないため、人材育成では育成対象者のモチベーション管理も大切です。
モチベーションは単なる「やる気」と捉えられる場合も多いのですが、正確には「やる気を起こさせる動機づけ」のことです。「行動するための目的や理由」と表すと、よりイメージしやすいでしょう。
モチベーションは主に「内的モチベーション」と「外的モチベーション」に分けられます。
| 内的なモチベーション | 外的なモチベーション | |
|---|---|---|
| 特徴 | ・上がりにくく下がりにくい ・外部の影響を受けにくい ・自らコントロールしやすい (中長期) | ・上がりやすく下がりやすい ・外部の影響を受けやすい ・自らコントロールしにくい (短期) |
| 例 | ・どうなりたいのか ・何がしたいのか ・どう生きたいかなど | ・給料アップ ・報奨金 ・ライバルの存在など |
人材育成においては、日々の指導や面談などを通じて内的なモチベーションを高めつつ、社内施策などで外的なモチベーションにも働きかけるのがポイントです。
特に、内的なモチベーションは外部の影響を受けにくく自らコントロールしやすいため、やる気を安定させるのに有効です。
内的なモチベーションと外的モチベーションそれぞれに働きかける指導や施策を組み合わせて、育成対象者のやる気が高まった状態を維持するのがおすすめです。
育成担当者のスキルを高める
人材育成を行ううえで、育成担当者のスキル向上も欠かせません。
人材育成ができる人の特徴やスキルは、以下のとおりです。
- 目標・目的を部下と共有している
- 達成に向けた動き方を部下に考えさせている
- こまめにコミュニケーションやフォローを行なっている
具体的には、設定した目標を達成できるようにする「目標管理能力」、ティーチングやコーチングなどを含む「コミュニケーションスキル」、正確な状況把握と判断に役立つ「ロジカルシンキング」などが必要です。
しかし、多忙な業務に追われるなかで、並行して学び、適切な評価をくだすことは困難を極めます。育成担当者のスムーズなスキルアップを図るならば、育成対象者が好きなタイミングで学びを深められる「e-ラーニング」の活用がおすすめです。
オンラインで学習できるeラーニングシステムを使えば、時間や場所に縛られることなく、より広範囲な人材のスキルアップや教育の均質化を実現できます。
また、最新の情報に常にアップデートして学習コンテンツを提供できるため、新人向け・管理職向けといった階層別研修や、従業員のリスキリングなども幅広く対応可能です。
eラーニング成功のコツは”導入設計”にあります
eラーニングの基本的な仕組みは理解できても、実際に成果につながる運用を継続することは簡単ではありません。多くの企業が「導入したが受講率が低い」「コンテンツ作成に時間がかかりすぎる」「効果測定ができない」という課題に直面しています。
これらの課題解決には、単なるシステム選定ではなく、学習文化の醸成から効果測定まで含めた包括的な導入戦略が不可欠です。成功企業では、5つのステップで段階的にeラーニングを組織に定着させ、継続的な学習環境を構築しています。
戦略的な視点からeラーニング活用を推進する、体系的な導入アプローチを学んでみませんか。
人材育成に対する正当な評価システムを設ける
人材育成のためには、育成対象者の成長を評価するシステムが必要不可欠です。評価が不適切、まったく行われていないなどといった場合、スキルアップの進行具合を把握しづらくなり、個々に合わせた指導ができない可能性も生じます。
一般的な評価システムでは、以下のような項目が設定されます。
| 項目 | 評価基準 |
|---|---|
| 専門性 | 専門知識、技術の習得度 |
| コミュニケーション | チーム内での意思疎通の取れ具合 |
| リーダーシップ | チームを引っ張る能力 |
| プロジェクト管理能力 | 進行管理、予算管理など |
| 積極性・主体性 | 自身で課題を見つけ解決する能力 |
評価は定期的に行い、その結果をフィードバックとして育成に活用すると、育成対象者の成長を具体的に可視化し、育成の方向性を定められます。
適切なリソース、時間を割く
人材育成は、組織の中長期的な成功に直結する大切なプロセスです。しかし、多忙を極める企業では、「人材育成に十分な時間を割けない」という問題がしばしば見受けられます。
短期的な業績追求や火急の課題解決などが優先され、結果として人材育成が後回しにされてしまうケースも多いでしょう。
しかし、人材育成は時間と手間をかけた分、そのまま結果が現れる長期的な投資ともいえます。したがって、人材育成に必要な時間を確保し、計画的に取り組むことが重要です。
例えば、一定の時間を設けて定期的に育成プログラムを行う、業務の中で育成を意識したマネジメントを行うなどの工夫が求められます。
人材育成に必要な時間の確保は、組織の成長と社員一人ひとりのスキルアップにつながるため、中長期的な視点で見る必要があります。
最適な育成スキームを選択する
人材育成を成功させるためには、最適な育成スキームの選択が重要です。育成スキームの選択が適切でないと、時間やコストを無駄に消費し、結果として育成が進まないどころか、育成対象者のモチベーション低下を招くこともあります。
以下は、具体的な職位とそれに対応する育成スキームの例です。
| 職位 | 育成スキーム |
|---|---|
| 新入社員 | ・OJT ・OFF-JT ・メンター制度 ・eラーニング |
| 中堅社員 | ・OJT ・メンター制度 ・eラーニング ・ジョブローテーション |
| 管理職 | ・eラーニング ・外部研修 ・人事評価研修 |
新入社員には実務を通じた学習(OJT)やメンター制度、中堅社員には経験豊富なメンターから学ぶ制度やジョブローテーションが効果的です。管理職になると、多角的な視点をもつための外部研修や人事評価研修が推奨されます。
育成スキームは職位や能力によって最適な選択が異なるため、企業全体が推進する人材育成モデルの整備(最適な育成スキーム選び)が重要になるでしょう。
フレームワークを活用する
人材育成では、フレームワークを活用するのも有効です。フレームワークには、以下のようなものがあります。
| 目的 | 有効なフレームワーク |
|---|---|
| 目標管理 | ベーシック法 SMARTの法則 |
| トレーナー選出・育成段階管理 | 思考の6段階モデル |
| スキル管理 | カッツモデル |
| 効果測定 | カークパトリックモデル |
効果的に活用するには、目的に合ったフレームワークを選択しましょう。
フレームワークや人材育成に大切なことについて、詳しくは以下の記事も参考にしてください。
関連記事:人材育成で大切なこと9つ|必要なスキルやフレームワークを解説
関連記事:人材育成に役立つフレームワーク|6つの活用ステップと注意点を解説
人材育成にeラーニングを活用した成功事例3選
人材育成の成功には、各社が抱える独自の課題に適したアプローチの選択が重要です。
ここでは、eラーニングを効果的に活用して、異なる業界・規模・課題に対応した人材育成を実現した企業事例をご紹介します。自発的学習文化の醸成、ナレッジ共有の体系化、KPI連動による学習習慣定着など、各社が工夫を凝らした独自の取り組みが特徴的です。
これらの成功事例から、自社の課題・強みに適した人材育成アプローチのヒントを見つけることができます。
スキマ時間活用で全社員に教育機会を提供|株式会社フレスタ様

広島県を中心にスーパーマーケットを展開する株式会社フレスタ様では、コロナ禍で集合研修が困難になり、OFF-JTと自己啓発の強化が課題でした。店舗中心の事業で全員が同じ時間に集まることが困難な業態において、これまでは昇格候補者や管理職等の特定の人たちを対象とした研修が中心で、全社員への教育機会提供が課題となっていました。店舗への移動負担や宿泊工数により研修受講の敷居が高く、動画研修の内製も容量制限で限界がありました。
AirCourseの導入により、スキマ時間を活用した学習環境を構築しました。天候不順で業務に余裕があるときにログインして学習を進めるなど、従業員が自身の都合に合わせて時間を活用できる環境を実現。受講後の振り返りシートには「動画研修を受講して、自分はいつまでにこういうことができるようになる」といった個人目標を記載し、上長のサインを得て提出する仕組みを整備しています。標準コースの自発的申し込み制度も導入し、少しずつ自発的な学習風土が根付き始めています。
導入後の主な成果
- スキマ時間活用により全社員がOff-JTを受けられる環境を実現
- 上長を巻き込んだ振り返りシートで学習効果を最大化
- 自発的申し込み制度により学習風土の醸成を推進
参考:PC1人1台の環境でなくとも、AirCourseを活用して全従業員に教育機会を提供|株式会社フレスタ様 AirCourse活用事例
視聴履歴レポートで研修効率50%向上を実現|リノべる株式会社様

リノベーション・プラットフォーマーであるリノべる株式会社様では、各自が社内資料や動画を共有サイトにアップしており、コンテンツ数はあったものの情報が整理されておらず、進捗状況の可視化やテストの一元管理ができない状況でした。散在及び属人化していたナレッジの共有と体系化、新卒・中途採用者への効率的な教育体制構築が課題となっていました。
AirCourseの「簡単に自社コースが作成できる機能」と「自由度の高さ」を評価し、学習支援ツールの統一と管理の一元化を実現しました。視聴履歴のレポート機能を活用した進捗管理により、順調に進捗しているかの確認と受講漏れのチェックを実施。特定のレッスンを長時間視聴したり何回も繰り返し受講している状況から個人のウィークポイントを可視化し、効率的なフォローアップ研修を実施しています。一つの研修コース業務を90時間から45時間に半減する50%の工数削減を実現しました。
導入後の主な成果
- 散在していたナレッジの体系化により学習支援ツールを統一
- 研修業務の50%工数削減(90時間→45時間)を実現
- 視聴履歴レポートによる個人の弱点可視化とフォローアップを確立
参考:プロセス学習の蓄積で育成効果アップ!eラーニングを活用したコンテンツ作成|リノべる株式会社様 AirCourse活用事例
動画コンテンツのKPI化で自主学習文化を確立|エフエムジー & ミッション株式会社様

化粧品、栄養補助食品、ファッション関連品の製造・販売を展開するエフエムジー & ミッション株式会社様では、マネジメント層から「各社員のボトムアップ」「マネージャー層の育成」「会社方針の理解度向上」の要望がありました。また、DXやリスキリングへの社員の意識付けが課題で、従来の別サービスでは受講履歴が残らず受講管理ができない状況でした。受講管理機能と自社オリジナルコンテンツ配信の両方が必要でした。
AirCourseの「料金の安さ」「コンテンツの数と質の充実」「自社動画配信機能」を評価し、標準コースと自社作成コースを組み合わせた教育体制を構築しました。上・下半期で2コースずつ(年間4コース)を受講必須としてKPIに含め、評価にも反映。営業研修(セールス研修)、階層別研修、会社方針等のメッセージ配信など幅広く活用しています。「セルフラーニング・自己学習」の風土が形成され、受け身だった社員も積極的に受講を求めるようになり、AirCourseをきっかけにDXに興味を持つ社員も現れています。
導入後の主な成果
- KPI化と評価連動により「セルフラーニング・自己学習」の風土を形成
- 標準コースと自社コースの組み合わせで幅広い分野での人材育成を実現
- DXやリスキリング対応の基礎となる学習習慣の定着を推進
参考:自社コンテンツと組み合わせて「各種研修」から「会社方針の理解促進」までフル活用|エフエムジー & ミッション株式会社様 AirCourse活用事例
まとめ
人材育成は、さまざまな取り組みが集積する、一つの大きなプロジェクトとも言えます。このプロジェクトを成功に導くためには、「人材育成を通じて、社員がどのように企業に貢献できるようになるのか」という視点を常にもっておくことが大切です。
また、他の仕事とも並行しながら取り組まなければいけない社員にとって、いかに効率良く進めるかもポイントとなります。今回紹介した人材育成の手法やフレームワークを、積極的に活用してみてください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。