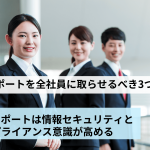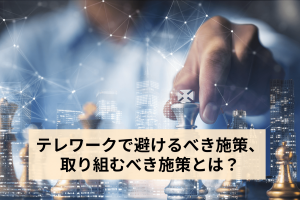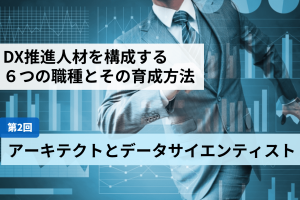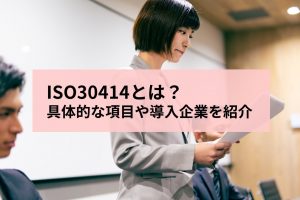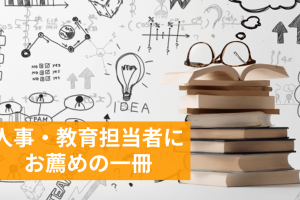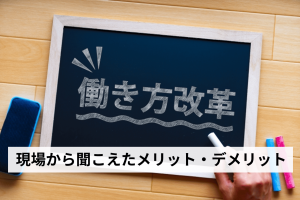昨今、人材育成やマネジメントの手法としてコーチングが注目されています。本記事の読者の中にも、多様な価値観を持つ部下との接し方や、チームの主体性を引き出す手段を模索し、コーチングに興味を持っている人もいるでしょう。
しかし、次のような悩みもあるのではないでしょうか。
「ティーチングとの違いがわからない」
「マネジメントに活用できるのか不安」
「具体的な実践の仕方がわからない」
実際、コーチングは成果が出るまでに時間がかかり、やり方も相手によって異なります。そのため、コーチングを効果的にビジネスで活用するためには、しっかりとコーチングの考え方を理解し、長期的な視点で取り組むことが大切です。
そこで本記事では、コーチングの基本的な考え方をはじめ、すぐにでも始められるコーチングの実践方法を紹介していきます。コーチングは部下の主体的な行動を引き出すのに有効な手段です。最後まで読んで、ぜひ早速実践してみてください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
コーチングとは
コーチングとは、コーチとクライアントの対話を通じて、クライアントが目標達成に向けて主体的に行動することを支援するプロセスです。コーチングの特徴は、あくまでも目標達成までの主導権はクライアントが握っているという点にあります。
コーチの役割は、クライアントの目標達成に必要な現状把握や分析を、問いかけを通じてサポートしていくことです。
組織の成長において、社員自身の主体的な行動が求められるなか、従来のティーチングやトーレーニングといったトップダウン型のマネジメントスタイルに加え、社員の主体性の育成に有効なコーチングが今注目を集めています。
コーチングとティーチングの違い
日本語でコーチ(英:coach)というと、スポーツやダンスなどの指導者を想起することが多いでしょう。そのため、ティーチングとの違いが曖昧になってしまっています。しかし、ティーチングとコーチングは、考え方に大きな違いがあります。
ティーチングは上司や教師が答えを提示し、部下や生徒がそれを学ぶというスタイルです。教える側が目的達成のために必要な情報を知っており、教わる側は何も知らないという情報の非対称性が、そもそものスタート地点になります。
一方でコーチングでは、基本的にそのような情報の非対称性は重要ではありません。先ほど、コーチングではクライアントが主導権を握っていると説明しましたが、コーチングのスタート地点ではクライアントも目標達成までに必要な答えを知っているわけではなく、ましてやコーチも答えを用意していません。
では答えはどこにあるのか。「答えはクライアントの中にある」とコーチングでは考えます。
その答えを引き出す、または共に探求していくプロセスがコーチングです。コーチは答えを引き出す術をいくらか心得ているため、クライアントが自分で気付き、目標達成に向かうことを支援できるのです。
とはいえ、コーチングとティーチングは必ずしも相反するものではありません。知識やスキルを教える際にはティーチングが必要ですし、部下の主体性を引き出したり、成果が上がらないと感じている人のサポートをしたりする時にはコーチングが有効でしょう。状況に応じて使い分けることが大切です。
メンター制度との違い
コーチングとメンター制度は、似た側面もありますが、その目的や位置づけは異なります。
| 項目 | コーチング | メンター制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 相手の気づきを促し、自己実現を支援する | 長年の経験に基づく指導・助言を行う |
| 期間 | 一定期間に限定される | 長期的な関係が一般的 |
| 関係性 | 対等な立場 | 上位者から下位者への一方向 |
コーチングでは、コーチはクライアントに質問を投げかけ、自らの気づきを引き出すプロセスをサポートします。一方で、メンターは自身の豊富な経験から助言やノウハウを伝授する立場となります。
1on1ミーティングとの違い
1on1ミーティングとコーチングは、よく似た概念のように見えますが、大きな違いがあります。
| 項目 | 1on1ミーティング | コーチング |
|---|---|---|
| 目的 | 上司と部下間での情報共有、課題への助言など | 自己実現と成長を促すこと |
| 進行 | 上司主導で進行することが多い | コーチが質問を投げかけ、相手の気づきを促す |
| 関係性 | 上下関係 | 対等な関係 |
1on1ミーティングは、主に上司が部下の業務状況を把握し、課題解決のアドバイスをすることが目的です。一方、コーチングは、相手の自己実現と成長を促すことが目的であり、コーチは解決策を与えるのではなく、質問を通して相手自身に気づきを得てもらうことが重要となります。
また、1on1ミーティングには上下関係がありますが、コーチングは対等な関係で行われます。コーチは専門家として上から目線で接するのではなく、相手の成長を共に喜び合える関係性が求められます。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
コーチングが必要とされる背景
コーチングが必要とされている背景は主に2つあります。1つはトップダウン型の組織マネジメントが見直されているということ、もう1つは、組織開発の一環として社員同士のコミュニケーションの質を高める必要が出てきたということです。
昨今、価値観が多様化したことで世代間ギャップが拡大しています。そのため、従来のトップダウン型で一方向的なマネジメント体制では、パワーハラスメントなどのリスクがあるだけでなく、部下の主体的な行動を引き出すことも困難です。
また、日本においては社員同士のコミュニケーションの質も問題視されています。コーチ・エィの調査を見ると、主要15か国の比較で、日本は上司と部下の関係性の良好度が低い状況です。特に、「上司と部下が話す割合」という項目では、「上司が話している時間の方が長い」と回答した割合が大きいという特徴があります。
このような状況で求められるのは、社員一人ひとりに合った指導を行うことです。そしてコーチングは、クライアント自身が主役であるため、昨今の時代にマッチしたマネジメント手法として注目されています。
ビジネスにおけるコーチングの役割と効果
コーチングのメリットは、相手の内発的な行動を引き出すという結果が得られるだけではありません。コーチングをマネジメントや人材育成に取り入れることで、組織が活性化し、自律的な成長を促すこともできるのです。
具体的には、以下のような効果がコーチングによってもたらされます。
- 部下の主体性を引き出す
- 信頼関係の構築による組織力の向上
- セルフ・コーチングができるようになる
部下の主体性を引き出す
コーチングでは、コーチの問いかけを通じて、目標達成に向けて必要な考え方や行動を、クライアント自身が気付くというプロセスが重視されます。コーチが先導したり強制したりすることはありません。
自分自身の中から生まれたものだからこそ、クライアントは納得感を持って主体的に行動に移すことができます。つまり、コーチングはクライアントの内発的動機付けによる行動を引き出すことができるのです。
部下が主体的に行動しない、指示を待つ癖があると感じているのであれば、コーチングはその悩みを解消する助けになるでしょう。
信頼関係の構築による組織力の向上
コーチングでは「質問」を通じてクライアントの考えを引き出していきますが、その過程で大切なことは相手の存在や行動、発言を「承認」することです。
承認はさまざまな場面で行うことができます。1対1で話している時は相手の考え方を否定せずに受け止め、チャットツールでの発言に対してはこまめにリアクションすることで、徐々に相手は自分の存在が認められているという安心感を持つことができます。
こういったこまめなコミュニケーションを取ることで、相手との信頼関係を構築することができます。互いに存在を認め合うことができている組織では、一人ひとりが安心して主体的に行動することができるため、健全性・生産性の高い組織となるでしょう。
セルフ・コーチングができるようになる
コーチングを行うことで、自身を客観的に見ることができるようになります。これはクライアントだけでなく、コーチ自身にも言えることです。
自分自身を客観的に分析し、目標を達成する経験を通じて、今度はそのプロセスを自分ひとりで完結できるようになるのです。これをセルフ・コーチングと呼びます。
セルフ・コーチングができるようになれば、持続的な自己成長のサイクルを回すことができるようになるでしょう。そして自己成長の習慣化ができているメンバーが集まるチームは、自律的に成長していきます。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
コーチングのデメリット
コーチングは現代にマッチした効果的なマネジメント手法です。しかし、時間をかけて対話を重ねていくという特徴のため、いくつか注意点があります。
コーチによって成果にばらつきがある
コーチングは、コーチとクライアントの関係性や、コーチの質問や傾聴、承認のスキルによって成果にばらつきが出る可能性があります。
また、コーチングは長期的なプロセスです。なかなか成果が出ないからといって、相手を急かすと、むしろ関係性を悪化させるリスクもあります。
成果が出るまで時間がかかる
コーチングは他者に与えられた目標を達成するものではありません。自分自身で目標を設定し、現状とのギャップを認識することで、主体的に行動する必要があるのです。これは一朝一夕に効果が出るものではないでしょう。また、一人ひとりの課題や問題意識の持ち方によって成果が出るスピードも異なります。
そのため、緊急性の高い課題解決の手法としては適していません。コーチングは、重要ではあるが緊急性は高くない課題にこそ有効なアプローチなのです。
コーチングの効果的な進め方
コーチングは、元々日常で行われていた良質なコミュニケーションを体系化したものです。そのため、コーチングは専門的なスキルとして学ぶこともできますが、基本的な考え方は普段のコミュニケーションでも取り入れられます。
オープンクエスチョンで問いを立てる
例えば、同僚や部下が会議に遅れて来ました。開口一番にどう自分なら発するか考えてみてください。
「会議に遅れていいのですか?」や「どうして事前に伝えてくれないのですか?」
という問いはオープン(open:開かれた)とは対極にある、クローズド(closed:閉ざされた)な問いと分類されます。問われた側は、
「質問者が期待する答えは何だろうか?」
というようにに、質問者の解を探る、いわば非生産的な方へ思考が狭まってしまいます。もしかすると、これまでに皆さんも一度は自分で言ったり、上司に言われたりしたことがあるかもしれません。
しかし、コーチングで重要なことは聴き手視点で問いかけを行うことです。
では、オープンクエスチョンではどのような問いを立てるのでしょうか。
例えば、
「優先事項が何かありましたか?」
「会議の目的を再確認しましょう。」
など相手の思考を限定しない、先を見据えた質問が考えられます。
仮に、理由なく遅刻してしまい、自責の念に駆られている社員であっても「会議に遅れた分取り返さなければ。」と生産的な方向へ「導く」ことになります。
セカンドシグナルを情報や指示の前に添える
コーチングだけで業務を回すことはできません。組織においては指示命令が必要な場面があります。そのような指示命令を下す場合でもコーチングの考え方は有効です。
具体的にはセカンドシグナルと呼ばれる手法を使います。
危険回避など急を要するケースなど例外を除いては、一方的に指示や情報を伝えるだけでは、時に相手としては冷酷に受け取られ、自発性や動機付けを損ねることに繋がりかねません。
指示や命令の直後に、一言思いやりを示す、一見関係のない雑談を添えることで、指示に対する自発性を喚起することができます。
例えば、「〜をやって欲しい」とお願いした後に一言、「君に任せたい」などを付け加えることで、相手の自己肯定感を高めることができます。この少しの気遣いによって、自発的に指示内容に取り組んでくれる可能性が高まります。
アクノレッジメントで高める自己肯定感
コーチングにおいては自発性や内発性など、相手側の視点で考えることが大切です。ここで挙げるアクノレッジメント (英:acknowledgment)とは相手を承認する、認めることです。先ほども簡単に説明しましたが、具体的にみていきましょう。
相手の何を承認するかは様々ですが、まず第一に、相手の存在をしっかりと認めることが必要です。自分だけが「認めている」と感じているだけではだめで、相手が「認められている」と感じる必要があります。
そのためには、社内のチャットツールでの発言に反応したり、こまめに話しかけたりすることが大切です。このような行動の積み重ねを通じて、相手は「存在を認められている」と感じることができます。
コーチングの学び方
コーチングの考え方は、誰でもすぐに取り入れられるものですが、専門的なスキルとして身につけることも可能です。
コーチングを受ける
プロのコーチングを受けることで、実際のコーチングを体験することができます。プロがどのような質問を行なっているのか、またコーチングを受ける側の気持ちも体験することができます。コーチングを体系的に学ぶべきか迷っている人も、まずはコーチングを受けてみると良いでしょう。
セミナーや研修に参加する
各種団体が個人向けの説明会やセミナー、法人向けの研修などを行っています。これらの研修やセミナーでは、講義形式で知識やスキルを身につけたり、その場で実習を行うことができます。実践形式でコーチングを学びたい人におすすめです。
資格を取得する
コーチングにはいくつか資格があります。資格を取得することで、コーチとしての技能を証明することが可能です。例として代表的な認定コーチを3つ紹介します。
- 一般財団法人生涯学習開発財団(GLLC)後援の認定コーチ
GLLCは文科省所管の団体です。GLLCでは、企業や団体が行う資格認定を厳密に審査し、各団体が行う資格認定に「認定証」を発行する形で後援しています。コーチングについては、コーチ・エィの認定コーチが用意されています。どの資格を取れば良いか迷っている人は、まずはGLLC後援の資格を取得してみてはいかがでしょうか。
- 一般社団法人日本コーチ連盟(JCF)の認定コーチ
JCFでは、コーチとして活躍するための資格と、コーチングの技能を教授するインストラクターとしての資格を用意しています。さまざまなレベルのプログラムが用意されているため、自分の目標にあった資格を選択することができます。
- 国際コーチ連盟(ICF)の各種資格
ICFの資格はレベル別に、「アソシエイトコーチ(ACC)」「プロフェッショナルコーチ(PCC)」「マスターコーチ(MCC)」が用意されています。各資格は取得までに50万円〜90万円の費用がかかりますが、国際的に活躍したい人におすすめの資格です。
eラーニングで学ぶ
コーチングはeラーニングで学ぶことも可能です。eラーニングとは、パソコン、スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器、インターネットを利用して教育、学習、研修を行うことを指します。
eラーニングでは、コーチングのスキルや流れをドラマ仕立てで学ぶことができるので、具体的な活用方法を知りたい人におすすめです。
また、インターネットを通じて学習するため、会場に受講者を集めて実施する「集合研修」とは異なり、時間や異なり時間や場所を選ばずに受講者個人の事情に応じて、いつでもどこでも学習できる特徴があります。
受講者個人の習熟度に合わせて自分のペースで学習できる点も大きなメリットです。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
主体的な学びにeラーニングを活用した事例
コーチングスキルの向上や主体的な学習文化の醸成において、eラーニングを効果的に活用した企業の事例を紹介します。
企業内大学で全社的な学習文化を醸成|豊田合成九州株式会社様

トヨタグループの豊田合成九州株式会社様では、集合研修中心の教育体制で「決まった時間、決まった場所での受講」という制約により、社員の主体的な学習機会が限定されていました。「階層別研修」「ビジネス基礎」「IT/DX教育」「自己学習の文化醸成」など様々な人材育成領域の強化が課題でしたが、一部の社員しか受講できない状況で均等な教育機会を提供できていませんでした。
AirCourse導入により企業内大学「TGKU」を開設し、標準化された一貫性のある教育と全社員への均等な学習機会を実現しました。必須の階層別研修に加え、従業員が自主的に学べる自己申告型の研修プログラムを提供し、「自ら学び合う文化」の土台づくりを行いました。eラーニングを「情報のインプット」、集合研修を「社員同士の対話」と役割分担することで、コーチング的な相互理解促進の場を確保しています。
導入後の主な成果
- 企業内大学として全社的な「学び合う文化」を醸成
- インプットと対話の役割分担で効率的かつ効果的な人材育成を実現
- 自己申告型研修で社員の主体的な学習姿勢を促進
社員の自主性を重視した学習環境で97%の受講率を達成|日本瓦斯株式会社様

総合エネルギー企業の日本瓦斯株式会社様では、別のeラーニングサービスを利用していましたが、数年が経過するとコンテンツが重複し、新鮮味に欠ける状況となっていました。IT改革とDX推進に伴い、社員のITリテラシー強化とともに、主体的な学習文化の構築が急務となっていました。
AirCourse選定のポイントは、講師による登壇型の研修動画とコース数の充実、そして利用者がスムーズに利用できるログイン設定の柔軟性でした。導入後は社員の自発的な学習に重きを置き、全コンテンツを視聴できる環境を構築。ハラスメントとメンタルヘルスを必須受講とし約97%の受講率を達成しながらも、現場での活動を優先するため必須コンテンツは最小限に抑え、各社員が自己啓発として自由に受講できる環境を実現しています。
導入後の主な成果
- 社員の自主性を重視した学習環境で97%の高い受講率を達成
- 現場活動と学習のバランスを取った効果的な運用を実現
- 豊富なコンテンツで各社員の関心に沿った自己啓発を促進
若手主導のコンテンツ作成で主体性と教育を両立|北越メタル株式会社様

創立80周年の鉄鋼メーカーである北越メタル株式会社様では、技術的なスキルや資格習得中心の教育から、社員との絆をテーマとした教育体系の再構築が課題となっていました。社員の能力にばらつきが見られ、長期的なビジョンを踏まえた教育面でのベースアップが必要でした。
AirCourse選定の決め手は、若手からマネジメント層まで幅広く揃ったコンテンツと、自社でのオリジナルコース作成機能でした。入社2〜3年目の若手社員10名程のプロジェクトチームを結成し、「来年の新入社員向けに必要なコンテンツを作って欲しい」というテーマで自由な発想によるコンテンツ作成を実施。若手同士の交流の場としても機能し、経営陣や上司への発表の場を設けることで、主体的な提言とフィードバックの好循環を創出しています。
導入後の主な成果
- 若手プロジェクトチームによる主体的なコンテンツ作成を実現
- 社員同士の交流促進と経営陣との対話機会を創出
- 現場レベルでのコンテンツ作成推進により全社浸透を図る仕組みを構築
まとめ
コーチングは相手との対話を通じて、主体的に目標達成が行えるようサポートするプロセスです。ティーチングとは異なり、あくまでも相手に主導権を持たせる点に特徴があります。このため、多様な価値観を持つ社員の育成や、組織の自律性を高める手段として非常に有効なのです。
コーチングは、資格によってスキルを証明することができますが、根本的な考え方はすぐにでも実践できます。本記事で紹介したオープンクエスチョンやアクノレッジメントなど、できることからはじめてみるのはいかがでしょうか。
人材育成の推進にeラーニングシステムを活用しませんか
コーチングの理論や手法を理解することは重要ですが、実際の成果は「いかに組織全体で継続的に実践し、コミュニケーション品質を向上させるか」にかかっています。多くの企業がコーチング研修を実施しているものの、個人のスキル向上が組織の成果に結びついていないのが現実です。
コーチングスキル向上と実践的な組織コミュニケーション改善を効率的に支援するツールとして、AirCourseをご活用いただいている企業様も多くございます。1000コース以上の動画コンテンツで体系的なコーチング手法と実践的なマネジメントスキルの向上を同時に実現できます。
月額200円~の低コストで継続的なコーチングスキル向上環境を提供し、既存教材がそのまま使えてコーチング研修の負担を軽減します。今なら、AirCourseの『機能詳細』『導入事例』『料金プラン』がわかる資料3点セットを無料でお受け取りいただけます。