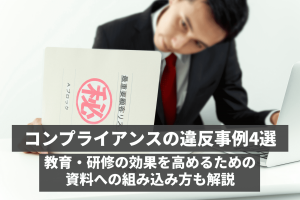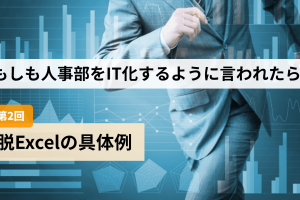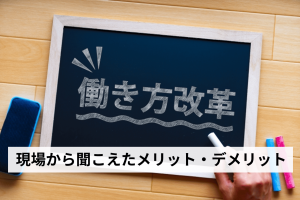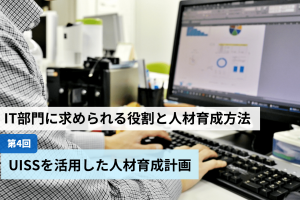社員の学習意欲向上や研修の定着率に課題を感じていませんか?従来の長時間研修では、忙しい社員が最後まで受講できなかったり、学習内容が身につかなかったりする問題が生じることがあります。
こうした課題の解決策として注目されているのが「 マイクロラーニング 」です。マイクロラーニングは、 5〜10分程度の短時間コンテンツで学習を進める手法で、スキマ時間を活用した効率的な人材育成を可能にします 。
本記事では、 マイクロラーニングの基本概念から導入メリット、成功のポイント、実際の企業での活用事例 まで、人事担当者が知っておくべき情報を体系的に解説します。 社員の自発的な学習習慣を育み、組織全体の成長を加速させたい方は、ぜひ参考にしてください。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
マイクロラーニングが注目される背景
マイクロラーニングが注目される背景には、学習を取り巻く環境やビジネスの変化、そして従来の学習手法が抱える課題があります。
学習者と学習環境の変化
現代の学習者は、日々の業務に忙殺される中で、まとまった学習時間の確保が難しくなっています 。また、スマートフォンの普及、働き方の多様化(リモートワークの浸透など)により、学習環境も大きく変化してきました。
そのため、時間や場所を問わず、移動中や休憩時間といった「スキマ時間」にサクッと学びたいというニーズが高まり、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視する傾向も強く、短時間で効率的に知識やスキルを習得できる学習スタイルが求められています。
マイクロラーニングは、こうした現代の学習者の行動様式に対応できる学習手法として注目されています。
ビジネス環境と求められる人材育成の変化
ビジネス環境の変化が激しい現代において、企業は常に最新の情報に基づいた迅速な対応が求められます。これに伴い、 従業員一人ひとりにも、新しい知識やスキルを継続的に学び、変化に適応していく能力が不可欠 となりました。
企業は、従業員のスキルアップを迅速かつ効率的に行う必要に迫られています。しかし、従来の研修手法では、最新情報をタイムリーに反映させたコンテンツを迅速に提供することが難しい場合があります。
マイクロラーニングは、短いコンテンツのため作成や更新が容易であり、変化の速いビジネス環境に対応したタイムリーな人材育成を可能にします。
従来の研修手法が抱える課題
従来の集合研修は、時間や場所の制約があり、参加者のスケジュール調整や会場手配に手間がかかります。また、長時間の研修は参加者の集中力維持が難しく、学習内容の定着率に課題がありました。
一方、長時間のeラーニングコンテンツも、最後まで受講してもらうのが難しかったり、教材の作成・更新に時間とコストがかかったりするという課題があります。
マイクロラーニングは、短い時間で完結するコンテンツ形式であるため、受講者の負担が少なく、企業側もコンテンツの作成・更新の負担も少なくて済みます。 従来の研修手法だけでは対応しきれなかった、時間やコスト、学習効果といった課題の解決策として期待されている学習法です 。
また、個々の受講者の学習進捗や理解度に合わせて、柔軟に学習内容をカスタマイズしやすい点も、マイクロラーニングが支持される理由のひとつです。
マイクロラーニングを導入する際のメリット
マイクロラーニングを導入することで、企業の人材育成に関するさまざまな課題を解決できます。
ここでは、主なメリットを企業と受講者に分けてそれぞれご紹介します。
学習効率と定着率の向上
マイクロラーニングは、学習効率と定着率の向上に効果的です。 学習内容が小さく分割され、1つのコンテンツが5分~10分程度の短い時間で完結するため、受講者は集中力を維持しながら学習を進めることができます 。
また、短時間の集中した学習は記憶の保持につながりやすいのも特徴です。反復学習や確認テストなどを組み合わせると、より効果的に知識を定着させることもできます。これにより、企業としては効率的に社員のスキルアップを図ることが可能です。
社員の自発的な学習習慣を促進できる
マイクロラーニングは、受講者である社員の自発的な学習習慣の定着を促進することができます。
受講者は自分のペースで、好きな時間・場所を選んで学習を進めることができるだけではなく、学習内容が短く分割されているため、 学習を習慣化させやすいというメリットがあります 。
カリキュラムを終えた達成感がさらなる学習意欲へとつながり、受講者は能動的な学習習慣を身に着けていきます。社員が自ら学ぶ姿勢を育むことは、企業の持続的な成長につながります。
コンテンツの修正・作成が容易
マイクロラーニングのコンテンツは、短い時間で学習できるよう設計されるため、コンテンツの新規作成や修正が容易です。
従来型のeラーニングでは、長時間の動画を作成・編集する必要があり、更新にも手間がかかっていました。 マイクロラーニングでは、数分程度の動画や短いテキスト、クイズ形式のコンテンツが中心となるため、内容の修正や更新がしやすいのもメリットです 。
また、新しいコンテンツの作成も比較的短時間で行うことができるため、常に最新の情報に基づいた研修を提供しやすくなります。
マイクロラーニングを導入する際のデメリット
この章ではマイクロラーニングを導入する際のデメリットをご紹介します。
複雑な内容のコンテンツには不向き
マイクロラーニングは、複雑な内容や専門性の高い内容を扱うには不向きです。
これは、学習内容が専門的で難解な場合、マイクロラーニングで提供できる短い時間内では、受講者が十分に理解することが難しいためです。
マイクロラーニングは、学習内容を簡潔にまとめられ、要点を押さえて提供できるコンテンツに適しているため、例えば、プログラミングや、法律の専門知識など、複雑な概念や手順の理解が必要な分野の場合、座学やワークショップで専門的な内容を扱った後に、マイクロラーニングで復習や知識の補完を促すなど、他の学習方法と組み合わせて利用すると良いでしょう。
eラーニングシステムの導入に金銭的・時間的コストが発生する
eラーニングシステムの導入には、システム選定、コンテンツ作成、導入・設定、運用・保守などに費用がかかります。
また、社内での運用体制を整えるための時間的コストが発生します。
コストを抑える方法として、クラウド型eラーニングシステムの活用が挙げられます。
クラウド型は初期費用が比較的安価で、自社でサーバーなどのインフラを用意する必要がありません。さらに、システムのアップデートやセキュリティ対策はベンダーが対応するため、運用管理の負担も軽減されます。
マイクロラーニングを効果的に導入するためには、eラーニングシステムにかかるコストを事前に見積もり、予算内で最適な方法を選ぶことが重要です。
自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう
クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。
階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。
マイクロラーニングの効果を高める方法
この章では、マイクロラーニングの効果を最大限に引き出し、学習内容をしっかりと定着させるための方法をご紹介します。
反転学習を取り入れる
反転学習とは、研修前に事前学習(インプット)を行い、研修では学んだ知識の応用や実践(アウトプット)に重点を置く学習方法です。
事前学習にマイクロラーニングを活用し、反転学習で学習内容をさらに深めることで、より効果的な人材育成が期待できます 。
例えば、マイクロラーニングで新製品の機能や特徴を学習し、反転学習で営業ロールプレイングを実施する、といった方法が考えられます。
参考: 反転学習とは?メリットやデメリット、活用方法を解説 | 人材育成サポーター
デザイン思考を取り入れる
マイクロラーニングにデザイン思考を取り入れることで、受講者のニーズに合った効果的な学習体験を提供できます 。
デザイン思考とは、デザイナーがデザインを行う際に用いる思考プロセスを指します。ユーザー中心の問題解決手法であり「共感」「問題定義」「アイデア創出」「プロトタイプ作成」「テスト」の5つのステップから成り立ちます。
例えば、新入社員研修にマイクロラーニングとデザイン思考を組み合わせた研修プログラムを導入することで、自社のサービスや顧客について深く理解することができるようになります。
参考: デザイン思考とは?若手社員育成に効果的な導入方法について徹底解説
ソーシャルラーニングと組み合わせる
ソーシャルラーニングとはSNSやブログなどのソーシャルメディアを学習ツールとして活用する学習方法です 。ソーシャルメディアを使って、マイクロラーニングで得た知識を社員同士が教え合い、学び合うことができます。
また、アウトプットの機会を設けることで、記憶の定着を促し、他のメンバーの発言から新たな発見や気づきを得ることも可能です。グループワークやディスカッションで共有・議論することで、理解を深め、疑問を解消することができるでしょう。
参考: ソーシャルラーニングを実現するためのITインフラとは?第1回 | 人材育成サポーター
ゲーミフィケーションを取り入れる
ゲーミフィケーションを取り入れることで、マイクロラーニングの学習効果を向上させることができます。
ゲーミフィケーションとは、ゲームの要素や考え方をゲーム以外の分野に応用することを指します。具体的には、ポイント・バッジ・ランキング・レベルアップ・クエスト形式の課題などを導入することで、受講者のモチベーションを高め、学習の継続率を向上させることが可能です。
例えば、クイズ形式で学習を進めることで即時フィードバックを得られる仕組みを作ったり、学習達成ごとにバッジを付与することで達成感を得られるようにしたりすることができます。
ゲーミフィケーションを取り入れることで、学習の「義務感」を減らし、楽しみながらスキルを習得できる環境を提供できるため、特に自主的な学習が求められるeラーニングと相性が良いといえます 。
参考: ゲーミフィケーションとは?企業研修への導入の際のポイントとメリット、注意点について解説 | 人材育成サポーター
マイクロラーニングの運用を成功させるポイント
この章では、マイクロラーニング運用を成功させるためのポイントをいくつかご紹介します。
人材育成カリキュラムを作成する
効果的なマイクロラーニング運用のためには、まず人材育成カリキュラムを作成することが重要です。
育成カリキュラムがないままマイクロラーニングを導入しても、期待する効果を得ることは難しいでしょう。
なぜなら、 マイクロラーニングはあくまでも人材育成の手段のひとつに過ぎない からです。
人材育成の目的を達成するための全体像を描き、その中でマイクロラーニングをどのように活用するかを明確にする必要があります。
また、カリキュラム作成にあたり、自社の課題やニーズを把握することも重要です。
カリキュラム作成の手順は以下の記事で詳しく解説しています。
参考: 新入社員研修カリキュラムの作成手順|基本と職種別の内容例 | 人材育成サポーター
ブレンディッドラーニングの一環として運用する
マイクロラーニングを他の学習方法と組み合わせたブレンディッドラーニングの一環として運用することで、受講者の高い学習効果が期待できます。
ブレンディッドラーニングとは、集合研修やOJT、オンライン研修やeラーニングといった複数の学習手法を組み合わせた学習方法 です。
例えば、集合研修で学んだ内容の復習にマイクロラーニングを活用したり、eラーニングで学習する前の導入としてマイクロラーニングを活用したりすることで、学習内容の定着率を高められます。
ブレンディッドラーニングで使えるマイクロラーニングの活用方法は以下の通りです。
| 学習フェーズ | 学習内容 | マイクロラーニングの活用例 |
|---|---|---|
| 導入 | 学習内容の導入、興味関心の喚起 | 5分程度の動画で学習内容の概要を説明する |
| 知識習得 | 講義形式で知識を習得する | eラーニングで学習した内容を要約した動画を視聴する |
| 実践 | 学んだ知識を応用して課題に取り組む | ロールプレイング形式で、学んだ知識を活用する練習を行う |
| 確認・定着 | 学習内容の理解度を確認する | 小テスト形式で、学んだ内容を復習する |
| フォローアップ | 学習内容を復習する | 1週間後に、学習内容をまとめた動画を視聴する |
研修後アンケート・理解度テストの実施なら「AirCourse」
研修後のアンケートや理解度テストの実施は、管理がしやすい「AirCourse(学習管理システム)」がおすすめです。
AirCourseなら、動画視聴後・集合研修後のアンケート・テスト実施が容易で、必要に応じて追加の学習や声かけを行うことができます。システムに標準搭載されているコンテンツに加え、企業オリジナルのコンテンツを作成・配信することが可能です。
自社の社員研修を実りあるものにしたい、さらにアップデートしたいとお考えの方はAirCourseが分かる下記資料をご覧ください。
1つのコンテンツで完結させる
マイクロラーニングのコンテンツは、短く簡潔に作成することが重要です。1つのコンテンツは5分~10分程度におさめ、1つのテーマに絞って学習内容を完結させましょう。 複数のテーマを混在させると学習内容が断片的になり、学習効果が半減する恐れがあります 。
また、1つのテーマに絞って作ったコンテンツは再利用しやすく、新たなコンテンツ作成の手間を省くこともできます。
モバイル端末での学習を想定し、音声解説などを加えることで、さらに学習効果を高めることができます。視聴覚に訴えることで、記憶への定着を促進する効果が期待できるでしょう。
参考: マイクロラーニング・ツールの種類と選択のポイント | 人材育成サポーター
eラーニングのコンテンツを再利用する
eラーニングですでに保有しているコンテンツがある場合、それらをマイクロラーニングに適したサイズに分割・編集することで教材として再利用することができます。
この場合、 1から教材を作成しなくて済むので、手間とコストを削減できます 。
例えば、eラーニングで1時間の研修動画があったとします。
この動画を5分程度のマイクロラーニングコンテンツに分割・編集することで、受講者は1時間というまとまった時間が取れなくても、5分×12本という形で学習を進めることができます。
受講者に学習内容をアウトプットしてもらう体制を整える
受講者に学習内容をアウトプットしてもらう仕組みを社内で整えることも重要です 。
受講者はアウトプットすることで学習内容の理解が深まり、記憶に定着しやすくなります。また、企業側が受講者の学習成果を可視化することで、より質の高い学習計画を作ることもできます。
効果的なアウトプット方法のひとつとして、学んだ内容を「他の人に説明する」という方法があります。人に説明しようとすると、曖昧な理解では説明できないため、より深く理解しようという意識が働きます。
また、説明する過程で自身の理解不足な点や疑問点が明確になり、自己学習の促進にもつながります。その際、業務に直結したアウトプットの機会を正式に設けるとより学習に効果的です。
評価方法としては、テストや課題提出、グループワーク、実技試験、自己評価、360度評価など、さまざまな方法があります。これらの方法を組み合わせて自社に最適な評価体制を構築することがポイントです。
参考: 研修の効果測定とは|4つの評価レベルと段階別の測定手法を解説 | 人材育成サポーター
eラーニングによるマイクロラーニングの成功事例
マイクロラーニングは、以下の特徴を持つ企業で導入されると効果を発揮します。
24時間体制でマイクロラーニングによるスキマ時間学習を実現|医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様

福岡市近郊で600床以上を有する総合病院として地域医療を支える医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様(約1,800名の職員)では、24時間体制の医療現場という特殊な勤務環境における人材育成が課題でした。事務職には医療事務の専門スキルに加え、リーダーシップやKPI管理、多様性理解などの幅広いビジネススキルが求められるようになったものの、夜勤やシフト勤務があるため全員が一堂に会する集合研修の実施が困難で、コロナ禍では感染リスクも懸念材料となっていました。
同院が導入したAirCourseのマイクロラーニングは、講師の話し方や背景デザインが統一された見やすいコンテンツと、30分程度の内容が5分に区切られた短時間学習設計が決め手となりました。役職別に課長クラスには「アカウンティング」「KPI管理」、係長クラスには「リーダーシップ」「フォロワーシップ」、主任クラスには「Excel統計」など、階層別研修を体系的に実施し、人事評価への反映により受講率ほぼ100%を達成しています。
導入後の主な成果
- 24時間体制の勤務環境でも公平な学習機会を提供
- 朝の10分や業務の合間などスキマ時間を活用した効率的学習を実現
- 役職に応じた体系的なスキルアップ環境を構築
- 受講率ほぼ100%を達成し、全職員の能力向上を促進
参考: 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様|AirCourse活用事例
マイクロラーニングと反転学習で研修効率化と売上向上を実現|株式会社SHIFT様

ソフトウェアテスト専門として5兆円市場のリーディングカンパニーを目指す株式会社SHIFT様(グループ約5,000名)では、急成長に伴う人材育成の課題に直面していました。毎月100名の中途入社者に対する集合研修は拠点ごとの講師手配が必要で研修内容に差が生じるケースがあり、さらに地方拠点も含めた全社統一の教育環境整備が急務でした。また、スキルアップとキャリアアップを目指す独自の社内検定試験制度「トップガン教育」の全社展開も課題となっていました。
同社がAirCourseを選んだ決め手は、受講者からの問い合わせがほとんど発生しない直感的なUI/UXと、スマートフォンでの簡単利用でした。入社者研修では講義動画を各自がAirCourse上で事前学習し、対面時間は演習やディスカッションに集中する反転学習を実現しました。「トップガン教育」では学習から試験までワンストップで運用し、合格者には上位業務へのアサインと収入アップという明確なインセンティブを設定し、全社的な検定試験ブームを創出しています。
導入後の主な成果
- 平均受注単価15.2%アップを実現
- 反転学習により研修効率が格段に向上
- 拠点に関係ない平等な学習環境を全社に提供
- 約1,000名が登録する自発的学習文化を構築
参考: 株式会社SHIFT様のAirCourse導入・活用事例
組織急拡大期における効率的教育体制でスピードと品質を両立|株式会社MS-Japan様

管理部門・士業特化の人材紹介事業を展開し東証一部上場を果たした株式会社MS-Japan様では、従業員50名規模での組織拡大と株式上場準備に伴う教育体制強化が喫緊の課題でした。従来の代表による独自研修や社員作成マニュアルでは限界があり、上場に必要なインサイダー取引研修、ハラスメント研修、情報セキュリティ研修などのコンプライアンス強化が必須となりました。さらに営業スタッフが多いため同じ時間・場所への集合が困難で、効率的な研修実施ができていませんでした。
AirCourse導入の決め手は、自社独自のeラーニングを簡単に作成できることと、「場所と時間」の制約を解決できることでした。まずインサイダー取引について独自コンテンツを作成し、誰が受講済み・未完了・進捗状況かが一目でわかる学習管理機能により管理側の負担を大幅に軽減しました。標準コースも活用してセクハラ・パワハラ研修や新人研修は作成不要とし、自社独自に必要なもののみ作成する効率的な運用を実現しています。
導入後の主な成果
- 上場に必要なコンプライアンス研修を効率的に全社展開
- 研修管理の手間を大幅削減し人事リソースを最適化
- 中途入社者の即戦力化に向けたオンボーディング体制を強化
- 時間・場所・内容を制約しない柔軟な教育環境を構築
参考: 株式会社MS-Japan様のAirCourse導入事例
まとめ
マイクロラーニングは、現代の働き方に適した効果的な人材育成手法です。短時間集中による学習効率の向上、スキマ時間活用による受講率改善、コンテンツ更新の容易さといった特徴により、従来の研修課題を解決できます。
ただし、複雑な専門知識の習得には限界があるため、集合研修やOJTとの組み合わせが重要です。成功のカギは、明確な育成カリキュラムの設計、ブレンディッドラーニングとしての活用、そして学習者のアウトプット機会の確保にあります。
効果的な導入には、反転学習やゲーミフィケーションなどの手法を組み合わせることで、学習の継続性と定着率をさらに向上させることができるでしょう。社員一人ひとりが自発的に学び続ける組織文化の構築に向けて、マイクロラーニングは強力なツールとなるはずです。
マイクロラーニングを活用し、組織の競争力向上と持続的成長を実現していきましょう。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。