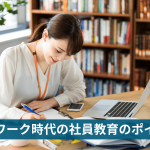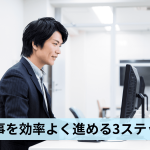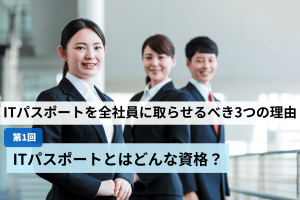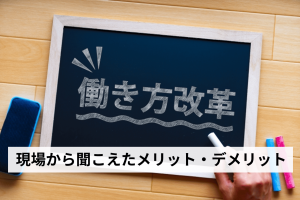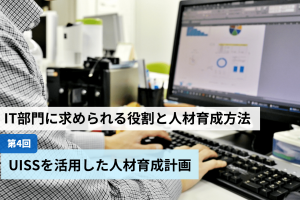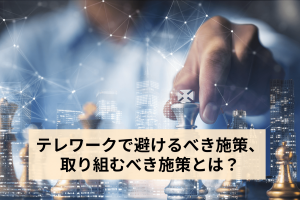ビジネススキルとは、仕事を遂行するうえで必要なスキルのことを指します。 ビジネススキルを高めることは、個人の成長に加え、組織の発展や生産性向上にもつながります。
組織運営していくうえでビジネススキルは、トップマネジメントからロワーマネジメントまで、ほぼ全員が習得すべきスキルといえます。それゆえに、ビジネススキルの研修など、スキル習得に投資をしている企業も多いのが実情です。
ただし、ビジネススキルのなかでも「コンセプチュアルスキル」と「ヒューマンスキル」の習得は簡単ではないため、教育をするにあたって上手くいかずに困っている担当者も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、ビジネススキルの構成要素やその具体例、習得方法を解説していきます。教育時の参考にしてみてください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
ビジネススキルを構成する要素
ビジネススキルは以下3つの要素から構成されています。
- コンセプチュアルスキル
- ヒューマンスキル
- テクニカルスキル
3つの要素は役職や業務内容によって、重要視される度合いが異なります。例えば、コンセプチュアルスキルはトップマネジメント(経営者層)、ヒューマンスキルはミドルマネジメント(管理者層)、テクニカルスキルはロワーマネジメント(監督者層以下)のように、重視するべきスキルが異なります。
それぞれのスキルがどの層に重視されるのかを知ることで、ビジネススキルを教育する際に重視するポイントを適切に判断できるようになるでしょう。
コンセプチュアルスキル
コンセプチュアルスキルとは、ある事象の本質を理解して適切な判断をするための能力です。
組織運営をする中で、市場の変化や日常業務上でのトラブルは頻繁に発生します。このような事象に対し、冷静な分析によって本質を捉え、最適な判断を下せるようにするためのスキルです。
それゆえに、経営者層に特に求められるスキルとして考えられています。また、管理職の中でも経営者層に近い人たちにとっても必要なスキルとなってくるでしょう。
ヒューマンスキル
ヒューマンスキルとは、良好な対人関係を構築および維持するための能力です。業務では、上司・部下との関係性、顧客との商談での信頼関係づくりなど「人」と関わるあらゆる場面で求められます。
ヒューマンスキルはミドルマネジメントに特に求められるスキルですが、トップマネジメントとロワーマネジメントにも必要とされます。人と人の関係を構築するためのヒューマンスキルはあらゆる場面で求められ、人員の入れ替えや新たな顧客と繋がりができた際に役立つでしょう。
テクニカルスキル
テクニカルスキルとは、特定の業種や職種で必要とされる能力のことです。担当業務を問題なく遂行して、顧客や自社から求められる成果を提供するために必要な能力と表すこともできます。
業界により様々ですが、専門性の高い仕事をこなすために重要なスキルです。このスキルは習得までに時間がかかり、仕事の成否を大きく左右します。
そのため中長期的な育成計画の中で、スキル習得のロードマップを労使双方で描くことが重要となります。
ビジネススキルの具体例
ビジネススキルには、コンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルの3つの要素があります。各要素には該当するスキルがいくつかあり、それらを鍛えることが結果的にビジネススキルを高めることに繋がります。
コンセプチュアルスキルの具体例
| 要素 | 概要 |
|---|---|
| ロジカルシンキング(論理的思考) | 物事の結果と原因を明確にとらえ、両者のつながりを考える思考法。様々な事象を結果と原因に分解・整理して、本質を見極めるのに役立つ。 |
| クリエイティブシンキング(水平思考) | 前提を設けず水平方向に発想を広げる思考法。ラテラルシンキングと表される場合もある。固定観念や既存の手法にとらわれず自由に考えることで、新しい発想につなげられる。 |
| クリティカルシンキング(批判的思考) | 物事の本質を見極めるためにあえて疑いをもって考える思考法。本質を見極めて改善やリスク回避につなげることが目的。「本当にこの方法でよいのか」や「もっと効率的・効果的な方法があるのではないか」など、あえて疑いをもつことでより良い結果に導く。 |
| 多面的視野 | ひとつの物事や課題に対して複数のアプローチを行う能力。多面的視野があると、行き詰った状況に対する打開策や、異なる角度からの解決策などを導き出すことができる。 |
| 柔軟性 | 想定外の事態に対して臨機応変に対応すること。事業および業務において想定外やイレギュラーは避けられないため、どのような事態であっても、冷静な状況把握と状況に応じた判断が求められる。 |
| 受容性 | 自分のものとは異なる意見や価値観を受け入れること。社内会議で意見の対立が生じた際でも、相手の意見に耳を傾けることで、より良い結論を導き出すことが可能。 |
| 知的好奇心 | 自らが知らないことに対して関心をもち、知識を得るための姿勢のこと。知的好奇心をもてば知識量を能動的に増やすため、必要に応じて適切な判断や新しい提案を行える確率が高まる。 |
| 探求心 | 物事をより深く理解するために調査や分析を行うための姿勢のこと。物事の成り立ちや背景など、表面的な情報のみでは分からない内容を知ることで、新たな発想や提案につなげられる。 |
| 応用力 | 得た知識や経験を他の事象でも活用する能力。応用力が高ければ、経験していない事態であっても過去の経験から得た知見を活かして対処できる。 |
| 俯瞰力 | 物事の全体像を把握する能力。自分や自社が置かれている状況や周囲の状況、今後の見通しなどを広い視野でとらえられる。今後の方向性を決める際や、イレギュラーに対処する際に必要。 |
コンセプチュアルスキルには、ロジカルシンキングやクリティカルシンキング、多面的視野など物事を客観的に分析し、本質を捉えるためのスキルが多いです。また、知的好奇心や探求心など新しいことに対して抵抗を抱かないようなスキルも多く、事業展開や新規開拓にも役立ちます。
ヒューマンスキルの具体例
| 要素 | 概要 |
|---|---|
| リーダーシップ | 組織や部署を目標に向かってけん引する能力。課せられた目標に対して責任をもち、達成に必要な活動をメンバーの信頼を得ながら推進していく。責任感や信頼性、決断力などが集約された能力といえる。 |
| 動機付け(働きかけ力) | 部下やメンバーの目標達成などに対する意欲を引き出す能力。意欲を引き出すだけでなく、持続や再起させることも求められる。 |
| コミュニケーション力 | 相手と情報を正確にやり取りするための能力。情報のやり取りには対面での会話に限らず、電話やメールも含まれる。ポイントは双方向であること。単に話すのが上手い・話が面白いなどではなく、相手の話をきちんと聞き理解することが求められる。また、やり取りのなかで相手に与える印象や感情も重視される。 |
| プレゼンテーション力 | 相手から合意や賛同を得るために必要な情報を的確に伝える能力。伝える内容を考える「構成力」や分かりやすい資料を作成する「表現力」、聞き手を惹きつけて訴えかける「説得力」が求められる。論理と感情の両面から訴えることが重要。 |
| ヒアリング力 | 相手の話を耳で聞くだけでなく、目で表情やしぐさをみながら、相手の感情や真意に寄り添い共感を示す能力。傾聴力ともいわれる。 |
| 交渉力 | 利害関係が異なる相手と互いが納得できる点を見つけ出して合意を得るための能力。相手の立場や関心ごと、性格などを把握することで高められる。社外に対してはもちろんのこと、社内で意見の対立や利害の相違が生じた際に必要とされる。 |
ヒューマンスキルにはその名の通り、人間関係を構築するスキルが多いです。人をけん引するスキルはもちろんのこと、ヒアリング力や交渉力など、管理職として求められるスキルが揃っています。
テクニカルスキルの具体例
テクニカルスキルは、業務をスムーズに遂行するために必要な知識や技術のことです。スキルの具体例は以下の通りです。
| 職種 | 具体例 |
|---|---|
| 営業職 | 自他社の商品知識、提案力、市場知識 |
| 技術職 | 機械操作技術、工具の扱い方、電気工事士などの資格 |
| 事務職 | パソコン操作技術、簿記などの資格 |
テクニカルスキル全般が専門的なスキルであるため、職種ごとにスキルが異なります。そのため、福祉関係であれば介護福祉士の資格や医療知識、小売り関係であれば接客マナーや流通に関する知識など業界によって、求められるテクニカルスキルがさまざまです。
会社員が身につけるべきビジネススキル
結論として、会社員が身につけるべきスキルは、ここまで紹介したすべてのスキルを身につけるべきといえます。すべてのスキルを高めることができれば、昇進の可能性を高めることにも繋がるでしょう。
ただし、身につける優先度は役職によって異なってくるため、これからビジネススキルの教育を実施しようとしている場合は教える相手の立場に合わせて優先度の高いものを選ぶことが重要です。
例えば、それぞれのスキルの優先度は以下のようになってきます。
こちらはカッツモデルといって、各役職層における求められるスキルの割合を示したモデル図です。
トップマネジメントはコンセプチュアルスキルの割合が多いため優先度が高く、ミドルマネジメントは比較的全般、ロワーマネジメントはテクニカルスキルの優先度が高いことを示しています。
これらを参考に会社員が身につけるべきスキルを判断し、個別に不足している細かなスキルを教育して強化することが重要です。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
ビジネススキルの習得方法
ビジネススキルは基本的に全般を身につけた方がビジネスの場における高い能力が得られます。しかし、スキルを身につけることは簡単ではありません。
そのため、適切な習得方法を知り、できる限り短い時間で身につけられるように努めることが大切です。ビジネススキルの習得方法は主に以下の3つになります。
- OJT
- Off-JT
- 研修・セミナー
それぞれの詳細を解説します。
OJT
「OJT」とは「On-the-Job Training」の略で、職場での実務経験を通じて知識やスキルを習得する育成方法です。業務を実践する現場で、トレーナーとなる社員が一人ひとりに対し教育を行い、スキルを身につけてもらいます。
OJTは4つのステップを通して教育を実施します。
- Show(やってみせる):仕事をやって見せることで、仕事の全体像を理解してもらう
- Tell(説明・解説する):具体的な仕事の内容を説明
- Do(やらせてみる):実際にその仕事をやってもらう
- Check(評価・指導をする):できていなかったことについてのフィードバックやできていたことの感想などを伝える
この習得方法は、特にテクニカルスキルの習得に役立つでしょう。
Off-JT
Off-JTとは、「Off the Job Training(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略で、日常の業務から離れて行う座学の集合研修などのことです。
職場外で実施する研修のことで、OJTのようなトレーニングではなく、別部署の担当者が企画する教育プログラムや、社外の機関が提供している研修などを受講し、必要な知識やスキルを習得する方法です。
Off-JTはOJTを実施する前に取り組むと良いとされています。OJTは実務で学ぶ場ではありますが、何の知識もない状態で挑むと覚えることが多すぎて身に付くスピードが遅くなりやすいデメリットがあります。しかし、Off-JTで実務に関する座学を前もって実施しておけば、実務を覚えるための時間を短縮できる可能性が高くなるでしょう。
研修・セミナー
研修やセミナーを実施している場合には、そこで学んでもらうのも一つの方法です。例えば、機械やツールの操作方法などは社内で教えるよりも、メーカーが実施している研修やセミナーを利用した方が効率よく習得できる場合があります。他にも、専門的なスキルになるほど、研修やセミナーで専門的な知識を学んだ方が、現場で応用がしやすくなります。
新入社員のビジネススキル習得に効果的な「eラーニング」
eラーニング(e-Learning)とは、パソコンやスマートフォン、タブレットなどのデジタル機器、インターネットを利用して教育、学習、研修を行うことです。
リモートワークが普及している昨今の状況にもマッチしています。また、自発的に学ぶ従業員にとって、場所を問わず学べる方法は最適な習得方法とも言えるでしょう。比較的効率よく学べる方法としておすすめです。
最近は、AIやVRの登場によってさらに質の高い学習が見込めるようになってきており、利用方法次第では管理者の負担を最小限に抑えつつ効率的な学習を新入社員に促せるでしょう。
eラーニング成功のコツは”導入設計”にあります
eラーニングの基本的な仕組みは理解できても、実際に成果につながる運用を継続することは簡単ではありません。多くの企業が「導入したが受講率が低い」「コンテンツ作成に時間がかかりすぎる」「効果測定ができない」という課題に直面しています。
これらの課題解決には、単なるシステム選定ではなく、学習文化の醸成から効果測定まで含めた包括的な導入戦略が不可欠です。成功企業では、5つのステップで段階的にeラーニングを組織に定着させ、継続的な学習環境を構築しています。
戦略的な視点からeラーニング活用を推進する、体系的な導入アプローチを学んでみませんか。
スキル習得にeラーニングを活用した事例
ビジネススキルの効果的な習得を実現するために、多くの企業がeラーニングを活用しています。時間や場所に制約されない学習環境により、専門性の高いスキルから汎用的なビジネススキルまで、体系的に学習できる事例をご紹介します。
中途入社者オンボーディングと資格試験対策を効率化|株式会社ニチイケアパレス様

介護付有料老人ホーム「ニチイホーム」を首都圏中心に展開する株式会社ニチイケアパレス様では、3,000名を超える従業員への統一的な研修提供が課題でした。従来の集合研修では全員に同じ内容を伝えることが困難で、ヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルの体系化も不十分でした。また、コロナ禍により集合研修が実施できない状況が約半年続いていました。
同社がAirCourseを選んだ理由は、自社コンテンツのスムーズなアップロード機能と、豊富な既製研修コンテンツでした。毎月1日と16日に入社する30名前後の中途入社者に対するオンボーディング研修として活用し、介護福祉士やケアマネジャーの資格試験対策にもテスト機能を活用しています。受講者の声を聞くためのアンケート機能も積極的に活用し、顔が見えないeラーニングの課題を解決しています。
導入後の主な成果
- 移動時間の大幅削減(片道2時間以上の移動が不要に)
- 365日稼働する現場でのスキマ時間学習を実現
- 資格試験対策の効率化と学習機会の拡大
参考:株式会社ニチイケアパレス様のAirCourse導入・活用事例
集合研修とeラーニングの使い分けで学習効率を向上|第一勧業信用組合様

第一勧業信用組合様では、職員の資産形成に関する専門知識習得とコンサルティング能力向上が重要な課題でした。従来の集合研修では往復の移動時間ロスや欠席による機会損失が発生し、営業担当者の負担軽減が急務となっていました。
同社がAirCourseを導入した決め手は、受講者の学習進捗状況の分かりやすさと、管理者側でのオリジナル教材作成の容易さでした。集合研修は対話重視の内容、AirCourseは知識習得のための研修と使い分けることで、効率的な学習体系を構築しています。金融庁作成のガイドブックをベースにしたオリジナルテストや資産形成ビデオクリップの視聴を組み合わせ、定期的な実施により学習の習慣化を実現しています。
導入後の主な成果
- 集合研修とeラーニングの効果的な使い分けを実現
- 支店別進捗状況の把握と個別フォローアップが可能に
- 金融リテラシー向上のための継続的学習環境を構築
ブレンディッド研修で人材育成を効率化|株式会社エムエム総研様

BtoBマーケティング支援とインサイドセールス人材育成を手がける株式会社エムエム総研様では、独自の講義プログラムによる人材育成の効率化が課題でした。体系化された研修プログラムをさらに効率化し、インサイドセールス・デジタルマーケティングのノウハウを効果的に伝える方法を模索していました。
同社がAirCourseを選んだ決め手は、運用サイドからの「最も使いやすい」という評価でした。インプット部分をeラーニング化し、オンライン×オフラインのブレンディッド研修を実現しています。直感的に操作できるUI/UXと独自コンテンツの作成の簡単さにより、講義プログラムの効率的なeラーニング化を成功させています。受講者は繰り返し復習が可能となり、学習効果の向上を実現しています。
導入後の主な成果
- インプット部分のeラーニング化により研修効率が向上
- 受講者がいつでも繰り返し復習可能な環境を提供
- 運用サイドの負担軽減と直感的な操作性を実現
参考:株式会社エムエム総研様のAirCourse導入・活用事例
まとめ
ビジネススキルは、その名の通りビジネスで活用するスキルのことを指します。コンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルの3つの要素から構成されており、それぞれのスキルを習得することでビジネススキルの向上が図れます。
基本的に、すべてのスキルに精通している方が様々な視点から発想を得やすくなるため、ビジネスの質を高めやすくなります。しかし、全てを学ぶのは時間と労力を要するため、学ぶべきものを適切に選択することが重要です。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。