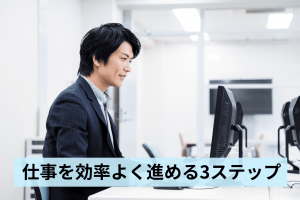多くのビジネスパーソンが論理的思考の重要性を理解していますが、「情報を鵜呑みにして判断を誤る」「思い込みや偏見に気づけない」「本質的な課題を見落とす」といった問題に直面しています。しかし、これらの課題はクリティカルシンキング(批判的思考)を身につけることで解決できます。
クリティカルシンキングとは、認識した情報をあえて批判的に見ることで客観性を高め、物事の本質を見極める思考法です。日常業務や会議で「本当にそうなのか?」「他に方法はないか?」と問い続けることで、より良い判断と新たな視点を得ることができます。
本記事では、クリティカルシンキングの基本概念から3ステップの実践方法、4つの鍛え方、さらに例題と解答例まで詳しく解説します。物事の本質を見極め、より良い判断力を身につけましょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
クリティカルシンキングとは
クリティカルシンキング(批判的思考)とは、物事の本質を見極めるために、多角的な視点を持ち、論理的・客観的に考える思考法です。
物事を無批判に見るようなことはせず、認識した情報をあえて批判的に見ることで客観性を高められます。
「批判的思考」と和訳されますが、批判のために誤りや欠点を探すわけではありません。
本来の目的は、以下のような「考え方」と「問い」を用いて、本質を見極め、改善やリスク回避につなげることにあります。
クリティカルシンキングの「考え方」と「問い」
- 的確に事象を定義する:事実は?
- 客観的に情報を把握する:数値的には?
- 本質的な部分に集中する:そもそも?
- 広い視野で多面的に把握する:他には?
- 主観や感情にとらわれない:本当に?
具体的には「本当にこの方法でよいのか」や「他に効率的・効果的な方法があるのではないか」といったあえて疑いをもつ思考法でより良い結果に導くのです。
目的と論点を常に意識する
「何の目的を達成するのか」と「今の論点は何か」を、常に意識しましょう。
クリティカルシンキングでは、前提条件を含むあらゆる情報を批判的にとらえるため、思考の範囲がひろがります。そのため、考えがまとまらなくなることや、迷うことにも繋がりかねません。
そもそも何のために考えているのか(目的)や、今考えるべきこと(論点)をしっかり意識することでブレや迷いなく答えを見出すことができるでしょう。
思考のクセや偏りをふまえて考える
自他ともに「思考にはクセや偏りがある」ことを前提に考えることが重要です。人間である以上は、少なからず価値観や思い込み、偏見といった思考のクセや偏りを持っています。
クリティカルシンキングを行う上では「自らの好き嫌いを反映していないか」や「主観にとらわれていないか」を自問自答しましょう。
また他者の思考のクセや偏りを把握することも、客観性を保ちながら議論を行うために重要です。
問い続ける
結論に至っても思考を止めず「問い続ける」ことも大切です。結論に対してもあえて疑いをもち、本当に正しいのかを問うことで、より良い結論の糸口が見つかることもあるでしょう。
また、一度確定した結論であっても時間経過や環境変化により、本来の目的や本質からズレてしまうこともあります。
こうしたズレや違和感に気付くためには、クリティカルシンキングによって「問い続ける」ことが重要です。
ロジカルシンキングとの違い
クリティカルシンキングとロジカルシンキングの違いは、認識した情報を「疑うか否か」です。認識した情報は、原因や結果、前提条件などを示します。
ロジカルシンキング(論理的思考法)とは、物事の結果と原因を明確にとらえ、両者のつながりを分解・整理しながら考える思考法です。
認識した情報は一旦「疑わずに」思考を進め、原因と結果のつながりに矛盾が生じた際などに追究します。
一方でクリティカルシンキングは、認識した情報そのものをあえて「疑う」ことで、客観性をさらに高めます。
ロジカルシンキングとクリティカルシンキングをあわせて活用することで、本質を見極めやすくなるでしょう。
クリティカルシンキングの例題と解答例
クリティカルシンキングの例題と解答例を紹介します。クリティカルシンキングの練習や社内研修のために練習問題などが必要な場合は以下を参考にしてください。
以下の例題に対してクリティカルシンキングを用いて、反論や指摘を考えてみましょう。
【例題】
- 新聞を読んでいる人は情報収集し、知識も豊富なのでビジネスでも成功しやすい
- 売上が伸びないのは、昨年と比べて市場が大幅に縮小しているのだから仕方ない
- 若手社員が育たないのは、パワハラを恐れて先輩社員が指導できないせいだ
クリティカルシンキングの練習問題のポイントは「一見すると正論に思えること」です。日常生活や業務中のなかで「一旦は納得したものの後から疑問が思い浮かんだこと」などは良い題材になります。
【解答例】
- 新聞を読んでいても知識が多いとは限らない、知識とビジネスの成功に因果関係はない可能性がある
- 大幅とは具体的にどの程度なのか、同じ市場でも成功している他企業はいるのではないか
- 先輩社員がパワハラを恐れている事実は確認できるのか、少なくとも全員が恐れているわけではないのではないか、他の要因も考えられるのではないか、そもそもなぜ育っていないと言えるのか
解答を考える際のポイントは、「事実は?」「数値的には?」「そもそも?」「他には?」「本当に?」などのクリティカルシンキングの「問い」を当てはめて考えることです。
クリティカルシンキングの「考え方」と「問い」※再掲
- 的確に事象を定義する:事実は?
- 客観的に情報を把握する:数値的には?
- 本質的な部分に集中する:そもそも?
- 広い視野で多面的に把握する:他には?
- 主観や感情にとらわれない:本当に?
クリティカルシンキングのメリット
クリティカルシンキングを身につけることで期待できるメリットを6つ紹介します。
- 具体的事実に基づいた判断を行える
- 矛盾点や漏れに気づける
- リスクを回避できる
- 新たな視点やアイデアを得られる
- コミュニケーションが円滑になる
- 育成にも活用できる
メリットを知ることで、クリティカルシンキングを活用する重要性・価値を正しく把握できるでしょう。
具体的事実に基づいた判断を行える
クリティカルシンキングでは的確に事象を定義するため、具体的な事実に基づいた判断が可能です。例えば「昨年同月比で売上が大幅に下落した」という事象があった場合、「本当に大幅といえるのか?数値は?」のように具体化していきます。
こうして導き出された正確な事実を基に判断できるのは、クリティカルシンキングのメリットといえるでしょう。
矛盾点や漏れに気づける
クリティカルシンキングは認識した情報をあえて批判的にとらえるため、見落としがちな矛盾点や漏れに気づけます。
「本当にそうなのか?」「他にはないか?」といったクリティカルシンキングに基づいた問いが矛盾点や漏れを明らかにします。
リスクを回避できる
クリティカルシンキングは、疑いをもちにくい前提条件や結論なども対象とします。
そのため、誤った前提条件による無意味な議論や、安易な結論付けなどのリスクを回避できるメリットがあります。
新たな視点やアイデアを得られる
クリティカルシンキングにおける前提条件や結論までも批判的にとらえる姿勢は、これまでになかった視点やアイデアをもたらすことがあります。
「そもそも前提は正確なのか?」「もっと良い方法があるのではないか?」といった問いが新たな切り口となるでしょう。
コミュニケーションが円滑になる
互いにクリティカルシンキングに基づくことで、事実をベースとしたスムーズなコミュニケーションが可能となります。
クリティカルシンキングによる批判的視点での議論が前提となるため、意見や問いかけに過敏に気をつかう必要もありません。
また、議論に限らず、説得や交渉などさまざまなコミュニケーションの機会でも役立ちます。
ただし、社外でクリティカルシンキングを行う場合は、威圧的にならないように問いかけの表現や質問の量などには留意しましょう。
育成にも活用できる
クリティカルシンキングは人材の育成にも活用できます。
例えば、部下との個人面談の際に、部下から「今期の目標達成が危ういので、新規訪問件数を今の1.5倍にします」と発言があったとします。
クリティカルシンキングに基づき考えた場合、「本当に新規訪問1.5倍で達成できるのか?」「伸び悩む原因は他にあるのではないか?」など様々な問いを思いつくことができます。
こうした問いを部下へ丁寧に確認していくことで、本人にとってより良い解決策や、実は本人が発したかった本音などに行きつくことができるのです。
クリティカルシンキングのやり方
クリティカルシンキングは以下の3ステップで実践します。
個人で考える場合や、複数人で議論する場合など、さまざまな場面で活用可能です。
- 目的と論点を意識する
- 思考のクセや偏りをふまえて考える
- 事実と意見を分ける
目的と論点を意識する
はじめに、どのような目的と論点を意識すべきなのか把握しておきましょう。
クリティカルシンキングを行なう目的と論点が明確になっていれば、思考を繰り返すうえでブレや迷いが少なくなり、スムーズに進行できます。
思考のクセや偏りをふまえて考える
自他ともに「思考にはクセや偏りがある」ことを前提に思考を繰り返していきます。
人間である以上は、少なからず価値観や思い込み、偏見といった思考のクセや偏りをもっているため、その点を考慮したクリティカルシンキングをしなければいけません。
クリティカルシンキングを行う上では「自らの好き嫌いを反映していないか」や「主観にとらわれていないか」を自問自答しましょう。
また、他者の思考のクセや偏りを把握することも、客観性を保ちながら議論を行うためには重要です。
事実と意見を分ける
クリティカルシンキングにおいて事実と意見の区別は必須です。
なぜなら、ひとつの物事に対しての見え方というのは人によって異なるため、それに合わせて意見も違ってくるからです。
主観に偏った結論を出さないためにも、事実と意見のどちらを述べているのか意識しながら思考を進めていきましょう。
クリティカルシンキングの鍛え方・トレーニング方法
クリティカルシンキングは鍛えることが可能です。
以下では、自らだけでなく、部下ひいては組織全体のクリティカルシンキングを鍛える方法について解説します。
日常業務でもクリティカルシンキングを意識する
クリティカルシンキングを鍛えるためには、日頃から意識してクリティカルシンキングを行うことが重要です。日常業務においてもクリティカルシンキングを用いることができる場面は多いため、意識して行うようにしましょう。
例えば、上司からの指示を受けた際にもクリティカルシンキングを活用できます。
仮にあなたが以下の指示を受けたとします。
「例の営業先への提案書、明日までに素案を作成しておいてね」
あなたは最近の活動状況から、おおよそ上司が意図していることを読み取れたつもりです。そこにクリティカルシンキングを用いることで以下のような発想につなげます。
- 読み取れた「つもり」では自分の「主観」でしかない、詳しく確認しよう
- 「例の営業先」とは自分の思っている〇〇商事で「本当にあっているのか」
- 「明日までに」とは「明日の何時まで」だろうか
- 「素案」とはどのような状態なのだろうか
このように、認識した情報をあえて批判的にみることで客観性を高めることで、確認すべきことが明らかとなり精度の高い仕事へとつながります。
ただし、確認の仕方には注意が必要です。
良くない例として「例の営業先とは〇〇商事のことですか?」「明日とは明日の何時までですが?」「素案とはどんな状態ですか?」のように全てをそのまま質問にしてしまうのは、おすすめできません。
良い例としては「〇〇商事の提案書ですね。明日の15時までに目次までが完成した状態でお持ちすればよろしいでしょうか?」のように、推察した情報を交えて確認します。
具体的に伝えた結果、異なる場合は明確な訂正が入り、より確実な意図を知ることが可能です。
確認の前に「念のため確認させてください」と一言添えると、さらに好印象でしょう。
また、そもそも上司が部下に指示をする時点で「本当にこの指示で部下に伝わるのか?」といったクリティカルシンキングの発想をもつとよりスムーズです。
今回の事例からも分かるように、クリティカルシンキングはお互いの理解と歩み寄りが重要といえます。
会議・打合せで積極的に用いる
会議や打合せでも積極的に用いることで、クリティカルシンキングを鍛えることができます。
クリティカルシンキングは、とくに課題の洗い出しや解決策の検討とは相性がよい思考法です。
前項の「クリティカルシンキングの実践方法」で紹介した3ステップを、ぜひ参考にしてください。
また、会議や打合せの開始前にクリティカルシンキングを活用して議論することをルールにしておくと良いでしょう。
参加者の意欲向上や質疑の活性化につながり、スムーズかつ客観性が高い本質的な議論を実現できるためです。
研修に参加する
クリティカルシンキングは、基本姿勢・考え方・実践方法・関連する思考法など、学ぶべき内容が多岐にわたるため、研修形式でじっくり学ぶことも有効です。
具体的な研修形式には以下のようなパターンがあります。社内全体のクリティカルシンキングを鍛える手段として参考にしてください。
- 集合型研修(社内講師もしくは社外講師)
- web研修(社内講師もしくは社外講師)
- 社外で開催の集合型研修へ派遣
集合型研修であれば、グループワークによる演習を行いやすいというメリットです。ただし、スケジュール調整や一か所への集合が必要など、負担が大きい点はデメリットです。
web研修であれば、時間とネット環境を確保できればどこからでも参加できるのがメリットですが、グループワークを行いにくい点はデメリットでしょう。
社外の集合型研修への派遣は、社内での準備や運営の手間が少ないのがメリットですが、そもそも開催しているタイミングをはかる必要があります。
eラーニングを活用する
クリティカルシンキングは学ぶべき内容が多岐にわたります。
そのため、時間を有効活用して効率よく学べるeラーニングはクリティカルシンキングを鍛えるのに最適です
eラーニングはネット環境さえあればいつでもどこでも受講できるため、受講側は空き時間などを活用できます。開催側も受講案内のみで、研修のために参加者全員のスケジュール調整を行う必要もありません。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
eラーニングを通じてスキルアップを実現した事例
クリティカルシンキングをはじめとする思考力向上や課題解決能力の強化において、eラーニングを効果的に活用した企業の事例を紹介します。
医療現場での批判的思考による安全性向上|医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様

急性期医療を担う福岡徳洲会病院様では、医療従事者の判断力向上と医療安全の強化が課題でした。医療現場では一つの判断ミスが重大な結果に繋がるため、事実に基づいた客観的な判断力と批判的思考による安全確認が不可欠でした。しかし、24時間体制の医療現場において、全職員が均等に思考力向上研修を受講することが困難でした。
AirCourse導入により、「医療安全」「感染対策」「リスクマネジメント」研修を通じて、医療従事者の批判的思考力向上を図りました。「本当にこの手順で安全か?」「他にリスクはないか?」といったクリティカルシンキングの考え方を日常業務に浸透させ、eラーニングでの理論学習と現場での実践を組み合わせることで、医療の質と安全性向上を実現しています。
導入後の主な成果
- 医療従事者の批判的思考力向上により医療安全が強化
- 事実に基づいた客観的な判断により医療ミスが減少
- 継続的な学習により医療の質が向上
参考:医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様のAirCourse導入事例
金融専門知識の批判的分析能力を強化|第一勧業信用組合様

第一勧業信用組合様では、お客さま本位の業務運営を進めるため、職員の金融商品知識と批判的分析能力の向上が課題でした。金融商品の提案には、商品のメリットだけでなくリスクや課題も含めた客観的な分析と、お客さまの状況に応じた批判的検討が必要でした。従来の集合研修では、深い思考を促す継続的な学習が困難でした。
AirCourse導入により、「資産形成」「金融商品知識」「コンサルティング」研修を実施し、職員の批判的思考力向上を図りました。「本当にこの商品がお客さまに最適か?」「他の選択肢はないか?」といったクリティカルシンキングの視点を育成。eラーニングによる反復学習と実務での活用により、お客さま本位の提案力向上を実現しています。
導入後の主な成果
- 金融商品の批判的分析能力が向上しお客さま満足度が向上
- 客観的な判断力向上により適切な商品提案を実現
- 継続的な学習により専門性と思考力を同時に強化
M&A・経営コンサルでの多角的思考力強化|エフエムジー & ミッション株式会社様

M&A仲介・経営コンサルティング事業を展開するエフエムジー & ミッション株式会社様では、高度なコンサルティング業務において、多角的視点からの批判的分析と本質的な課題発見能力の向上が求められていました。クライアントの状況を客観的に分析し、表面的な課題だけでなく根本的な問題を見極める思考力が事業成功の鍵でした。
AirCourse導入により、「ロジカルシンキング」「問題解決」「コンサルティング」研修を通じて、コンサルタントの批判的思考力向上を図りました。「本当にこれが根本的な課題か?」「他の観点から見るとどうか?」といったクリティカルシンキングの視点を強化し、eラーニングでの体系的学習と実際のコンサルティング業務での実践により、提案力と課題解決力を大幅に向上させています。
導入後の主な成果
- コンサルタントの多角的思考力向上により提案品質が向上
- 批判的分析により本質的な課題発見能力が強化
- 客観的な判断力向上によりクライアント満足度が向上
参考:エフエムジー & ミッション株式会社様のAirCourse導入事例
クリティカルシンキングの精度を高める思考法6選
クリティカルシンキングを実践するにあたり、あわせて用いることで高い成果を期待できる思考法を6つ紹介します。
クリティカルシンキングを主軸としながら、必要に応じて適した思考法を組み合わせて活用しましょう。
仮説思考
仮説思考とは、こうではないかと先の見通しを立て、結果や答えを予測する思考法です。
具体的には以下の5ステップで実践します。
- 検討材料を集める
- 結果・答えを予測し、仮説を立てる
- 仮説を再度検討し、精度を上げる
- 仮説を実行・検証する
- 仮説と事実のギャップを反映させる
仮説と検証を反復して行うことがポイントです。クリティカルシンキングで疑問をもった点を検証する際や、結論の精度を高める際などに活用しましょう。
論点思考(イシュ―思考)
論点思考とは、本当に考えるべきこと(論点・課題・目的)を絞り込むための思考法です。次々に生じる課題を一つずつ全て解決していくのではなく「本当に考えるべきこと」を絞り込んでから行動した方が結果として早く達成できるという発想に基づいています。
クリティカルシンキングを実践する際に行う「ゴールの明確化」に役立つでしょう。
アナロジー思考
アナロジー思考とは、経験や出来事を抽象化して本質を見出し、他の状況へ応用する思考法です。例えば、子育てで学んだことを部下の育成にも応用する、歴史上の人物の成功哲学を自社の経営に応用するなどです。クリティカルシンキングの「他には?」という発想をさらにひろげることにも応用できるでしょう。
コンセプチュアル思考
コンセプチュアル思考とは、あらゆる事象の本質を理解するための思考法です。
具体的には、抽象化あるいは具体化して考えたり、言葉を再定義したり、原理や法則を見出したりすることで「本質」の理解を目指します。
クリティカルシンキングとあわせて用いることで、共通の目的である物事の「本質」を見出しやすくなるでしょう。
コンセプチュアル思考については、こちらの記事でも「コンセプチュアルスキル」として解説しているので、参考にしてください。
PAC思考
PAC思考とは、前提・仮説・結論を批判的に分析し、各要素の精度を高める思考法です。PACは、Premise(前提)・Assumption(仮定)・Conclusion(結論)の3要素を示しています。
例えば「商品Aは昨年3万個販売できたから、今年も継続的な需要があり、3万個以上は販売できるはずだ」という主張があったとします。
この主張にPAC思考を用いると以下のようになります。
- P(前提):商品Aは昨年3万個販売できた →「実数値での確認が必要だ」
- A(仮説):今年も継続的な需要がある →「明確な根拠はない」
- C(結論):3万個以上は販売できるはずだ →「仮説同様に根拠がない」
一つの主張を前提・仮説・結論に分けて批判的な分析を行うことで、バイアス(偏見や思い込み)に気づくことができ、各要素の精度を高めることができるのです。
メタ思考
メタ思考とは物事や状況を俯瞰して、視座を高くもつための思考法です。メタとは「より上位の」という意味です。
視座を高めるには以下の5つの視点を意識しましょう。
- 本来の目的を前提にする
- 全体の視点立場に立つ
- 時間の展開をひろげる(過去と未来も考える)
- 抽象的に言語化する
- 構造を把握する
業務においては、経営者レベルで組織の状況を俯瞰することがメタ思考を実践できている状態といえるでしょう。
まとめ
クリティカルシンキングとは、物事の本質を見極めるために、認識した情報をあえて批判的に見ることで客観性を高める思考法です。
クリティカルシンキングを用いることで、事実に基づいた判断ができるだけでなく、新たな視点やアイデアの発見にも繋げられるでしょう。
実際に取り組む際は、「目的と論点を常に意識する」「思考のクセや偏りをふまえて考える」「問い続ける」の3つの姿勢を意識することで、実践において成果を出すことができます。
またクリティカルシンキングを鍛えるためには、日常業務や会議の場などで積極的に用いることが大切です。
他にも、組織内での研修実施や、eラーニングを活用すれば、さらに効率よく修得できるでしょう。
クリティカルシンキングは個人の思考能力を高めるひとつの思考方法であり、この考え方が全てではありません。
クリティカルシンキングだけでなく、様々な思考法やスキルなどの学びや実践を経て、人材一人ひとりが成長することが企業にとっては重要です。
弊社が提案する『デジタル時代の人材育成モデル』は、従業員の成長をさらに促すのに最適なノウハウが詰まっています。
クリティカルシンキング以外にも、従業員を成長させるために必要な情報を必要としている方は、ぜひ参考にしてください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。