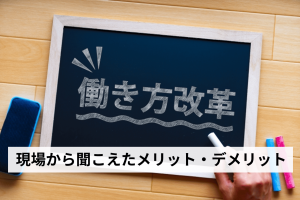「社員のスキルアップが進まない」「研修の効果が薄い」「OJTの負担が大きい」そんな人材育成の課題に頭を悩ませている企業は多いのではないでしょうか。
変化の激しい現代において、従業員の継続的な成長は組織の存続・発展に不可欠です。しかし、従来型の集合研修だけでは限界があり、より効果的で実務に直結した学びの手法が求められています。
そこで注目されているのが、ワークプレイスラーニングです。本記事では、ワークプレイスラーニングとは何か、なぜ今注目されるのか、導入することで得られるメリット、具体的な手法、そして導入・推進のためのステップとポイントをわかりやすく解説します。
成功企業に学ぶ”人材育成のノウハウ”を無料でお届け
現場の人材育成がなかなか成果に結びつかない…。教育担当者の多くが直面するこの壁を、実際に乗り越えた企業の事例から解き明かします。
従来の研修やOJTで成果が出ない真の理由と、デジタル時代ならではの効果的な育成モデルを厳選事例とともに公開。「時間がない」「効果が見えない」という課題に、他社が語らない人材育成の現実解が具体的な打開策を提示します。
これまでの育成施策に行き詰まりを感じている方こそ、『デジタル時代の人材育成モデル』をぜひご活用ください。
目次
ワークプレイスラーニングとは
ワークプレイスラーニング(Workplace Learning)とは、職場を学びの場として捉える概念です。職場でのあらゆる経験や他者との関わり、情報へのアクセスを意図的に学習機会と捉え、それらを統合的にデザイン・促進することで、個人そして組織全体のパフォーマンスを高めていく考え方であり、そのための環境構築に主眼を置いたアプローチと言えます。
ワークプレイスラーニングの定義
ワークプレイスラーニングは、Rothwell & Sredl(2000)によって「個人や組織のパフォーマンスを改善する目的で実施される学習その他の介入の統合的な方法」と定義されています。
これは、ワークプレイスラーニングが単に「職場で勉強する」という狭い意味ではなく、「仕事の経験からの学び」「上司や同僚との関わりからの学び」「Webや書籍などの情報からの学び」など、職場内で作り出される多様な学びを従業員成長の機会につながるものとして捉える、ということを意味しています。
従業員の「学び」は多様であり、大きく以下の4つに分類できます。
- 経験学習:日々の業務経験を通じて、自ら学び、実践に活かしていく学び
- 上司・先輩・同僚からの学び:OJT、1on1、対話、相談など、他者との関わりから得られる学び
- 情報からの学び:Webサイト、書籍、資料、社内ナレッジシステムなどから得られる学び
- 研修での学び:Off-JT、eラーニング、集合研修など、計画的に提供されるフォーマルな学び
このうち、ワークプレイスラーニングは主に、1の経験学習、2の上司・先輩・同僚からの学び、3の情報からの学びといった、職場での日常的な活動を通じて得られる学びを指します。
このように、職場での学びは多くの比重を占めています。従業員の学習効果を最大化し、パフォーマンスにつなげるためには、職場における多様な学びの機会を意図的に捉え、環境を整備することが重要であるとわかります。
ワークプレイスラーニングとOJTとの違い
ワークプレイスラーニングと混同されやすいものにOJT(On the Job Training)がありますが、両者には以下のような違いがあります。
- OJT:主に、先輩社員や上司が部下に対し、実際の業務を通して必要な知識やスキルを指導する、比較的フォーマルな人材育成手法。指導者から被指導者への一方向的・受動的な学びの側面が強い傾向がある
- ワークプレイスラーニング:従業員自身の経験からの学び、同僚との対話や協働、ナレッジ共有システムからの情報収集、必要に応じたeラーニングの活用など、OJTを含む職場でのあらゆる学びの機会を対象とし、それらの機会を効率よく提供する環境構築に主眼を置く。これにより、学習者のより能動的かつ自律的な学習に寄与する
つまり、ワークプレイスラーニングは、OJTを含む職場での多様な学びを統合し、個人と組織の成長につなげようとする、より広範なアプローチと言えます。
ワークプレイスラーニングの学習段階
企業におけるワークプレイスラーニングのアプローチは、組織の成熟度や意識、導入している仕組みによって、いくつかの段階に分けて考えることができます。現状がどの段階にあるのか、そして今後どの段階を目指すべきかの参考になります。
段階1:個人主体の模倣
この段階は、組織としてワークプレイスラーニングを意図的に設計・支援する仕組みがほとんど整っていない状態です。従業員の学びは、個々人が職務を遂行する中で自然発生的に行われる、個人に依存した模倣中心の学習が中心となります。
具体的には、上司や先輩のやり方を見て真似る、困った時に身近な同僚に質問するといった、いわゆる「OJT」に近い形の学びが多くを占めます。しかし、これは組織として計画されたものではなく、指導者の経験や知識、コミュニケーション能力に質が大きく左右される属人的な学びになりがちです。公式なサポート体制や、学びを促進する環境整備は十分ではありません。
この段階では、個人の経験や努力に委ねられる部分が大きく、組織全体の学習効率や質は安定しにくい傾向があります。
段階2:組織主体の一律学習
この段階では、企業として従業員の学習に対して意識を持ち始め、組織主導で計画的な学習機会を提供するようになります。
例えば、新入社員向けにOJT指導員を配置したり、全社員共通のビジネスマナー研修やコンプライアンス研修を実施したりします。デジタルツールを活用したeラーニングで、基本的な知識やスキルを一定レベルで習得させる取り組みもこの段階に含まれます。
しかし、これらの仕組みは全社で一律に導入されることが多い一方で、実際の運用は各部署や現場に任されることが多く、継続的なフォロー体制が不十分であったり、職場の実態に合わせたカスタマイズが難しかったりします。結果として、現場ごとの運用にばらつきが生じ、必ずしも効果的な職場学習につながっていないケースも見られます。
段階3:最適化された職場学習
この段階は、ワークプレイスラーニングが組織文化として根付き、職場ごとの特性や個人のニーズに合わせて最適化された学習環境が構築されている状態です。
この段階では、従業員自身が自律的に学び、経験を次に活かす「経験学習を回すマインド」を持ち、それを実践できるような支援が行われます。また、上司は部下の学習状況を把握し、適切なフィードバックやコーチングを通じて学習を積極的にサポートする役割を果たします。
この段階では、職場が単なる業務遂行の場ではなく「常に学び、成長し続ける場」として機能しています。
なぜ今、ワークプレイスラーニングが注目されるのか
ビジネスを取り巻く環境が目まぐるしく変化する現代において、ワークプレイスラーニングが注目されるのにはいくつかの理由があります。
継続的な学びの重要度が高まっている
デジタル技術の進化やグローバル化により、ビジネスの常識や必要なスキルは常にアップデートされ続けます。一度学べば通用するという時代ではなくなり、従業員一人ひとりが変化に適応するために継続的に学び続けることが不可欠です。
そこで、職場におけるさまざまな機会を学びと捉え、その効果を高める環境を構築する考え方であるワークプレイスラーニングが注目されています。
従業員の自律的な成長意欲が向上している
近年、従業員は企業が用意した研修を受けるだけでなく、自身のキャリアアップや市場価値向上のために、自らの意思で学びたいという意欲を持つ傾向が強くなっています。
企業には自律的な学びを支援する環境が求められており、それはまさにワークプレイスラーニングの方向性と一致するため、重要視している企業が増えていると言えます。
従来の教育だけでは不十分な場合が多い
従来の集合研修は、会場費や講師謝礼、参加者の拘束時間など、コストや時間的負担が大きい上に、学んだ内容が実務で活かされない、効果測定が難しいといった課題が指摘されています。OJTも指導者の質にばらつきが出やすく、属人化しやすいという問題があります。
ワークプレイスラーニングは、OJTや集合研修を含め、職場における多様な学びをどう組み合わせれば学習者の学びが最大化されるかに重きを置きます。従来の教育にあったデメリットを補完するような考え方である点も、今企業に注目されている理由のひとつでしょう。
ワークプレイスラーニングが企業にもたらすメリット
ワークプレイスラーニングの導入は、従業員と組織の双方に多くのメリットをもたらし、人材育成の課題解決に役立ちます。ここでは、個人と組織の両側面から、課題解決のためのメリットについて考えてみましょう。
個人へのメリット
ワークプレイスラーニングが個人にもたらすメリットは、以下の項目が考えられます。
- 実務と直結した効率的なスキルアップ
- 自律的な学習習慣の定着
- 労働へのモチベーション・企業へのエンゲージメントの向上
- キャリア開発への貢献
ワークプレイスラーニングによって、従業員は実務と直結した効率的なスキルアップができるようになります。日々の業務で直面する具体的な状況や課題の中で学ぶため、知識やスキルが現場で活かせる形で身につきやすく、学びの定着率が高いのが特徴です。
また、ワークプレイスラーニングは従業員の自律的な学習習慣の定着を後押しします。与えられる教育だけでなく、自身で課題を発見し、解決のために必要な情報を調べたり他者と協力したりする過程で、「学びたい」という動機が育まれ、主体的に学習を進める姿勢が身につくでしょう。自身の成長を実感できる機会が増え、自律的に学びを進められるようになることは、従業員の労働へのモチベーションや企業へのエンゲージメントの向上に大きく影響します。
さらに、ワークプレイスラーニングで培われる実践的なスキルや自律性は、個人のキャリア開発においても重要な役割を果たします。自身の市場価値を高めるだけでなく、新しい業務への挑戦、異動、昇進といったキャリアの選択肢を広げるための確かな土台となるでしょう。
組織へのメリット
ワークプレイスラーニングの導入によって得られる組織へのメリットは、以下の項目が挙げられるでしょう。
- 組織全体のパフォーマンス・生産性向上
- 変化対応力の強化
- 従業員同士の信頼関係の深まりとコミュニケーションの活性化
- 採用力・定着率の向上
ワークプレイスラーニングを組織全体で推進することで、従業員一人ひとりのスキルが向上し、業務効率が高まります。これは、組織全体のパフォーマンス・生産性向上へとつながります。
また、常に新しい情報やスキルを現場で取り入れ、学び続ける文化が根付くことで、外部環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる力の強化にもなります。個人の持つ知識やノウハウが組織全体に共有され、問題解決のスピードが向上し、チームや部署を超えた連携が生まれる可能性があります。これにより、従業員同士のコミュニケーションが活性化し、協力的な職場環境が醸成されるため、信頼関係の深まりだけでなく、組織全体としての競争力の向上にも貢献します。さらに、従業員の成長を積極的に支援する企業の姿勢は、社外からの評価を高め、優秀な人材を惹きつける採用力向上にもつながります。
“成果を出す”人材育成とは?解説資料を無料公開
OJTや集合研修を実施しているものの、「思うような効果が感じられない」「継続的な成長につながらない」といった課題を抱えていませんか。
その背景には、デジタル時代の働き方に適さない従来型の育成モデルがあります。では、実際に成果を上げている企業は、どのような人材育成モデルを構築しているのでしょうか?
『デジタル時代の人材育成モデル』では、現代の課題を解決する新しい育成アプローチと、それらを実現するための具体的な手法を、成功企業の実例をもとに詳しく解説しています。育成を見直したい方は、ぜひご覧ください。
ワークプレイスラーニングの具体的な手法
ワークプレイスラーニングは、単一の手法ではなく、職場での多様な学びの機会を組み合わせることで効果を発揮します。ここでは、主な手法を3つの切り口からご紹介します。
経験学習モデルを活用した指導
経験学習モデルは、「経験」「省察(内省)」「概念化」「実践」という4つのステップからなる学習サイクルです。ワークプレイスラーニングでは、日々の業務で得られる経験を意図的にこのサイクルに乗せることで、より深い学びと実践的なスキル習得を促します。
具体的な手法と活動例は以下の通りです。
| 手法 | 活動例 |
|---|---|
| 意図的な業務アサインで「経験」を積む | 従業員の成長段階や目標に合わせて、少し難易度の高い業務や新しい分野のプロジェクトにアサインし、意図的に新しい経験を積ませる |
| 定期的な振り返りの実施で「省察」を深める | 業務の区切りやプロジェクト終了後などに、個人の振り返りやチームでのミーティングを通じて、成功点や課題、そこから学んだことを言語化し、内省を深める機会を設ける |
| 学びの概念化を促す活動で「概念化」を支援する | 経験を通じて得られた教訓やノウハウを文書化したり、共有会で発表したりすることで、学びを概念化し、組織に還元する |
| 学びを積極的に活かす「実践」の機会設定 | 概念化された学びを、次の類似した業務や、新しいチャレンジの場面で実際に試してみる機会を設ける |
このように、業務におけるさまざまな経験を、「省察」や「概念化」といったステップを経て次の「実践」へとつなげていく仕組みや活動を取り入れることで、従業員は自身の経験からより多くの学びを得て、着実に成長していくことが可能になります。
メンター制度などを取り入れたOJTの実施
ワークプレイスラーニングにおいてもOJTは重要な位置を占めますが、指導者によって質にばらつきが生じやすいという課題も抱えています。そこで有効なのが、メンター制度をOJTに組み込むアプローチです。
メンター制度を取り入れたOJTでは、直属の上司や指導担当者(OJTトレーナー)による業務知識・スキルの指導に加え、年齢や社歴が近い斜めの関係の先輩社員などが「メンター」として、業務の悩み、キャリア、人間関係など幅広い相談に乗り、精神的なサポートやキャリア形成に関するアドバイスを行います。
これは、学びを包括的に捉えるワークプレイスラーニングならではの手法と言えます。
eラーニングを活用した継続的な学びの促進
現代においては、変化のスピードに対応し続けるために、一度学んだら終わりではなく、常に新しい知識やスキルを学び続けることが求められます。eラーニングをはじめとするデジタルツールは、この「継続的な学び」を促進するための強力な手段となります。
eラーニングの最大の利点は、時間や場所を選ばずに自分のペースで学習できることです。これにより、忙しい業務の合間やリモートワーク環境下でも、継続的に学習に取り組むことが可能になります。
eラーニング単体だけでなく、以下のような具体的な手法・活動を通じて、デジタルツールを活用した継続的な学びを促進します。
| 手法 | 活用例 |
|---|---|
| 多様なeラーニングコンテンツの整備と提供 | ・業務に必要な専門知識、最新技術、ビジネスマナー、コンプライアンスなど、幅広いテーマのeラーニングコンテンツを用意し、従業員がいつでもアクセスできるようにする ・短時間で手軽に学べるマイクロラーニング形式のコンテンツは、日常業務の中での継続的な学習に適している |
| 社内ナレッジ共有プラットフォームの運用 | ・従業員が持つ個々の知識やノウハウ、成功事例、FAQなどを一元的に管理 ・共有できるプラットフォーム(社内Wiki、FAQシステムなど)を運用する ・従業員は疑問が生じた際や、新しい業務に取り組む際に必要な情報に素早くアクセスでき、自己解決や学びを深めることができる |
| 学習履歴の可視化とフィードバック | ・LXP(Learning Experience Platform)などのツールを活用し、個人の学習履歴や進捗状況を可視化する ・従業員自身が自身の学びの状況を把握しやすくなるだけでなく、上司が部下の学習状況を把握し、適切なフィードバックやサポートを行うことが可能になり、継続的な学習意欲を維持することにつながる |
| オンラインコミュニティやフォーラムの活用 | ・従業員同士がオンライン上で知識や情報を交換したり、疑問点を質問したりできるコミュニティやフォーラムを設ける ・eラーニングで得た知識を深めたり、実務での応用について議論したりする場を提供し、情報からの学びと他者からの学びを組み合わせた継続的な学習を促進する |
eラーニングをはじめとするデジタルツールを効果的に活用することで、企業は従業員に対して、時間や場所の制約なく、個人のペースに合わせた継続的な学習機会を提供し、「学び続ける組織」を実現することができるでしょう。
ワークプレイスラーニング導入ステップとポイント
ワークプレイスラーニングを組織に定着させ、効果を最大化するためには、計画的かつ継続的なアプローチが必要です。以下に、導入のステップとそれぞれのポイントを解説します。
ステップ1.「学び」の基盤づくり環境を整備する
ワークプレイスラーニングを根付かせるためには、まず従業員が自然と学びたくなる「学びやすい環境を整える」ことが重要です。これは、単に学習ツールを導入することだけを指すのではなく、組織文化や物理的な環境も含みます。
学びたい情報にアクセスしやすい環境
業務に必要なマニュアル、過去の成功事例、社内研修コンテンツ、外部学習リソースなど、学習に必要な情報が整理され、従業員がいつでも簡単に見つけられるような情報共有基盤を整備します。
他者と交流・対話しやすい環境
部署内やチーム内だけでなく、部署や役職を超えて従業員同士が気軽にコミュニケーションを取り、教え合ったり相談したりできる雰囲気を作ります。オープンスペースの設置や社内交流イベントの推奨なども有効です。
失敗を恐れずに挑戦できる心理的安全性の確保
新しい業務にチャレンジする際や、不明点を質問する際に「失敗したらどうしよう」「こんなことを聞いたら恥ずかしい」といった不安を感じさせない、心理的に安全な職場環境を作りましょう。リーダーが率先して自身の失敗談を共有したり、部下の挑戦を応援したりする姿勢が重要です。
ツールやテクノロジーの活用(LXPなど)
学習コンテンツの提供、進捗管理、レコメンデーション機能などを備えたLXP(Learning Experience Platform)などのツールを導入し、個人の学習状況を可視化し、主体的な学びをサポートします。
推進におけるリーダーシップの役割
経営層や管理職が率先して学びを奨励し、環境整備にコミットすることは、ワークプレイスラーニングを効果的に推進する上で極めて重要です。リーダー自らが学びの姿勢を示すことで、従業員に「学びが価値ある行動である」と認識させ、学習文化の定着を促します。
ステップ2.業務と連動した学習機会の計画を立てる
環境整備と並行して、どのような学習機会をどのように提供するか、具体的な計画を立てます。ワークプレイスラーニングは業務と密接に関わるため、計画段階から現場の状況やニーズを深く理解することが重要です。
組織の課題・目標と連携した学習ニーズの特定
経営戦略や事業計画、現場の業務プロセスにおける課題、将来必要となるスキルなどを分析し、組織全体のゴール達成につながる学習ニーズを具体的に特定します。
どのような手法を取り入れるかの検討・選択
特定された学習ニーズに基づき、具体的な手法の中から自社に最適なものを検討し、組み合わせを計画します。
ステップ3.「学び」の実践とサポート計画を実行する
計画した施策を実際に職場で実行し、従業員の学びをサポートする段階です。
スモールスタートでの導入と改善
最初から全社的に大規模な導入を行うのではなく、特定の部署やテーマで小さくスタートし、効果測定を行いながら改善を加えていく「スモールスタート」が推奨されます。これにより、リスクを抑えつつ、実践的なノウハウを蓄積できます。
効果測定とフィードバック
設定した評価指標に基づき、ワークプレイスラーニングの取り組みが実際にどの程度効果を上げているのかを測定します。単に学習時間や参加率だけでなく、従業員の行動変容や具体的な業務成果に注目し、定期的にフィードバックを収集・分析することで、施策の有効性を評価し、改善点を見つけ出します。
ステップ4.効果測定とワークプレイスラーニングの継続的な改善
ワークプレイスラーニングは継続的に効果を測定し、改善を繰り返すことで、組織の成長に合わせて進化させていくことが重要です。
業務成果や行動変容に基づく効果測定とフィードバック収集
実行段階での効果測定に加え、中長期的な視点でワークプレイスラーニングが組織の業績や従業員のキャリアにどのように貢献しているかを評価します。従業員への定期的なアンケートやヒアリングを通じて、取り組みに対する現場の声を継続的に収集し、改善のヒントを得ます。
現場の声を反映した施策の見直しと改善
効果測定の結果や現場からのフィードバックを深く分析し、計画通りに進まなかった点、予期せぬ課題、あるいは新しいニーズなどを特定します。これに基づき、学習内容、提供手法、サポート体制などを柔軟に見直し、より効果的なワークプレイスラーニングの仕組みへと改善を加えていきます。
成功事例の共有と組織全体の学習文化の定着
ワークプレイスラーニングの取り組みを通じて生まれた、個人の成長やチームの成果につながった具体的な成功事例を社内で積極的に共有します。これにより、他の従業員の「自分も学びたい」「自分も貢献したい」という意欲を高め、「学ぶことが当たり前」「互いに教え合うことが自然」といった学習文化を組織全体に根付かせます。
ワークプレイスラーニングの実践事例
ワークプレイスラーニングは、その概念の広さから、企業によってさまざまな形で実践されています。ここでは、ワークプレイスラーニングに通じる企業の取り組み事例をいくつかご紹介します。これらの事例を自社でワークプレイスラーニングを導入・推進する際の参考にしてみてください。
トッパン・フォームズ株式会社
トッパン・フォームズ株式会社は、従業員が自らのキャリアを主体的に考え、必要な学びを選択できる自己申告制度や、さまざまな背景を持つ従業員が安心して共に学び成長できる職場環境の整備を行っています。これらの取り組みは、特定の学習プログラム以上に、従業員の自律性を育み、学びやすい組織文化を醸成している点で、職場で継続的な学びを促進するワークプレイスラーニングの実践例と言えます。
厚生労働省人材育成事例007
株式会社アイエスエフネット
株式会社アイエスエフネットは、「人は財産」という考えのもと、従業員に明確なキャリアパスを示し、従業員が必要な知識・スキルを能動的に学べる仕組みを整備しています。これは、従業員一人ひとりが自身のキャリアと向き合い、多様な働き方の中でも主体的に学び続け、成長していくワークプレイスラーニングの実践と言えます。
厚生労働省人材育成事例026
株式会社セリオ
働く女性の支援事業を展開する株式会社セリオでは、業務の性質上、従業員がまとまった研修時間を確保しにくいという課題がありました。
この課題解決のため、時間や場所を選ばずに学べるeラーニングシステム「AirCourse」を導入。従業員は業務の合間などの「スキマ時間」を利用して、社会人基礎やコンプライアンスといった職場で必要な知識を継続的に学べるようになりました。
セリオの事例は、事業特性による時間的な制約がある中でも、eラーニングを活用することで従業員が必要な学びを継続できる環境を整備し、職場でのパフォーマンス向上やコンプライアンス意識向上を図っているワークプレイスラーニングの実践例です。これは、限られた時間の中で「eラーニングなどを活用した継続的な学びの促進」を実現する有効なアプローチと言えます。
カナツ技建工業株式会社
社会インフラ整備を手掛けるカナツ技建工業株式会社は、未来を見据えた人材育成のため「カナツアカデミー」を発足させ、eラーニングシステム「AirCourse」を活用したワークプレイスラーニングを実践しています。
この取り組みの核となるのは、各部門の現場従業員が講師となり、自身の経験に基づく実践的なオリジナル研修コンテンツを自社で作成し、eラーニングで組織全体に提供している点です。
これは、現場で培われた生きた知識を組織内で共有可能な形(情報からの学び)にすることで、組織全体の知識レベル向上や技術継承を促進する、ワークプレイスラーニングにおける重要な実践例です。従業員は時間や場所を選ばずに自社の業務に必要な知識を学ぶことができ、継続的なスキルアップにつながっています。
まとめ
ワークプレイスラーニングを導入することで、従業員は実務に直結したスキルを効率的に習得し、自律的に成長できるようになります。組織にとっては、従業員のスキルアップによる業績向上、変化対応力の強化、知識共有の促進、そして強い組織文化の構築といった多くのメリットが期待できます。
もし既存の人材育成に課題を感じていたり、より費用対効果の高い育成手法を求めていたりするのであれば、ワークプレイスラーニングは有効な解決策となる可能性があります。
ご紹介した導入ステップやポイント、具体的な手法や事例を参考に、ワークプレイスラーニングの導入を検討してみてください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。