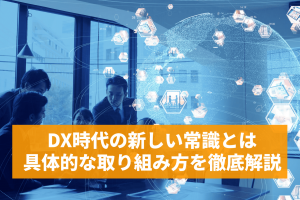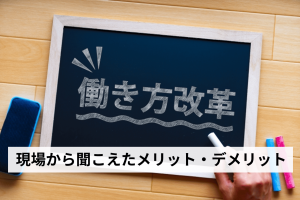人材育成を進めるうえで、「研修の効果が見えにくい」「環境の変化のスピードに人材育成が追いつかない」という課題に直面していませんか。従来の教育研修やOJTだけでは、組織のパフォーマンス向上につながりにくいと感じているかもしれません。
そこで注目されているのが、HPI(ヒューマンパフォーマンスインプルーブメント)という考え方です。HPIは、単に研修を行うのではなく、パフォーマンスの「なぜ」を深く分析し、ビジネス成果に直結する多様なアプローチで課題を解決する体系的なプロセスです。
本記事では、HPIの基本的な定義から、組織のパフォーマンス課題を解決するための具体的なプロセス、そして導入を成功させるためのポイントまで、わかりやすく解説します。
成功企業に学ぶ”人材育成のノウハウ”を無料でお届け
現場の人材育成がなかなか成果に結びつかない…。教育担当者の多くが直面するこの壁を、実際に乗り越えた企業の事例から解き明かします。
従来の研修やOJTで成果が出ない真の理由と、デジタル時代ならではの効果的な育成モデルを厳選事例とともに公開。「時間がない」「効果が見えない」という課題に、他社が語らない人材育成の現実解が具体的な打開策を提示します。
これまでの育成施策に行き詰まりを感じている方こそ、『デジタル時代の人材育成モデル』をぜひご活用ください。
目次
HPI(ヒューマンパフォーマンスインプルーブメント)とは?
HPIとは、Human Performance Improvementの略称であり、「ヒューマンパフォーマンスの改善」を意味します。これは、単に個人の能力を向上させるだけでなく、組織や個人のパフォーマンスに存在するギャップ(あるべき姿と現状の差)を特定し、その根本原因を分析した上で、研修にとどまらない多様な解決策(介入策)を実行し、最終的にビジネス成果を出すための体系的なアプローチプロセスを指します。
HPIは、世界最大の人材開発・組織開発に関する会員制組織であるATD(Association for Talent Development、旧称:ASTD)によって提唱・推進されてきました。ATDでは、HPIを「あるべき姿と現状の重要な成果とのギャップを発見・分析し、成果向上に向けて、そのギャップを埋める効率的かつ倫理的に妥当な施策を立案・実行し、成果・業績を測定するシステム的なプロセス」と定義しています。
ここで重要なのは、「パフォーマンス」が単なる「行動」や「活動」だけを指すのではなく、「成果」につながる行動や、その行動によって得られる結果であるという点です。そして、パフォーマンスギャップの原因は、必ずしも「人」の知識やスキルの不足だけにあるわけではありません。組織を取り巻く環境、システム、業務プロセス、適切な動機づけやフィードバックの欠如など、さまざまな要因が複合的に影響していると考えます。
ASTDによるHPIの定義
HPIは、世界最大の人材開発・組織開発に関する会員制組織であるATD(Association for Talent Development、旧称:ASTD)によって提唱・推進されてきました。ATDでは、HPIを「あるべき姿と現状の重要な成果とのギャップを発見・分析し、成果向上に向けて、そのギャップを埋める効率的かつ倫理的に妥当な施策を立案・実行し、成果・業績を測定するシステム的なプロセス」と定義しています。
ここで重要なのは、「パフォーマンス」が単なる「行動」や「活動」だけを指すのではなく、「成果」につながる行動や、その行動によって得られる結果であるという点です。そして、パフォーマンスギャップの原因は、必ずしも「人」の知識やスキルの不足だけにあるわけではありません。組織を取り巻く環境、システム、業務プロセス、適切な動機づけやフィードバックの欠如など、さまざまな要因が複合的に影響していると考えます。
HPIを導入する目的
HPIを導入する主な目的は、研修に対する課題を克服し、組織のパフォーマンスとビジネス成果を最大化することにあります。例えば、次のような効果が期待できます。
- 効果の薄い研修や施策への無駄な投資を削減できる
- パフォーマンスギャップの原因にアプローチすることで、個人レベルだけでなく組織全体のパフォーマンスを向上させる
- パフォーマンス課題の解決プロセスに関与することで、従業員の主体性やエンゲージメントが高まり、自律的な成長が促進される
HPIは、行き当たりばったりな人材育成ではなく、データに基づいた分析と戦略的なアプローチによって、限られた予算と時間の中で最大の効果を追求する考え方と言えます。
従来の教育研修(OJT)との違い
HPIと従来の教育研修やOJTは、どちらも人材育成に関連する活動ですが、その目的やアプローチには明確な違いがあります。この違いを理解することが、HPIの本質を掴む上で非常に重要です。
| 比較項目 | HPI | 従来の教育研修・OJT |
|---|---|---|
| 最終目的 | ビジネス成果・業績の向上 | 主に知識・スキルの習得、行動変容 |
| アプローチの開始点 | まずビジネス成果と現状のパフォーマンスの「ギャップ」を診断・分析する | 主に「知識・スキルが不足しているだろう」という仮説から始まる |
| 原因特定 | ギャップの根本原因を多角的に分析(知識・スキル以外に環境、システム、動機づけなども考慮) | 主に個人の知識・スキルの不足に焦点を当てる |
| 解決策(介入策) | 原因に応じて、研修を含む多様な手法から最も効果的なものを選択・組み合わせる | 主に座学研修やOJTといった特定の教育手法に偏りがち |
| 対象範囲 | 個人、チーム、組織全体のシステムとしてパフォーマンスを捉える | 個人に焦点を当てることが多い |
| 評価基準 | 実行した施策がビジネス成果につながったか、パフォーマンスギャップが解消されたかを重視 | 研修内容の理解度、満足度、行動変容などを評価することが多い |
このように、従来の研修が「知識やスキルを習得させること」を主な目的とするのに対し、HPIは「ビジネス成果を最大化するために、パフォーマンスのギャップを解消すること」を最終目的とします。そのため、HPIではまず徹底的な分析から入り、原因に即した最適な解決策を柔軟に選択します。そして、その効果をビジネス成果の視点から厳密に評価します。
HPIが重要視される背景
なぜ今、HPIという考え方が重要視されているのでしょうか。その背景には、現代ビジネスが抱えるさまざまな課題と、従来の人材育成アプローチの限界があります。
変化の激しいビジネス環境
現代は「VUCA時代」と呼ばれ、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)が高まっています。このような予測困難な状況下では、企業には市場の変化に迅速に対応し、競争優位性を維持するための高い組織能力が求められます。市場環境の急速な変化により、従来型の固定的な人材育成アプローチでは対応が難しくなっており、柔軟性と即応性を備えた仕組みが必要とされています。
さらに、グローバル化の進展や技術革新の加速、それにともなう企業へのDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進の要求も、HPIの重要性を高めている要因です。特にAIを始めとする新たな技術の導入により、従業員が新しいスキルを迅速に習得し、変化する業務要件に適応する能力がこれまで以上に求められています。また、近年注目されている「人的資本経営」の潮流もHPIの重要性を後押ししています。これは、人材を単なるコストとしてではなく、企業の持続的な成長に不可欠な「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで企業価値向上を目指すという考え方です。人材のパフォーマンスを組織全体の成果に結びつけるHPIは、この人的資本経営を実現するための強力なフレームワークとなり得ます。
従来の教育研修の限界
多くの企業で、従来の教育研修やOJTだけでは十分な効果が得られない、という課題が顕在化しています。例えば、以下のような理由が挙げられます。
- 研修が現場の成果につながりにくい
- 研修コストに対する効果が見えにくい
- 研修だけでは解決できない課題の存在
研修で学んだ知識やスキルが、実際の業務で活かされない、成果に直結しない、といった声は少なくありません。また、多額の投資をしても、それが具体的にどのようなビジネス成果につながったのか、効果測定が難しいという課題もあります。そして、パフォーマンスの課題が、単に個人の知識・スキル不足ではなく、非効率な業務プロセス、不明確な目標設定、不十分なフィードバックなど、組織構造やシステムに起因している場合は、いくら研修を実施しても根本的な解決には至りません。
HPIを支える4つの原理
HPIが効果的に機能するには、いくつかの基本原則があります。これらの原則を理解し、実践することで、HPIの取り組みが成功に近づきます。
結果重視
HPIの中心にあるのは、常にビジネスゴールとの連動を追求する姿勢です。単なる行動や活動に終始するのではなく、具体的な成果(売上増加、コスト削減、顧客満足度向上など)に結びつく施策を設計・実行することが求められます。そのため、目指すべき成果を明確にしたうえで施策を進めることが鍵となります。
システム思考
HPIは、個人の能力向上だけを目的とするものではありません。組織全体をひとつのシステムとして捉え、複雑に絡み合う要因(業務プロセス、環境、動機づけなど)を分析し、包括的な解決策を講じます。この視点により、単なる知識やスキルの不足だけではない、潜在的な課題を発見しやすくなります。
科学的アプローチと費用対効果
データや根拠に基づいた解決策を検討する姿勢も、HPIの特徴です。課題に対する複数のアプローチを比較・検討し、効果が見込める手法を選択します。同時に、施策の費用対効果を意識することで、限られたリソースを最大限に活用できます。
顧客・現場との信頼関係構築
現場や関係者と連携し、当事者意識を持って協働することも、HPIを推進するうえで欠かせません。関係者間の信頼関係を築くことで、取り組みの目的や意図が共有され、協力が得られやすくなるだけでなく、施策の実行力や持続性も向上します。
HPIの標準的なプロセスと手法
HPIは、パフォーマンス課題を解決し、ビジネス成果を達成するための体系的なプロセスに従って進められます。このプロセスは、組織や課題の性質によって多少異なりますが、ここではATDモデルなどを参考に、多くのHPIアプローチに共通する標準的なプロセスをご紹介します。
ステップ1:パフォーマンスギャップの特定
この最初のステップでは、「あるべき姿」と「現状」を明確にし、その間の「ギャップ」を特定します。以下のポイントに留意して分析しましょう。
- 目指すべきビジネス成果の明確化:HPIが最終的に貢献すべきビジネス目標(売上向上、コスト削減、顧客満足度向上など)を明確にする。経営戦略と連動させることが重要
- 理想のパフォーマンスの定義:ビジネス成果を達成するために、個人や組織がどのような状態であるべきか、どのような行動や結果を生み出すべきか(パフォーマンスゴール)を具体的に定義する
- 現状のパフォーマンスの把握:現在のパフォーマンスレベルを客観的なデータや観察、インタビューなどを通じて正確に把握する
- ギャップの明確化:「理想のパフォーマンス」と「現状のパフォーマンス」の差、つまりパフォーマンスギャップを具体的に特定。このギャップこそが、HPIの取り組みによって解消すべき課題となる
ステップ2:原因の分析
特定されたパフォーマンスギャップが「なぜ」発生しているのか、その根本原因を深く掘り下げて分析します。安易に「個人の能力不足」と決めつけず、多角的な視点から原因を探ることがHPIの特徴です。
原因分析のステップでは、以下のような要因がギャップに影響していないかを包括的に検討します。
- 知識・スキル:必要な知識やスキルが不足しているか
- 環境:業務遂行に必要なツールや情報、物理的な環境は整っているか
- 動機づけ:適切な報酬、評価、フィードバック、キャリアパスなどが用意され、働く意欲を高めているか
- フィードバック:パフォーマンスに対するタイムリーで具体的なフィードバックは行われているか
- システム・プロセス:業務プロセスは効率的か?組織構造や役割分担に問題はないか
- 情報:業務に必要な情報に適切にアクセスできるか
原因分析の手法としては、さまざまなフレームワークが用いられます(例:ホワイトツリー、イシカワダイアグラム(特性要因図)など)。これらのツールを活用することで、表面的な原因ではなく、真の根本原因を特定することができます。
ステップ3:計画の設計・選択
特定された根本原因に対し、パフォーマンスギャップを解消するために最も効果的で効率的な解決策(介入策)を検討・設計します。HPIでは、研修だけではなく、原因に即した多様な選択肢の中から最適なものを組み合わせることが重要です。
例えば、原因が知識・スキルの不足であれば、効果的な研修やOJTが有効ですし、原因が環境にあれば、必要なツールの導入や業務プロセスの改善が必要になってきます。また、原因が動機づけにあれば、評価制度やインセンティブ制度の見直しをするのもひとつでしょう。
このように、単一の解決策に固執せず、複数の介入策を組み合わせることも一般的です。費用対効果も考慮しながら、最適な解決策を設計します。
ステップ4:計画の実施・実行
設計した解決策を実行に移します。このステップでは、計画通りに施策が進行しているかのモニタリングや、関係部署・従業員の協力を得るためのコミュニケーションが重要になります。
単に施策を実施するだけでなく、それが意図した通りに機能しているか、予期せぬ問題が発生していないかなどを注意深く観察・管理します。
ステップ5:評価と改善
実施した解決策が、当初特定したパフォーマンスギャップを解消できたか、そしてそれがビジネス成果にどのように貢献したかを評価します。この評価は、単なる参加者の満足度調査ではなく、具体的なデータや成果に基づいた客観的なものである必要があります。
- 当初設定したパフォーマンスゴールやビジネス目標は達成できたか
- 解決策の実施によって、生産性や収益性は向上したか
- 投資に見合う効果は得られたか
以上のように具体的な項目を設け評価結果を分析し、成功した点、改善が必要な点を明確にします。そして、その結果を次のHPIサイクルのための情報として活用します。HPIは継続的なプロセスであり、評価結果を基に次の改善策を検討し、再びステップ1に戻ることで、組織のパフォーマンスを継続的に向上させていきます。
HPIで用いられる主な手法(解決策)
ステップ3で触れたように、HPIではパフォーマンスギャップの根本原因に応じて、研修にとどまらない多様な手法(介入策)が用いられます。主な手法には以下のようなものがあります。
| 原因 | 手法 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| 知識スキル | ・効果的な研修 ・OJTの設計、実施 ・コーチング、メンタリング | ・HPIプロセスを活用した研修 ・OJTプログラムの実施 ・eラーニングシステムの導入 ・個別指導によるパフォーマンス向上支援 |
| 環境ツール | ・ジョブ・エイド(業務支援ツール、チェックリストなど)の導入 ・物理的な環境整備 | ・業務中に参照できるツールを提供 ・業務に必要な設備、スペース、情報アクセス環境の改善 |
| システムプロセス | ・組織構造、業務プロセスの改善 ・使用ツールの改善・導入 ・ナレッジマネジメント、情報共有の仕組み構築 | ・ボトルネックとなっている組織構造、プロセスの見直し ・業務効率を高めるITツールなどの導入、活用 ・必要な情報にスムーズにアクセスできる体制構築、組織全体の知識活用 |
| 動機付けフィードバック | ・フィードバックシステム、目標設定 ・管理システムの改善 ・報酬、インセンティブ制度の見直し | ・従業員のパフォーマンスを適切に評価し、成長を促す仕組み構築 ・成果につながる行動やパフォーマンスを適切に評価し、報酬や昇進、昇格に反映 |
このように、HPIは原因に応じてこれらの多様な手法を柔軟に組み合わせることで、効果的なパフォーマンス向上を実現します。
HPIを組織に導入・推進するためのポイント
HPIを組織に導入し、推進していくためには、いくつかの重要なポイントがあります。HPIは人事・教育部門の活動に留まらず、経営戦略と連携した全社的な取り組みとして位置づけることが成功の近道です。
推進体制の構築
誰がHPIを推進し、実行するのか、明確な推進体制を構築する必要があります。人事・教育部門が中心となることが多いですが、現場の管理職や従業員、必要に応じて外部の専門家との連携も視野に入れます。関係部署を巻き込み、共通認識を持って進める体制が不可欠です。
スモールスタートと段階的な拡大
いきなり全社的にHPIを導入するのではなく、まずは特定の部署や、明確なパフォーマンス課題を抱えるプロジェクトなどで小さく開始し、成功事例を作ることを目指します。そこで得られた知見やノウハウを蓄積し、段階的に取り組みを拡大していく方が、リスクを抑えつつ組織への浸透を図りやすいでしょう。
コミュニケーションと透明性
なぜHPIが必要なのか、HPIの目的、プロセス、期待される効果について、従業員や関係者に分かりやすく丁寧に伝えることが大切です。透明性の高いコミュニケーションは、取り組みへの理解と協力を促し、変化に対する抵抗感を和らげます。
継続的な評価と改善
HPIは一度行えば完了するものではありません。常にパフォーマンスの変化をモニタリングし、評価結果を基に改善策を検討・実行するというサイクルを継続することが最も重要です。組織を取り巻く環境は常に変化するため、それに合わせてHPIのアプローチも進化させていく必要があります。
この評価プロセスにおいて、学習管理システム(LMS)は有用なツールとなります。LMSに蓄積された受講者の学習データ(学習完了率、テストの得点、コンテンツへのアクセス状況など)は、知識・スキル定着度の一側面を示す情報源となり得ます。これらの学習データと、実際の業務パフォーマンスデータ(例:営業成績、生産効率、エラー率など)やビジネス成果データ(例:売上、利益、顧客満足度)を結びつけて分析することで、教育施策が実際の成果にどの程度結びついたのかを検証し、次のHPIサイクルにおける改善策立案の参考にすることができるでしょう。
まとめ
HPI(ヒューマンパフォーマンスインプルーブメント)は、現代ビジネスの複雑な課題に対応し、組織の持続的な成長を実現するための強力なアプローチです。
コーチング、業務プロセス改善、eラーニングシステムの導入、評価制度見直しなど、HPIで用いられる手法は多岐にわたります。その管理・評価を支援する学習管理システム(LMS)は、HPIを進めるうえで力強い味方になってくれるでしょう。
自社が抱える組織や個人のパフォーマンス課題に対して、HPIの観点からどのように取り組むべきかを検討し、成果につながる人材育成・組織開発の実現を目指してください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。