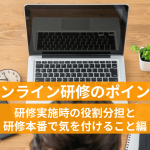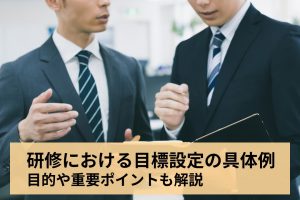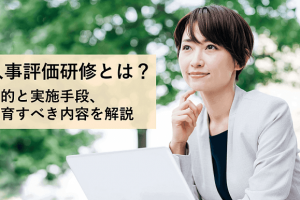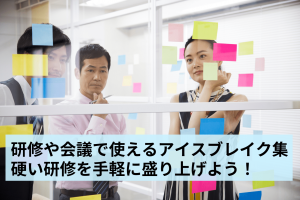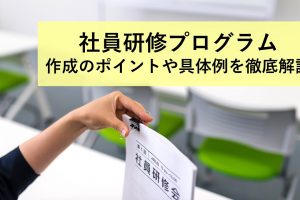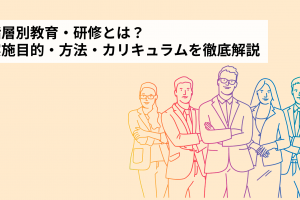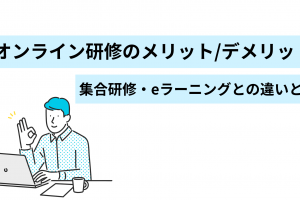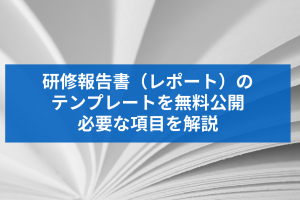ここまで2回に分けてオンライン研修を成功させるための具体的なポイントをご紹介してまいりました。
実践編その1 研修実施時の役割分担と研修本番で気を付けること編
今回は実践編その2ということで、研修実施前後の取り組みについて解説します。
オンライン研修の効果を最大限引き出すために欠かせないのが、オンライン研修の特性を生かしたプログラム構成です。ポイントは研修実施前と実施後に受講者をしっかりフォローすること。おすすめの構成は以下のとおりです。
◆研修実施前
1)eラーニング
2)課題に取り組む
◆研修本番
◆研修終了後
1)課題に取り組む
2)共有の場を設定する
研修実施前と研修終了後の取り組みについて、それぞれ具体的に解説いたします。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
研修実施前
1)eラーニング
eラーニングとは、パソコン、スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器とインターネットを利用して教育、学習、研修を行うことです。
具体的には、受講に必要な知識やスキルを動画セミナーとして提供します。研修前に視聴してもらうことで、テーマに対する前提知識を理解した状態で、スムーズに研修を受講することができます。
eラーニングのメリットは、事前に用意しておけば、受講者は自分の好きなタイミングで視聴できるということです。さらに受講者全員に同じ動画セミナーを視聴してもらうことで、研修に対する前提知識のばらつきを最小限に抑えることができます。
動画セミナーの構成は1項目5分~10分程度を5項目~10項目、合計60分以内を目安にしたマイクロラーニングがおススメです。
1項目を短く区切ることで、移動時間など仕事の合間のちょっとした時間を使って動画セミナーを効率的に視聴してもらうことができます。
2)課題に取り組む
eラーニング視聴後、研修本番までに取り組んでもらう課題を出します。
例えば、研修に対する期待、仕事で悩んでいること、どんな問題を仕事で抱えているか、など。取り組んだ課題は、研修の冒頭で全員に発表してもらいます。
発表時間の目安は1人30秒~60秒程度。自己紹介を兼ねて発表してもらうことで発言の練習になり、研修本番でもリラックスして発言してもらうことができます。
もし一人ひとり発表することが時間的に難しいようでしたら、事前に提出してもらったり、研修開始前にチャットに書き込んでもらったりしてもよいでしょう。
提出された課題を講師が研修の冒頭で取り上げてフィードバックすることで、これから受講する研修に対する参加意識を高めることができます。
なお、提出課題の管理に関しては、AirCourseが提供する「提出課題」機能を利用することで、受講者側の課題提出と講師側の課題管理をスムーズかつ効率的に行うことができます。
「提出課題」機能詳細
https://aircourse.com/submission_subject.html
研修終了後
1)課題に取り組む
研修終了後の課題は、研修実施前とは違う課題を設定します。
ポイントは、研修を受講して得たスキルや知識を活かして、職場で実践した結果を報告してもらうということです。
研修を「いい話を聞いた、勉強になった」だけで終わらせないように、自分が担当する仕事に対して、何か工夫できないか、何か改善できないか、といった視点で、研修を受講して得たスキルや知識を実践してもらうように促しましょう。
この実践結果を、課題に取り組んだ結果として報告してもらいます。
研修終了後の課題「職場で実践した結果を報告する」に取り組むことで、研修を受講して得たスキルや知識が「知っている」から「できる」に変わり、仕事の成果に直結させることができます。
2)共有の場を設定する
研修終了後の課題に取り組んだ結果を、報告だけで終わらせるのはもったいないです。
研修受講から半月後~1か月後など、研修の記憶が残っているうちに受講者全員が集まる場を設定しましょう。
この場で課題に取り組んだ結果を全員で共有します。共有する結果は成功事例だけではありません。
試行錯誤した様子や、失敗した結果も共有してもらいます。
失敗したのは新しいことに挑戦した証。結果だけを評価するのではなく、挑戦する姿勢も評価することで、仕事に対して積極的に取り組む姿勢を引き出すことができます。
課題を共有する場は、研修と同じオンライン会議システムである必要はありません。チャットのグループやメーリングリストといった仕組みでもOKです。どんな手段を使うにしても、受講者全員の課題に取り組んだ結果をもれなく共有できるように、講師または研修主催者が働きかけましょう。
なお、課題の共有に関しては、AirCourseが提供する「提出課題」と「ナレッジ共有」を組み合わせて利用することで、セキュリティが確保された安心安全な場でスムーズに課題を共有することができます。
「ナレッジ共有」機能詳細
https://aircourse.com/knowledge_sharing_organization.html
まとめ
今回は実践編その2ということで、オンライン型研修の効果を最大限に引き出す研修プログラム構成、とくに研修実施前と研修終了後にどんな仕掛けを取り入れたらよいかを解説いたしました。
現在オンラインで社員研修を増えていることが多い状況ですので、本コラムの内容がすこしでもお役にたてばうれしい限りです。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。