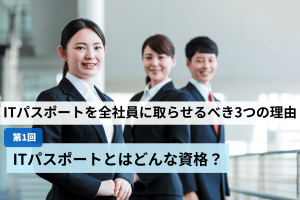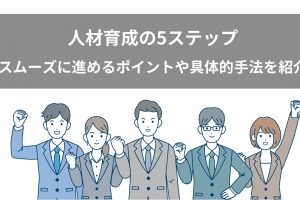近年、企業の人材育成において「ブレンディッドラーニング」が注目されています。
ブレンディッドラーニングは、集合研修やOJTなどの従来型の学習手法に、オンライン学習やeラーニングを組み合わせ、柔軟かつ効果的な学習体験を提供する手法です。
人材育成の投資対効果が向上する手法であることから、採用する企業が増えています。
本記事では、ブレンディッドラーニングが注目されている理由やメリット、具体的な活用方法について解説するとともに、導入時のポイントもご紹介します。
成功企業に学ぶ”人材育成のノウハウ”を無料でお届け
現場の人材育成がなかなか成果に結びつかない…。教育担当者の多くが直面するこの壁を、実際に乗り越えた企業の事例から解き明かします。
従来の研修やOJTで成果が出ない真の理由と、デジタル時代ならではの効果的な育成モデルを厳選事例とともに公開。「時間がない」「効果が見えない」という課題に、他社が語らない人材育成の現実解が具体的な打開策を提示します。
これまでの育成施策に行き詰まりを感じている方こそ、『デジタル時代の人材育成モデル』をぜひご活用ください。
目次
ブレンディッドラーニングとは?
ブレンディッドラーニングとは、集合研修やeラーニング、オンライン学習などを効果的に組み合わせた学習手法です。
ブレンディッドラーニングは、オフラインとオンラインの利点を組み合わせた学習方法で、それぞれの学習形態を組み合わせることによって、短所を補完し、より効果的で柔軟な学習環境を提供できるのが魅力です。
ブレンディッドラーニングが注目される背景
ブレンディッドラーニングが注目される背景には、デジタル化の進歩や働き方の多様化といった現代社会の変化が挙げられます。
従来の研修は、集合研修が主流でしたが、時間や場所の制約と、受講者の理解度や学習スピードの違いへの対応が難しいといった課題がありました。
しかし、オンライン学習の普及によって、研修コンテンツの個別化や柔軟な学習が可能になり、オンライン学習のニーズが急増しました。
これにより、従来の集合研修と組み合わせた、より効果的な研修が求められるようになったのです。
ブレンディッドラーニングは柔軟性と効果の高さにより、現在の企業研修において重要な学習手法として注目を集めています。
ブレンディッドラーニングのメリット
ブレンディッドラーニングは、企業と受講者の双方に多くのメリットをもたらす、学習効果の高い手法です。企業側と受講者側のそれぞれに焦点を当て、メリットを詳しく解説します。
企業側のメリット
ブレンディッドラーニングを導入することで、企業側は以下のような3つのメリットが得られます。
研修コストの削減
ブレンディッドラーニングを導入すると、研修にかかるコストを効率的に削減できます。具体的には、オンライン学習やeラーニングを積極的に活用することで、従来の集合研修で必要だった会場費、交通費、宿泊費、講師への謝礼など、多くの費用を抑えられるほか、移動にかかる時間コストも減らせます。
研修コストが下がれば、予算をより多くの従業員の研修機会の拡充や、研修内容の充実に再分配するなど、さらに高い学習効果を生み出すための施策ができるようになります。
研修時間の短縮
ブレンディッドラーニングでは、事前学習をeラーニングで行うことで、集合研修の時間を大幅に削減し、効率化を図ることが可能です。
従来の集合研修では、準備や基礎内容の説明に多くの時間が割かれていましたが、オンライン学習を活用すれば、事前に基礎知識を習得した状態で集合研修に臨めるため、集合研修の時間を応用的かつ実践的な内容に集中させることができます。
これにより、従業員は短時間で質の高い学びを得られるだけでなく、空いた時間を本来の業務に活用できるため、業務効率の向上にもつながります。
効果的な学習体験の提供
ブレンディッドラーニングでは、オンライン学習やeラーニングを導入するため、受講者の学習進捗や成果を可視化できるようになります。
これによりデータに基づいたフィードバックが可能になり、より効果的な学習体験を提供できます。
受講者側のメリット
ブレンディッドラーニングには、企業だけではなく受講者にとっても以下のようなメリットがあります。
学習内容の定着率向上
ブレンディッドラーニングでは、集合研修とオンライン学習を組み合わせることで、インプット(知識の習得)とアウトプット(実践や応用)の両方をバランス良く行います。
この学習プロセスにより、受講者における学習内容の理解度が向上するとともに、復習が容易になるため記憶の定着が進みます。例えば、オンライン学習で基礎知識を学んだあとに集合研修で実践的な演習を行うと、受講者の中の理論と実践のギャップが埋まり、学んだ内容が学習者の血肉につながりやすくなります。
参加への負担軽減
ブレンディッドラーニングでは、オンライン学習を導入するため、従来の集合研修のみのときよりも時間や場所に縛られず、柔軟に学習計画を立てられます。
また、集合研修の時間が短縮されることで、長時間拘束の負担が軽減され、学習に対する心理的なハードルも下がります。
“成果を出す”人材育成とは?解説資料を無料公開
OJTや集合研修を実施しているものの、「思うような効果が感じられない」「継続的な成長につながらない」といった課題を抱えていませんか。
その背景には、デジタル時代の働き方に適さない従来型の育成モデルがあります。では、実際に成果を上げている企業は、どのような人材育成モデルを構築しているのでしょうか?
『デジタル時代の人材育成モデル』では、現代の課題を解決する新しい育成アプローチと、それらを実現するための具体的な手法を、成功企業の実例をもとに詳しく解説しています。育成を見直したい方は、ぜひご覧ください。
ブレンディッドラーニングの実践例
ブレンディッドラーニングで効果的な学習効果を得るには、研修内容に適したオンラインとオフラインの組み合わせが重要です。
例えば、新入社員研修で「ビジネスマナー」を学ぶケースの場合を考えてみましょう。
オンラインで座学によるマナー理解を促し、オフラインでロールプレイングを通して実践力を養うことで、より効果的な研修になります。
ブレンディッドラーニングで使われる教育手法
ブレンディッドラーニングで使われる教育手法には、それぞれ特徴があります。
以下にブレンディッドラーニングで使われる教育手法の特徴とメリット・デメリットをまとめました。
| 手法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 集合研修/講義形式 | 講師が一方的に知識や情報を伝える | 多くの受講者に効率的に情報を伝えられる | 受講者の主体性が低くなりやすい |
| 集合研修/演習形式 | グループワークやディスカッションを行う | 実践的なスキルや知識を習得できる | 時間や場所の制約がある |
| オンライン研修 | Web会議システムなどを用いた研修 | 場所を選ばずに参加できる | 通信環境に左右される |
| eラーニング | インターネットを利用した自己学習 | 自分のペースで学習できる | 学習進捗の管理が難しい |
| OJT | 実際の業務を通して指導する | 実践的なスキルが身につく | 指導者の負担が大きい |
それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、研修目的に合った手法を組み合わせることが、ブレンディッドラーニングの効果を高めるコツです。
ブレンディッドラーニングの具体的な組み合わせモデル
ブレンディッドラーニングの具体的な組み合わせモデルについて、それぞれの特徴と活用方法を解説します。これらの組み合わせモデルは、それぞれの特性を活かしながら、自社の研修目的や受講者のニーズに合わせて活用することが重要です。
ローテーション型
ローテーション型は、受講者がオンライン学習と集合研修を計画的に交互に行うモデルです。例えば、事前にeラーニングで基礎知識を学び、集合研修で実践的なスキルを磨くといった形式が挙げられます。このモデルは、体系的な知識習得と実践的な学びをバランスよく進めたい場合に適しています。
反転授業
反転授業は、受講者がオンラインで事前に学習し、集合研修ではその内容を基に議論や演習を行うモデルです。事前学習により基礎的な知識を理解しておくことで、集合研修ではディスカッションやケーススタディなど、より深い学びに時間を充てることができます。
参考:反転学習とは?メリットやデメリット、活用方法を解説 | 人材育成サポーター
分散型
分散型は、オンライン学習と集合研修を並行して行い、それぞれの学習内容が相互に補完し合うモデルです。オンラインで得た知識を集合研修で共有・発展させる、集合研修での疑問や課題をオンライン学習で解消するといった形で活用されます。学習内容の定着を促進し、多様な学びのスタイルに対応可能です。
ハイフレックス型
ハイフレックス型は、受講者がオンラインまたはオフラインのいずれかを選択して学習できるモデルです。それぞれの受講者が自身のスケジュールや学習環境に応じて柔軟に参加できるため、多様な働き方やニーズに対応しやすいのが特徴です。特に、場所や時間の制約を受けやすい受講者にとって有効な手法です。
研修の実施スタイルの組み合わせと実践例
研修の実施スタイルの最適な組み合わせは、自社の研修の目的や課題に合わせて検討していきましょう。以下は、具体的な活用シーンを含めて解説したブレンディッドラーニングの例です。
研修の目的や対象者の特性に応じて柔軟に組み合わせることで、ブレンディッドラーニングの効果を最大化できます。
【基礎固め×実践】eラーニングで予習 → 集合研修で実践 → OJTで定着
このパターンは、新入社員研修や階層別研修など、基礎知識の習得と実践力の向上が求められる場合に有効です。
例えば、新人営業担当者向けの研修では、eラーニングを活用して営業の基礎知識(商品知識や営業プロセスなど)を学んでもらい、集合研修でロールプレイングを通じて顧客対応の実践スキルを習得します。その後、OJTで実際の顧客訪問を通じて実践を積むことで、学んだ知識を行動に結びつけます。
このスタイルは、基礎をしっかり固めた上で現場経験を重ねるため、成果を出すまでのプロセスをスムーズに構築できる点が特長です。【個別学習×全体共有】オンライン研修で個別学習 → 集合研修で共有と深堀り
このパターンは、多様な学習ニーズを持つ受講者が多い場合や、研修内容に深い理解が求められる場合に適しています。
例えば、新製品の開発プロジェクトを担当するチーム向けには、オンライン研修で各メンバーが事前に製品の技術仕様や市場分析を学ぶ機会を設けます。その後、集合研修でそれぞれの視点から学んだ内容を共有し、議論やグループワークを通じて解決策を深めていきます。
このプロセスでは、受講者ごとの学習スピードに柔軟に対応しながら、集合研修で知識を統合することが可能です。個別学習と全体共有を組み合わせることで、個々の強みを活かしながら集団としての理解力を高められます。
【スキルアップ×現場適用】集合研修でスキル習得 → eラーニングで復習と確認 → OJTで実践
このパターンは、特に実践的なスキルや業務手法を習得するための研修に有効です。
例えば、管理職向けのリーダーシップ研修では、集合研修でリーダーシップ理論やチームマネジメントのスキルを学びます。その後、eラーニングで学んだ内容を復習し、チェックリストやケーススタディを通じて理解を確認します。最終的には、OJTで実際のマネジメント業務において活用することでスキルを定着させます。
このスタイルは、理論学習と現場実践を繰り返し行うことで、学んだスキルを即戦力化したい場合に特に効果的です。
ブレンディッドラーニングの効果的な導入方法
ブレンディッドラーニングを効果的に導入するためのポイントを解説していきます。
eラーニングによる復習コンテンツの提供や、定期的なフォローアップ研修の実施など、受講者の継続学習を促進する工夫を凝らしましょう。
研修目的を設定する
ブレンディッドラーニングを導入する際には、研修の目的設定が最も重要です。
目的が曖昧なまま研修の設計や実施を進めてしまうと、期待する効果を得られない可能性が高くなります。
研修によってどのような成果を出したいのかを明確にすることで、適切な手法を選択し、効果的な研修を実施できます。
目的設定の手法は以下の記事で詳しく解説しているので、ご覧ください。
【テーマ別】研修の目標設定例|設定する狙いやポイントも解説 | 人材育成サポーター
具体的な目標を設定すれば、研修の効果測定を適切に行い、改善につなげることができます。
具体的なロードマップを作成する
ブレンディッドラーニングを成功させるには、具体的なロードマップの作成も重要でです。
受講者のモチベーション維持と学習効果の向上には、目標達成までの道のりを明確にすることが欠かせません。
人材育成におけるロードマップ作成の手順は、以下の記事で解説しています。
受講者自身が「この研修で何を学び、どのようなスキルや能力を身につけることが求められているのか」という点を理解できるようにしましょう。
適切な研修スタイルを選定する
ブレンディッドラーニングを効果的に行うために、目的に沿った研修スタイルを選定するようにしましょう。
集合研修やオンライン研修、eラーニングそれぞれの特徴を確認し、それぞれの手法のメリットを活かしながら、デメリットを補完する組み合わせを実現しましょう。
受講者が継続して学習するサイクルを作る
ブレンディッドラーニングで効果を出すためには、継続的に学習できるサイクルを作ることが重要です。
学習サイクルを作ると、受講者は学んだ知識やスキルを定着させ、実践に活かすことができます。
ブレンディッドラーニングを通じて、受講者が発見した自身の課題を改善できるような学習サイクルを作ると良いでしょう。
ブレンディッドラーニング導入時の注意点
ブレンディッドラーニングを効果的に実施するには、事前学習を徹底させ、組み合わせる手法の内容に一貫性をもたせることが重要です。
受講者に事前学習を徹底させる
事前学習は、受講者が集合研修の内容をスムーズに理解し、実践的な学びを深めるための重要なステップです。受講者の自主性に依存するだけでは学習が疎かになる可能性があるため、研修担当者は以下の工夫を行う必要があります。
| ポイント | 具体例・説明 |
|---|---|
| 事前学習の重要性 | ・集合研修では議論や実践に集中できるよう、オンラインで基礎知識を事前に習得させる |
| LMS(学習管理システム)の活用 | ・学習コンテンツの提供と進捗管理が可能 ・小テストや課題で理解度を確認し、弱点克服を促す |
| モチベーションを高める工夫 | ・目的や目標を明確に伝える、学習時間確保をサポートする、質問窓口を設けるなど、受講者が安心して取り組める環境を整える |
事前学習を徹底することで、限られた研修時間を最大限に活用することができます。また、学習管理システム(LMS)を活用すれば、受講者が計画的に学習を進められるだけでなく、研修担当者も進捗状況を把握しながら必要な支援を行うことが可能です。
学習テーマを明確にし、内容に一貫性をもたせる
学習テーマを明確にし、内容に一貫性をもたせることは、ブレンディッドラーニングを成功させる鍵です。関連性のない内容を組み合わせると、受講者の混乱を招き、学習効果が低下するリスクがあります。
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 集合研修:営業トークの基本を学ぶ オンライン研修:営業トーク事例紹介、ロールプレイング練習を実施 | 集合研修:営業トークの基本を学ぶ オンライン研修:関連性のない顧客管理システムの使い方を学ぶ |
一貫性のある内容を設計するためには、研修目的と目標を明確に設定し、受講者がどのようなスキルを身につけ、どのように活用するかを具体的に示す必要があります。
まとめ
この記事では、ブレンディッドラーニングが注目されている理由やメリット、具体的な活用方法について解説するとともに、導入時のポイントについてもご紹介してきました。
ブレンディッドラーニングは、オンラインとオフライン学習を組み合わせ、両者のメリットを最大限に活かす学習手法です。費用対効果、時間効率、学習効果の向上など、企業と受講者双方に多くの利点があります。
自社の課題や従業員のスキルに合わせて、適切な学習手法を選択し、ブレンディッドラーニングを実施しましょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。