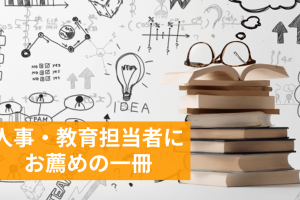企業の研修担当者の中には、 「 研修の効果を高めたいけれど、時間やコストは抑えたい…」 という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
従来の一斉講義型の研修では、参加者の理解度や学習意欲にばらつきが出やすく、研修内容の定着率が低い、研修後の業務への活用が進んでいないなど、さまざまな課題を感じている担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで近年注目を集めているのが「反転学習」です。 反転学習とは、ディスカッションやグループワーク、実務演習などのアウトプットを主体とした学習手法です 。
反転学習を活用することで、企業は研修を効率的に運営できるようになるだけではなく、従業員に自発的かつ能動的な学習姿勢を促すことができます。
この記事では、反転学習のメリット・デメリット、企業研修における具体的な活用方法、成功事例などを詳しく解説していきます。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
企業研修に反転学習が取り入れられるようになった背景
企業研修に反転学習が注目され、取り入れられるようになった背景には、いくつかの要因があります。
例えば、講師が一方的に知識やノウハウを伝える従来の講義形式では、従業員の主体性や学習効果を高めるのに限界がありました。
これに対し、 事前学習と対面でのアウトプットを組み合わせる反転学習は、従業員が自ら主体的に学ぶスタイルであるため、従業員の主体的な学びと深い理解を促す有効な手法として認識されるようになりました。 特にアメリカの教育現場での実践研究で一定の効果が報告されていることも企業研修での導入を後押ししています。
さらに、インターネットの普及によるオンライン学習の浸透や、コロナ禍でのリモート研修増加も普及を加速させました。
変化の速い現代ビジネスにおいて、従業員一人ひとりの自律的な学びは不可欠です。反転学習は、主体性向上と学習効果向上に有効なアプローチとして、企業研修で広く採用されるようになっています。
反転学習を企業研修で活用するメリット
この章では、企業研修に反転学習を取り入れることによって得られるメリットをご紹介します。
従業員の自発的な成長を促進できる
反転学習では、従業員は事前に教材でインプットを行い、集合研修では学んだ内容を基にアウトプット活動に取り組みます。この 「自ら事前に学ぶ→集合研修で活用する」という能動的な学習プロセスそのものが、従業員の学習に対する主体的な姿勢を引き出します 。
自分でペースを調整しながら知識を習得し、集合研修でその知識をディスカッションや演習を通して「使う」経験を積むことで、学びへの関与度が高まり、「もっと知りたい」「実際にできるようになりたい」という内発的な動機が生まれます。
これにより、業務に関連する新たな知識やスキルの習得に対しても、自ら積極的に取り組む習慣が身につきやすくなります。
個々の理解度に合わせた学習機会を提供できる
反転学習を導入すると、事前学習として行われるeラーニングでの小テストや、提出されるレポートなどを通して、講師は従業員ごとの知識の定着度や、どの部分でつまずいているかを具体的に把握できます。それによって、 個々の理解度を踏まえた学習の機会を提供することが可能になります。
例えば、理解度の高い従業員には、より高度な内容の演習問題やグループワークに取り組んでもらうなど発展的な学習を提供する一方、理解が進んでいない従業員には事前に把握した疑問点に対して個別にフォローアップしたり、補足説明の時間を設けたりするなどです。
また、個々の理解度や習熟度に応じた手厚いフォローアップができれば、社員全体の知識やスキルのばらつきもおさえやすくなります。社員間のスキルレベルの標準化にも役立つのが反転学習のメリットです。
効率の良い研修運営ができる
集合研修において反転学習を活用することで、研修時間を短縮できます。
従来型の研修の場合、集合研修中はインプット学習に多くの時間を割くことになり、演習課題に十分な時間を割けない、あるいは持ち帰りになってしまうケースもあります。
一方、 反転学習では、従業員が事前に動画視聴などでインプット学習を行うため、集合研修中のインプット学習の時間を大幅に削減可能 です。
その結果、集合研修中の多くの時間を演習課題やグループワーク、ディスカッションといったアウトプット型の学習に時間を割くことができるようになり、研修内容の理解を深めることができます。
タイムマネジメント研修を例に挙げると、従来型の研修であれば「タイムマネジメントの原則」や「自分のワークスタイルを知る」といった内容を座学で学ぶ時間が必要でした。
反転学習では、これらの内容を従業員が事前に動画などで学習しておくことで、研修の時間帯では「自分の仕事を4つに分類し、仕事の時間が妥当か振り返る」といった能動的な学習に多くの時間を割くことができるようになります。
このように、反転学習は集合研修の時間を有効活用できるため、時間効率の良い研修運営につながります。
反転学習を企業研修で活用するデメリット
反転学習にはデメリットも存在します。
実施準備にコストが発生する
反転学習の実施には、 実施準備のためのコストが発生します 。
例えば、反転学習を実施する際、企業は事前に学習教材を用意する必要があります。eラーニング教材や動画教材など、教材の種類にもよりますが、いずれも作成には時間とコストがかかります。
特に動画教材の場合、教材作成のための機材の準備や動画編集作業などが必要になるため、eラーニング教材よりもコストと時間がかかる可能性もあります。
また、集合研修の内容も反転学習に適したものとして別途準備する必要があります。
これらの準備作業には、従来型の研修以上に時間と労力がかかる可能性があることを覚えておきましょう。
学習効果が不十分になるリスクがある
反転学習には、学習効果が不十分になるリスクもあります。
例えば、従業員が事前学習に十分な時間を割けなかったり、研修で扱うテーマや内容が難解であったりする場合、研修の効果が不十分になることがあります。
その結果、 集合研修で他の参加者との理解度に差が生じ、議論についていけなくなり、最終的に業務に支障をきたすリスクが生じることがあります 。
企業研修での反転学習の実施方法
反転学習を研修に導入するには、綿密な準備と設計が必要です。
この章では、企業研修で反転学習を実施する際の5つのステップを解説します。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 目的の設定 | 研修を通して従業員にどのようなスキル・知識を習得させ、業務にどのような影響を与えたいかを明確にする |
| 2. 改善点の分析 | 既存研修の課題を洗い出し、反転学習でどのように解決できるか分析する |
| 3. テーマの設定 | 研修の目的に沿って、反転学習に適した実践的なテーマを設定する |
| 4. 事前課題の決定と共有 | 事前学習の内容を具体的に決定し、従業員に事前に共有する |
| 5. 集合研修の実施 | 事前学習の内容や作成したレポートを踏まえて、研修を実施する |
| 6. フィードバック | 研修を受講した従業員が、上司からフィードバックを受ける |
1. 目的の設定
研修を実施するにあたって、まずは目的を明確にしましょう。 目的とは「最終的に成し遂げたい事柄」のことです 。
研修の目的が不明確なままでは、適切な目標設定や効果的な研修内容を検討することができません。結果として、時間や費用をかけたにも関わらず、期待した成果を得られない可能性があります。
例えば、「新入従業員の早期戦力化」を目的とした研修の場合「3ヶ月後に部署の業務を一人でこなせる」という具体的な人材像を明確に示すことが大切です。
2. 改善点の分析
研修の目的がはっきりしたら、現状の研修における改善すべきポイントを分析します。 現状把握に十分な時間をかけて正確に改善点を理解することが、効果的な反転学習導入の鍵となります 。
改善点の洗い出しの手法として、以下の4つの方法が有効です。
| 手法 | 内容 |
|---|---|
| 社内ヒアリングやアンケートの実施 | 研修の従業員や関係者から現状の研修に対する意見や課題点を直接聞く、またはアンケートで広く意見を集めることで、具体的な問題点を把握する |
| 顧客へのアンケート | 顧客のニーズや期待を把握し、研修内容を顧客視点で見直すことで改善点を発見し、顧客満足度向上につながる |
| 競合他社分析 | 競合他社の研修内容や方法を分析し、自社の強み・弱みを客観的に評価することで、競合との差別化や効果的な研修内容に向けた改善点を洗い出す |
| フレームワークの活用 | ロジックツリーや特性要因図などのフレームワークを活用し、問題の原因を構造的に分析して根本原因を特定し、問題解決のための効果的な対策立案に役立てる |
これらの手法を用いる際は、現状把握に十分な時間をかけること、短期的な効果にとらわれず長期的な視点を持つことが大切です。
3. テーマの設定
反転学習では、 事前学習と集合研修の内容を効果的に連携させることが必要です 。そのため、テーマ設定は研修全体の成否を左右する重要なステップとなります。
反転学習は、すべての研修テーマに適しているわけではありません。効果的に反転学習を活用できるテーマの特徴を理解し、適切なテーマを選びましょう。
| テーマの特徴 | 内容 |
|---|---|
| 入力と出力のバランスが良い | ・事前学習で知識をインプットし、集合研修でアウトプットを重視する反転学習の特性を活かせるテーマを選ぶ ・一方的に知識を詰め込むだけのテーマには不向き |
| 従業員間の相互作用が期待できる | ・集合研修でのグループワークやディスカッションを通して、従業員同士が学びを深められるテーマが適している |
| 事前学習教材の作成がしやすい | ・動画教材やテキスト、eラーニング教材など、事前学習用の教材を用意する ・教材作成の手間を考慮し、比較的容易に教材化できるテーマを選ぶ |
| 従業員レベルに合っている | ・従業員の知識レベルやスキルに合わせたテーマ設定が必要 ・難易度が高すぎると学習意欲を損ない、低すぎると研修の効果が薄れてしまう |
| 業務に直結する | ・研修で得た知識やスキルを、実際の業務に活かせるテーマを設定することで、学習意欲の向上につながる ・研修内容が業務にどう関連するのかを明確にすることで、従業員はより主体的に学習に取り組むことができる |
4. 事前課題の決定と共有
反転学習では、集合研修の前に、従業員に事前学習の課題を与えます。
この 事前課題をうまく消化できるかどうかで、研修の成果が左右されます 。効果的な事前課題を設定し、共有するためのポイントを以下にまとめました。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 目的の明確化 | ・事前課題は、集合研修で何を学ぶのか、何を達成するのかを明確にする ・課題の目的を具体的に示すことで、従業員は学習の意図を理解し、主体的に取り組むことができる |
| 課題の適切な難易度設定 | ・事前課題の難易度は、従業員の理解度に合わせて、適切なレベルの課題を設定する |
| 学習時間の考慮 | ・事前課題にかかる時間を想定し、従業員の負担にならない範囲で設定する ・課題の量が多すぎると、従業員は時間内に終わらせることができず、学習効果が低下する可能性がある |
| さまざまな学習形式 | ・事前課題は、動画視聴、資料の読解、小テスト、レポート作成など、さまざまな形式で設定することができる ・従業員の特性や学習内容に合わせて、効果的な学習形式を選択する |
| 課題内容の共有方法 | ・事前課題の内容は、LMS(学習管理システム)やeラーニングシステムなどを活用して共有することで、従業員はいつでもどこでもアクセスして学習できる ・課題に関する質問や疑問を共有できる場を設けることで、従業員の理解を深めることができる |
これらのポイントを踏まえることで、従業員は事前学習を通じて、集合研修でより深い学びを得ることができます。
また、このフェーズでは、従業員に課題後のレポートを提出してもらうようにしましょう。
レポート提出には従業員の理解度の確認、疑問点の把握、従業員のモチベーション向上、自己学習力の向上という目的があります。
企業研修においても、事前課題とレポート提出を組み合わせることで研修の効果を高めることができるでしょう。
5. 集合研修の実施
集合研修の実施は、それまでの事前学習の成果を発揮し、学びを深める重要なステップです。
集合研修には「知識の活用と深化」を重視した設計が重要で、事前学習との効果的な連携がポイントです 。
事前学習で挙がった疑問点や不明点を払拭できるような研修を実施しましょう。
6. フィードバック
研修後1週間以内に、従業員が自分の行動目標を上司に共有し、フィードバックを受ける仕組みを整備することも研修効果を最大化するためには重要です。
従業員はフィードバックに基づき、次の行動を具体的に設定することで、学習内容をより深く定着させ、業務パフォーマンスの向上につなげることができます 。
また、定期的に上司と進捗状況を共有し、必要に応じて軌道修正を行うことで、目標達成に近づくことができるようになります。じて軌道修正を行うことで、目標達成に近づくことができるようになります。
反転学習を用いた研修を成功させるコツ
反転学習による研修を成功させるには、いくつかのコツがあります。
この章では、反転学習を成功に導くためのポイントを解説します。
学習管理システム・eラーニングと組み合わせる
反転学習の成功には、学習管理システム(LMS)とそれを効果的に活用したeラーニングの実施が不可欠です。
学習管理システム(LMS)を活用すれば、学習コンテンツの配信・管理、学習進捗の追跡、コミュニケーション機能など、反転学習を取り入れるうえで事前学習と集合研修を効果的につなぐ役割を果たします 。
例えば、 従業員が動画教材、資料、小テストなどをeラーニングで学習できれば、自分のペースで繰り返し学習できます。
また、小テストや課題の結果を学習管理システム(LMS)で記録できるため、講師は個人の理解度を把握でき、集合研修の内容を調整できます。
さらに、フォーラムやチャット機能を使いながら、学習者同士が疑問点を共有し、意見交換することで、集合研修に向けた準備がスムーズに進みます。
講師への質問も容易になり、疑問を解消した上で集合研修に臨むことができるようになるでしょう。
研修後アンケート・理解度テストの実施なら「AirCourse」
研修後のアンケートや理解度テストの実施は、管理がしやすい「AirCourse(学習管理システム)」がおすすめです。
AirCourseなら、動画視聴後・集合研修後のアンケート・テスト実施が容易で、必要に応じて追加の学習や声かけを行うことができます。システムに標準搭載されているコンテンツに加え、企業オリジナルのコンテンツを作成・配信することが可能です。
自社の社員研修を実りあるものにしたい、さらにアップデートしたいとお考えの方はAirCourseが分かる下記資料をご覧ください。
事前課題に取り組みやすい環境を作る
反転学習を成功させるには、従業員が事前課題にしっかり取り組んでもらう必要がありますが、 企業側による取り組みやすい環境整備が大切 です。
具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| 学習時間の確保 | 業務時間内に学習時間を確保する、目安時間を伝える |
| 事前学習ツールの提供 | 研修内容に合わせた動画教材やテキストなどを用意する |
| 質問しやすい環境づくり | 研修担当者に質問できる窓口を設ける、チャットツールを活用する |
| 学習場所の確保 | 集中できる自習スペースを用意する、オンライン会議システムを利用する |
| 事前の不安解消 | 研修内容や進め方、事前学習の目的などを事前に説明する |
事前課題では、レポートや小テストの提出を求めると効果的です。提出を必須にすることで、従業員の事前学習への取り組み姿勢が変わり、学習内容の定着が進みます。提出物から個々の理解度が把握できるので、集合研修でのフォローアップや演習内容の調整にも役立ちます。
また、従業員にはあらかじめ事前学習にかかる時間の目安を伝えておくことも大切です。
研修内容や事前学習の目的についても事前に丁寧に説明することで、従業員の不安を解消し、安心して研修に取り組む意欲を高めることができます。
企業研修における反転学習導入の成功事例
反転学習は、すでにさまざまな現場で導入されています。
この章では、反転学習を用いた事例の中から、新入社員研修と管理職研修の2つの事例を紹介します。
新入社員研修
【新入従業員的な研修に反転学習を導入し、学習効率の向上と従業員の学習促進に成功。フジ産業株式会社様】
フジ産業株式会社の新入従業員研修では、反転学習の導入により、学習効率と本体性の向上が見られました。
課題
- 事業所が国内各地に点在しており、新入社員の勤務時間や曜日も異なるため、全員が同じ時間に集まる集合研修の実施に限界があった
- 限られたマンパワーでは新入社員に必要な多様な教育メニューを十分に提供することが難しく、従来の研修形式では新入社員の理解度や主体性にばらつきが生じやすい点も課題だった
取り組み
- eラーニングシステム( AirCourse LMS )を導入し、新入社員研修では、一部に反転学習形式を取り入れた
- 「傾聴力」研修では、事前学習として、現場の良い例・悪い例を収めた寸劇動画などの教材をeラーニングで配信し、基礎知識のインプットを促しました
- 続くオンラインでの集合研修では、事前学習の内容に基づいた解説や、ケーススタディを用いたディスカッション、演習など、実践的なアウトプットに時間を重点的に充てる設計とした
- 事前学習教材は、新入社員が見やすく分かりやすいよう、10~15分程度のチャプターに分けたり、資料を添付したりする工夫をした
効果
- 反転学習の導入により、新入社員は場所や時間を選ばずに自分のペースで事前学習を進められるようになり、勤務シフトの制約を克服できた
- 集合研修では基礎知識の確認に時間を割く必要がなくなり、実践的な内容に集中できたことで、新入社員の学習効率と主体性が向上し、研修内容の理解度・定着率が高まった
- 90%以上の新入社員が反転学習の有効性を実感し、自ら学ぶ意識を高めることにつながっている
- 講師側の講義負担軽減や、管理側での受講進捗管理の容易化など、研修運営全体の効率化も実現した
管理職研修
【ムーブメントにまで発展した社内検定試験制度により、受注単価15.2%アップを実現。株式会社SHIFT様】
株式会社SHIFTは、AirCours LMSを活用して効率的な反転学習のサイクルを実現しました。
独自のキャリアアップ制度を設け、管理職に限らず幅広い従業員に対しての研修や資格取得の後押しをしています。個々の意識が高まり、個人のスキルアップだけでなく、組織全体のスキル底上げにも貢献しています。
課題
- 個人のスキルアップへの意識を高め、組織全体のスキルレベルを底上げする必要があった
- 管理職を含む幅広い従業員の継続的な学習と成長を促進する仕組みが求められていた
取り組み
- AirCourse LMSを活用し、効率的な反転学習のサイクルを構築。独自のキャリアアップ制度と連携させ、管理職に限らず幅広い従業員が自律的に学び、資格取得を目指せる環境を整備した
- 事前学習(eラーニングなど)で知識を習得し、集合研修や実務でのアウトプットを通じて定着・活用を促す反転学習の手法を取り入れた
効果
- 社内検定試験制度がムーブメントとなり、従業員個々の学習意欲とスキルが向上した。
- 結果として、組織全体のスキルレベルが底上げされ、受注単価15.2%アップという具体的な成果につながった
参考: 管理職研修にはeラーニング導入が効果的|講座例や活用事例を解説 | 人材育成サポーター
まとめ
この記事では、反転学習のメリット・デメリット、企業研修における具体的な活用方法、成功事例などを詳しく解説してきました。
反転学習は、企業の人材育成戦略に関して、非常に有効な学習手法です。
反転学習を導入することで、従業員個人の効果的なスキルアップが期待でき、結果的には組織全体の成長につながります。
この記事を参考に、反転学習を自社研修に取り入れ、人材育成の活性化を図りましょう。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。