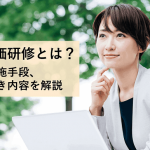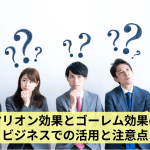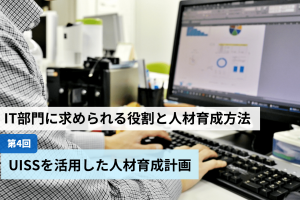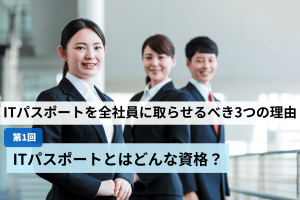人事評価制度の設計に取り組む企業の多くが、評価項目の設定に課題を感じています。「どのような評価項目を設定すれば公正な評価ができるのかわからない」「職種別に適した項目がわからない」「評価結果が人材育成に活用できていない」といった悩みは、人事制度運営において深刻な問題となっています。
これらの課題は、体系的な評価項目設計と適切な運用により解決できます。人事評価項目は、社員の成長促進と組織目標達成を両立させる重要なツールです。業種・職種に応じた適切な項目設定、明確な評価基準、そして継続的な改善により、公正で効果的な人事評価制度を構築している企業が増えています。
本記事では、人事評価項目の基本的な考え方から具体的なサンプル例、職種別の調整ポイントまで、実践的な評価制度構築に必要な情報を体系的に解説します。評価シートの作成方法や運用のコツも含め、自社に最適な人事評価システムの設計をサポートします。
効果的な人事評価項目で、組織と個人の成長を促進しましょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
そもそも「人事評価」とは?
そもそも人事評価とは、各社員の「業績・能力・勤務態度や意欲」などを客観的指標により評価することです。
人事評価で出た結果は各社員の給与や賞与、昇格などの処遇を決める指標として活用され、これを制度化したものを「人事評価制度」と言います。
人事評価制度には「等級」「評価」「報酬」の3つの機能があり、評価により等級が決まり、等級に応じて報酬も決まるなど、それぞれの機能が互いに影響し合います。
ここで重要なのが、各機能において適正かつ公平な評価項目を設定を行うことです。適切かつ公平に評価されることで、社員のモチベーションアップや現時点で欠けている能力・スキルアップの指標としての活用が可能になります。
人事評価の目的
人事評価の目的は主に4つです。以下でそれぞれを解説します。
理念や行動指針を浸透させるため
評価項目を設定することで、理念や行動指針に基づいた言動を促すことができます。各社員は人事評価で定められた評価項目を意識しながら日々の活動を行うため、理念や行動指針が徐々に社内へ浸透していくのです。
自社の理念や行動指針と社員の評価が結びつくことで、組織と社員の成長をあわせて期待できます。
ただし、組織に与える影響の大きさをふまえ、理念・行動指針を人事評価へ正確に反映させる点は十分に留意しましょう。
社員の処遇を公正に決定するため
給与や賞与、役職の昇格など、社員の処遇を公正に決定することも人事評価における重要な目的のひとつです。
明確な評価基準による公正な処遇は、社員の「頑張りに応じて評価してもらえる」という意識につながり、仕事に対する意欲や帰属意識の向上を期待できます。
人材を育成するため
人事評価は、各役職や立場に応じて求められる能力やスキルを明確にします。
各社員が「自らのポジションでは、どのような能力やスキルを高めるべきか」を理解できるため、成長意欲の向上を期待できます。
また部下の育成を担当する上司も、人事評価における評価基準を基に指導を行うため、指導内容の平準化が可能です。
以上のように人事評価は、より効果的な人材育成を実現するためにも重要といえるでしょう。
人員配置に活用するため
明確な評価項目により、各社員の特性を客観的に把握・比較することが可能となります。各社員の特性を活かした人員配置を考える上での根拠として活用できるのです。
特性に応じた人員配置は、社員の働きがい向上や定着率アップにもつながるでしょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
人事評価に必要な3つの基準
人事評価の項目は「業績評価」「能力評価」「情意評価」の3つにより成り立ちます。
それぞれについて解説します。
業績評価
業績評価は、評価期間内での業務成績を基準とした評価項目です。
評価期間の開始当初に定めた目標を、評価期間の終了時点でどの程度達成できたかによって評価します。達成できたか否かのみではなく、達成に至るまでのプロセスも含めて評価する場合が多いでしょう。
例えば、営業職を例として目標「売上30万円アップ」に対して、結果「売上25万円アップ」の場合は、目標に対しては未達となります。ただし未達であっても、目標に対して「何%まで達成できたか」や、目標達成に向け「毎日5件以上の新規訪問を行ったか」など客観的に判断できるプロセスを評価に加味するのです。
評価項目としては、目標をどの程度達成できたかを示す「目標達成度」や、目標達成のために設定した課題の達成度を示す「課題達成度」などを設けます。
なお業績評価の項目にできるのは、あくまでも「客観的に評価できる内容」のみです。「最後まで諦めずに取り組んだ」のような取り組み姿勢などについては、後述する情意評価にて評価しましょう。
客観的な評価を可能にするためにも、目標は評価期間の開始時に具体的に設定しておきましょう。
目標設定の方法やポイントについては以下の記事も参考にしてください。
参考記事:人材育成の目標とは?基本的な設定方法や管理のポイントを紹介
能力評価
能力評価は、企画力や実行力、改善力など業務遂行に求められる能力がどの程度備わっているかを基準とした評価項目です。
具体的な項目例としては、所属部署や担当業務に関して提案を行えたかを示す「企画力」、担当業務を独力で行えたかを示す「実行力」、業務改善を行えたかを示す「改善力」などがあげられます。
このほか、リーダーシップやリスク管理能力などもあり、役職や部署によって求められる能力を項目として設けます。
また業績評価が数値など客観的な指標を基に評価するのに対して、能力評価は日々の発言や行動、影響力の大きさなどを基にした主観的な評価を求められるのが特徴です。
そのため評価者となる上司は、普段から部下の言動に注目しておき、具体的エピソードや事例を根拠とした納得度の高い評価を行えるようにしましょう。
情意評価
情意評価は、勤務態度や業務に対する意欲の高さなどを基準とした評価項目です。
具体的な項目例としては、職務を全うする姿勢を示す「責任性」、部署を問わず周囲と協力できたかを示す「協調性」、自主的に業務に取り組めたかを示す「積極性」などがあげられます。
そのほか自社が重視する要素に応じて、遅刻・早退などをふくめた「勤務態度」や、研修やeラーニングなどの取り組み姿勢を示す「学習意欲」、「礼節・マナー」を項目として設ける場合もあります。
能力評価と同様に主観的な評価が必要なため、普段から部下の言動を注視しておく必要があります。情意評価に関する項目を注視することは、部下のモチベーションや帰属意識の現状把握にも役立つでしょう。
また、業績評価や能力評価とは切り離して考えることもポイントです。
人事評価項目のサンプル
ここでは評価項目のサンプルを職種ごとに紹介します。
運用時には、各部署に適した評価項目を、数字評価できる内容として「評価シート」に記載して用います。
自社の場合なら「どの項目を設けるべきか」や「どの項目のウェイトを高めるべきか」などの参考にしてください。
営業職の評価項目サンプル
営業職では、売上などの数値目標達成を重視するため「業務目標達成度」「課題目標達成度」のウェイトを高くしました。
お客様との商談や取引に関わる「企画力」「交渉力」、自身の活動スケジュールや納期に関わる「スケジュール管理」も同様です。
| 評価基準 | 評価項目 | 評価内容 | ウェイト | 自己評価 | 最終評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 目標を達成できたか | 2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 課題目標達成度 | 目標達成のために定めた 課題を達成できたか |
2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 能力評価 | 企画力 | 主体的に提案を行えたか | 2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 実行力 | 独力で業務を行えたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 改善力 | 業務改善を行えたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| クレーム対応 | クレームを適切に処理できたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| スケジュール管理 | 予定通りに行えたか (納期を守れたか) |
2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 交渉力 | 有利な条件を 引き出せたか |
2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 正確性 | ミスは無かったか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 情意評価 | 責任性 | 職務を全うできたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 協調性 | 周囲と協力・連携 できたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 積極性 | 自主的に業務に 取り組めたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 勤務態度 | 遅刻などをせず、 社内ルールを守れたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 礼節・マナー | 社内外で礼節を守り、 印象良くふるまえたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 学習意欲 | 社内研修への参加 | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 合計点 (100点満点) |
|||||
技術職の評価項目サンプル
技術職として、ここでは機器の出張修理担当者を想定します。
技術職(機器の出張修理担当者)には、「安全管理」と「技術力」の項目を設けました。
また、独力で修理を行えるかを示す「実行力」、故障などによるクレームへの対応が求められるため「クレーム対応」、お客様からの印象や業務効率を著しく低下させる再修理を防ぐために「正確性」のウェイトを高めています。
| 評価基準 | 評価項目 | 評価内容 | ウェイト | 自己評価 | 最終評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 目標を達成できたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 課題目標達成度 | 目標達成のために定めた 課題を達成できたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 能力評価 | 企画力 | 主体的に提案を行えたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 実行力 | 独力で業務を行えたか | 2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 改善力 | 業務改善を行えたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 安全管理 | 安全性に意識を向け、 事故やケガを発生させる ことが無かったか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| スケジュール管理 | 予定通りに行えたか (納期を守れたか) |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| クレーム対応 | クレームを適切に処理できたか | 2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 技術力 | 修理可能な機器が増えたなど、 新たな技術を身につけたか |
2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 正確性 | ミスは無かったか (再修理を発生させなかったか) |
2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 情意評価 | 責任性 | 職務を全うできたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 協調性 | 周囲と協力・連携 できたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 積極性 | 自主的に業務に 取り組めたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 勤務態度 | 遅刻などをせず、 社内ルールを守れたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 礼節・マナー | 社内外で礼節を守り、 印象良くふるまえたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 学習意欲 | 社内研修への参加 | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 合計点 (100点満点) |
|||||
事務職の評価項目サンプル
事務職はルーチン業務が多いため、現状の業務をより効率化できたかなどを示す「改善力」、納期通りに行えたかを示す「スケジュール管理」、ミスなく行えたかを示す「正確性」のウェイトを高めています。
とくに事務職には財務や経理、営業事務なども含まれており、組織や他部署への影響も大きいため「正確性」のウェイトを3倍に設定しました。
また、経理や労務などの専門性も求められるため「専門知識」の項目を設けています。
さらに総務や経理などコストに関わる業務に携わる機会も多いため「コスト削減」を設けました。
| 評価基準 | 評価項目 | 評価内容 | ウェイト | 自己評価 | 最終評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 目標を達成できたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 課題目標達成度 | 目標達成のために定めた 課題を達成できたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 能力評価 | 企画力 | 主体的に提案を行えたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 実行力 | 独力で業務を行えたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 改善力 | 業務改善を行えたか (効率化や時間短縮など) |
2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 専門知識 | 担当業務に関する 専門知識を習得したか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| スケジュール管理 | 予定通りに行えたか (納期を守れたか) |
2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| クレーム対応 | クレームを適切に処理できたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| コスト削減 | コスト削減に貢献できたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 正確性 | ミスは無かったか | 3 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 情意評価 | 責任性 | 職務を全うできたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 協調性 | 周囲と協力・連携 できたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 積極性 | 自主的に業務に 取り組めたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 勤務態度 | 遅刻などをせず、 社内ルールを守れたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 礼節・マナー | 社内外で礼節を守り、 印象良くふるまえたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 学習意欲 | 社内研修への参加 | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 合計点 (100点満点) |
|||||
管理職の評価項目サンプル
管理職は、より成果や影響力を重視されます。
そのため、プロセス評価である「課題目標達成度のウェイト」は1ですが、成果にあたる「業務目標達成度」は3に設定しました。
部署・部門への影響力に関する「リーダーシップ」「指導・育成」「経営方針の理解・促進」のウェイトも高くしています。
また「情意評価」に関しては、管理職はできていて当たり前という前提のもとで、あえてウェイトを低くしています。
| 評価基準 | 評価項目 | 評価内容 | ウェイト | 自己評価 | 最終評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業績評価 | 業務目標達成度 | 目標を達成できたか | 3 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 課題目標達成度 | 目標達成のために定めた 課題を達成できたか |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 能力評価 | 企画力 | 主体的に提案を行えたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 実行力 | 独力で業務を行えたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 改善力 | 業務改善を行えたか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| リーダーシップ | 部門・部署全体をまとめ上げ 業務に取り組めたか |
3 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| スケジュール管理 | 予定通りに行えたか (納期を守れたか) |
1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 指導・育成 | 部下を成長させることができたか | 3 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 経営方針の 理解・促進 |
経営方針を理解し、 部門・部署も巻き込めたか |
2 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 正確性 | ミスは無かったか | 1 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 情意評価 | 責任性 | 職務を全うできたか | 0.5 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 |
| 協調性 | 周囲と協力・連携 できたか |
0.5 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 積極性 | 自主的に業務に 取り組めたか |
0.5 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 勤務態度 | 遅刻などをせず、 社内ルールを守れたか |
0.5 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 礼節・マナー | 社内外で礼節を守り、 印象良くふるまえたか |
0.5 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 学習意欲 | 社内研修への参加 | 0.5 | 1・2・3・4・5 | 1・2・3・4・5 | |
| 合計点 (100点満点) |
|||||
ご紹介した営業職/技術職/事務職/管理職の人事評価項目サンプルを以下よりExcel形式でダウンロードいただけます。ぜひ自社の人事評価項目を検討される際にご参考ください。
評価項目を設定する際のポイント
人事評価項目を設定する際は、ただ部署ごとのサンプルを模倣するのではなく、自社の理念や行動指針を反映させたり、部署や職種に応じて評価項目のウエイトを調整したりすることが重要です。
評価項目の設定ではよくある失敗例として、「業務で不要な能力を評価する項目が存在する」や「より評価されるべき項目が、他の項目と同じ評価ウエイトになっている」などがあり、人事評価が適切に行われない原因となってしまいます。
人事評価項目の設定は、人事評価の目的を達成するために設定される項目であるため、事前に不要な項目は削除し、評価すべき項目はウエイトを高く設定しておくなど、職種・役職ごとに適切な人事評価が行えるようチェックしておきましょう。
自社の理念や行動指針を反映させる
人事評価における評価項目には、理念や行動指針を正しく反映させましょう。評価項目による具体化は、社員の理念や行動指針に即した活動につながるためです。
部署や職種に応じて評価項目を調整する
評価項目は部署や職種に応じて調整が必要です。
例えば営業職と事務職では、重視される評価項目が異なります。
営業職では「交渉力」が重視されますが、事務職では各事務処理における「正確性」がより重視されるはずです。
そこで、以下2点の調整を行います。
1点目は、異なる項目を設定する方法です。
営業職には「交渉力」を含みますが、事務職には求めません。評価対象となる業務が存在しない場合に用いる方法です。
2点目は、項目にウェイトをもたせる方法です。
営業職において重視したい「交渉力」は評価点を2倍に、同様に事務職においては「正確性」評価点を2倍にします。5段階評価なら1〜5点が2〜10点になります。
評価項目の調整により、組織として役割ごとに重視させたい点を強調でき、社員も自らがより意識すべき点を把握しやすくなるでしょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
人事評価の手順
人事評価の項目を用いた評価手順について解説します。
1. 業務目標決定
全社目標・部署目標をふまえて各個人の業務目標を決定します。
まずは本人が目標を考えて設定し、上司との面談ですり合わせを行いましょう。
業務目標設定のポイントは「結果を客観的に判断できるか」です。「数値目標」が望ましいですが、困難な場合は「客観的に確認できる状態」を目標にしましょう。
例:数値で表しにくい「整理整頓」を目標として設定したい場合
✕:倉庫の商品をつねに整理整頓する
〇:倉庫の商品がつねに「定位置にある状態」にする
また面談の際には前回の結果を振り返り、今回において能力評価や情意評価で意識すべき項目を共有しておきます。
2. 節目での個別面談
半期や四半期など評価期間の節目には個別面談を開催します。目標の進捗確認や業務に関する相談を受ける場です。
面談後は必要に応じて、期間内に目標を達成するためのフォローを行います。
大きな進捗遅れや停滞を発生させないためにも、日頃から部署内の定期ミーティングや週報・日報などで細やかな進捗確認を行うようにしましょう。
3. 評価シート記入と面談準備
評価期間が終了次第、自己評価により評価シートを記入し、上司へ提出します。
上司は自己評価の結果を確認し、評価面談に備えます。本人の評価と相違がある場合は、明確な根拠をもって説明できるように準備しておきましょう。
4. 評価面談
上司(評価する側)と部下(評価を受ける側)による評価面談を行います。
まずは部下が自分で記入した評価シートをもとに評価の根拠を説明します。説明を受けた上司は、根拠をもって評価を調整しましょう。
最終的には評価者である上司による評価が優先されますが、部下の納得を得ることが重要です。
5. 経営層や管理職での評価会議
評価面談で定まった評価を、経営層や各部署の管理職と共有して、評価の最終調整を行います。
部署間で評価の厳しさに明らかな差がある場合などには、調整を施します。
関連部署からの意見を根拠とした評価の調整もあり得るでしょう。
以上によって、より公正な評価を実現させるのです。
6. フィードバック
評価会議で定まった最終評価を本人にフィードバックします。
評価会議内で言及された内容や評価の変化はもちろんのこと、次回に向けての改善点や期待している点も含めて伝えましょう。
また、報酬制度や等級制度への反映がある場合も説明が必要です。
人事評価項目に即した人材育成を効果的に行う方法
人事評価項目に即した人材育成を効果的に行うには、まず人事評価を実施する前に評価者を育成する必要があります。制度に対する理解が不足したまま実施してしまっては、人事評価制度によるメリットが薄れるため、実施前には制度に対する評価者の理解促進に努めましょう。
また、人事評価後に被評価者が求められている能力・スキルを取得しやすい環境を整えておくことも重要です。ただ単に「評価」で終わらないようにするために、空いた時間で手軽に能力・スキルを高められる手段を構築しておくことが求められます。
評価者の教育と、被評価者が学べる環境を準備してこそ、人事評価による効果的な人材育成が可能になります。
人事評価研修を行う
人事評価研修とは、評価者に対して「人事評価制度の正確な理解を促し、公正・公平な評価および人事育成を行えるようにする」ことを目的に実施される研修です。
人事評価を実施する真の目的は組織全体の成長です。組織の成長は社員の成長なくしてありえません。社員の成長には適正な評価による公正な処遇決定や評価結果を用いた育成が不可欠です。
しかし、評価者が人事評価制度を単なる社員の評価として捉えていたり、制度の運用方法を理解していなかったりした場合、組織と社員の成長は望めません。そのため、評価者の理解不足が見受けられる場合は人事評価研修を行う必要があります。
企業向けeラーニングを活用する
人事評価制度によって足りない能力やスキルを割り出せたとしても、必要な能力・スキルを身に付ける手段が分からないために人材育成に行き着かないケースも珍しくありません。
そうした場合に会社側が研修を用意するのも1つの手ですが、日常業務に追われる社員たちが業務を気にせずに参加できる日程を設定するのは、ほぼ不可能でしょう。
そこでおすすめなのが、時間や場所にとらわれずに学習できる「eラーニング」です。
各評価項目ごとに受講すべき講座を示しておけば、能力・スキルの身に付け方が分からない状況に陥ることを予防できます。また、ネット環境さえあれば受講できるため、社員はいつでもどこでも自社の評価制度に応じた学びを得られます。
情意評価に「学習意欲」や「自己研鑽」といった項目を設け、その評価内容に「eラーニングの受講」を含めれば受講を促しやすくなるでしょう。
eラーニング成功のコツは”導入設計”にあります
eラーニングの基本的な仕組みは理解できても、実際に成果につながる運用を継続することは簡単ではありません。多くの企業が「導入したが受講率が低い」「コンテンツ作成に時間がかかりすぎる」「効果測定ができない」という課題に直面しています。
これらの課題解決には、単なるシステム選定ではなく、学習文化の醸成から効果測定まで含めた包括的な導入戦略が不可欠です。成功企業では、5つのステップで段階的にeラーニングを組織に定着させ、継続的な学習環境を構築しています。
戦略的な視点からeラーニング活用を推進する、体系的な導入アプローチを学んでみませんか。
人材育成にeラーニングを活用した事例
人事評価制度と連動した効果的な人材育成を実現するために、多くの企業がeラーニングを活用しています。評価項目に基づいた体系的な学習環境の構築により、社員の専門性向上と組織全体の成長を同時に実現している事例をご紹介します。
専門性向上と経営理念浸透を実現|C-United株式会社様

C-United株式会社様では、本部スタッフの専門性向上が重要な課題でした。約半数が店舗出身のメンバーで構成される本部において、各部署に必要な専門知識の習得が急務となっていました。
同社がAirCourseを選んだ決め手は、各部署の異なるニーズに対応できる豊富な専門コンテンツと、既存の社内教育プログラム「珈琲大学」との連携でした。経理部門には経理財務や経営戦略、マーケティング部門にはマーケティング関連コースを提供し、部署ごとに月60分の学習時間を確保しています。学習を促進するビンゴカード制度や就業時間内での学習推奨により、社員の約70%が「知識が増えた」「仕事に活用できた」と回答し、上長からも80%以上が「部下のスキルが向上した」との評価を得ています。
導入後の主な成果
- 学習者の約70%が知識向上と業務活用を実感
- 上長の80%以上が部下のスキル向上を評価
- 部署間異動時の専門知識習得を効率化
参考:C-United株式会社様のAirCourse導入・活用事例
24時間体制に対応した階層別研修を実現|医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様

地域医療を支える医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様では、24時間体制の勤務環境下での効率的な人材育成が課題でした。事務職には医療事務の専門スキルに加え、リーダーシップやKPI管理など幅広いビジネススキルの習得が求められていました。
同社がAirCourseを導入した理由は、短時間で体系的に学べるマイクロラーニング機能と、役職に応じた階層別研修の実現でした。課長クラスには「アカウンティング」「KPI管理」、係長クラスには「リーダーシップ」「フォロワーシップ」、主任クラスには「Excel統計」「実務スキル」を提供し、受講状況を人事評価に反映する仕組みを構築しています。5分程度に区切られた動画コンテンツにより、スキマ時間を活用した学習が可能となり、受講率はほぼ100%を達成しています。
導入後の主な成果
- 受講率ほぼ100%を達成
- 階層別に必要なスキルを体系的に強化
- 24時間体制でも公平な学習機会を提供
参考:医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様のAirCourse導入・活用事例
技術継承と若手育成を効率化|カナツ技建工業株式会社様

カナツ技建工業株式会社様では、「一人前になるには10年」といわれる建設業界において、社員の高齢化が進む中での効果的な技術継承が重要な課題でした。従来のOJTだけでは限界があり、ノウハウを体系的に教育できる仕組みの構築が急務となっていました。
同社は「KANATSU AKADEMY」という委員会を発足し、各部門のメンバーが講師となってオリジナルコースを作成する体制を構築しました。土木部門では新入社員教育に必要な内容をeラーニング化し、現場取材による動画撮影やPowerPointスライドを活用した質の高いコンテンツを自社制作しています。アカデミーメンバーの活動は人事考課で評価され、受講者も各コースの受講歴をもとに評価される仕組みを導入しています。
導入後の主な成果
- 技術継承の効率化とノウハウの体系化を実現
- 自社制作オリジナルコンテンツで実践的な教育を提供
- 採用時のアピールポイントとして人材育成制度を活用
参考:カナツ技建工業株式会社様のAirCourse導入・活用事例
まとめ
本記事では、人事評価の目的や基準、具体的な項目とサンプル、評価手順について解説しました。
人事評価は、業績評価・能力評価・情動評価の3つの基準で成り立ちます。評価項目には理念や行動指針や、各部署や職種に求められる能力を反映させることが重要です。
本記事のサンプルを自社に最適な評価項目および評価シートの作成に役立ててください。
各項目に即した人材育成にはeラーニングの活用も有効です。
人事評価を適切かつ効果的に運用し、組織の目標達成と社員の成長を同時に実現させましょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。