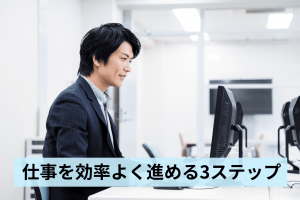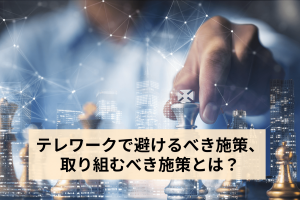変化の激しい時代を生き抜くためには、従来の知識やスキルに加え、新たな課題を発見し、解決策を生み出す力が不可欠です。
そこで現在、注目を集めているのが「デザイン思考」と呼ばれる思考法です。
デザイン思考とは、顧客中心の視点に立ち、共感に基づいて課題の本質を捉え、プロトタイプ作成とテストを繰り返すことで、革新的なソリューションを生み出すことができる思考法です。
企業は社内でデザイン思考を普及させることで、顧客を起点とした新たなサービス・製品開発が可能となるだけではなく、組織をアップデートすることもできます。
この記事では、デザイン思考の基本的な概念から、5つのプロセス、人材育成への具体的な導入方法まで、分かりやすく解説します。
成功企業に学ぶ”人材育成のノウハウ”を無料でお届け
現場の人材育成がなかなか成果に結びつかない…。教育担当者の多くが直面するこの壁を、実際に乗り越えた企業の事例から解き明かします。
従来の研修やOJTで成果が出ない真の理由と、デジタル時代ならではの効果的な育成モデルを厳選事例とともに公開。「時間がない」「効果が見えない」という課題に、他社が語らない人材育成の現実解が具体的な打開策を提示します。
これまでの育成施策に行き詰まりを感じている方こそ、『デジタル時代の人材育成モデル』をぜひご活用ください。
目次
デザイン思考とは?
デザイン思考とは、ユーザーの視点から課題を見つけ、解決策を生み出すデザイン的な考え方を取り入れる思考法です。
デザイン思考はビジネスにおける課題解決、特に商品やサービスの開発・改善に役立ちます。
デザイン思考では、従来の「企業視点」の開発ではなく、「ユーザー視点」――あくまでもユーザーを起点に潜在的なニーズを捉え、真に求められる商品やサービスを創り出すことが目的です。
ユーザーは物質的な充足だけでなく、体験や感情といった精神的な満足を求めるようになりました。
そのため、企業はデザイン思考によってユーザーの深層心理を読み解き、潜在ニーズに応える必要性が高まっています。
デザイン思考の5つのプロセス
デザイン思考は、以下の5つのプロセスを繰り返すことで、ユーザーのニーズを真の意味で捉えた課題解決やイノベーション創出を実現します。
- 共感
- 定義
- 概念化
- 試作
- テスト
それぞれのプロセスについて詳しく見ていきましょう。
1. 共感(Empathize)
ユーザーの行動やニーズ、課題を深く理解するために、観察やインタビューなどを通して情報を集めます。
例えば、新しい飲料の開発を行う場合、ユーザーがどのタイミングで飲料を購入し、どのように消費しているかを観察することが重要です。また、インタビューを通じて、現状の飲料に何を求めているのか、どんな不満を感じているのかを具体的に聞き出します。ポイントは、ユーザーから得られる情報が断片的である可能性もあるため多様な視点から情報を収集すること、「ユーザーはなぜそう感じるのか」を掘り下げることです。
ユーザーになりきって考えると、まだ顕在化していない隠れたニーズを発見できる可能性が高まります。
2. 定義(Define)
共感フェーズで得られた情報から、真の課題を明確に定義します。
例えば、前述の飲料開発であれば、「忙しい朝でも手軽に栄養を摂りたい」というユーザーのニーズが見えてきたとします。この場合、課題を「手軽さと栄養価を両立する飲料の提供」と定義することで、目標が具体化されます。課題を特定する際には、ユーザーの視点を忘れず企業側の都合や制約を直接反映しないよう注意が必要です。
また、課題をできるだけシンプルかつ具体的に絞り込むことも重要です。曖昧な定義では、次のアイディア創出の段階で迷走するリスクが生じます。
3. 概念化(Ideate)
定義された問題に基づき、さまざま 様々な解決策を自由に発想します。
このフェーズでは、発想の幅を広げることが重要です。例えば、飲料の例では、「ストロー付きの栄養ドリンク」「携帯用のパウダー飲料」など、形式やアプローチを問わずアイディアを出します。ブレインストーミングを活用し、メンバー間で自由な発想を生み出す環境を整えることが肝心です。
コツとして、質より量を重視し、制約を一旦取り払ってアイディアを出すことです。そのためにも、 批判的な意見や否定的な態度によってアイディアの広がりを抑制しないように、建設的な雰囲気作りが求められます。
4. 試作(Prototype)
アイディアを具体的な形にするために、試作品を作成します。
例えば、飲料商品の場合、実際に試飲可能なサンプルを試作することで、ユーザーから直接的なフィードバックをもらうことができます。この段階では、完成度を求めすぎるのではなく、アイディアを簡易的に形にすることが重要です。プロトタイプの目的は、アイディアを検証し、次に進むためのヒントを得ることにあります。
試作を進める際のコツは、プロトタイプを複数作成し、比較しながら進めることです。また、誰にでも使用方法が伝わるよう、できるだけシンプルにすることがポイントです。
5. テスト(Test)
試作品をユーザーに試してもらい、フィードバックを得ることで、アイディアの有効性を検証します。
飲料の例では、試飲会を開催し、味、使いやすさ、パッケージデザインなどについて感想を集めることが考えられます。ユーザーからの意見をもとに、試作品を改善したり、新たなアイディアを創出したりすることで、より優れた製品が生まれる可能性が高まります。
このフェーズの注意点は、フィードバックを鵜呑みにせず、本質を見極めることです。ユーザーが表現する感想や意見を深く掘り下げ、「なぜそう感じたのか」を探求することが重要です。また、フィードバックの結果を迅速に反映し、次の改善につなつなげるサイクルを回すことが成果を向上させます。
従来の問題解決手法との違い
消費者のニーズが多様化している現代においては、従来の問題解決手法だけでは不十分です。消費者が潜在的に抱えている問題や、まだ顕在化していないニーズを捉えることが、競争優位性を築くうえで重要になります。
従来の問題解決手法は、論理的思考に基づき、既存のデータや過去の経験から問題の原因を分析し、解決策を導き出す方法でした。効率的に解決できるというメリットがある一方で、「すでにわかっている問題」しか解決できないというデメリットがあります。
例えば、既存製品の不良率が高いという問題に対して、従来の手法では過去のデータを分析し、不良が発生しやすい工程を特定することで解決策を導き出します。
一方デザイン思考は、ユーザーインタビューやフィールドワークを通じてユーザーの行動や感情を深く理解し、そこから得られたインサイトを元に、プロトタイプを作成します。そして、検証を繰り返すことで、ユーザーにとって本当に価値のある解決策を創り出せるのがデザイン思考なのです。
それぞれの特徴をまとめると以下の通りです。
| 項目 | 従来の問題解決手法 | デザイン思考 |
|---|---|---|
| アプローチの視点 | 論理的思考に基づく企業中心のアプローチ | ユーザー中心のアプローチ |
| 課題の対象 | 「すでにわかっている問題」の解決が主 | 潜在的な問題や隠れたニーズの発見と解決 |
| データ活用 | 過去のデータや経験を分析して解決策を導出 | フィールドワークやインタビューを通じてユーザーインサイトを取得 |
| 解決策の検証プロセス | 既存データに基づいた一次的な検証が中心 | プロトタイプを作成し、ユーザーからのフィードバックを通じて反復的に検証 |
| 成果 | 問題の原因を特定し効率的な解決策を提示 | ユーザーにとって真に価値のある革新的な解決策を創出 |
“成果を出す”人材育成とは?解説資料を無料公開
OJTや集合研修を実施しているものの、「思うような効果が感じられない」「継続的な成長につながらない」といった課題を抱えていませんか。
その背景には、デジタル時代の働き方に適さない従来型の育成モデルがあります。では、実際に成果を上げている企業は、どのような人材育成モデルを構築しているのでしょうか?
『デジタル時代の人材育成モデル』では、現代の課題を解決する新しい育成アプローチと、それらを実現するための具体的な手法を、成功企業の実例をもとに詳しく解説しています。育成を見直したい方は、ぜひご覧ください。
なぜ人材育成にデザイン思考が必要なのか?
Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった「VUCA」という言葉で表現されるほど変化の激しい時代において、課題に対してユーザー目線から柔軟にアプローチできる人材を育成することこそが、企業の成長には重要な課題となっています。
このため、企業活動においては、まず人々が直面する「困りごと」を特定し、理想の未来を設定し、現状と理想のギャップを埋めるべく解決策(ビジネス)を構築することが急務です。
デザイン思考のプロセスでは、市場調査による表層的なニーズの把握にとどまらず、仮説検証を繰り返すことでユーザーが真に求めているものを把握し、新しいビジネスと価値創造が可能となります。
特に、若手社員にデザイン思考が身につけば、組織全体の主体的に課題解決に取り組む姿勢や自律的な学習を維持することが期待できます。
社内にデザイン思考を取り入れるメリット
デザイン思考をビジネスに取り入れることで、さまざまなメリットがあります。その中から4つのメリットを紹介します。
社内でアイディアの提案が習慣化する
デザイン思考のプロセスを繰り返し実践することで、社内でアイディアの提案が習慣化されます。
ユーザーのニーズを深く理解し、共感に基づいたアイディアを創造する中で、自然とアイディア発想力が養われていきます。
これらのプロセスを繰り返すことで、アイディアを「思いつく」だけでなく「形にする」ことを意識するようになります。
また、他者からのフィードバックを通して、アイディアをブラッシュアップしていく力も身につきます。
特に若手社員にとって、アイディアの提案はハードルが高いと感じられるかもしれません。しかし、デザイン思考では具体的な手順に沿ってアイディアを生み出し、検証していくため、心理的なハードルが下がり、積極的にアイディアを提案できるようになります。
イノベーションの創出がしやすくなる
デザイン思考により、顧客の潜在的なニーズを捉えることで、イノベーションの創出へとつなげることができます。
デザイン思考は、顧客中心の起点でのアプローチを重視し、共感を通して真のニーズを理解することに重点を置きます。
従来型の開発プロセスでは、市場調査に基づいて既存製品の改良を行うことが一般的で、顧客自身も気づいていない潜在的なニーズを掘り起こすことは難しい状況でした。
一方、デザイン思考では、顧客の行動観察やインタビューを通じて、本質的なニーズを理解することに努めます。
多様性を重視した風土を作ることができる
デザイン思考のプロセスでは、共感・問題定義・アイディア創出・プロトタイプ・テストの各段階で、チームメンバーとの対話や協働が不可欠であるため、互いを尊重した組織風土づくりを促進します。
特に「共感」のフェーズでは、ユーザーインタビューなどを通して多様な意見やニーズを丁寧に汲み取ることが求められます。
また「アイディア創出」のフェーズでは、ブレインストーミングなどを通して自由に意見を出し合い、それを組み合わせたり発展させたりすることで、革新的なアイディアを生み出せる可能性もあります。
これらのプロセスを通じて、多様な意見を尊重し、それらを建設的に活用する姿勢を身につけることができます。
組織力の強化につながる
デザイン思考は、多様なメンバーの視点を取り入れながら価値を共創していくプロセスであるため、組織力の強化にもつながります。
デザイン思考のプロセスは、年次に関係なく、チームメンバーそれぞれの強みを活かすことができます。
例えば、共感フェーズでは、高いコミュニケーション能力を持つメンバーが活躍します。
また、アイディア創出フェーズでは、発想力豊かなメンバーが中心となって、自由なアイディアをどんどん出し合えるようになるでしょう。
プロトタイプ作成フェーズでは、実際に手を動かして形にすることが得意なメンバーが活躍します。
テストフェーズでは、分析力に優れたメンバーが検証結果を客観的に評価し、次の改善につなげます。
それぞれのフェーズで各メンバーが強みを発揮することで本質的な価値創造が可能となります。
デザイン思考を取り入れる際の注意点
デザイン思考を社内に導入する際には、さまざまな課題や障壁に直面する可能性があります。それを回避し、効果的に活用するためには、適切な準備と運用方法を理解し実践することが重要です。
適切なチーム編成を行う
社内でデザイン思考を取り入れる際、メンバーの選定には注意が必要です。
チーム編成には共感力や創造力、協調性などが求められ、これらの能力を備えたメンバーを選ぶことが重要です。しかし、スキルや経験だけでは判断が難しい場合もあるため、選定には十分な時間と配慮が必要です。加えて、年功序列や組織の慣習が障壁となる場合があるため、自由闊達なチーム編成を心がけ、フラットな環境を作ることが成功の鍵となります。
取り入れるシーンを間違えない
デザイン思考は、明確な課題や顧客ニーズが存在しない段階では効果が限定的になることがあるため、適切なシーンで導入することが大切です。
ゼロベースで新たなビジネスや製品を創出する場合よりも、顧客の具体的な課題を深掘りしたい場合や、既存のプロセスを改善したい場合に効果を発揮します。導入するシーンを慎重に見極めれば、より確かな成果を得ることができます。
結果に固執しすぎない
デザイン思考の成功は、必ずしも初期段階で明確な結果を求めることではありません。過信しすぎて「必ず成功する」という考えに陥らないよう注意が必要です。
デザイン思考はプロセスを重視するアプローチであり、試行錯誤を繰り返しながら改善していくことに価値があります。そのため、初期の失敗や結果の不確実性を恐れず、プロセス全体を通じて学びを得る姿勢を持つことが大切です。
デザイン思考と他の思考法との違い
デザイン思考と混同しやすい思考法として、アート思考と論理的思考が挙げられます。
この章ではデザイン思考と、それぞれの思考法との違いを解説していきます。
アート思考との違い
アート思考とデザイン思考の大きな違いはアイディアの起点です。
アート思考は、思考する主体の目線から0→1でアイディアを生み出す思考法です。
常識に囚われない自由な発想が特徴ですが、それが必ずしも顧客のニーズを満たすものになるとは限りません。
一方、デザイン思考はユーザーの本質的な課題の特定と解決が目的となっています。
論理的思考との違い
デザイン思考と論理的思考は、問題解決に至るまでのアプローチに違いがあります。
デザイン思考は、ユーザー中心のアプローチを取り、共感を通じて課題を深く理解し、プロトタイプ作成とテストを通じて、新しい解決策を創造することに重点を置きます。
まだ明確な問題が定義されていない場合や、新しい製品やサービスを開発する場合に有効です。
ユーザーの潜在的なニーズを掘り起こし、革新的なアイディアを生み出すことができます。
一方で論理的思考は、既存の知識やデータに基づき、分析的に問題の原因を特定し、解決策を導き出します。
従来の問題解決方法は、論理的思考が使われることが多く、すでに明確な問題が存在する場合に有効です。
例えば、売上が減少している原因を分析し、対策を立てる場合などは、論理的思考が適しています。
デザイン思考を効果的に導入する方法
社内でデザイン思考を導入・普及させていくためには、従業員に継続的なトレーニングの機会を提供することで、普及・浸透させていく必要があります。
この章では社内での具体的な取り組みについて紹介します。
実践形式の研修を取り入れる
従業員にデザイン思考を効果的に身につけてもらうには、実践形式の研修を取り入れることが重要です。
ワークショップ形式で、実際のビジネス課題に取り組むことで、より深い理解と実践的なスキルを習得できます。
また、チームでの共同作業を通じて、コミュニケーション能力や問題解決能力の向上も期待できるでしょう。
加えて、研修後も継続的にデザイン思考を実践していくために、社内での勉強会やコミュニティ活動を実施することも効果的です。
研修では、顧客インタビュー、アイディア創出、プロトタイプ作成、テスト・評価といったデザイン思考の過程をグループワークで体験できるコンテンツを用意しましょう。
デザイン思考の事例を共有する
他社の成功事例や失敗事例を共有することで、従業員はデザイン思考の具体的なイメージを掴みやすくなります。
以下には、デザイン思考を取り入れたAppleのiPod開発事例を示します。
Appleは、多様な専門家チームを結成してユーザーの音楽体験を観察・分析し、その結果、「すべての音楽をポケットに入れて持ち運ぶ」という潜在的なニーズを発見します。この洞察を基に、スクロールホイールによる直感的な操作性やiTunesとのオートシンク機能を開発し、ユーザーの利便性を大幅に向上させました。
さらに、試作品をユーザーに試してもらい、フィードバックを活用して製品を改良し続けた結果、iPodは市場で圧倒的な成功を収め、音楽の楽しみ方そのものを変える存在となりました。
この事例は、デザイン思考がユーザー中心の課題解決と市場でのイノベーション創出にどれだけ有効かを示す好例です。従業員に共有することで、デザイン思考のプロセスを実際の業務に活かすヒントを提供できます。
研修後のフォローアップを重視する
デザイン思考の研修効果を最大化するためには、研修後も継続的な学習と実践の機会を提供する必要があります。
フォローアップの方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- メンター制度
- 勉強会・ワークショップ
- コミュニティサイト
- プロジェクト参加
これらのフォローアップ施策を通じて、研修参加者は継続的にデザイン思考を学び、実践する機会を得ることができます。
組織文化や制度の面からも浸透を図る
デザイン思考を浸透させるには、研修やワークショップだけでなく、組織文化や制度といった側面からも働きかける必要があります。
特に若手社員は、新しい考え方や手法を受け入れやすい傾向があります。組織全体でデザイン思考の導入を新たに推進することで、若手社員も興味を持ってくれるでしょう。それが、企業の未来を担う人材の育成や、企業全体のイノベーション創出力の向上につながります。
組織文化や制度の面から浸透させる方法としては、主に以下が挙げられます。
| 項目名 | 内容 | 目的・効果 |
|---|---|---|
| 新入社員研修への導入 | 入社直後からデザイン思考に触れる機会を設ける | 早期に思考法を習得し、その後の業務に活かす |
| 若手社員主体のプロジェクトの実施 | デザイン思考を活用したプロジェクトに積極的に参加させる | 実践的な経験を積ませ、スキルアップを図る |
| 若手社員向けのワークショップ開催 | デザイン思考ワークショップを開催 | 実践的なスキル習得を支援する |
| 社内表彰制度の導入 | デザイン思考を用いた優れた成果を上げた社員を表彰する | モチベーション向上と更なる挑戦を促す |
デザイン思考と相性のよいフレームワーク
デザイン思考は、他のフレームワークと組み合わせることで、さらなる効果が期待できます。
この章では、デザイン思考と特に相性の良い4つのフレームワークを紹介します。
共感マップ
共感マップは、デザイン思考と相性の良いフレームワークの一つです。
共感マップとは、顧客のニーズを的確に捉えるための手法です。
共感マップによって顧客の行動や思考、感情を可視化することで、より深く顧客を理解できるため、商品開発やサービス改善に役立ちます。
顧客が何を考え、何を感じ、どのような行動をとるのかを深く掘り下げることで、隠れたニーズを明らかにするプロセスは、デザイン思考とも相関性が高いです。
共感マップを作成する際には、以下の6つの要素を考慮します。
- SEE(顧客がの目に映るもの)
- HEAR(顧客の耳に入ってくる情報)
- THINK and FEEL(顧客の思考や感情)
- SAY and DO(顧客の発言や行動)
- PAIN(顧客の悩みや課題)
- GAIN(顧客が求める解決策や価値)
これらの要素を埋めるためには、顧客へのインタビューが不可欠です。
インタビューを通じて得られた情報を整理し、共感マップに落とし込むことで、顧客のニーズを明確に捉えることができます。
作成した共感マップは一度きりではなく、定期的に見直し、ブラッシュアップしていくことが重要です。
SWOT分析
SWOT分析とは、以下の4つの要素を洗い出して現状を客観的に分析するフレームワークです。
- 強み(Strengths): 組織の内部で活用できるポジティブな要素や特徴
- 弱み(Weaknesses): 組織の内部で改善が必要なネガティブな要素や課題
- 機会(Opportunities): 組織の外部環境から得られるチャンスや有利な要因
- 脅威(Threats): 組織の外部環境から影響を受けるリスクや障害
デザイン思考のプロセスにおいて、SWOT分析は特に「共感」と「問題定義」の段階で役立ちます。
例えば、顧客へのインタビューを通して得られた情報を元に、SWOT分析を行うことで、顧客のニーズや潜在的な問題点を明確にできます。
SWOT分析を行う際のポイントは、客観的な視点を持つことです。
感情や主観に左右されず、事実ベースでの分析が大切です。また、分析結果を元に具体的なアクションプランを策定することで、より効果的に活用できます。
ビジネスモデルキャンバス(BMC)
ビジネスモデルキャンバス(BMC)は、以下の9つの要素で構成されます。
- 顧客セグメント:提供価値を届ける対象となる顧客層
- 顧客との関係:顧客との接点や関係性を築く方法
- チャネル:顧客に価値を届けるための手段や経路
- 提供価値:顧客が得られる利益や解決される課題
- 収益の流れ:ビジネスが収益を生み出す仕組み
- 主要活動:ビジネスモデルを実現するために必要な活動
- 主要な資源:ビジネスを運営するために必要な資産
- 主要パートナー:ビジネス成功のために協力する外部組織や企業
- コスト構造:ビジネスモデルを運営するために発生するコスト
これらを1枚のシートにまとめると、ビジネスの全体像を効果的に把握することができます。デザイン思考のプロセスで生まれたアイディアを、具体的なビジネスモデルに落とし込む際に役立ちます。
カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップとは、顧客がサービスや商品を利用する際の行動や思考、感情を時系列で可視化するものです。
顧客体験全体を俯瞰することで、顧客の行動を理解し、課題や改善点を発見することができます。デザイン思考のプロセスで得られた顧客への共感を、具体的な改善策に落とし込む際に役立ちます。
ジャーニーマップの作成は、顧客視点を取り入れるための重要な手法です。顧客がどのような行動をとり、どのような感情を抱いているのかを詳細に分析することで、顧客体験の向上につなげることができます。
まとめ
この記事では、デザイン思考の基本的な概念から、5つのプロセス、人材育成への具体的な導入方法まで、分かりやすく解説してきました。
デザイン思考は、ユーザー中心のアプローチで革新的なアイディアを生み出す、変化の激しい現代において役立つスキルです。
メリットや注意点を踏まえたうえで、自社の人材育成にお役立てください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。