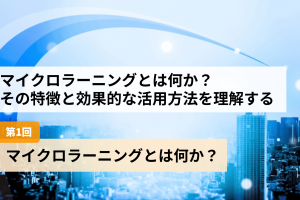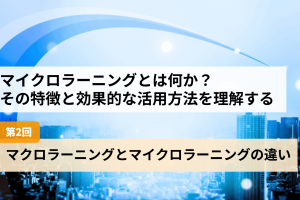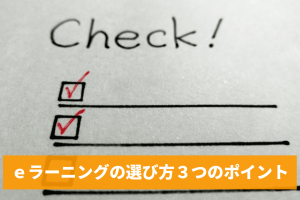eラーニング以外にも言える事ですが、eラーニングとして提供されているサービスは多数あるため、導入する際には数社の資料を取り寄せて比較することが一般的になっているようです。
しかし、それぞれのサービスの特徴や価格体系など異なることが多いため、どのように比較し、選べばよいのかが難しくなっています。 eラーニングの導入に失敗しないためにも、今回は選び方の10個のポイントについてご紹介します。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
eラーニングを選ぶ10のポイント
eラーニングの選び方10個のポイントについて、それぞれ解説します。
1. 短期的な視点だけで選ばないこと
- 個人情報保護などのコンプライアンス研修を年に1回行うのが必須になってしまったが、集合研修では困難なのでeラーニングを利用したい
- 新入社員研修が忙しいので、一部でもeラーニングで代用したい
- 派遣社員の方にとにかく法定時間だけeラーニングで勉強してもらって教育実績を作りたい
といった対象や範囲が限定されたeラーニングの活用のご相談が増えています。
いずれもeラーニングを利用した方が効率よくなる話ですので、利用方法として間違っているわけではありませんが、それだけでeラーニングサービスを選んでしまうのは少し問題がありそうですね。
少子高齢化、100年LIFE、働き方改革、人材不足、企業が経営課題として人材面で直面する課題は拡大している中で、eラーニングのプラットフォームは今後その解決の根幹を成す重要な機能になる可能性があり、その 選択と導入は重要な経営判断 と言っても過言ではありません。
直面している短期的、部分的な課題への対策としてだけで考えるのではなく、中期的、長期的な視点で、自社の人事戦略、人材育成方針をどうするのか、そのためには何が必要なのか十分に検討する必要があります。
しかしながら、すぐに中長期的な人事戦略や育成方針を決めるのは難しい場合もありますから、その際には 「小さく初めて、大きく育てる」 ことができるような 拡張性のあるeラーニングプラットフォームを選択することが重要です。
経営環境の変化によっては戦略や方針の変更もあり得るでしょうから、柔軟性や進化への対応が可能なものを選択する視点も重要です。
短期的なニーズに合わせて作り込みすぎたり、短期的なニーズに対応するだけで拡張性が低いものを導入してしまうと、発展性が見込めませんね。
eラーニングサービスは、中長期的な視点も持って検討し、経営判断として選択と導入を進めましょう。
2. 機能の豊富さだけに捉われないこと
eラーニングサービスを検索して調べ始めて、各社の機能を一覧表に並べて比較している人事担当者をよくみかけます。
とにかく書き出した機能項目について対応の可否だけを埋めようとして、できあがった一覧表で一番成績の良いものを選ぼうとします。
比較する項目も調べていくうちにどんどん拡大し、本当に必要な要件から外れてしまっているものもたくさん盛り込まれてしまいます。
「同じ値段なら機能が豊富な方がお得」に感じますし、各社の「機能を比較したという根拠があると上司へ説明し易い」など理由は様々なようです。
しかしながら、この検討の仕方では本当に自社にとって最適なeラーニングサービスは見つかりません。
そもそもなぜeラーニングを導入したいのか、eラーニングを導入してどのような教育を実現したいのか、そのためにはどんな要件が必要なのか、そこから考えて必要な機能についてだけ比較すべきでしょう。
機能が豊富なeラーニングサービスを導入したが 使われない機能がたくさんある といったケースはよくあります。
また、同じ機能でもスペックが異なることも多々あります。
例えば「動画対応」といっても容量、画質、配信方法、視聴環境、画面の見易さ、利便性など様々な要素があります。 本当に必要な機能については十分な比較やトライアルが必要です。
安易に選んでしまうと項目として機能はあるが、十分なスペックがないため使い難い、やりたいことができないといったこともあり得ます。
各社の過剰な機能PRに惑わされずに、自社にとって本当に必要なeラーニングサービスを見極めましょう!
3. 管理者の使い勝手だけでなく受講者目線で選ぶこと
eラーニングサービスを選ぶ際、管理者となる人事担当者が検討することが多いため、検討の視点が管理者目線だけになってしまい、導入後に受講者から使い難いといった不満が生じることも少なくないようです。
例えば、受講者の多くはスマーフォンなどのモバイルで利用するが、管理者は会社のパソコンで利用するため、モバイルでの利用検証をあまりせずに導入したところ、スマートフォンでは画面が見にくいとか、モバイルの通信環境では動画がうまく再生されないなどといったことが生じています。
また、管理者は利用説明書を熟読するだけの余裕がありますが、受講者側には説明を受ける余裕もなく操作することが求められたりもします。
そのため管理者と受講者の間には、立場や環境の違いがあることを考慮して検証しなくてはいけません。
受講者のIDで、受講者と同じ環境で、受講者として利用 してみること。
もしくは実際に受講者となる従業員数名で受講側のトライアルを行ってみることが必要でしょう。
4. カリキュラムが充実していること
eラーニングのカリキュラムが充実しているか確認しましょう。カリキュラムが充実していれば、学習者はより多くの知識やスキルを習得できます。また、カリキュラムが充実していることで、学習者が自分の目的や興味に合わせたコースを選びやすくなります。
加えて、カリキュラムの難易度や進め方も重要なポイントです。自分のレベルに合ったコースを選ぶことで、学習効果がより高まります。さらに、コースの進め方が分かりやすいかどうかも確認しましょう。学習者が分かりにくいままカリキュラムを進めてしまうと、学習効果が低下しかねません。
カリキュラムの内容で失敗しないためにも、取り扱っている学習内容が明確かどうかを確認しましょう。カリキュラムのタイトルだけではなく詳細ページも確認して、具体的な学習内容やトピックスをチェックしましょう。
5. eラーニングが使いやすいこと
使いやすいeラーニングを選ぶようにしましょう。使いやすいeラーニングであれば、学習者はストレスなく学習を進められるからです。一方で、使いにくいシステムだと、操作に時間がかかったり、学習者が混乱したりするケースがあります。その結果として、学習効果が低下してしまう事態も想定されるのです。
そうしたトラブルを回避するためにも、eラーニングのシステムが使いやすいかどうかをチェックしましょう。まず、システムのレイアウトや操作方法が分かりやすいかどうかは大切なポイントです。次に、学習コンテンツが使いやすいかどうかも重要です。例えば、テキスト・動画・音声ファイルなど、学習コンテンツが分かりやすく、直感的に利用できるかどうかを実際に使用して確かめましょう。
6. 学習の管理が行いやすいこと
eラーニングを選ぶ際には学習の管理が行いやすいことにも注目してみましょう。
具体的にチェックしたいポイントは以下の通りです。
- 学習者ごとの進捗管理ができる
- 学習履歴の記録ができる
- 成績の管理ができる
- 学習者へのフィードバックが行える
- 学習のスケジュール管理ができる
このように、eラーニングを選ぶ際には、学習管理機能が充実していることが重要です。学習者の進捗状況を把握し、必要な指導やサポートを提供することで、効果的な学習環境を提供しましょう。
7. 学習成果を評価する仕組みがあること
学習成果を評価する仕組みが備わっているかチェックしましょう。eラーニングは自己学習の形式が一般的ですが、学習成果を確認して評価する仕組みがあると、より効果的な学習を提供できます。例えば、以下のポイントを確認してみてください。
- テストや課題が用意されている
eラーニングの中には、学習成果を確認するためのテストや課題が用意されているものがあります。テストや課題があると自分が学んだ内容をどの程度理解できているかを確認できます。
- 報酬制度がある
学習成果を評価するためにポイントや認定証などの、報酬制度が用意されているeラーニングもあります。報酬制度を活用することで、学習意欲を高められます。
- 学習の進捗状況が自動的に記録される
eラーニングによっては学習の進捗状況を自動的に記録するシステムが用意されているケースがあります。学習者は手間をかけずに、自分の進捗を確認できます。
8. サポート体制が充実していること
サポート体制が充実しているeラーニングを選ぶようにしましょう。サポート体制が整っていれば、学習者が悩みや疑問を抱いても解決できる環境を提供できます。例えば、学習中に何らかのトラブルが発生した場合や、学習コンテンツについて理解が不十分な場合、サポート体制が充実しているeラーニングであれば、適切な対応を行えるのです。具体的なサポート体制に関するチェック項目としては以下の通りです。
- 問い合わせ窓口の有無
- 問い合わせ方法(メールや電話など)
- 対応可能な時間帯
- FAQ
加えて、サポート担当者の力量も重要なチェックポイントです。例えば、eラーニングのサポート担当者が専門的な知識を持っているかどうか、丁寧かつ迅速に対応してくれるかどうかを確認しましょう。
9. 評判やレビューに満足できること
評判やレビューにも目を通して、満足できるeラーニングを選びましょう。まずは、eラーニングのサイト内に掲載されている、レビューや評価をチェックすることをおすすめします。eラーニングのサイトなのでポジティブな内容の意見が目立ちますが、サービスへの理解を深めることができ参考になる言葉も見つかるはずです。
次に、eラーニングについての口コミサイトやレビューサイトを活用してみましょう。サービスのマイナス面も含めてさまざまな意見が掲載されているので、自分に合ったeラーニングを選ぶことに役立てられます。ただし、信頼性の高いサイトを選ぶことが大切です。
さらに、同業者の意見を聞くことも有益です。自分と同じ分野で働いている方にeラーニングについての評判や、おすすめのサービスを聞いてみましょう。悩みや課題が共通していれば、eラーニングを選ぶ際の参考になるはずです。
10. 異なるデバイスで学習できること
異なるデバイスでeラーニングの学習を進められるサービスを選びましょう。異なるデバイスで学習が可能だと、学習者が自由に学習できる環境を整えられます。例えば、学習者が自宅のパソコンで学習する場合もあれば、外出先でスマートフォンやタブレットで学習する場合もあります。異なるデバイスで学習できることにより、学習者は自由に学習環境を選択できるようになるのです。
異なるデバイスで学習を行えるeラーニングを選定できたとしても、いくつかの項目は実際に確認が必要です。まず、eラーニングのシステムや学習コンテンツが、それぞれのデバイスで正常に動作するか確認しましょう。スマートフォンやタブレットでの操作性や、パソコンと異なる環境での動作安定性などについてチェックできていると安心できます。次に、異なるデバイスで学習する場合に、学習状況や履修履歴などの情報が同期されるかどうかも確認しましょう。
【1分完了】『eラーニングシステム選定比較シート』をダウンロードする
eラーニングを導入する企業が増えている
本題に入る前に、なぜeラーニングを導入する企業が増えているのでしょうか。
eラーニングの概要やメリットについて簡単に整理しておきましょう。
そもそもeラーニングとは
eラーニングは、電子技術を利用してインターネット上で行われる学習のことを指します。
コンピューターやスマートフォンなどのデバイスを使用して、オンラインで講義を受けたり、ビデオやテキストなどの教材を利用したりすることが可能です。企業の教育や研修において、従業員のスキルアップや業務効率化に貢献する教育手段として、eラーニングを導入する企業が増えています。
eラーニングが注目される背景
eラーニングが注目される背景としては、いくつかの理由が挙げられます。まず、技術の進化によってeラーニングのサービス品質が向上したことは大きな要因です。スマートフォンやタブレットなどのデバイスが普及し、インターネットによる高速通信環境が整備されたことでeラーニングが容易に実施できるようになりました。学習者のスタイルに合わせてストレスなくeラーニングで学べる環境が社会全体で広がっています。
次に、リモートワークが増加したこともeラーニングを後押ししています。新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの企業がリモートワークを導入するようになりました。このため、対面式の研修やセミナーが難しくなり、eラーニングが注目されるようになったのです。高品質な映像と音声で学べるeラーニングを採用する企業が増加しています。
eラーニングのメリット
eラーニングには数多くのメリットがあります。ここでは代表的なeラーニングの利点について解説します。
- 時間や場所を選ばない
eラーニングはインターネットで行われる学習のため、場所や時間にとらわれることがありません。従業員は自分の都合の良い時間や場所で学習できるため、仕事と学習を両立させることができます。
- 学習効果を可視化できる
eラーニングは学習データを記録できるため、従業員の学習状況を把握できます。これにより、従業員の学習効果を可視化でき、適切なサポートを提供できます。
- コストを抑えられる
従来の対面式の研修やセミナーでは、会場や講師の確保や移動などに費用がかかります。一方、eラーニングであれば、これらの費用を大幅に削減できます。また、従業員が自分の都合の良い場所で学ぶことができるため、生産性の向上につながるというメリットも創出できるのです。
実際の導入事例を見て、自社に最適なツールを選びましょう
eラーニングのメリットについて、実際に導入した企業の成功事例や効果測定の方法を詳しく紹介しています。自社と似た業種・規模の企業の事例を参考に、導入後の効果をイメージしてください。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
eラーニングの効果的な活用事例
ここでは、実際に選定ポイントを重視してeラーニングシステムを選択し、効果的に活用している企業の事例をご紹介します。
既存コンテンツの豊富さと使いやすさを重視した選定|フジ産業株式会社様

産業給食、メディカル給食、学校保育園給食を提供する「食のスペシャリスト」であるフジ産業株式会社では、事業所が国内各地に点在し、勤務時間帯や曜日が異なる社員への効率的な教育が課題となっていました。365日3食が必要な福祉施設や交代制勤務の工場など、全員が同じ時間に集まることが困難な業態特性から、集合研修には限界を感じていました。
同社がeラーニングシステム選定で重視したのは、「シフト勤務の社員も含め、いつでも受講できること」「受講履歴を管理できるテレワーク環境下での教育体制整備」「振り返り学習ができる環境づくり」の3点でした。機能面では「自社オリジナルコースのアップロード」「アンケート」「受講管理」を求め、最終的に3社まで絞り込んで比較検討を実施しました。
AirCourseを選択した決め手は、受け放題の既存コンテンツが豊富で早期に社員教育を開始できる点でした。教育メニュー不足を感じていた同社にとって、幅広い動画研修が導入後すぐに利用でき、内製コンテンツでは賄えない自己啓発分野もカバーできることが魅力的でした。加えて、使いやすいユーザーインターフェースと利用しやすいコストパフォーマンスも評価されました。
導入後は、毎年開催していた安全衛生講習会のeラーニング化により全社員受講を実現し、若手育成研修の事前課題や階層別研修での活用など、様々な場面で効果を発揮しています。受講者からは「会場に行かなくても受講できる」「空いた時間に受講できる」といった声が寄せられ、講師側の負担軽減と受講者の利便性向上というwin-winの環境を構築できています。
選定・導入後の主な成果
- 豊富な既存コンテンツにより早期の教育開始を実現
- 集合研修の制約を解消し全社員への教育機会提供
- 講師負担軽減と受講者利便性向上のwin-win環境構築
- 受講履歴管理による未受講者への確実なフォローアップ
自社オリジナルコース作成の柔軟性を重視した選定|株式会社セリオ様

働く女性の支援を軸に就労支援事業、放課後事業、保育事業を展開する株式会社セリオでは、人材採用後のオンボーディング不足による早期離職が課題となっていました。専門職に必須の研修で手いっぱいとなり、本来実施したかったビジネススキル教育や階層別研修にリソースを割くことができない状況でした。
同社では総合職だけでなく保育士・栄養士などの専門人材も在籍し、保育園の稼働を止められないという制約から、全社一律での集合研修は現実的ではありませんでした。そのため人材育成手法はeラーニング一択となり、7社ほどを検討して最終的に2社まで絞り込みました。
当初は各社が用意している既製の研修コンテンツ利用を想定していましたが、事業部ごとに独自の研修コンテンツが必要という結論になり、自社オリジナルのeラーニングコースを柔軟に作成できることが重要な選定要件となりました。また全社員にPCを貸与していないため、共用PC・タブレットでの受講に対応したマルチデバイス対応も必須条件でした。
AirCourseを選択した決め手は、これらの要件をすべてクリアしていた点に加え、もう1社では自社作成動画のアップロード時に追加料金が発生することや、タブレット非対応だったことでした。さらに、受け放題の標準コースが1章数分単位で構成されており、まとまった時間を確保しにくい事業特性に適したスキマ時間学習が可能な点も高く評価されました。
導入後は、社長自らが会社のミッション・ビジョンを伝える「Serio ism研修」や「インサイダー取引未然防止研修」などのオリジナルコースを作成し、標準コースと組み合わせて全社員共通の必須コースとして活用しています。
選定・導入後の主な成果
- 自社オリジナルコース作成の柔軟性により事業部特有のニーズに対応
- マルチデバイス対応でPC未貸与社員も受講可能な環境を実現
- 短時間コンテンツによりスキマ時間を活用した効率的学習を促進
- 直感的操作により導入後の問い合わせ発生を最小限に抑制
コンテンツの質と量、マイクロラーニング設計を重視した選定|医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様

600床以上を有する総合病院として地域医療を支える福岡徳洲会病院では、約1,800名の職員が24時間体制で勤務する中、事務職員に求められるスキルの多様化が課題となっていました。医療事務の専門スキルに加え、リーダーシップやKPI管理、多様性への理解など、現代の病院経営に必要な幅広いビジネススキルの体系的習得が求められていました。
しかし、24時間体制の病院運営では夜勤やシフト勤務があるため、全員が一堂に会する集合研修は困難でした。加えて、コロナ禍における感染リスクを考慮すると、集合形式の研修実施はさらに制約が大きくなっていました。このような背景から、効率的で公平に教育を届けられるeラーニングの導入が検討されました。
同社がeラーニングサービス選定で重視したのは、「24時間体制の不規則な勤務時間への対応」と「専門スキルとビジネススキルをスキマ時間で学べる環境整備」でした。複数のeラーニングサービスを比較検討した結果、AirCourseのコンテンツは講師の話し方やリズム感が統一されており、背景やスライドのデザインも一貫性があることで、どのコンテンツを受講してもストレスなく学べる環境が整っていることが高く評価されました。
さらに、AirCourseの多くのコースが30分程度の内容を5分程度に区切ったマイクロラーニング設計となっており、まとまった時間の確保が困難な医療現場の職員でも、朝の10分間や業務の合間などのスキマ時間を活用して無理なく学習を進められる点が決め手となりました。
導入後は事務職を対象とした階層別研修を実施し、課長クラスには「アカウンティング」「KPI管理」、係長クラスには「リーダーシップ」「フォロワーシップ」、主任クラスには「Excel統計」「実務スキル」など、役職ごとに必要なスキルを体系的に提供しています。受講状況を人事評価に反映する仕組みの導入により、受講率はほぼ100%に近い水準を達成しています。
選定・導入後の主な成果
- コンテンツの質と一貫性により医療現場の職員もストレスなく学習
- マイクロラーニング設計で24時間体制勤務でもスキマ時間活用が可能
- 階層別研修の体系化により役職ごとに必要なスキルを効率的に習得
- 人事評価連動により受講率ほぼ100%の高い学習定着を実現
参考: 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様|AirCourse導入事例
まとめ
eラーニングを導入した事がある方も、これから導入する方も、eラーニングの乗り換えや新規導入に失敗しないためにも、正しい選び方をご紹介いたしました。
- 短期的な視点だけで選ばないこと
- 機能の豊富さだけに捉われないこと
- 管理者の使い勝手だけでなく受講者目線で選ぶこと
eラーニングを提供している各社ありますが、惑わされず、自社で必要なものを 「経営判断」 という認識で選んで頂ければ幸いです。
社員研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
社員研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。