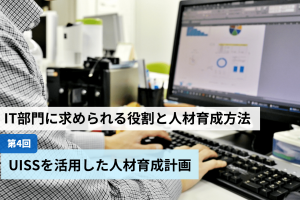1on1の導入を検討・実施する企業が増える中、多くの管理職や人事担当者が効果的な運用に課題を感じています。
「1on1を導入したが形式的な面談になってしまう」「部下が本音を話してくれず信頼関係が築けない」「上司のスキル不足で期待する効果が得られない」といった悩みは、人材育成とマネジメント強化において深刻な問題となっています。
これらの課題は、1on1の本質を理解し、効果的な実施方法を身につけることで解決できます。1on1は、上司と部下が1対1で対話する重要なマネジメント手法であり、部下の成長促進、信頼関係の構築、そして組織力強化を実現するツールです。
適切な目的設定、効果的な進め方、そして継続的な改善により、社員のパフォーマンス向上と離職防止を同時に実現している企業が増えています。
本記事では、1on1の基本概念から注目される理由、具体的な実施手順、効果を高めるポイントまで、実践的な1on1運営に必要な情報を体系的に解説します。上司に必要なスキルや注意点も含め、自社に最適な1on1制度の構築をサポートします。
効果的な1on1で、強いチームと成長する組織を実現しましょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
1on1とは
1on1とは、社員のパフォーマンスやモチベーションを向上することなどを目的として、上司と部下が1対1の状況で自由なテーマを用いて面談を行うことです。1on1ミーティングとも呼ばれます。
一般的には、頻度が週1回〜月1回ほど、所要時間が30分~1時間ほどになります。
1on1は、もともとアメリカの企業から始まった手法ですが、現在では日本の企業でも積極的に導入されています。
面談との違い
1on1と面談の違いは、以下のとおりです。
| 違い | 1on1 | 面談方法 |
|---|---|---|
| 方向性 | 上司と部下が対話 | 上司(評価者)から部下へ |
| 目的 | 日々の悩みの解消や部下の成長の促進、信頼関係の構築などを図る | 指示や指摘、目標や進捗の管理、フィードバックなどを行う |
面談は上司から部下へ一方向で伝える場であり、人事面談や評価面談、目標設定面談などがあります。
一方、1on1ミーティングは、上司と部下が対話する双方向な話し合いの場であり、さまざまな目的に合わせテーマを変えて行われます。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
1on1が注目されている理由
1on1ミーティングは、リモートワークの普及やキャリアの多様化などを背景に、注目されています。
それぞれ解説しますので、自社に適しているか確認しましょう。
リモートワークの普及
新型コロナウイルスの流行や働き方改革でリモートワークが普及したことで、働き方が大きく変化しました。
近年では、他の社員とのコミュニケーションの機会が減り、誰が何の作業をしているのか把握しづらい、どのような悩みを抱えているのかが見えづらいといった問題が浮き彫りとなってきています。
1on1ミーティングは、そのようなリモートワークで生じるデメリットの解消に効果的です。上司と部下の良好な関係を構築しつつ、部下の進捗を把握できます。
誰にも相談できずに問題を抱えてしまうリスクの軽減にも活用できる手段です。
キャリアの多様化
現代では転職が当たり前の時代になり、目指すべきキャリアが多様化しています。
そのなかで企業には、社員一人ひとりのモチベーションや生産性を維持するために、本音で話し合える環境の構築や価値観を共有できる場を提供することが求められています。
1on1ミーティングは、これらの変化に対応して一人ひとりに向き合える方法です。そのため、多くの企業が導入を検討していると考えられます。
1on1の目的
企業が1on1を行う主な目的には、部下の成長促進や上司と部下における信頼関係の構築、組織力の強化などが挙げられます。
部下の成長促進
1on1の最大の目的は、部下の成長促進を支援して能力を引き出すことです。
上司は、部下が普段言えないような悩みや不安を打ち明けられるように話を進め、適切なアドバイスやフィードバックを行い、現状と課題を整理できるようにサポートを行います。
上司は部下と双方向のコミュニケーションがとれるように意識しつつ、「今後なにをすべきか」「どのように業務に取り組むべきか」を部下が気づけるよう対話することが重要です。
部下の口から直接話してもらうことで、部下自身も自分で意識していなかった思いが明確化できます。
自分のやりたいことや価値観が自覚できると、部下も意識的に業務に活かせるようになるでしょう。
上司と部下の信頼関係の構築
上司と部下が定期的に本音で話し合い、信頼関係を構築することも1on1の目的の一つです。
この目的の場合には、上司はあえて業務と関係のない趣味や世間話など、短時間でのアイスブレイクを活用するのがおすすめです。
気軽に話せるような雰囲気を作り、部下の意見や考え方を尊重しながら肯定的に捉えてあげると、円滑なコミュニケーションが実現できるでしょう。
うまく話を聞き出せると、部下は「自分の話を聞いてもらえている、理解してもらえている」と感じてくれる可能性があります。
上司は「安心感をもってもらえている、本音で打ち明けてくれる」と、自信につながりやすくなります。
組織力の強化
1on1は部下の成長促進と上司と部下の信頼関係の構築が実現できるため、組織全体の生産性やパフォーマンスの向上が期待できます。
うまく1on1を進められると、自主性をもって働ける社員の増加や社員同士のコミュニケーションの活性化につながるでしょう。
話し合った内容に合わせ、担当する業務の割り振りなどを行えると、事業全体の業務効率にもつながります。
1on1のメリット
1on1には、社員のパフォーマンスやモチベーションが向上する、上司と部下のコミュニケーションが円滑化するなどのメリットがあります。
自社の期待するメリットが得られるか、確認しておきましょう。
部下のパフォーマンスやモチベーションの向上
上司が1on1を通じて、実践に活かせるアドバイスをすることで、部下は困難を乗り越える力を身に付けられます。
業務の効率的な進め方や行き詰った課題の解決策につながるヒントが得られ、部下の業務に対するパフォーマンスを向上させられるでしょう。
また、パフォーマンスが向上すれば成功体験も多く得られるようになり、部下のモチベーションアップにもつながります。
上司と部下のコミュニケーション円滑化
上司と部下が1対1で話すことで、お互いの性格や仕事、プライベートでの考え方、出来事などを共有しやすくなります。
悩みや不安などを本音で話せる機会があると、互いの理解や信頼につながり、普段のコミュニケーションにも良い影響を及ぼします。
離職の防止
上司が、部下に一人で抱え込ませないように寄り添ってあげると、結果として離職防止につながります。
1on1では、上司と部下が、雑談や業務上のアドバイス、仕事・プライベートでの悩みの共有など、さまざまなテーマで向き合います。
上司は部下の心理や状況を整理でき、エンゲージメントやモチベーションの低下を察知しやすくなるでしょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
1on1の注意点
1on1には、時間的な負荷がかかる、内容によっては効果が得られないなどの注意点もあります。それぞれの対策を確認して、自社で行う際に取り入れてみてください。
時間的な負荷がかかる
1on1は一般的に、月に1回、30分程度の時間をかけて行います。加えて、準備の時間も必要であり、時間的な負荷はかかるでしょう。
対策として、育成を強化したい社員を絞り実施する、1on1支援ツールを活用するなどの方法を取り入れるのがおすすめです。
内容によっては効果が得られない
1on1は、テーマや話の進め方を誤ると効果が得られなくなります。信頼関係を構築できているつもりになり、雑談だけで終わってしまう可能性もあります。
上司は、日頃からコミュニケーションを重視し、意見や本音を言いやすい環境を作っておくのがおすすめです。
また、1on1の目的を改めて把握し直し、部下の特性や習熟度、前回のミーティング内容なども踏まえ、聞き出す内容や効果的なアドバイスを考えておきましょう。
1on1の基本的な流れ
1on1ミーティングを実施するときには、以下の流れで行うと効果的です。
- ミーティング前に必要な準備をする
- ミーティングをすることを伝えて日時・場所を決める
- ミーティングを実施する
- 次回のミーティングを設定する
各段階で重要なポイントを解説しますので、実施の際に役立ててください。
ステップ1.ミーティング前に必要な準備をする
1on1によくある悩みとして、部下が乗り気ではない、部下と話すことがない、話が続かないことが挙げられます。
そうした状況にならないようにするには、部下の情報を正確に把握すること、話のテーマを決めることが重要です。
部下の情報をできるかぎり把握する
1on1前に部下の情報をなるべく把握することは、部下の信頼獲得につながります。
現在どういった業務を担当しているのか、何が得意で何を苦手とするのかなどの業務に関することはもちろん、仕事への姿勢や考え方などのよりマインドの部分や、そもそもの性格や趣味など人となりの部分もできるかぎり把握しておきましょう。
| 把握すべき情報 | 詳細 |
|---|---|
| 業務状況 | ・担当業務の内容 ・現在の進捗状況 ・課題や問題点 |
| スキル・能力 | ・得意な分野/苦手な分野 ・伸ばしたいスキル |
| キャリアプラン | ・今後のキャリアプラン ・キャリアプラン実現のための課題 |
| 仕事に対するマインド | ・仕事への価値観 ・仕事に対する考え方 ・仕事への姿勢 ・職場環境への満足度 |
| 部下自身のこと | ・性格 ・趣味 |
これらの情報は、人事評価制度や目標管理シート、日報、周りの社員の話、日頃の様子から確認できます。加えて、本人との普段のコミュニケーションを通して得られる情報も参考になるでしょう。
事前に情報を集めると、部下を知った気になってしまいますが、そのような態度で1on1に臨むと部下に知ったかぶりと見られ、かえって信頼を得にくくなります。情報収集は、部下自身の言葉を引き出すためにするものと意識することが大切です。
話のテーマを決める
1on1において、有意義なものにするには、話すテーマを事前に決めておくことが重要です。テーマを設定する際は、1on1の目的である「部下の成長促進」「上司と部下の信頼関係の構築」「組織力の強化」に沿うと決めやすいでしょう。
| 目的 | テーマ例 |
|---|---|
| 部下の成長促進 | ・部下自身の強みや長所 ・業務におけるやりがい ・今後やりたい業務 ・従事するうえで大切にしていること |
| 上司と部下の信頼関係の構築 | ・業務で悩んでいること ・チーム内の人間関係で困っていること ・睡眠への影響 ・ストレス発散状況 ・残業や持ち帰り仕事のこと ・働き方についての考え方 ・上司への要望 |
| 組織力の強化 | ・目標の達成度合い、プロジェクトの進捗状況 ・現状の課題 ・課題解決のために行った部下のアクション ・プロジェクトのリソース ・体制に対する要望 |
これらのテーマを事前に部下と共有しておくことで、1on1の準備がしやすくなります。
ステップ2.ミーティングをすることを伝えて日時・場所を決める
1on1を実施する目的を共有したら、具体的な日時と場所を決定します。
日時は部下の1on1に対するモチベーションが低下しないように、部下のスケジュールを優先して調整しましょう。
また、場所も部下の希望を聞き、リラックスして話せる場所を選ぶことが大切です。ラフな話題であれば、会社の会議室ではなく、カフェやラウンジなど開放的な場所にするのもいいでしょう。
日時と場所が決まったら、お互いに忘れずにスケジュールに登録します。また、急な予定変更にも対応できるように、事前に連絡方法や変更手順などを決めておくとベターです。
ステップ3.ミーティングを実施する
ミーティングを実施する際にはいくつかのポイントがあります。ポイントを押さえたうえで実施しましょう。
まずは他愛のない話から始める
1on1では、まずは他愛のない話から始めましょう。
時間が限られているからといっていきなり仕事の話を始めると、部下は身構えてしまいます。部下の話を引き出すためにも、雑談を挟み、リラックスしてもらえるようにしましょう。
雑談には週末の過ごし方や趣味、最近面白かったこと、あるいは季節の変わり目や最近の気候についての話などがありますが、これらの話題はあくまで例です。部下のキャラクターに合わせて適切な話題を選びましょう。
もし部下が乗り気ではない場合は、上司のほうから自分の趣味や最近の出来事などを話すのもひとつです。
傾聴・質問・自己開示を意識しながら部下の話を聞く
雑談で部下の緊張がほぐれたら、事前に設定したテーマの話に移ります。部下が現在置かれている状況や本人の心境について、正確に理解するよう努めましょう。
現状を理解する際は、部下に話してもらうことを優先します。そのためにも、上司は「傾聴」「質問」「自己開示」の3つを意識することが大切です。
これらをバランスよく行うことで、部下が主体性をもって話してくれるようになります。
傾聴
傾聴とは、相手の言葉に真剣に耳を傾け、その背景にある感情や考えを理解し、共感しようと努めることです。傾聴では単に話を聞くだけでなく、相槌を打ったり、要約したり、内容がわからない場合は丁寧に聞き返したりします。傾聴を心がけると、部下に真摯な態度が伝わり、部下もより安心して話せるようになります。
質問
質問は、部下の思考を深め、自ら課題や解決策を見つける手助けとなります。質問には、一般的に、相手に自由な回答を求めるオープン型と、回答の選択肢を狭めるクローズド型があります。オープン型は相手の考えや気持ちを深く理解できる一方、相手に心理的な負担を与えます。クローズド型はオープン型よりもそうした負担はないものの、話がそこで終わってしまいやすい特徴があります。オープン型の質問をした際に部下が答えに窮している場合はクローズド型に切り替える、クローズド型の質問をしながらここぞというときにオープン型の質問で深堀りするなど、両者を上手に使い分けることが、質問で部下の言葉を引き出すポイントです。
自己開示
自己開示は、「自分も前にこんなことがあった」「自分はこのように思う」と上司自身の経験や考えを共有することです。自己開示は、上司の人間性を伝え、部下との信頼関係を築く上で役立ちます。もちろん、自己開示ばかりしていると部下が主体性をもてなくなってしまうので、発言に困っているときに用いるなど、タイミングを見計らうことが重要です。
課題の特定と行動の決定
部下から聞いた話をもとに、現状の課題を特定し、これからの行動を決定します。
課題の特定では、「今の話で特に解決したい点はどこかな?」「うまくいかない理由は何だと思う?」といった質問を投げかけます。あくまで、本人にネックとなっている課題を見つけてもらうことが重要です。
課題が明確になったら、「何か考えている対策はある?」のように、部下がどのような行動をとる予定かを確認してみましょう。
回答に困っている様子がみられるようであれば「例えば、○○をしてみるのはどうかな?」「私がサポートできそうなことはある?」などと投げかけて、行動の決定まで導きます。
課題の特定や行動の決定は、部下のよりパーソナルな部分に触れることになるため、信頼関係がある程度できてからのほうがスムーズな場合があります。
部下がまだ心を開いていないように感じるときは、無理をせず、次回以降の1on1に譲るのもひとつです。
ステップ4.次回のミーティングを設定する
1on1は一度きりではなく、継続してこそ効果を発揮します。
ミーティングの最後に、次回の日程を決めましょう。その場で次回の予定を決めてしまうのが望ましいですが、もし難しければ、候補日をいくつか提示し、部下に選んでもらうとスムーズです。
また、1on1で話し合った内容を踏まえ、次回までに部下が取り組むべき宿題を設定します。宿題は、部下の成長につながる具体的な内容にしましょう。
目標達成のための小さな一歩となるような内容が理想的です。上司も部下の宿題達成をサポートするために、できることを明確にしておきましょう。
あわせて、次回の1on1で話すことを事前に決めておくと、双方が事前に準備できます。部下に話したいテーマを考えてきてもらうように促すと、主体性を育むことにもつながります。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
1on1で上司が身につけておきたいスキル
上司が円滑なコミュニケーションを行うためのスキルを習得していれば、より効果的に1on1を実施できます。
主に必要とされるスキルは、以下のとおりです。
| スキル | 概要 |
|---|---|
| コーチングスキル | 主に対話を通じて対象者の能力・気力を引き出し、自己成長や自発的な行動を促すためのスキル。上下関係を意識せず並走しながら目標達成を目指す |
| 傾聴力 | 相手の話を耳で聞くだけでなく、目で表情やしぐさを見ながら、相手の感情や真意に寄り添い共感を示すスキル |
| 質問力 | 不明点を解消する的確な問いかけを行うスキル。部下が誤った解釈や望ましくない発想をもっている場合に、質問を通じて本人に気づきを与えることも可能 |
| ロジカルシンキング(論理的思考) | 物事の結果と原因を明確にとらえ、両者のつながりを考える思考法。さまざまな悩みごとや不安などの課題を結果と原因に分解・整理して、本質を見極めるのに役立つ |
| クリエイティブシンキング(水平思考) | 前提を設けず水平方向に発想を広げる思考法。固定観念や既存の手法にとらわれず自由に考えることで、新しい発想につなげる |
| クリティカルシンキング(批判的思考) | 物事の本質を見極めるために、あえて疑いをもって考える思考法。批判のために誤りや欠点を探すわけではなく、本質を見極めて改善やリスク回避につなげる |
企業としては、上司にスキルを与えるための研修を実施するのも一つの方法です。
1on1でよくある質問
1on1に関して、よくある質問にお答えします。
1on1は誰がやるべき?
1on1は、直属の上司が担当するのが一般的です。直属の上司であれば、日常的に接する機会が多く、部下の仕事ぶりや課題を把握しやすいというメリットがあります。
ただし、必ずしも直属の上司が担当しなければいけないわけではありません。上司は部下を評価する立場にあるため、部下の心理的安全性が確保されにくいという理由から、先輩社員や人事部が担当するケースも見られます。
重要なのは、1on1の目的を達成するために、誰と実施するのが最適かを柔軟に考えることだといえます。
1on1でやってはいけないことは?苦痛を与えないようにするには?
1on1は間違ったやり方をしてしまうと、部下に苦痛を与える可能性があります。特に以下の行動は避けなければいけません。
- 「君には無理だよ」「なぜできないのか私にはよくわからない」といった否定的な発言をする
- 部下からの言葉や質問に対して「でも……」と否定的な返答をする
- 「私はこうするべきだと思う」と一方的に考えを押し付ける
- 「○○さんはできたのに、君はできていないよね」「自分のときはこうだったのに、どうしてそれが難しいのかな」と他人や上司自身と比較する
- 過去の失敗を蒸し返す
- 距離感を無視したプライベートな質問をする
- ミーティング時に記録を取らず、これまでの会話内容を忘れる
- ミーティングのキャンセル・リスケが多い
ただ、これらの行動は、部下への配慮があれば自ずと避けられるものです。
部下だったらどう思うか常に考えることが、1on1をより効果的なものにし、部下の成長を促進、良好な関係構築につながる第一歩です。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
人材育成にeラーニングを活用した事例
未来人材育成でオリジナル研修コンテンツを構築|カナツ技建工業株式会社様

創業以来、土木・建築・水処理施設などの社会資本整備とそのメンテナンスを通じて住みよい地域づくりに貢献するカナツ技建工業株式会社様では、建設事業において「一人前になるには10年」といわれる中、社員の高齢化も進み、効果的な技術継承が大きな課題となっていました。また未来を担う人材のために、ノウハウをきっちりと教育できる仕組みを整える必要がありました。
同社では社内横断的なプロジェクトで「人材育成・人づくり」を目的にeラーニングシステムを活用してOJTの効率化を図る計画が持ち上がり、他社比較検討の結果AirCourseを選定しました。現在は各部門からメンバーを選出した「KANATSU AKADEMY(カナツアカデミー)」という個別委員会が発足し、アカデミーのメンバーが講師となってオリジナルコースを作成しています。現場への取材・撮影から動画編集まで自社で実施し、渾身のオリジナル研修コンテンツを構築しています。
導入後の主な成果
- 各部門の専門ノウハウをeラーニング化で体系的に継承
- アカデミーメンバーの評価制度組み込みでモチベーション向上
- 採用におけるアピールポイントとして人材育成への取り組みを活用
自主学習文化醸成でDX人材育成基盤を構築|エフエムジー & ミッション株式会社様

化粧品や栄養補助食品、ファッション関連品の製造・販売を行うエフエムジー & ミッション株式会社様では、マネジメント層から「各社員のボトムアップ」「マネージャー層の育成」「会社方針の理解度向上」といった要請が高まっていました。しかし、既存のサービスでは受講履歴が残らないため受講管理ができず、DXやリスキリングへの対応や社員の意識付けも課題となっていました。
AirCourse選定の決め手は、料金の安価さとコンテンツの数・質の充実、そして自社作成動画を配信できる機能でした。営業部門のセールス研修、階層別研修、会社方針に関するマネジメント層からのメッセージ配信など様々な場面で活用し、標準コンテンツと自社コンテンツを組み合わせた効果的な運用を実現しています。受講をKPIに含めて評価に反映させることで受講を促進し、関連会社間でも共通コンテンツと各社独自コンテンツを柔軟に運用しています。
導入後の主な成果
- 「セルフラーニング・自己学習」の風土が形成され始める
- DXやリスキリングに対応するための基礎を構築
- 関連会社間での効率的なコンテンツ運用を実現
参考:エフエムジー & ミッション株式会社様のAirCourse導入事例
24時間体制の医療現場で実現した公平な学習機会|医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様

600床以上を有する総合病院として地域医療を支える医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様では、約1,800名の職員を対象とした教育体制の強化が課題でした。24時間体制で運営される病院では、夜勤やシフト勤務により全職員が同じ時間に集まることが困難で、看護部、医療技術部、薬剤部、リハビリテーション科、事務部など多職種にわたる職員それぞれに適した研修を効率的に実施する必要がありました。
AirCourse導入の決め手は、スマートフォンでいつでもどこでも学習できる利便性と、豊富な標準コンテンツに加えて自社独自のコンテンツも配信できる機能でした。現在は新入職員研修から管理職研修まで幅広く活用し、感染対策、医療安全、接遇など医療現場に必要な研修を体系的に配信しています。夜勤明けや休憩時間など個々のペースで受講でき、全職種に公平な学習機会を提供することで、医療の質向上と職員の成長を同時に実現しています。
導入後の主な成果
- 24時間体制でも全職員に公平な学習機会を提供
- 多職種対応の体系的な研修体制を構築
- 個々のペースでの学習により医療の質向上を実現
参考:医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院様のAirCourse導入事例
まとめ
1on1は、うまく実施できると、部下の成長を促進させ、上司と部下の信頼関係の構築や組織力の強化につながります。
働き方が変化してコミュニケーションの機会が不足している昨今においては、上司と部下が1対1でしっかりと話し合える貴重な時間です。
1on1を効果的に行うためには、気軽に話せるような環境を構築するとともに、上司が部下の意見・考え方を尊重しながら課題解決に導けるスキルを習得することが求められます。
円滑なコミュニケーションを実現させ、部下の成長と組織成長の貢献につなげていきましょう。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。