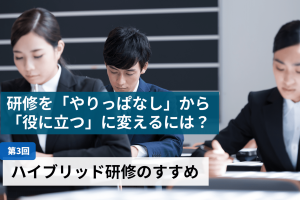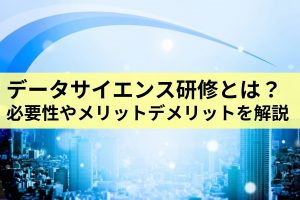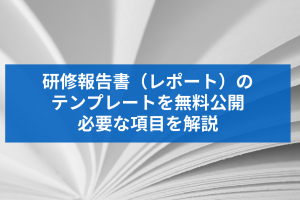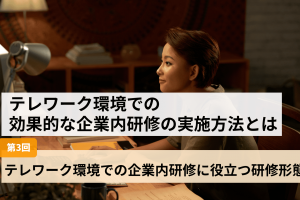多くの企業で研修目標設定を実施していますが、「目標は設定したが研修効果が実感できない」「形式的な目標設定に留まり受講者の意識が向上しない」「目標と実際の研修内容が連動していない」といった課題を抱えています。しかし、これらの課題は適切な目標設定手法と運用方法により解決できます。
研修の目標設定には、研修内での目標設定と研修後に向けた目標設定の2種類があり、受講者の成長、組織の成果、目的意識の向上を実現するために重要です。
成功する研修目標設定の核心は、受講者の成長と組織の成果を直結させる具体的で測定可能な目標を設定することです。研修内での目標と研修後の行動目標を明確に分け、定量的な指標を盛り込むことで、受講者の学習意欲向上と組織の成果創出を同時に実現できます。
本記事では、研修目標設定の重要ポイントからビジネスマナー・マネジメント・コンプライアンスなど13のテーマ別目標設定例まで詳しく解説します。効果的な研修目標設定により、組織の成長を加速させましょう。
テーマ別・階層別研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
テーマ別・階層別研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。
目次
研修における目標設定の重要ポイント
効果的な研修目標を設定するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。
受講者の意識を変え、研修効果を最大化するための目標設定の重要ポイントを3つ見てみましょう。
先に研修自体の目的を受講者に理解させる
研修の目標が正しく設定されるためには、先に研修自体の目的を受講者に理解させます。研修の目的が曖昧な状態では、受講者は目標を設定できません。
- なぜこの研修を開催したのか
- 組織、社員が抱えている課題が何か
- 研修で学んでほしいことは何か
研修の目的が分かると、受講者は目標を設定しやすくなります。
また、目的がブレにくくなり、研修の成果が発揮されやすくなります。
自社に合った最適な学習プログラムを導入しましょう
クラウド型eラーニングサービス「AirCourse」では、1,000コース・6,000本以上の動画研修を用意しており、幅広いテーマに対応しております。
テーマ別・階層別研修をはじめとする「動画研修の体系図・コースリスト」を無料でお配りしておりますので、気になる方は実施したい研修目的にフィットするかご確認ください。
研修のなかで目標を発表させる
受講者が自分の口で目標を発表すると、常に目標を意識して研修に挑むことができます。発表する目標は、研修内での目標と研修後に向けた目標のいずれも対象となります。
また発表した目標は周りと共有することができるメリットがあります。他の受講者の目標を聞くと、自分の目標と比較することができるため、設定した目標が鮮明になります。
立てた目標は、研修の前半で発表してもらいます。そして、研修の終盤で目標が達成できたのかを改めて発表させると、研修で学んだことが受講者に残りやすくなります。
研修内で目標を発表させることで、達成に対する意欲と責任感が高まります。
目標は具体的な内容にする
研修で設定する目標は具体的な内容の方が意識しやすいです。以下のような目標設定は悪い例です。
- 一生懸命に頑張る
- 何かを学んで持ち帰る
- 次の仕事に活かす
これらの目標設定では、研修で何を学ぼうとしているのかが曖昧で、研修のメリットが活かせません。研修の目標は、誰が見ても分かるように具体的な内容で設定しましょう。
例えば、以下のような目標設定が理想的です。
- ハラスメントの概要を理解する
- 明日からビジネスマナーが利用できるようになる
- セキュリティを理解して新人教育できるようになる
目標設定は、タイトルと内容に分けることをおすすめします。
先ほどの例であれば、目標設定のタイトルが「セキュリティを理解して新人教育できるようになる」になります。
詳細の内容は「セキュリティの種類を学び、セキュリティ違反を起こしていないか自分の行動をチェックする。よくあるセキュリティ事故を書き留めておき、部署に新人が配属されたときに教育できるよう、体系化してまとめておく」となります。
また、目標は数値化して定量的な測定ができるようにしておくといいでしょう。例えば、ビジネス文書の研修を受講した時の目標設定は「ビジネス文書のレビュー時に指摘件数を1件以内とする」や「ビジネス文書の作成スピードを30%向上させる」などです。
定量的な目標設定は、研修の前後で受講者が成長したことを実感しやすくなります。研修の目標が具体的であればあるほど、スキルは身に付きやすく研修の成果が発揮されます。
研修における目標設定の具体例|テーマ別
研修における目標設定の具体例をテーマ別にご紹介していきます。研修の内容によって設定する目標も変わりますので、紹介する具体例を参考にしてみてください。
ビジネスマナー研修
ビジネスマナー研修とは、主に新入社員を対象に実施されますが、マナー不足を感じた時は中堅社員に対しても実施することがあります。名刺交換や電話対応、挨拶や言葉遣いなど、ビジネスの基本的なマナーを学びます。
- 研修内での目標設定の例:ビジネスマナーを理解して、正しい言葉遣いを身に着ける。
- 研修後に向けた目標設定の例:1日に10件の電話に率先して出るようにする。話している内容をメモしておき、担当者に正しく引き継ぐことができるようになる。
ビジネスマインド研修
ビジネスマインド研修とは、社会人としての仕事への取り組み方や心構えを学ぶ研修です。会社という組織で働くことの自覚を持ち、社会人として正しい行動ができるようにします。
高いモチベーションを維持する方法やビジネスにおけるコミュニケーション手法も学ぶことができます。
タスク管理やタイムマネジメントといった効率的な仕事の進め方もビジネスマインド研修に含まれます。
- 研修内での目標設定の例:研修で積極的にコミュニケーションを取り、ビジネスコミュニケーションのコツをつかむ
- 研修後に向けた目標設定の例:毎朝、当日のタスクを書き出して1日のスケジュールを立てる。消化できなかったタスクがあった場合は、その原因を把握して今後のタイムマネジメントに活かす
コミュニケーション研修
コミュニケーション研修とは、社内でのコミュニケーションだけでなく、交渉力やプレゼンテーション力など社外に向けたスキル向上を目的としています。部下とのコミュニケーションを円滑に行うことでマネジメントが機能し、組織の成果につながります。
また、お客様のニーズを正しく理解して提案することで、難しい交渉を前に進めることができるようになります。
リモートワークを取り入れている企業が部下のメンタルケアを目的として、積極的に受講している研修の1つです。
- 研修内での目標設定の例:これまでのコミュニケ-ション方法を一から見直し、お客様をイメージして交渉力を伸ばす
- 研修後に向けた目標設定の例:研修で学んだことをお客様との交渉に活かし、成約率を20%アップさせる
ビジネスシンキング研修
ビジネスシンキング研修とは「〇〇シンキング」と呼ばれるビジネスのフレームワークを学ぶ研修です。主に、ロジカルシンキングやラテラルシンキング、クリティカルシンキングなどがあります。
ロジカルシンキング研修では、論理的思考能力を伸ばし、原因と結果を順序立てて整理する能力が身に付きます。
ラテラルシンキングは水平思考と言われ、前提を疑いながら新しい発想を生み出す能力のことです。ビジネスの新しいアイデアを生み出すためには、ラテラルシンキング研修が有効的です。
クリティカルシンキング研修では、前提を疑うところから始めます。常識を疑うことによって、新たな発見を導き出したり、事前にリスクを回避できるようになったりします。
- 研修内での目標設定の例:ラテラルシンキングのコツを身に着け、思考を習慣化できるようにする
- 研修後に向けた目標設定の例:お客様に対して、ラテラルシンキングを活かした提案を年間3件以上実施する
ハラスメント研修
ハラスメント研修とは、職場で各種ハラスメントを起こさせないようにするための研修です。
2022年4月に施行されたパワハラ防止法では、全ての企業を対象にパワーハラスメントの防止が義務付けられました。パワハラ防止法をきっかけに、様々なハラスメントを学ぶ研修が注目されています。
ハラスメントには、以下のような種類があります。
- パワーハラスメント:職場の上下関係や権力を利用した高圧的な嫌がらせ行為のこと。身体的だけでなく精神的な苦痛を与えることもパワーハラスメントに当たる
- セクシュアルハラスメント:性別や年齢、プライベートや容姿について不要な発言をしたり、不用意に身体に触れたりする行為
- モラルハラスメント:悪口や嫌がらせ、無視などを続けて精神的な苦痛を与える行為
- マタニティハラスメント:妊娠、出産、子育てを理由とした嫌がらせや不利益な扱いをする行為
- ジェンダーハラスメント:仕事の割り振りや配置転換の判断に性別を用いる行為
- セカンドハラスメント:ハラスメントを訴える人に対してバッシングなどの精神的な苦痛を与える行為
- アルコールハラスメント:飲み会への強要やお酒の席での暴言など、飲酒に関連する迷惑行為
- スメルハラスメント:体臭や口臭、香水などで臭いで他人を不快にする行為
他にも、テクノロジーハラスメントやスモークハラスメントなどがあります。
ハラスメント研修では、固有のハラスメントに特化した研修と、全体的にハラスメントを学ぶことができる研修があります。
- 研修内での目標設定の例:ハラスメントを学び、少しでも疑わしい行為をしていないかセルフチェックする
- 研修後に向けた目標設定の例:月に1回、講習で学んだことを振り返り、自分の行動を見直す
参考:ハラスメント研修の目的と必要性|研修内容やポイントを解説
コンプライアンス研修
コンプライアンス研修とは、会社に損害を与えるような不祥事を起こさせないための研修です。
コンプライアンスとは「法令遵守」のことです。コンプライアンスでは、会社の就業規則を学ぶことから、SNSの正しい活用方法、仕入先との取引ルールなどを学びます。
良かれと思って実施したことがコンプライアンス違反になるケースもあるため、会社と社員を守るためにも重要な研修と言えます。
- 研修内での目標設定の例:コンプライアンスの事例を学び、コンプライアンス違反になりそうな業務を洗い出す
- 研修後に向けた目標設定の例:コンプライアンス関連の情報収集をし、毎月部門内で共有して意識を高める
参考:コンプライアンス研修とは?目的やテーマ例、実施方法を解説
ITスキル・情報セキュリティ研修
ITスキル・情報セキュリティ研修とは、IT関連のスキルアップと情報セキュリティについて学ぶ研修です。
ITの利用が当たり前となっている社会では、ITエンジニアでなくてもITのスキルが求められています。情報セキュリティを正しく理解していないと、会社に損害を与える情報流出を引き起こす可能性もあります。
IT技術は日々進化をしており、セキュリティ事故のニュースも後を絶ちません。ITスキル・情報セキュリティ研修は、一度実施して終わりではなく、定期的に開催することが大切です。
- 研修内での目標設定の例:情報セキュリティを学び、セキュリティ事故が起きそうな業務をリスト化する
- 研修後に向けた目標設定の例:ビジネスだけでなくプライベートで利用しているサービスも対象とし、3か月に1回パスワードを変更する
人事評価研修
人事評価研修とは、会社の評価者が公平・公正に部下を評価して育成につなげる研修です。自社の評価制度や基準を理解して、心理的な要因で評価が偏らないようにします。
また、人事評価を通じて社員の成長や育成を実現させる方法を研修で学びます。
- 研修内での目標設定の例:人事評価基準を理解し、人材育成の要点を学ぶ
- 研修後に向けた目標設定の例:部下との1on1ミーティングを月に1回以上実施し、部下の成長を促すアドバイスをする
研修後アンケート・理解度テストの実施なら「AirCourse」
研修後のアンケートや理解度テストの実施は、管理がしやすい「AirCourse(学習管理システム)」がおすすめです。
AirCourseなら、動画視聴後・集合研修後のアンケート・テスト実施が容易で、必要に応じて追加の学習や声かけを行うことができます。システムに標準搭載されているコンテンツに加え、企業オリジナルのコンテンツを作成・配信することが可能です。
自社のテーマ別・階層別研修を実りあるものにしたい、さらにアップデートしたいとお考えの方はAirCourseが分かる下記資料をご覧ください。
新入社員研修
新入社員研修とは、ビジネスの基本である報連相や資料の作成方法、社会人としての心得などを教える研修です。マナー研修やビジネスマインド研修と組み合わせて開催するケースが多いです。
新入社員研修では、会社の経営理念や創業からの歴史、各部署がどのような仕事をしているかなど、会社の基本情報を学ぶことも大切なテーマとなっています。
- 研修内での目標設定の例:ビジネスの基本を学び、研修内容を上司に正しく報告できるようにする
- 研修後に向けた目標設定の例:3か月後までに、資料を1から作ることができ、お客様に提案できるようになる
参考:新入社員研修カリキュラムの作成手順|基本と職種別の内容例
職種別研修
職種別研修とは、配属される部署で活用できるスキルを学ぶ研修です。
営業部ならば、営業のスキルを専門的に学ぶ場になり、技術職であれば機械の使い方や専門ソフトの利用方法を学びます。
職種別研修では法改正やトレンドを知ることも重要で、他社の事例と自社のやり方を比較して、課題の発見につなげます。
職種は様々あるため、経理職の職種別研修を受ける場合を想定して目標設定の事例をご紹介します。
- 研修内での目標設定の例:電子帳簿保存法を理解し、自社の業務フローで変更しなければならないポイントを洗い出す
- 研修後に向けた目標設定の例:半年後の法改正時に業務が円滑に推進できるよう、課題一覧を作成して対策と対応期日を明確にして取り組む
マネジメント研修
マネジメント研修とは、管理職や管理職候補の社員に対して、部下をマネジメントする術を学ぶ研修です。マネジメントの概念が広いため、マネジメント研修も細分化して実施することがあります。
目標管理研修やメンタルケア研修、部下育成能力向上研修などがマネジメント研修の対象です。
また、マネジメント力向上にはリーダースキルが欠かせないため、リーダー研修の要素を含むケースもあります。
- 研修内での目標設定の例:部下育成のポイントを知り、部下の強みと弱みを照らし合わせる
- 研修後に向けた目標設定の例:部下と面談をして強みを認識させ、部下の強みが仕事に活きた事例を毎月1件以上とする
チームビルディング研修
チームビルディング研修とは、チームワークを高めて組織力を向上させる方法を学ぶ研修です。
チームビルディング研修は、知識を学ぶタイプの研修もありますが、大半はゲーム性を取り入れたグループワークを通してチームビルディングのコツを学んでいきます。
- 研修内での目標設定の例:気づいていないチームビルディングのコツを研修報告書にまとめる。
- 研修後に向けた目標設定の例:組織力向上の成果を測るため、部門別収支を前年度と比較する。またチームミーティングを定期開催し、お互いのコミュニケーションに課題が無いかチェックする。
コーチング研修
コーチング研修とは、部下が自発的に行動できるようにする「コーチング」の技術を学ぶ研修です。
指示を出すだけでは部下は成長せず、部下の意見を傾聴して行動を促し、自己成長を続ける関係性を築かなければなりません。
- 研修内での目標設定の例:部下との接し方でコーチングできていたのかを確かめて、コミュニケーション方法を改める
- 研修後に向けた目標設定の例:部下が設定した目標に対して定期的に面談をし、自発的行動で部下が目標達成できるようにする
OJTトレーナー・メンター研修
OJTトレーナー・メンター研修とは、部下を教育する担当者に向けた研修です。
OJTトレーナーとは、業務を通して部下を教育する担当者であり、同じ部門の先輩が任命されます。メンターは、同じ部署の先輩とは限らず後輩のメンタル面をサポートし、成長促進と離職防止を担う役割があります。
OJTトレーナーとメンターの役割は、ともに後輩の成長になりますが、教育していく中で自身も成長できるメリットがあります。
- 研修内での目標設定の例:これまで部下を教育した時に意識していた内容との乖離を把握する
- 研修後に向けた目標設定の例:半年後、担当した部下と上司で面談をしてもらい、第三者視点でトレーナーとしての評価をレビューしていただく
社員研修にeラーニングを活用した事例
効果的な研修目標設定には、研修プロセス全体を体系的に管理し、成果を明確に測定できる仕組みが不可欠です。
ここでは、eラーニングを活用して研修目標の設定から達成度測定まで効率的に管理し、継続的な改善を実現した企業事例をご紹介します。営業プロセスの体系化、多様な働き方への対応、検定制度と反転学習の組み合わせなど、各社が工夫した目標管理手法が特徴的です。
これらの実践例から、自社の研修目標設定と管理をより効果的に行うための具体的なアプローチを学ぶことができます。
営業プロセス理解浸透のための体系的なコンテンツ作成|株式会社ぐるなび様

飲食店情報サイト「ぐるなび」を運営し、日本の外食の健全な発展を支える株式会社ぐるなび様では、営業メンバーの育成における受講管理の煩雑さが課題でした。
全国の営業所にいる数百名の営業メンバーをExcelファイルで管理し、外回りの多い営業のアポ調整や再研修の日程調整で膨大な手間が発生していました。また、様々なナレッジが社内に分散しており、一つのプラットフォームへの情報集約が求められていました。
AirCourseの「動画・プレゼン資料・テスト・アンケートの対応」と「利用動向の分析機能」を評価し、営業スキルアップを目的としたオリジナルコンテンツを作成しました。
営業プロセスを細分化して動画化し、理解浸透のための営業スキルアップeラーニングコンテンツとして展開。複数のExcelファイルによる受講管理から脱却し、育成に関する情報を一元管理することで運営工数を大幅削減しました。
標準コースの基本的なビジネススキルも活用し、すぐに使える包括的な研修体系を構築しています。
導入後の主な成果
- 営業プロセス細分化により理解浸透のための体系的なコンテンツを作成
- 育成情報の一元管理により運営工数を大幅削減
- 複数Excelファイル管理からの脱却で効率的な受講管理を実現
参考:効果的な目標設定で顧客満足度向上を実現|株式会社ぐるなび様 AirCourse活用事例
全社統一の研修目標で組織力強化|フジ産業株式会社様

産業給食・メディカル給食・学校保育園給食を提供するフジ産業株式会社様では、事業所が国内各地に点在し、勤務時間や曜日が異なる中でのOFF-JTと自己啓発の強化が課題でした。
福祉施設では365日3食分、工場では交代制勤務など、全員が同じ時間に集まるのは難しい業態で、集合研修には限界がありました。新型コロナウイルス感染拡大により、限られたマンパワーでの教育メニュー不足解消が困難な状況でした。
AirCourseの「既存コンテンツの豊富さ」「使いやすさ」「コストパフォーマンス」を評価し、シフト勤務の社員も含めていつでも受講できる環境を構築しました。
集合研修のeラーニング化により受講者と講師の双方にとってwin-winの教育環境を実現。階層別研修における事前課題として活用し、テレワーク環境下での受講履歴管理と振り返り学習環境を整備しています。
「見やすい、分かりやすいコンテンツ作成」を心がけた受講者ファーストの工夫により、多様な働き方をしている社員に平等な学習機会を提供しています。
導入後の主な成果
- シフト勤務を含む全社員がいつでも受講できる環境を構築
- 集合研修のeラーニング化により受講者・講師双方の負担を軽減
- 多様な働き方に対応する平等な学習機会の提供を実現
参考:多様な働き方に対応する適応力向上で全社員に平等な学習機会を提供|フジ産業株式会社様 AirCourse導入事例
検定試験制度と反転学習で研修効果を客観的に測定|株式会社SHIFT様

ソフトウェアテスト業界のリーディングカンパニーである株式会社SHIFT様では、毎月100名の中途入社者への研修と独自の社内検定試験制度「トップガン教育」において、拠点ごとの研修内容格差と効果測定の客観性確保が課題でした。
従来の集合研修では地方拠点も含めた均一な教育環境の提供が困難で、受講者の習得状況を正確に把握する仕組みが不足していました。
AirCourse導入により、学習から試験まで一貫したオンライン運用を実現しました。
入社者研修では講義動画を事前学習し、対面時間は演習やディスカッションに集中する反転学習により効率化を図っています。「トップガン教育」では約1,000名が登録し、学習から試験までワンストップで運用。コース評価機能により受講者の満足度とフィードバックを体系的に収集し、継続的なコンテンツ改善に活用しています。
合格者にはワンランク上の業務アサインと収入向上というインセンティブを設定し、学習意欲を高めています。
導入後の主な成果
- 検定試験により平均受注単価15.2%アップを実現
- 拠点に関係なく平等な学習環境を提供し研修格差を解消
- 約400名の受験者のうち半数が合格、平均学習期間4.3ヶ月の効果的な制度を構築
参考:マイクロラーニングと反転学習で研修効率化と売上向上を実現|株式会社SHIFT様 AirCourse導入・活用事例
まとめ
研修の目標設定について、目標設定の目的やポイント、研修ごとの目標設定事例を解説しました。
研修の目標設定には、研修内の目標設定と研修後に向けた目標設定があります。研修で目標設定をすることで、受講者はより成長しやすく組織力の向上にもつながるでしょう。
事前に研修の目的を周知することで、研修の目標を設定しやすくなります。目標設定は具体的な内容の方が研修の効果が働きやすくなります。
研修には様々な種類があり、研修に合わせた目標設定が必要です。研修内での目標だけでなく、研修が終わった後に学んだことを活かせるような定量的な目標設定が大切です。
本記事にて紹介した研修ごとの目標設定事例を参考にし、受講者がより成長できる研修プランを構築をしていきましょう。
テーマ別・階層別研修の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
テーマ別・階層別研修の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。