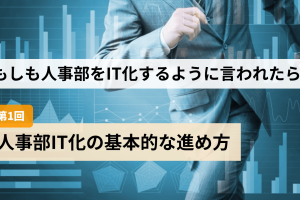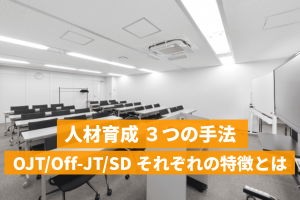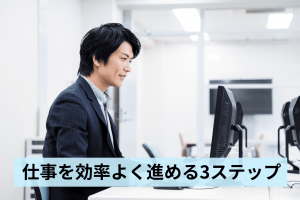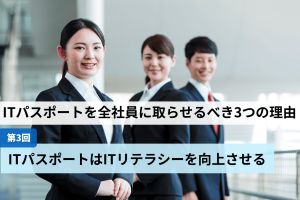「せっかく企画した研修なのに、どうも従業員の反応が薄い」「もっと自律的に学んでほしいけど、なかなかモチベーションが続かない」
人材育成を進めるにあたり、このような課題に直面したことがあるかもしれません。研修内容の質はもちろん重要ですが、それだけでは学習効果を十分に引き出せないことがあります。なぜなら、学ぶ側の「意欲」が伴わなければ、知識やスキルは定着しにくいからです。
そこで注目されているのが、学習者のモチベーション向上に焦点を当てた「ARCS(アークス)モデル」です。ARCSモデルは、学習者の「学びたい」という気持ちを引き出し、主体的な学習を促進するための効果的なフレームワークとして、多くの企業で活用されています。
この記事では、ARCSモデルの基本的な考え方から、その構成要素、研修に取り入れるメリットや具体的な活用事例、そして注意点までを詳しく解説します。
成功企業に学ぶ”人材育成のノウハウ”を無料でお届け
現場の人材育成がなかなか成果に結びつかない…。教育担当者の多くが直面するこの壁を、実際に乗り越えた企業の事例から解き明かします。
従来の研修やOJTで成果が出ない真の理由と、デジタル時代ならではの効果的な育成モデルを厳選事例とともに公開。「時間がない」「効果が見えない」という課題に、他社が語らない人材育成の現実解が具体的な打開策を提示します。
これまでの育成施策に行き詰まりを感じている方こそ、『デジタル時代の人材育成モデル』をぜひご活用ください。
目次
ARCS(アークス)モデルとは?
ARCSモデルは、アメリカの教育心理学者であるジョン・M・ケラー教授によって提唱された、学習者の意欲(モチベーション)を高め、維持することに焦点を当てたインストラクショナルデザインのモデルです。
どんなに優れた教材や講師がいても、学習者自身に「学びたい」という気持ちがなければ、十分な教育効果は得られません。「どうすれば、人は学びたくなるのか?」という問いに基づき、学習意欲に関わる主要な要因を分析し、それらを高めるための具体的なアプローチを体系化することが必要です。
ARCSモデルは学習意欲を高める強力なフレームワークですが、学習成果そのもの(知識やスキルの習得度)を直接保証するものではありません。あくまで学習に向かうための「動機づけ」に焦点を当てたモデルであり、学習内容の質や教え方といった他の要素と組み合わせて用いることが重要です。
ARCSモデルは、教育現場はもちろん、企業研修、eラーニング開発、OJT、部下指導など、学習者の学習姿勢の向上や行動変容を促したいさまざまな場面で活用されています。
インストラクショナルデザインについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ARCSモデルを構成する4つの要素
ARCSモデルは、学習者の意欲を高めるためにアプローチすべき4つの主要な要素(Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction)の頭文字をとって名付けられています。それぞれの要素が、学習プロセスの異なる段階や側面に作用します。
A:Attention(注意)
学習者の興味・関心を引きつけ、「面白そうだ」「何かありそうだ」と感じさせ、学びへ注意を向けさせ、持続させるための要素です。学びの最初のきっかけとなる部分なので、単調にならない工夫が大切です。
学習意欲を高めるアプローチとして、以下のような方法が考えられます。
| 知覚的喚起 | ・視覚、聴覚など感覚に訴えかける刺激(インパクトのある映像、サウンド、色使いなど)や、意外性のある情報、驚きなどを提示する |
| 探求心の喚起 | ・好奇心を刺激する問いかけ、問題提起、ミステリー要素、知的好奇心をくすぐる事実などを提示し、「もっと知りたい」と思わせる |
| 変化性 | ・単調さを避け、プレゼンテーションの形式や構成、声のトーン、活動の種類などに変化をつける ・ユーモアを取り入れることも有効 |
研修で活用するならば、冒頭で受講者の日々の業務に関する衝撃的なデータや、意外な事実を提示したり、短いクイズやインタラクティブな問いかけから始めるのも効果的です。
研修内容に関連性の高い印象的なショート動画やアニメーションを見せたり、グループワークやペアワークを挟んだりと、講師が一方的に話すだけにならないことがポイントとなるでしょう。
R:Relevance(関連性)
学習内容が自分にとって価値がある、重要である、役に立つと感じさせ、「学ぶ意義がある」「やりがいがありそうだ」と認識させる要素です。学習への積極性や、継続して取り組む意欲につなげます。
関連性を高めるアプローチとして、以下のような方法が考えられます。
| 親しみやすさ | ・受講者の既存の知識や経験、日々の業務と学習内容を結びつけて説明する ・身近な事例や比喩を用いる |
| 目的指向性 | ・学ぶことが、受講者の将来のキャリア目標、現在の業務上の課題解決、あるいは組織の目標達成にどうつながるのかを明確に示す ・学ぶことの「メリット」を伝える |
| 動機との一致 | ・受講者個人の興味、関心、ニーズ、価値観に合わせて学習内容を調整したり、選択肢を提供したりする |
例えば、研修の冒頭で「この研修で学ぶことは、皆さんが日々感じている〇〇という課題の解決に直結します」「このスキルは、将来△△な役割を目指す上で不可欠です」のように、受講者のメリットを具体的に伝えることが大切です。
また、業務で実際に起こった事例や、受講者が共感できるケーススタディを取り扱ったり、受講者の経験や知識を引き出しつつ新しい内容と関連付けたりすることで、受講者が自分事として研修を捉えることができるようになります。
C:Confidence(自信)
学習者が「自分にもできるかもしれない」「努力すれば成功できそうだ」と感じ、成功への期待感や自己効力感を持てるようにする要素です。困難に直面しても諦めずに、粘り強く学習に取り組むために不可欠です。
自信を高めるアプローチとして、以下のような方法が考えられます。
| 学習欲求 | ・成功体験の機会を意図的に設ける ・目標を一度に高く設定せず、達成可能な小さなステップに分割して提示する |
| 成功の機会 | ・学習内容の難易度を適切に設定し、受講者のレベルに合わせて調整する ・最初はやさしい課題から始め、徐々に難易度を上げる ・成功のための十分な情報やサポートを提供する |
| コントロールの個人化 | ・成功が、運や外部要因ではなく、自分自身の努力や能力(適切な戦略や学習方法)によるものだと感じさせるようなフィードバックを行う ・失敗に対しては学習者を責めるようなコメントをしない |
研修の序盤に全員が答えられるような簡単なクイズやワークを設け成功体験を積ませたり、難しい内容も図解や具体例を多く使い段階的に説明したり、学習者が成功への期待感を持てる要素を含めましょう。
また、「〇〇さんの今の理解度であれば、次のステップに進むのに十分な力がありますよ」のように、努力や成長に焦点を当てた肯定的なフィードバックを行うことも、学習者の意欲を高めるのに効果的です。進捗確認のテストは頻繁に行い、自分の理解度を自分で把握できるようにすると良いでしょう。
S:Satisfaction(満足感)
学習によって得られた成果や学習への努力が正当に評価され、「学んでよかった」「努力が報われた」と感じられる要素です。達成感や充実感は、次の学びへの意欲や、学んだことを継続的に実践する行動につながります。
満足感を高めるアプローチとして、以下のような方法が考えられます。
| 内発的な強化 | ・学びそのものの楽しさ、新しい発見の喜び、課題が解決できた達成感など、学習行為自体から得られる肯定的な感情を促進する |
| 外発的報酬 | ・目標達成や努力に対して、褒める、認める、感謝を伝えるといった言葉による承認や、修了証の発行、インセンティブの提供、昇進・昇格への反映など、外部からの肯定的な働きかけを行う |
| 公平さ | ・評価基準が明確で、誰に対しても公平に扱われていると感じられるようにする ・自分の努力が正当に評価されているという信頼感を培う |
研修の最後に、学んだことを発表したり、ミニワークで成果を共有したり、学びを実践する場を設けることで、研修に対する満足感がアップします。
評価する場合は、テストの点数だけでなく、研修への取り組み姿勢や、学んだ内容を業務に活かそうとする意欲なども含めて評価することを意識しましょう。
“成果を出す”人材育成とは?解説資料を無料公開
OJTや集合研修を実施しているものの、「思うような効果が感じられない」「継続的な成長につながらない」といった課題を抱えていませんか。
その背景には、デジタル時代の働き方に適さない従来型の育成モデルがあります。では、実際に成果を上げている企業は、どのような人材育成モデルを構築しているのでしょうか?
『デジタル時代の人材育成モデル』では、現代の課題を解決する新しい育成アプローチと、それらを実現するための具体的な手法を、成功企業の実例をもとに詳しく解説しています。育成を見直したい方は、ぜひご覧ください。
ARCSモデルを研修に取り入れるメリット
ARCSモデルの考え方を研修に取り入れることで、以下のようなメリットが期待できます。
学習効果・定着率の向上
学習者の注意を引きつけ、関連性を示すと、研修や教材への関心(エンゲージメント)が高まります。ただ情報を提供するだけでなく、インタラクティブな仕掛けや、学習者が「自分ごと」として捉えられる工夫をするため、より深く、主体的にコンテンツに関わってくれるようになります。
学習者のコンテンツへの主体的な関わりは、内容の深い理解や知識・スキルの定着のしやすさを決める要素のひとつです。受動的な研修が多い場合は、ARCSモデルを取り入れると学習効果・定着率の改善につながる可能性があります。
受講者・従業員のモチベーション向上
ARCSの4つの要素を意識して研修を設計・実施することで、受講者は「面白そうだ」「自分に関係がある」「これならできそうだ」「やってよかった」と感じ、学習に対して、
高いモチベーションで学習に取り組むことができます。これは研修期間中だけでなく、研修後の自分自身の成長のために必要な学習を自ら探し、取り組むという自律的な学習を促進することにも寄与します。
学習内容の業務への活用促進
ARCSモデルを活用した研修では、学習内容を業務へ活かせるよう工夫されています。
例えば、実際の業務に基づいたケーススタディを取り入れることで、受講者が自分事として学ぶ意識を高め、実務での活用を促進します。
また、練習問題やケースワークを通じて成功体験を積ませることで自信を養い、学んだ知識を実践に結びつけやすくします。このような取り組みにより、個々の成長と組織の成果向上を効果的に支援します。
ARCSモデルを研修に活用するときの参考例
ARCSモデルの4つの要素は、研修のさまざまな側面に適用できます。ここでは、いくつかの具体的な活用例をご紹介します。
研修プログラム設計への応用
研修プログラムを設計するときに、ADDIE(アディー)モデルのようなフレームワークと組み合わせて、ARCSモデルを各フェーズで意識すると、学習者の意欲を高める設計が可能です。
ADDIEモデルとは、効果的な学習プログラムや研修を開発するためのフレームワークです。「分析」「設計」「開発」「実施」「評価」の5つのステップを順に進めることで、根拠に基づいた、より効果的な学習プログラム開発を目指します。
例えば、「分析」は「なぜこの学習プログラムや研修が必要なのか?」「この学習プログラムや研修で何を達成したいのか?」を明らかにするフェーズです。その際に、アンケート調査やインタビューなどを実施して、「なぜ現在のモチベーションレベルなのか(成功体験や失敗体験)」「どのような内容に強く興味を示すのか」「不安の具体的な原因は何か(自信のなさ、内容への抵抗など)」などもあわせて分析する、といった具合です。
ADDIEモデルのフェーズに、ARCSモデルの要素を組み込む例をまとめました。
| フェーズ | 組み込む内容 |
|---|---|
| 分析(Analysis) | ・受講者の現状のモチベーションレベル ・興味関心 ・学習に対する不安 |
| 設計(Design) | ・各学習目標に対して、ARCSの各要素を高めるための具体的なアプローチ ・注意を引く導入 ・関連性を示す事例 ・自信を高める課題設定 ・満足感につながる評価方法 |
| 開発(Development) | ・設計に基づき、ARCSを高めるような表現 ・驚きのあるグラフ ・業務直結のケース ・スモールステップ課題 ・達成度が見える工夫 |
| 実施(Implementation) | ・実施中の声かけ ・フィードバック ・インタラクションを通じて、学習者のARCSを維持、向上させる |
| 評価(Evaluation) | ・学習内容の理解度 ・研修への意欲 ・満足度 |
ADDIEモデルについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
OJTや部下指導への応用
ARCSモデルは、形式的な研修だけでなく、日常的なOJTや部下指導においても非常に有効です。
以下に具体的な活用例をまとめました。
| 要素 | 活用例 |
|---|---|
| Attention(注意) | 新しい業務を教える際、まず「なぜこの業務が重要なのか?」「どんな面白い側面があるか?」など、部下の注意を引くような話から始める |
| Relevance(関連性) | その業務が部下のキャリア目標やチーム、会社全体の目標にどうつながるのかを具体的に説明し、学ぶ意義を伝える |
| Confidence(自信) | 最初から全てを任せるのではなく、達成可能な小さなタスクから任せ、成功体験を積ませる。「最初は難しく感じるかもしれないけど、〇〇さんの強みである△△を活かせば大丈夫だよ」のように、励ましと期待を伝える |
| Satisfaction(満足感) | 業務が完了したら、「ありがとう!〇〇さんがこの部分を担当してくれたおかげで、スムーズに進んだよ」「前に苦戦していた△△が、今回は自分で解決できたね!成長したね」のように、具体的な行動や成果を褒め、承認する |
ワークショップやグループワークへの応用
ARCSモデルは、ワークショップやグループワークの設計にも効果的に活用できます。ARCSモデルの各要素をどのように取り入れられるか、具体例をまとめました。
| 要素 | ワークショップでの活用方法 |
|---|---|
| Attention(注意) | ・ワークショップ冒頭で、参加者の身近な課題や業務に関連する驚くべきデータや興味深いストーリーを提示する ・動画やクイズ、インタラクティブな質問などを活用して参加者の興味を引きつける ・グループディスカッションのテーマにユーモアや意外性を取り入れる |
| Relevance(関連性) | ・ワークショップの目的を明確化し、参加者が自分の業務や目標とどう関連するのかを具体的に説明する ・業務や日常場面を想定したケーススタディを取り入れる ・参加者の経験を共有し、それを踏まえた解決策を議論する場を設ける |
| Confidence(自信) | ・課題を小さなステップに分け、初めての参加者でも取り組みやすい内容から始める ・成功体験を重ねることで「やればできる」という感覚を養う ・褒めるフィードバックや、達成感を共有する時間を設ける |
| Satisfaction(満足感) | ・ワークショップ終了時に成果を発表する機会を設ける ・参加者同士で学びを共有し、お互いに称賛し合う場を作る ・具体的な進捗が分かるよう、達成度を可視化する仕組みを導入する |
eラーニングでの活用
ARCSモデルは、自己学習が中心となるeラーニングとの相性が非常に良いです。システムやコンテンツの工夫で、ARCSの要素を効果的に組み込むことができます。
| 要素 | 活用例 |
|---|---|
| Attention(注意) | ・オープニングで目を引く動画やアニメーションを使用する ・モジュールの最初に意外性のあるデータや問いかけを入れる ・単調なテキストだけでなく、イラスト、写真、図解などを豊富に使う ・定期的に短い確認テストやインタラクションを挟む |
| Relevance(関連性) | ・コースの最初に学習内容が業務やキャリアにどう役立つかの説明動画を入れる ・業務でよくあるシナリオ形式のケーススタディを取り入れる ・学習内容に関連する最新ニュースや業界トレンドへのリンクを提供する |
| Confidence(自信) | ・学習内容を細かく分け、一つのモジュールを短時間で完了できるようにする(マイクロラーニング) ・練習問題や確認テストを豊富に用意し、すぐに正誤フィードバックを行う ・難しい内容には、ヒント機能や補足資料へのリンクを提供する ・学習進捗バーや完了率表示で、自分の達成度を可視化する ・挑戦的な課題には、成功のためのステップやヒントを丁寧に提示する |
| Satisfaction(満足感) | ・モジュール完了やテスト合格時に、称賛メッセージやアニメーションを表示する ・修了証の発行や、ゲーミフィケーション要素(バッジ、ポイントなど)を取り入れる ・LMSの分析機能で、学習時間やテスト結果をグラフなどで提示し、自分の頑張りや成長を実感できるようにする ・学びを業務に活かせる機会をシステム上で提示したり、成功事例を共有する場(フォーラムなど)を設けたりする |
ARCSモデルを研修に取り入れるときの注意点
ARCSモデルは学習意欲向上に有効ですが、導入にあたってはいくつかの注意点も存在します。注意点を意識しておくことで、スムーズに活用できるでしょう。
要素のバランスが崩れると成果につながりにくい
ARCSの4つの要素は互いに関連し合っています。例えば、注意(Attention)を引くだけで内容が関連性に欠けたり、自信を失わせるほど難しすぎたり、満足感が得られなかったりすると、学習意欲は維持できません。
特定の要素に偏りすぎず、4つの要素すべてをバランス良く満たすように設計・実施することが重要です。
対象者や状況に合わせたカスタマイズが必要になる
ARCSモデルは汎用的なフレームワークですが、学習者の年齢、経験、文化、学習内容、学習環境などによって、どの要素のどの側面が効果的かは異なります。対象者を深く理解し、状況に合わせてアプローチをカスタマイズする柔軟性が求められます。
効果測定が難しいため継続的な観察と評価が求められる
学習者の「意欲」や「モチベーション」は、知識量やスキルの習得度のように直接的に測定するのが難しい側面があります。
ARCSモデルの効果を測るには、アンケートによる満足度調査だけでなく、研修への取り組み姿勢、質問の量、自律的な学習行動の変化、実際の業務での行動変容など、定性的な要素を含めた継続的な観察と多角的な評価が必要です。
以下に4つの要素について、それぞれの評価の観点と方法例をまとめました。
| ARCSモデルの要素 | 評価の観点 | 評価方法の例 |
|---|---|---|
| Attention(注意) | 学習者の興味や関心が引きつけられたか | ・冒頭の内容についてのアンケート調査 ・研修中の質問や反応の頻度の記録 |
| Relevance(関連性) | 学習内容が業務や目標に結びついていたか | ・学習内容が業務に役立つと感じたかのアンケート ・研修後の業務改善例の共有 |
| Confidence(自信) | 学習者が内容を実践できる自信を持てたか | ・達成感や実践への自信についてのアンケート ・研修後の自己評価とスキルテスト |
| Satisfaction(満足感) | 学習経験に対する満足度 | ・研修の満足度や改善点の聞き取り調査 ・成果物や実績の振り返り会の実施 |
過度に効果を期待しすぎない
ARCSモデルは学習意欲を高めるための強力なツールですが、それだけで研修のすべてが成功するわけではありません。
研修の効果は、内容そのものの正確性や網羅性、講師の質、実施環境、そして組織文化など、さまざまな要因によって左右されます。ARCSモデルはあくまで学習意欲という側面にアプローチするものであり、研修の効果を高めるには、ARCSモデルだけでは不十分な可能性があることを理解しておく必要があります。
まとめ
従業員の学習意欲は、研修効果やその後の業務への成果、さらには組織全体の活性化に大きく影響します。
ARCSモデルは、この学習意欲を「注意」「関連性」「自信」「満足感」の4つの要素から戦略的に高めるための、非常に有効なフレームワークです。これらの要素を意識して研修を設計・実施することで、受講者は受け身ではなく、自ら進んで学ぶようになり、学習効果や定着率の向上が期待できます。特にeラーニングにおいては、コンテンツやシステム設計でARCSの要素を意識的に組み込むことが、学習完了率や満足度を高める鍵となります。
効果的なeラーニング研修の実現には、ARCSモデルに基づいた魅力的で飽きさせないコンテンツ提供をサポートし、学習者のエンゲージメントを高める機能を備えた学習管理システム(LMS)が役立ちます。
AirCourseは、ARCSモデルの考え方を活かしたeラーニングコンテンツの作成・配信や、学習者のモチベーション維持につながる機能(進捗可視化、達成度表示など)を提供し、学習者の意欲向上施策をサポートします。
ARCSモデルを活用し、従業員の「学びたい」という気持ちを引き出して、自社の人材育成をより一層加速させてください。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。