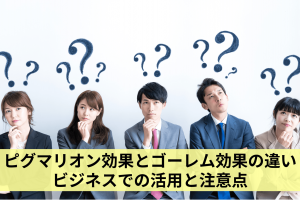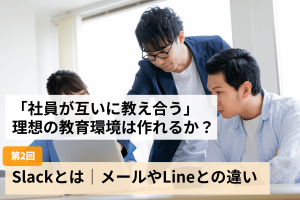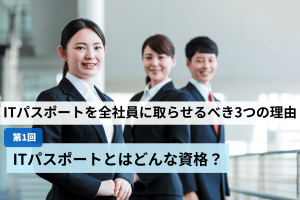従来の研修手法に限界を感じ、「もっと効果的で、受講者の意欲を引き出す新しい方法はないか」とインストラクショナルデザインにたどり着いた方もいるかもしれません。
しかし、「具体的に何をすれば良いのかわからない」「自社の研修にどう活かせるのだろう?」と、その内容や導入方法がわからず踏み出せずにいるのではないでしょうか。
インストラクショナルデザインは、勘や経験に頼るのではなく、科学的なアプローチで「効果測定できる」「現場で活かせる」研修を設計するための強力なフレームワークです。eラーニングを含め、多様な形式の研修で学習効果を高めるのに役立つ考え方として、今、多くの企業で注目されています。
この記事では、インストラクショナルデザインの基本的な考え方から、ADDIE(アディー)モデルやARCS(アークス)モデルといった代表的なモデル、そしてそれらを自社の研修にどう活用できるかまでを解説します。
成功企業に学ぶ”人材育成のノウハウ”を無料でお届け
現場の人材育成がなかなか成果に結びつかない…。教育担当者の多くが直面するこの壁を、実際に乗り越えた企業の事例から解き明かします。
従来の研修やOJTで成果が出ない真の理由と、デジタル時代ならではの効果的な育成モデルを厳選事例とともに公開。「時間がない」「効果が見えない」という課題に、他社が語らない人材育成の現実解が具体的な打開策を提示します。
これまでの育成施策に行き詰まりを感じている方こそ、『デジタル時代の人材育成モデル』をぜひご活用ください。
目次
インストラクショナルデザインとは?
インストラクショナルデザイン(Instructional Design, ID)とは、「人はどのように学ぶのか?」という科学的な知見に基づき、研修の目的設定から最適な学習内容・方法の選定、評価、継続的な改善まで、学習プロセス全体を計画的かつ論理的にデザインする手法です。日本語では「教育設計」や「学習設計」とも呼ばれます。
従来の研修設計が、「話題のテーマを取り上げる」「講師の知っていることを伝える」といったコンテンツや指導者中心になりがちだったのに対し、インストラクショナルデザインは徹底して学習者中心であり、最終的な「学習成果(行動変容)」に焦点を当てます。この根本的な違いが、研修を「受けっぱなし」にせず、企業のビジネス目標達成に貢献する戦略的な取り組みへと変える鍵となります。
インストラクショナルデザインの3要素
インストラクショナルデザインに基づく研修設計において中心となる3つの要素、学習目標・評価方法・教育内容は切り離すことのできない関係にあります。これらの要素は効果的な学習プログラムを作る上で不可欠です。
3つの要素が整合性を持ち、一貫して設計されることで、学習者は「何を学ぶべきか(目標)」を理解し、それを学ぶための最適な道筋(内容)を辿り、そして目標に到達できたか(評価)を確認しながら学習を進められます。これにより、学習効果が高まり、「学んだのに意味がなかった」という事態を防ぐことができます。
それぞれの要素については以下の通りです。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 学習目標 | ・研修修了後に学習者ができるようになることを、具体的かつ測定可能な形で定義したもの ・行動で示せる目標が重要となる |
| 評価方法 | ・設定した学習目標の達成度を測定する方法 ・筆記試験、実技試験、ロールプレイング、業務パフォーマンス測定などで行う |
| 教育内容 | ・学習目標達成のために提供される情報や活動 ・講義、テキスト、動画、eラーニング教材、演習問題、ケーススタディなどが挙げられる |
インストラクショナルデザイン導入のメリット
インストラクショナルデザインを研修に取り入れることで、従来の研修手法では得られなかったメリットを得ることができます。
研修内容を実務に活かせる
インストラクショナルデザインは、学習者が実際の業務で活用できるスキルや知識の習得に焦点を当てます。従来の「知識提供型」の研修ではなく、具体的な行動変容を目的に設計されるため、受講者が学んだことを現場で即実践できる研修を構築できます。これにより、業務改善やパフォーマンス向上が期待できます。
学習者のモチベーションを向上
インストラクショナルデザインは、学習者の主体性を引き出し、興味ややる気を高める仕組みを重視しています。たとえば、インストラクショナルデザインの一モデルであるARCSモデルの「注意喚起」や「関連性」の要素を研修に取り入れれば、学習内容が自分の業務やキャリアにどう役立つかを具体的に感じられるようにできます。これにより、受講者が学習に積極的に取り組む姿勢が生まれます。
効果の測定と継続的な改善が可能
インストラクショナルデザインでは、学習目標や評価基準を明確に設定するため、学習者の進捗状況や研修の効果を測定しやすくなります。例えば、LMS(学習管理システム)を活用して、テスト結果や学習データを収集・分析でき、研修効果を数値化すれば、データに基づいた改善が行えるため、研修プログラムの質を継続的に向上させられます。
インストラクショナルデザインが重視される背景
インストラクショナルデザインが近年重視されている背景には、ビジネス環境の急激な移り変わりや働き方の多様化、学習者のニーズの変化が挙げられます。
ビジネス環境の急激な移り変わり
現代は、テクノロジーの進化やグローバル化の進展などによって、必要なビジネスのあり方が目まぐるしく変わっています。
こうした状況の急激な移り変わりに対応するには、従業員に新しいスキルを効率的かつ効果的に習得してもらう必要がありますが、場当たり的な研修ではその実現が難しくなっています。そこで、目標・評価方法・教育内容を綿密に設計するインストラクショナルデザインの考え方が注目を集めています。
働き方の多様化と研修方法の変化
リモートワークやハイブリッドワークの定着により、働き方が多様化し、それに伴い研修方法も進化しています。従来の集合研修に加え、時間や場所を問わず学べるeラーニングやオンライン研修が主流となり、多忙な現代に適した手段へと変化してきました。
しかし、オンライン環境では、学習者の自律性がより求められ、集中力の維持やモチベーション管理が課題となります。
インストラクショナルデザインの知見を活用することで、学習内容を学習者の業務や目標に関連づけ、オンライン環境でも主体的な学びを促す設計が可能です。オ働き方や学び方にかかわらず、学びの質と継続性の向上を実現できる点も、インストラクショナルデザインが重視される理由のひとつです。
学習者のニーズの変化
現代の従業員は、自身のキャリアや成長につながる学びに対してより主体的になっています。
インストラクショナルデザインは、学習者の興味を分析し、彼らが「なぜ学ぶのか」を理解し、主体的に学習に取り組めるような仕掛け(関連性の提示、成功体験の提供など)を学習設計に組み込みます。こうしたニーズへの適切な対応は、従業員の企業へのエンゲージメント向上に影響するため、注目している企業は少なくありません。
インストラクショナルデザインの主要なモデル
インストラクショナルデザインを実践する上で、設計の思考プロセスや手順をガイドしてくれるさまざまなモデルが存在します。これらのモデルは、特定の状況や目的に応じて使い分けられたり、組み合わせて活用されたりします。
ADDIE(アディー)モデル
ADDIEモデルは、インストラクショナルデザインにおいて最も広く知られ、基礎として利用されている汎用的なモデルです。
ADDIEモデルでは、学習プログラムの開発プロセスを5つの要素に分けて捉えます。各要素は順に進むと説明されますが、実際には各段階で評価を行い、必要に応じて前の段階に戻る反復的なアプローチ(イテレーティブプロセス)として実践されることが多いです。
| 要素 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| 分析(Analysis) | ・根本原因と研修で目指す具体的な行動を明確にする | ・ヒアリング ・アンケート ・データ分析 |
| 設計(Design) | ・測定可能な目標を設定 ・効果的な学習方法を計画 | ・カリキュラム作成 ・教材選定 ・評価方法決定 |
| 開発(Development) | ・わかりやすく魅力的な教材の作成 ・試行で問題点を修正 ・研修環境の準備 | ・教材作成 ・動画編集 ・システム設定 ・テスト実施 |
| 実施(Implementation) | ・研修の実施と学習体験を提供 ・円滑な進行と学習者のサポート | ・運営 ・講師サポート ・技術サポート |
| 評価(Evaluation) | ・研修効果を測定 ・改善策を検討 ・次に活かすフィードバック | ・テスト ・アンケート ・行動観察 ・KPI分析 |
参考:ADDIEモデルとは?教育への活用メリットと導入のコツ
ARCS(アークス)モデル
ARCSモデルは、学習者の「動機づけ(モチベーション)」に特化したインストラクショナルデザインのモデルです。
米国の教育心理学者ジョン・ケラー教授によって提唱されました。学習者の学習意欲を高め、維持するための4つの要素 Attention(注意喚起)、Relevance(関連性)、Confidence(自信)、Satisfaction(満足感)の頭文字を取っています。特に、学習者の自律的な学習が求められるeラーニングやブレンド型学習において、学習者の離脱を防ぎ、継続的な学習を促すために重要な考え方です。
| 要素 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| 注意喚起(Attention) | 学習者の関心を惹きつけ、学習への意識を集中させる | ・研修の導入でメリットを具体化 ・研修内容を「自分ごと化」させる ・興味深い事例を提示する ・ 動画やインタラクティブな要素で飽きさせない工夫をする |
| 関連性(Relevance) | 学習内容の意義を明確化し、学習意欲を高める | ・学習内容が、業務などにどう関連しているかを明確に説明する ・学習者の経験や知識に関連づける ・ケーススタディやロールプレイングなど練習機会を提供する ・業界の成功事例やベストプラクティスを紹介し、学習のモチベーションを高める |
| 自信(Confidence) | 学習者に「自分にもできる」という自信を持たせる | ・スモールステップで達成可能な目標を設定する ・学習の各段階で、適切なフィードバックやガイダンスを提供する ・ 講師によるサポート支援を提供する ・ 学習の進捗状況を可視化し、達成度を明確にする ・ 適切なレベルの課題を設定する |
| 満足感(Satisfaction) | 学習成果への達成感と満足度を高め、持続的な学習を促進する | ・研修の成果を評価し、フィードバックを提供する ・学習の成果を客観的に評価できる仕組みを導入する ・ 学習内容を実際の業務に適用する機会を提供する ・表彰制度やインセンティブなどを活用し、学習意欲を高める ・ゲーミフィケーションやバッジシステムなどを活用し、達成感を演出する ・ 研修内容の振り返りやまとめを行い、学習内容の定着を図る |
参考:ゲーミフィケーションとは?企業研修への導入の際のポイントとメリット、注意点について解説 | 人材育成サポーター
TOTE(トート)モデル
TOTEモデルは、人間の認知プロセスや行動の制御メカニズムを説明するモデルです。
「Test(検査)」「Operate(操作)」「Test(再検査)」「Exit(終了)」の頭文字を取っています。インストラクショナルデザインにおいては、特に実践的なスキルの習得プロセスや、問題解決の手順を分析・設計する際に有用です。目標とする状態と現在の状態を比較し、ギャップがあれば解消のための操作を行い、再度目標に達したかを確認するという、フィードバックに基づいたループ構造を示しています。
| 要素 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| テスト(TEST) | 現在の状態と目標状態のギャップを明確にする | ・事前テストや自己診断で現状のスキルレベルを把握する ・現状分析を行い、目標状態とのギャップを明確にする ・基準となる指標や目標を設定し、現状との比較を行う |
| 操作(Operation) | ギャップを埋めるための具体的な行動・操作を行う | ・教材の学習、講義の受講、演習の実施など、知識やスキルを習得するための活動を行う ・ツールやシステムの操作練習、ロールプレイングなどを通して、実践的なスキルを身につける ・問題解決に必要な分析手法を学び、実際の課題に適用する |
| 再テスト(TEST) | 操作後の状態を評価し、目標状態とのギャップを確認する | ・演習問題、小テスト、理解度チェックなどで定着度を測る ・シミュレーションやロールプレイングで実践的なスキルを評価する ・問題解決策を実行した結果を分析し、目標達成度を評価する |
| 終了(EXIT) | 目標状態の達成を確認し、プロセスを終了する | ・最終テストや評価で目標達成度を最終確認する ・現場でのOJTを通して、実践的なスキルを習得したことを確認する ・問題解決策が効果的に機能していることを確認し、プロセスを終了する |
メリルのID第一原理
デビッド・メリルが提唱したID第一原理(First Principles of Instruction)は、「人が最も効果的に学習するにはどうすれば良いか」という教育学的知見に基づいた、5つの普遍的な原則です。特定のモデルというよりも、どのような学習設計を行う際にも共通して意識すべき、効果的なインストラクション(教え方)の基盤となる考え方を示しています。
ADDIEモデルなどのフレームワークの中で、具体的な学習内容や活動をデザインする際の指針として活用できます。
| 要素 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| 問題中心(Problem-Centered) | 現実的な問題解決を通して、学習意欲と応用力を高める | ・学習者が実際に直面する問題や課題を研修の中心に据える ・ケーススタディ、シミュレーション、ロールプレイングなどを活用する |
| 活性化(Activation) | 既存の知識や経験を活性化させ、新しい情報の理解を深める | ・ブレインストーミングやディスカッションを通して、参加者の既存の知識や経験を引き出す ・事前課題や質問を通して、学習内容に対する関心や好奇心を高める |
| 例示(Demonstration) | 具体的な例やデモンストレーションで、理解を促進する | ・事例、デモンストレーション、図表などを用いて、わかりやすく説明する ・成功例だけでなく、失敗例や非例を示すことで、理解を深める |
| 応用(Application) | 学んだ知識やスキルをさまざまな状況で応用する機会を提供する | ・演習問題、ロールプレイング、シミュレーション、グループワークなどを通して、学習内容を実際に適用する練習機会を設ける ・ 難易度を徐々に上げていくことで、学習者の自信とモチベーションを高める |
| 統合(Integration) | 学習内容を既存の知識や経験と統合し、実践に活かせるようにする | ・研修の最後に、学習内容を振り返り、要約する時間を設ける ・学んだことを実際の業務にどのように適用できるかを考えさせる ・グループディスカッションや発表を通して、学習内容を共有し、理解を深める |
ガニェの9教授事象
ロバート・ガニェの9教授事象(Nine Events of Instruction)は、効果的な教授(Instruction)を行うための9つのステップを示したモデルです。
一つのレッスンや研修セッションの具体的な流れとして応用され、学習者の認知プロセスに沿って、注意を引きつけ、情報を提示し、理解を深め、練習させ、評価するといった一連の活動を体系化しています。
| 要素 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| 注意の獲得 | 学習者の注意を引き、研修への関心を高める | 研修の導入で学習者の注意を引きつける(興味深い質問、驚くべき統計データ、短い動画やストーリーなど) |
| 目標の通知 | 研修で達成できる目標を明確に示す | 研修の開始時に、その研修で達成できる学習目標を明確かつ具体的に学習者に伝える |
| 前提条件の喚起 | 既存の知識や経験を思い出させ、新しい学習への準備を整える | 研修に関連する既存の知識や経験を思い出すための活動を行う(質問、ディスカッション、小テストなど) |
| 刺激の提示 | 学習内容を明確に提示する | 新しい情報、概念、スキルを、さまざまなメディアを用いて効果的に提示する(講義、テキスト、動画、eラーニングなど) |
| 学習の誘導 | 学習内容の理解を助けるガイダンスを提供する | 学習内容を理解しやすくするためのガイダンスを提供する(具体例、非例、図解、補足説明、関連情報へのリンクなど) |
| 遂行の引き出し | 学んだことを実際に使ってみる機会を提供する | 新しく学んだ知識やスキルを実際に使える練習の機会を提供する(演習問題、ケーススタディ、ロールプレイング、シミュレーションなど) |
| フィードバックの提供 | 学習結果へのフィードバックで理解と定着を促進する | 適切なフィードバックを提供する(正誤情報、改善点の指摘、模範解答の提示など) |
| 遂行の評価 | 学習目標の達成度を評価する | 学習目標の達成度を評価するためのテストや課題を実施する(筆記試験、実技試験、レポート、プレゼンテーションなど) |
| 保持と転移の促進 | 学習内容を長期的に記憶し、実践に活かせるようにする | 学習内容の長期的な保持と、新しい状況や実際の業務への移行を促進するための活動を行う(まとめと振り返り、応用練習、フォローアップ、追加学習リソースの紹介など) |
ラピッドプロトタイピング
ラピッドプロトタイピングは、インストラクショナルデザインの開発プロセスにおいて、特に効率性と柔軟性を重視する手法です。
特定の理論やフレームワークではなく、インストラクショナルデザインを実践する際の「開発手法」として活用されることが多いのが特徴で、インストラクショナルデザインをさらに効果的に実践するための補助的手法として役立ちます。
ラピッドプロトタイピングは、特にADDIEモデルの反復プロセスを効率化する点で、非常に相性が良い手法です。研修プログラムや教材の試作品(プロトタイプ)を迅速に作成し、学習者や関係者からフィードバックを得て、繰り返し改良を行うことで最適な成果物を完成させるというアプローチ方法です。
インストラクショナルデザインの具体的な実践方法
ここでは、インストラクショナルデザインを用いた研修を効果的に実践するための具体的な方法について、「ADDIEモデル」を使用し、それぞれのフェーズごとに解説します。
分析
分析フェーズでは、対象となる研修プログラムのニーズや課題を明らかにし、研修設計の基盤を構築します。
| ケース | 実践方法とポイント |
|---|---|
| 研修プログラムをゼロから作る場合 | ・学習者のニーズを特定するためにヒアリングやアンケート、業務データの収集を行い、課題や必要なスキルを明確化する ・研修の目的を、具体的かつ測定可能な形で定義し、目指すべき行動目標を設定する |
| 既存のコンテンツを改修する場合 | ・現行の研修プログラムが解決すべき課題を特定し、現場からのフィードバックや業務データを活用して原因を分析する ・設定された学習目標と現実の成果とのギャップを明確にし、改善すべき領域を洗い出す |
設計
設計フェーズでは、効果的な学習プログラムを構築するための詳細な計画を作成します。
| ケース | 実践方法とポイント |
|---|---|
| 研修プログラムをゼロから作る場合 | ・学習目標に基づき、必要なコンテンツを分解・再構成し、学習内容の順序を決定する ・学習者に最適な指導方法(講義、eラーニング、ケーススタディなど)とメディアを選定する |
| 既存のコンテンツを改修する場合 | ・現行プログラムの内容が学習目標に適しているかを確認し、不足点を補正する ・過剰な情報が含まれている教材は削減し、学びやすさを向上させる |
開発
開発フェーズでは、設計フェーズで決定した内容を基に、具体的な教材や環境を準備します。
| ケース | 実践方法とポイント |
|---|---|
| 研修プログラムをゼロから作る場合 | ・テキスト、動画、演習問題など、学習者に分かりやすい形式で教材を制作する ・ラピッドプロトタイピングを活用し、試作品を作成してフィードバックを得ながら改良する |
| 既存のコンテンツを改修する場合 | ・内容の古い部分や学習目標に合致していない部分を改善する ・eラーニングの場合はインタラクティブな要素や進捗管理機能を導入して、学習者のモチベーションを高める |
実施
実施フェーズでは、学習プログラムを提供し、学習者が実際に学ぶ環境を整えます。
| ケース | 実践方法とポイント |
|---|---|
| 研修プログラムをゼロから作る場合 | ・研修の目的や目標、進め方を学習者に事前説明し、期待値を共有する ・研修中は講師やファシリテーターが適切に学習者をサポートする |
| 既存のコンテンツを改修する場合 | ・ARCSモデルを活用し、学習者の関心を引き続ける要素を取り入れる ・対象者のスキルレベルや背景に応じてコンテンツを柔軟に調整する |
評価
評価フェーズでは、学習プログラムの成果を測定し、次回の改善に活かします。
| ケース | 実践方法とポイント |
|---|---|
| 研修プログラムをゼロから作る場合 | ・知識確認のためのテスト、行動変容を測定する観察、業務成果に基づく評価などを組み合わせる ・学習内容が業務に定着しているかを確認し、必要に応じて追加支援を行う |
| 既存のコンテンツを改修する場合 | ・既に実施済みの研修から得られたデータを分析し、改善の指針を明確にする ・学習者や講師から直接フィードバックを集め、プログラムの質を高める |
インストラクショナルデザインを取り入れた人材育成に役立つツール
インストラクショナルデザインの考え方を取り入れ、より効果的・効率的な人材育成を進める上で、テクノロジーの活用は非常に重要です。特に、LMS(学習管理システム)やTMS(タレントマネジメント)を支援するシステムは、インストラクショナルデザインの各フェーズをサポートしてくれます。
LMS(学習管理システム)
LMS(Learning Management System:学習管理システム)は、eラーニングコンテンツの配信、学習者の進捗管理、成績管理、受講者間のコミュニケーションなどを一元的に行えるプラットフォームです。特にeラーニングを活用した研修においては、LMSはなくてはならない基盤となります。
LMSの主な機能は以下の通りです。
- コンテンツ管理・配信機能:教材のアップロード・管理、受講者への効率的な配信
- 受講者管理機能:受講者情報の登録・管理、グループ分け、権限設定など
- 進捗・成績管理機能:学習状況やテスト結果を自動で記録・反映
- レポート・分析機能:学習データを集計・分析し、研修効果測定や改善点特定に活用可能
- コミュニケーション機能:受講者や講師間の交流、質疑応答、お知らせ配信などをサポート
- 管理機能:研修申請・承認、修了証発行などの事務手続きを効率化
LMSを効果的に活用すれば、インストラクショナルデザインで設計した学習プログラムを効率的に提供・管理し、学習データの収集・分析を通じて継続的な改善サイクルを回すことが可能になります。
TMS(タレントマネジメントシステム)
TMS(Talent Management System:タレントマネジメントシステム)は、従業員の採用から配置、評価、報酬、そして育成に至るまで、タレント(人材)に関する情報を一元管理し、戦略的な人材マネジメントを支援するシステムです。
インストラクショナルデザインに基づく人材育成は、個々の従業員の能力開発を通じて組織全体のタレントを最大化することを目的としているため、TMSとの連携は非常に有効です。
TMSの主な機能は以下の通りです。
- 人事情報管理:従業員の基本情報、職務経歴、スキル、資格、評価履歴などをデータベース化
- 目標設定・評価管理:個人目標の設定・進捗管理、人事評価、360度評価など
- スキル・コンピテンシー管理:従業員一人ひとりが持つスキルやコンピテンシー(行動特性)を定義・評価・記録
- サクセッションプランニング(後継者育成計画): 将来の重要なポジションを担う可能性のある人材を特定し、計画的な育成プランを設計
- 育成計画・研修管理:個々の従業員のスキルギャップやキャリアパスに基づき、必要な研修や能力開発プランを策定・管理
LMSとTMSは連携させることが重要
LMSが「学習コンテンツの提供と管理」に特化しているのに対し、TMSは「人材情報全般の管理と戦略的な活用」に重点を置いています。
TMSで管理されている従業員のスキル情報、評価結果、キャリア目標などをLMSと連携させることで、インストラクショナルデザインにおける以下のような活動をより高度に行うことができます。
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 正確なニーズ分析 | TMS上のスキルデータと評価結果から能力ギャップを把握 |
| 個別最適化された学習推奨 | スキルレベルとキャリア目標に合わせて、LMS上で最適なeラーニングコースや研修プログラムを学習コンテンツを推奨 |
| 研修効果の追跡 | スキル評価と業務パフォーマンスの変化を追跡・分析 |
| 戦略的な育成計画 | 人材情報と研修履歴を連携し、戦略的な育成プログラムを策定 |
TMSとLMSを連携させることで、インストラクショナルデザインの各フェーズがよりデータに基づき、個々の従業員の成長と組織全体のタレント戦略に直結する形で実行できるようになります。
インストラクショナルデザインを取り入れる際の注意点
インストラクショナルデザインは、研修効果を大きく高める可能性を秘めていますが、導入にあたってはいくつかの注意点があります。これらを事前に理解しておくことで、スムーズな導入と運用につながります。
導入には時間とコストがかかる
インストラクショナルデザインに基づく研修開発は、従来のやり方に比べて、特に最初の「分析」と「設計」のフェーズに時間と労力がかかります。関係者へのヒアリング、データ収集、目標設定、詳細な設計など、丁寧に進めなければならないためです。
また、効果的な学習プログラムを開発するためには、専門的な知識やスキル(インストラクショナルデザインの理論、分析手法、教材開発スキルなど)を持つ人材が必要です。社内に専門家がいない場合は、育成コストや外部委託コストが発生する可能性があります。
関係者の理解と協力が不可欠
インストラクショナルデザインの実践には、人事・研修部門だけでなく、経営層、現場の管理職、対象となる従業員など、さまざまな関係者の理解と協力が必要です。
特に、分析フェーズでの情報提供や、評価フェーズでの現場での協力(行動観察、効果測定への協力など)を得るためには、インストラクショナルデザインの目的やメリットを丁寧に説明し、共通認識を持つことが重要です。
スモールスタートで始める
最初から全ての研修プログラムに完璧なインストラクショナルデザインを適用しようとすると、負担が大きくなり挫折する可能性があります。
まずは、特定の重要な研修プログラム一つを選び、ADDIEモデルに沿って試行的に設計・開発・実施・評価を行ってみるなど、スモールスタートで始めることをおすすめします。実践を通じて経験を積み、徐々に適用範囲を広げていくのが現実的です。
継続的な改善が重要
インストラクショナルデザインでは、評価結果を分析し、次の研修プログラムの改善につなげる「継続的な改善サイクル」を回すことが最も重要です。
評価データの収集・分析には手間がかかる場合もありますが、LMSなどのツールを活用したり、評価の仕組みを簡素化したりするなど、自社の状況に合わせて無理なく続けられる方法を検討しましょう。
すべての研修にインストラクショナルデザインが必要とは限らない
インストラクショナルデザインは重要な考え方ですが、すべての研修に適用するべきというわけではありません。
例えば、短時間で終わる情報伝達型の簡単な研修などの場合、すべての学習機会にADDIEモデルの全フェーズを詳細に適用すると、かえって研修の効率が落ちる可能性があります。
研修の目的や重要度に応じて、どの程度インストラクショナルデザインの要素を取り入れるか(例:目標設定と評価だけは必ず行う、分析フェーズは簡易的に済ませるなど)を適切に判断することも重要です。
まとめ
インストラクショナルデザインは、効果的な学習プログラム設計のための体系的なアプローチです。
この考え方に基づき設計された学習プログラムの効果を最大限に引き出し、効率的に運用するためにはテクノロジーの活用が欠かせません。特にLMSは、設計されたコンテンツの配信、学習者の進捗・成績管理、そして重要な効果測定に必要なデータを収集・分析するための基盤となります。
ツールをうまく使いながらインストラクショナルデザインの考え方を取り入れ、自社の研修効果の向上を目指しましょう。
クラウド型LMSのAirCourseは、インストラクショナルデザインに基づいて設計した研修プログラムを、オンラインで効率的に展開・管理でき、スモールスタートからでも着実にインストラクショナルデザインの実践を進めることが可能です。
人材育成の課題解決に、今すぐ使える実践ツールを
人材育成の重要性は分かっている。でも「具体的にどう実行するか」で多くの企業が迷い、思うような成果が出せずにいます。あなたの組織も同じ悩みを抱えていませんか?
そんな課題を解決するために、900社以上が導入し成果を上げている「実践的な研修ノウハウ」と「すぐに使えるツール」をまとめた資料を無料でご用意しました。
1,000コース・6,000本以上の動画研修が受け放題の「eラーニングシステム」の詳細
AirCource(eラーニング)導入企業の具体的な成功事例と効果測定方法
階層×カテゴリでまとめた動画研修(標準コース、標準学習パス)の全体像
理論から実践へ着実にステップアップし、組織の成長を加速させたい方は、今すぐ以下資料をご活用ください。